【6 ⽉30 ⽇(⽊)開催】⽂化庁アートプラットフォーム シンポジウム「⼈々が作るパブリック・コレクション︓独・ルートヴィヒ美術館における現代美術コレクションの形成」
日本の現代アートがグローバルに適切な評価を受けるための基盤整備を推進している「文化庁アートプラットフォーム事業(事務局:国立新美術館)」では、ドイツ・ルートヴィヒ美術館のイルマーズ・ズィヴィオー館長をお招きし、シンポジウム「人々が作るパブリック・コレクション:独・ルートヴィヒ美術館における現代美術コレクションの形成」を6 月30 日(木)17:00-18:30 に開催します(国立新美術館3 階講堂及びオンラインライブ配信)。
文化庁は、日本の現代アートがグローバルに適切な評価を得るためには、官民が一体となって効果的・国際的な情報発信を実現するとともに、国内外の関係者の強固なネットワークを構築することが第一歩と考え、平成30(2018)年度より、「文化庁アートプラットフォーム事業」に取り組んでおり、シンポジウム等を通して、今後の現代アートの振興政策のあり方について有識者や視聴者とともに考えてきました。
ハンス・スローン卿のコレクションをもとに設立された大英博物館や市民の有志によって設立されたボストン美術館など、多くの欧米の美術館はコレクターにより収集されたプライベートな個人コレクションが美術館に収蔵され、パブリック・コレクションとして継承されたことにより、優れたコレクションが継続的に形成されてきました。
今回のシンポジウムでは、ズィヴィオー館長より、市民がコレクション形成やその拡大に寄与することを通して公的な美術館の活動に積極的に関わっているドイツの事例を紹介していただきます(モデレーター:片岡真実 日本現代アート委員会座長、森美術館館長)。そして、今後、我が国の美術館が持続的にコレクションを形成していくために、どのように市民との関係を築き、市民のプライベート・コレクションをパブリック・コレクションとして将来へ受け継いでいくことができるか、また、独立行政法人国立美術館が令和4(2022)年度中の開設を目指す「アート・コミュニケーションセンター(仮称)」が、国民の資産としてのパブリック・コレクションの形成に資することができるのか、多くの方々とともに考え、意見を交わします。
本シンポジウムへの参加費は無料です。国立新美術館での参加には、事前申込が必要です(オンライン配信は申込不要)。
■ テ ー マ:「人々が作るパブリック・コレクション:
独・ルートヴィヒ美術館における現代美術コレクションの形成」
■ 概 要:ドイツ・ルートヴィヒ美術館よりイルマーズ・ズィヴィオー館長をお招きし、
市民による美術館の現代美術コレクションの形成について紹介いただくとともに、
日本におけるパブリック・コレクション形成の在り方について考える。
■ 登 壇 者:【 講 師 】イルマーズ・ズィヴィオー(ルートヴィヒ美術館館長)
【モデレーター】片岡真実(日本現代アート委員会座長、
アート・コミュニケーションセンター(仮称)エグゼクティブ・アドバイザー、
森美術館館
■ 参加方法:①国立新美術館3 階講堂(東京都港区六本木7-22-2)
定員:70 名(先着申込順)
申込フォーム:https://forms.office.com/r/kNeX1bBkJx
②YouTube ライブ配信
定員:なし(事前申込不要)
視聴URL:<日本語> https://youtu.be/parTpvbxnYM
<英 語> https://youtu.be/mxRorcJOD88
■使用言語:英語及び日本語(日英同時通訳あり)
美術館の構想は、ペーター&イレーネ・ルートヴィヒが、ポップ・アートやロシア・アヴァンギャルドなど、約350 点の作品をケルン市に寄贈した1976 年に始まった。また同館は、ケルンの弁護士だったヨーゼフ・ハウプリヒが1946 年にケルン市に寄贈した表現主義や新即物主義などの近代美術や、レオ・フリッツ&レナーテ・グルーバーの協力から始まった膨大な写真コレクションなど、多数の個人コレクターに由来する作品群を所蔵する。
一方、同美術館の現代美術コレクションの形成には、「ルートヴィヒ美術館ケルン現代美術協会」も大きく貢献している。1985 年、現代美術振興と美術館支援を目的に設立されたこの組織は、現在約650 人の会員からなり、2018 年にはアメリカに国際支部も設けられた。協会は、さまざまなプログラムやイベントを実施するほか、作品の購入も支援している。また、同美術館の現代美術コレクションの拡大には、「ルートヴィヒ美術館芸術財団」が担う役割も大きい。2008 年にケルン市が設立したこの財団は、地方自治体が設置したドイツで初めての財団のひとつであり、作品の寄贈に関心があるコレクターを支援することで、美術館のコレクション拡大に寄与している。
このようにルートヴィヒ美術館では、市民の協力を得るさまざまなシステムがうまく機能している。そこで、館長のイルマーズ・ズィヴィオー氏より、美術館と市民の生きた交流とその成果を紹介いただき、日本において、どのように民間のプライベート・コレクションを、美術館のパブリック・コレクションとして継承していくことができるのか、美術館におけるコレクションの在り方について考える機会としたい。
イルマーズ・ズィヴィオー
ルートヴィヒ美術館(ドイツ・ケルン)館長
ドイツのハンブルク・クンストフェライン館長、オーストリアのブレンゲンツ美術館(KUB)館長を経て2015 年2 月より現職。2015 年のベネチア・ビエンナーレではオーストリア館の、今年2022 年にはドイツ館のキュレーションを務めた。
『Artforum』や『Camera Austria』、『Texte zur Kunst』に定期的に寄稿。20・21世紀美術に関して、展覧会カタログを含め50 冊以上の書籍の刊行に関わり、国外の美術館とのコラボレーションも数多い。アイデンティティ・ポリティクスや文化的帰属などを含めた社会的問題に焦点を当てており、アフリカ、ラテン・アメリカ、アジアに強い関心を持つ。近年手掛けた展覧会に「Haegue Yang:ETA 1994–2018」展(2018 年)、「We Call It Ludwig」展(2017 年)などがある。
Photo: Falko Alexander
モデレーター:片岡 真実
日本現代アート委員会座長/アート・コミュニケーションセンター(仮称)エグゼクティブ・アドバイザー/森美術館館長
ニッセイ基礎研究所都市開発部研究員、東京オペラシティアートギャラリー・チーフキュレーターを経て、2003 年より森美術館。2020 年より館長。2007~2009 年はヘイワード・ギャラリー(ロンドン)にて、インターナショナル・キュレーターを兼務。第9 回光州ビエンナーレ(2012 年)共同芸術監督、第21 回シドニー・ビエンナーレ芸術監督(2018 年)、国際芸術祭あいち2022 芸術監督。CIMAM(国際美術館会議)会長、京都芸術大学大学院客員教授、東京藝術大学客員教授。文化庁アートプラットフォーム事業・日本現代アート委員会座長。AICA(美術評論家連盟)会員。その他、日本およびアジアの現代アートを中心に執筆・講演・審査等多数。
©伊藤彰紀/撮影
https://artplatform.go.jp/ja/about-this-website
ハンス・スローン卿のコレクションをもとに設立された大英博物館や市民の有志によって設立されたボストン美術館など、多くの欧米の美術館はコレクターにより収集されたプライベートな個人コレクションが美術館に収蔵され、パブリック・コレクションとして継承されたことにより、優れたコレクションが継続的に形成されてきました。
今回のシンポジウムでは、ズィヴィオー館長より、市民がコレクション形成やその拡大に寄与することを通して公的な美術館の活動に積極的に関わっているドイツの事例を紹介していただきます(モデレーター:片岡真実 日本現代アート委員会座長、森美術館館長)。そして、今後、我が国の美術館が持続的にコレクションを形成していくために、どのように市民との関係を築き、市民のプライベート・コレクションをパブリック・コレクションとして将来へ受け継いでいくことができるか、また、独立行政法人国立美術館が令和4(2022)年度中の開設を目指す「アート・コミュニケーションセンター(仮称)」が、国民の資産としてのパブリック・コレクションの形成に資することができるのか、多くの方々とともに考え、意見を交わします。
本シンポジウムへの参加費は無料です。国立新美術館での参加には、事前申込が必要です(オンライン配信は申込不要)。
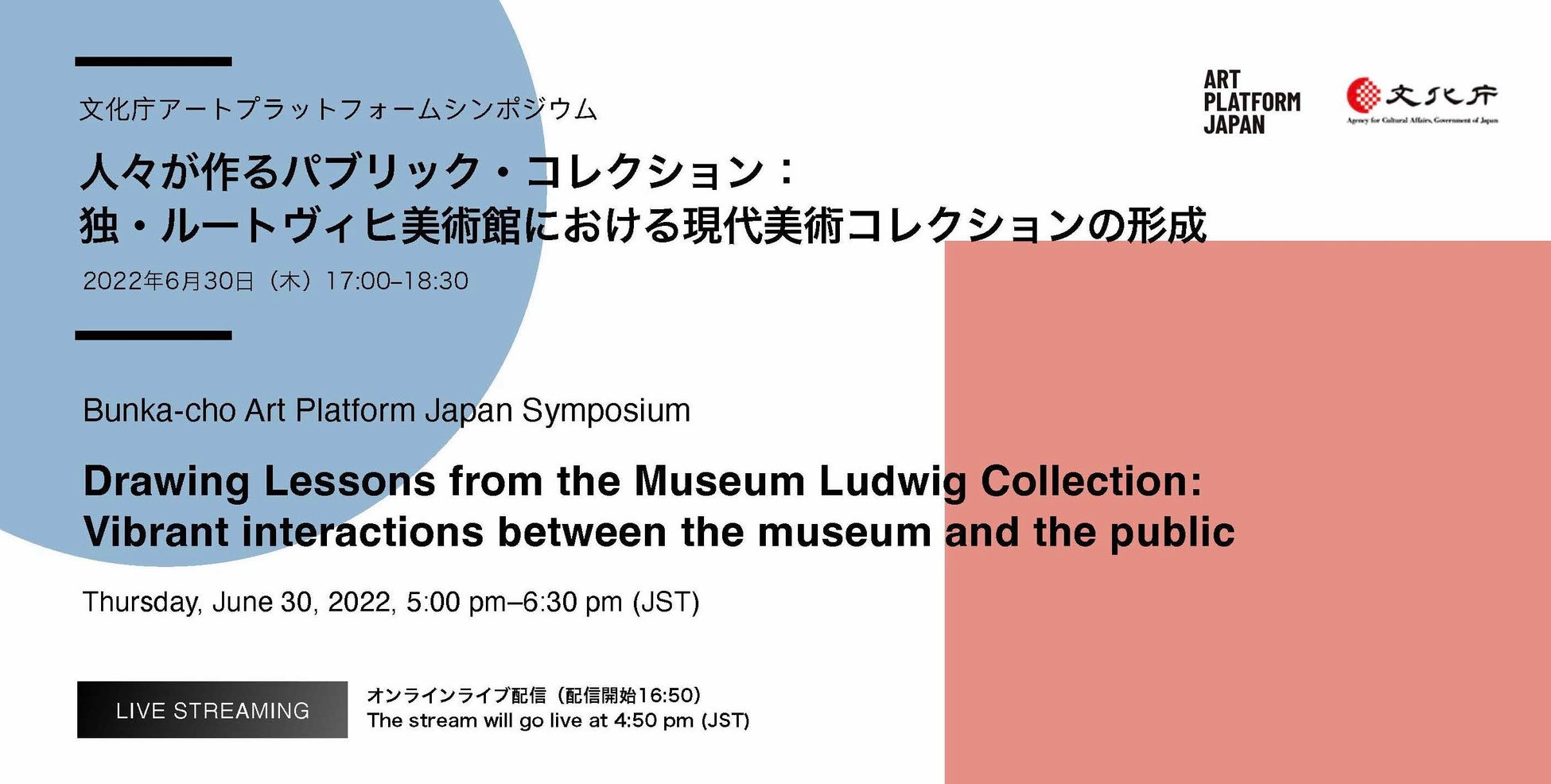
- プログラム概要
■ テ ー マ:「人々が作るパブリック・コレクション:
独・ルートヴィヒ美術館における現代美術コレクションの形成」
■ 概 要:ドイツ・ルートヴィヒ美術館よりイルマーズ・ズィヴィオー館長をお招きし、
市民による美術館の現代美術コレクションの形成について紹介いただくとともに、
日本におけるパブリック・コレクション形成の在り方について考える。
■ 登 壇 者:【 講 師 】イルマーズ・ズィヴィオー(ルートヴィヒ美術館館長)
【モデレーター】片岡真実(日本現代アート委員会座長、
アート・コミュニケーションセンター(仮称)エグゼクティブ・アドバイザー、
森美術館館

■ 参加方法:①国立新美術館3 階講堂(東京都港区六本木7-22-2)
定員:70 名(先着申込順)
申込フォーム:https://forms.office.com/r/kNeX1bBkJx
②YouTube ライブ配信
定員:なし(事前申込不要)
視聴URL:<日本語> https://youtu.be/parTpvbxnYM
<英 語> https://youtu.be/mxRorcJOD88
■使用言語:英語及び日本語(日英同時通訳あり)
- 企画背景
美術館の構想は、ペーター&イレーネ・ルートヴィヒが、ポップ・アートやロシア・アヴァンギャルドなど、約350 点の作品をケルン市に寄贈した1976 年に始まった。また同館は、ケルンの弁護士だったヨーゼフ・ハウプリヒが1946 年にケルン市に寄贈した表現主義や新即物主義などの近代美術や、レオ・フリッツ&レナーテ・グルーバーの協力から始まった膨大な写真コレクションなど、多数の個人コレクターに由来する作品群を所蔵する。
一方、同美術館の現代美術コレクションの形成には、「ルートヴィヒ美術館ケルン現代美術協会」も大きく貢献している。1985 年、現代美術振興と美術館支援を目的に設立されたこの組織は、現在約650 人の会員からなり、2018 年にはアメリカに国際支部も設けられた。協会は、さまざまなプログラムやイベントを実施するほか、作品の購入も支援している。また、同美術館の現代美術コレクションの拡大には、「ルートヴィヒ美術館芸術財団」が担う役割も大きい。2008 年にケルン市が設立したこの財団は、地方自治体が設置したドイツで初めての財団のひとつであり、作品の寄贈に関心があるコレクターを支援することで、美術館のコレクション拡大に寄与している。
このようにルートヴィヒ美術館では、市民の協力を得るさまざまなシステムがうまく機能している。そこで、館長のイルマーズ・ズィヴィオー氏より、美術館と市民の生きた交流とその成果を紹介いただき、日本において、どのように民間のプライベート・コレクションを、美術館のパブリック・コレクションとして継承していくことができるのか、美術館におけるコレクションの在り方について考える機会としたい。
- 登壇者プロフィール(敬称略)

イルマーズ・ズィヴィオー
ルートヴィヒ美術館(ドイツ・ケルン)館長
ドイツのハンブルク・クンストフェライン館長、オーストリアのブレンゲンツ美術館(KUB)館長を経て2015 年2 月より現職。2015 年のベネチア・ビエンナーレではオーストリア館の、今年2022 年にはドイツ館のキュレーションを務めた。
『Artforum』や『Camera Austria』、『Texte zur Kunst』に定期的に寄稿。20・21世紀美術に関して、展覧会カタログを含め50 冊以上の書籍の刊行に関わり、国外の美術館とのコラボレーションも数多い。アイデンティティ・ポリティクスや文化的帰属などを含めた社会的問題に焦点を当てており、アフリカ、ラテン・アメリカ、アジアに強い関心を持つ。近年手掛けた展覧会に「Haegue Yang:ETA 1994–2018」展(2018 年)、「We Call It Ludwig」展(2017 年)などがある。
Photo: Falko Alexander

モデレーター:片岡 真実
日本現代アート委員会座長/アート・コミュニケーションセンター(仮称)エグゼクティブ・アドバイザー/森美術館館長
ニッセイ基礎研究所都市開発部研究員、東京オペラシティアートギャラリー・チーフキュレーターを経て、2003 年より森美術館。2020 年より館長。2007~2009 年はヘイワード・ギャラリー(ロンドン)にて、インターナショナル・キュレーターを兼務。第9 回光州ビエンナーレ(2012 年)共同芸術監督、第21 回シドニー・ビエンナーレ芸術監督(2018 年)、国際芸術祭あいち2022 芸術監督。CIMAM(国際美術館会議)会長、京都芸術大学大学院客員教授、東京藝術大学客員教授。文化庁アートプラットフォーム事業・日本現代アート委員会座長。AICA(美術評論家連盟)会員。その他、日本およびアジアの現代アートを中心に執筆・講演・審査等多数。
©伊藤彰紀/撮影
- 文化庁アートプラットフォーム事業とは
https://artplatform.go.jp/ja/about-this-website
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
- 種類
- イベント
- ビジネスカテゴリ
- 政治・官公庁・地方自治体
- ダウンロード
