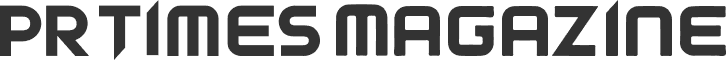企業が新たにサイトをオープンしたり、リニューアルしたりした場合にプレスリリースを配信することは、やるべき広報PR活動のひとつです。しかし、新商品や新サービスのプレスリリースと比べてそもそも記載できる情報が少なく、ただ配信しただけに留まるケースは少なくありません。
サイトオープンのプレスリリースの効果を最大限に生かすには、書き方に工夫が必要です。本記事では項目やポイント、広報PR事例なども紹介しながら、サイトオープン時のプレスリリースの良い書き方について解説します。
新サイトオープン・リリース時にプレスリリースを配信するメリット
新サイトのオープン・リリース時にプレスリリースを配信することで、主に3つの効果が期待できます。
1つ目は、自社の活動を効率的に多様なメディアに伝えられることです。主要なプレスリリース配信サービスは、Webメディア・雑誌・新聞・テレビ・ラジオ・通信社とさまざまなメディアと配信提携を行っています。プレスリリース配信サービスを利用し、配信先としてメディアを選定するだけで自社の活動を効率的に届けられます。製品やサービスのリリースに比べて新サイトオープンの情報はメディアに取り上げられにくいため、まずは情報の届け先の母数を増やす動きが必要です。
2つ目は、配信したプレスリリースを取り上げたメディアを閲覧している生活者にも情報を届けられることです。例えば、雑誌で取り上げられれば、その雑誌を購読している層にサイトオープンの情報を伝えられます。プレスリリースは公式文書なので文章が硬い表現になりがちですが、メディアの場合は読者である生活者にわかりやすく伝えるため、親しみのある言葉や文章で情報を届けられます。
3つ目は、生活者の目に触れる機会を作れることです。大手プレスリリース配信サービスには、業界や事業を問わずさまざまな企業の最新情報が掲載されています。そのため、メディア関係者や業界関係者だけでなく、生活者が情報収集手段のひとつとして利用しているという特徴があります。自社サイトでのリリース掲載以外にプレスリリース配信サービスを利用することで、新サイトのオープンに関する情報を生活者に直接伝えられるのも、プレスリリースを配信する大きなメリットです。
サイトオープンのプレスリリースに含めたい4つの項目
サイトオープンのプレスリリースには基本の4項目が存在します。プレスリリース作成前にこれらの情報を収集・整理して、メディア関係者や生活者の興味・関心を喚起する内容に仕上げましょう。4つの項目内に書く内容や書く際のポイントを解説しています。どんな項目で書けば効果的なサイトオープンのプレスリリースに仕上がるのか迷っている方は、参考にしてみてください。
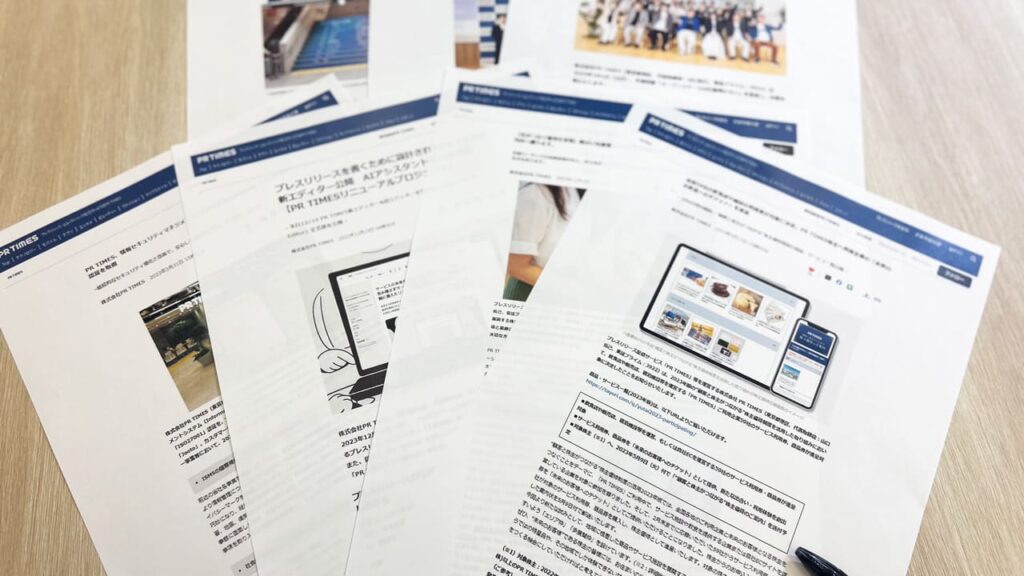
項目1.サイト概要
サイト概要の部分には、サイト名やサイトURLだけでなく、そのサイトにどんな情報が掲載されているのかや、サイトオープン日なども含めるようにしましょう。
概要なのであまり長くなっても良くありませんが、サイト名・サイトURLの情報だけでは、そのサイトやプレスリリースを配信している企業について知らない方が読んだ際に、把握できる内容が少なく、興味関心を喚起できません。情報を届けたい読み手を具体的にイメージし、その読み手に興味を持ってもらえるように、最低限必要な情報としてサイトに掲載されている内容について触れましょう。
サイトのオープンには、正式オープン・プレオープン・ベータ版とオープンの種類があります。そのことについてもきちんと明記してください。
項目2.サイトオープンの目的や経緯
新サイトをオープンする際は必ず目的があるはずです。プレスリリースにはその目的も必ず記載しましょう。
新サイトオープンのプレスリリースでよく見られるのは、サイト概要の情報のみが書かれているケースです。生活者も知るような企業やブランドの場合は限られた情報だけでも十分ですが、まだそこまで名が知られていない中小企業の場合は、プレスリリースの一つひとつにストーリー性を持たせることが大切です。
目的に加えて、サイトオープンに至るまでの経緯も可能な範囲で記載しましょう。明確な想いがあってサイトオープンに至ったことが伝われば、プレスリリースを読んだ方から共感が得られます。経緯に説得力を持たせる定量的・定性的なデータもあれば、なお良いでしょう。例えば、定量データであれば社会的背景やマーケティング時のデータなどが、定性データであれば顧客の声などがあります。
サイトオープンに至るまでの目的や経緯が記載されていれば、プレスリリースの情報を基に掲載されるだけでなく、興味を持ったメディア関係者や記者から詳細について話が聞きたいと連絡がある可能性も高まります。
項目3.担当者の声
新サイトのオープンを担った担当者の声は、自社の個性を出せる部分なので積極的にプレスリリースに取り入れましょう。担当者の声を加える際は、サイトオープンの目的や経緯と内容が重複しないように注意。サイトオープンに当たっての苦労や工夫など、担当者の想いにフォーカスを当てると、経緯や目的と内容が重複してしまうことを避けられます。コメントだけでなく、可能であれば担当者の写真も付けましょう。
項目4.自社情報
最後に自社情報を入れます。サイト概要やサイトオープンの目的や経緯、担当者の声がプレスリリースのメイン情報となるので、自社に関する情報のボリュームは抑えめにするのがベターです。
企業名・企業公式サイト・事業展開など基本的な情報に加えて、問い合わせ先も明記しましょう。
サイトオープンに関するプレスリリース作成時の5つのポイント
サイトオープンに関するプレスリリースを作成する際は、以下の5つのポイントに注意してみてください。プレスリリースを作成する際の基本的なポイントがほとんどですが、改めてこれらの点を意識することで、プレスリリースの内容がより良くなります。サイトオープンのプレスリリースは他社と内容が似通ってしまいやすいため、そのほかの点を工夫して差別化しましょう。

ポイント1.内容がわかるようなタイトルを付ける
プレスリリースの内容がわかるようなタイトルを付けることは重要なポイントです。
サイトオープンのプレスリリースのタイトルでよく見られるのが「サイトをオープンしました」とだけ書いてあるパターンです。メディア関係者は日々多くのプレスリリースを受け取っています。その中から、メールタイトルやプレスリリースのタイトルを見て内容を確認するかどうかを決めるため、タイトルには企業名や何を扱うサイトなのかを入れる必要があります。
長すぎるタイトルも良くありませんが、企業名・サイト名に加えて、サイトで扱っている内容は最低限盛り込みましょう。
ポイント2.リード文はコンパクトにする
サイトオープンのプレスリリースは、他社との差別化が難しいタイプのプレスリリースです。差別化を行うために多くの情報を盛り込んでしまいがちですが、リード文はあくまでもプレスリリースの概要を伝える部分なので、必要な情報は押さえつつ、なるべくコンパクトにまとめるように意識しましょう。
文量としては、パソコン・スマホともにファーストビューでメインの情報の最初の部分が閲覧できる程度が適切とされています。書いたリード文を自分以外の人に読んでもらって、長く感じるかどうかフィードバックをもらうこともおすすめです。
ポイント3.初めて自社を知る人に向けた構成にする
プレスリリースを読む人の多くは、自社や自社製品について知らないということを念頭に、わかりやすい構成のプレスリリースを作成することも大切なポイントです。企業そのものや製品に興味を持ってもらうことを目標に構成を考えると、わかりやすいプレスリリースが作れます。
基本的な構成は以下の通りです。
- 今回のメイン情報(概要文)
- サイトオープンの経緯・目的
- 自社のメインサービス、商品の説明(ここは端的に)
- 企業情報(簡潔に)
企業ページに飛ばずとも、その企業についてある程度知れるような情報を最低限入れるイメージで構成とその内容を考えます。
ポイント4.画像素材はなるべく豊富に用意する
サイトオープンのプレスリリースは、画像素材が少なくなりやすい傾向にあります。メディア情報の掲載を目的とするのであれば、画像素材はなるべく豊富に用意しましょう。サイトのスクリーンショットに加えて、ニュース記事で使えるような素材や動きのあるgifなどのイメージ画像が複数あるとベターです。
多くのメディアでは文字なしの画像が使われており、テキスト入りの画像は避けられる傾向にあります。基本はテキストなしの素材を用意しましょう。
現代は、生活者もプレスリリースを読んでいる時代です。気になったニュースがあればSNSでシェアする人も多いので、その際に使われやすいかどうかも意識すると良いでしょう。
ポイント5.ページのレイアウトにこだわる
プレスリリースは元々、テキストをベースとした企業のオフィシャルな文書です。そのため現在も多くのプレスリリースは文字がメインですが、最近ではプレスリリースをニュース記事のように読む人が増えているため、文字だけが大量に書いてあると最後まで読んでもらえる可能性が下がります。
文章、画像、文章、画像のリズムを意識し、読み手の読みやすさを考えたレイアウトでプレスリリースを作成しましょう。サイトオープンのプレスリリースの場合は、適度にサイトのスクリーンショットを差し込むことがおすすめです。
プレスリリースを閲覧する媒体として、パソコンとスマホのどちらに最適化すべきかもレイアウトを考える際に考慮したいポイントです。過去にプレスリリース配信サービスを使ったことがある場合は、パソコンとスマホの閲覧の割合を見てレイアウトを考えるのもおすすめです。
ほかにも、文字の大きさや色を工夫したり、表を差し込んだりとさまざまなレイアウト方法があります。興味・関心を喚起し、最後まで読んでもらうためにレイアウトも工夫してみてください。
サイトオープンに関するプレスリリース事例3選
サイトオープンに関するプレスリリースの事例を3つご紹介します。画像の選び方やレイアウトを工夫する方法、タイトルや見出しの付け方など、参考になる点が多い事例をピックアップしました。サイトオープンのプレスリリースを初めて作る方や、何度か作成していてより良くしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
事例1.株式会社川岸畜産
株式会社川岸畜産は、精肉の販売や卸などの事業を展開している企業です。2024年にECサイトをフルリニューアルし、関連するプレスリリースを配信しています。
このプレスリリースのポイントは、画像と文章をちょうど良いバランスで組み合わせていることです。ひとつの文章の後には必ず画像を入れるようにレイアウトを工夫しており、情報量がありながらも読みやすい内容に仕上げられています。
ECサイトのリニューアルだけでなく、サイト内で扱っている商品の魅力を画像と共に伝えているのもポイントです。用意されている画像を見るだけで、どんな事業を展開している企業なのか、情報が頭に入りやすい作りになっています。
サイトオープンのプレスリリースは画像やテキストの情報が少なくなりがちですが、メディアが記事にしやすい素材が揃っているのも参考になるポイントです。
参考:“4年に1度の肉の日、2月29日”「神戸ビーフ」の名門、川岸畜産がECサイトをリニューアルオープン!
事例2.株式会社松下工作所
株式会社松下工作所は、ECサイトオープンのプレスリリースを配信。自社のアウトドアブランドの名前や扱っている製品の名前を入れるなど、内容をイメージしやすくわかりやすいタイトル付けがされています。
プレスリリース内で使われている素材はテキスト入りがほとんどですが、画像素材としてテキストなしの画像を添付しているのもポイント。メディアで取り上げられることを意識してか、使いやすい素材を別途用意しています。
プレスリリースの見せ方として、レイアウトにもこだわっています。見出しをデザインして、何について説明しているのかがパッとわかるようになっています。タイトル・レイアウト・画像素材と参考になる点が多いプレスリリースです。
参考:4つの同時調理が可能な10年保証の焚き火台!製造直販のアウトドアブランド【ORANGEFACE】がECサイトをオープン!
事例3.株式会社アーツ
株式会社アーツは、本革製品を取り扱う自社ECサイト「本革工房 by ARTS」のリニューアルをプレスリリースとして配信しています。
レイアウトの工夫や見出しの付け方が参考になるプレスリリースで、レイアウトの部分では見出しをわかりやすく色付けしているほか、商品の種類を箇条書きにした部分を枠で囲んだり、重要な部分は太字にしたりするなど、重要な情報に目がいくような工夫がされています。
「製品概要」「開発背景」などではなく、キャッチーな見出しにしているのもポイント。ニュース記事のような読み応えのある構成と作りで、無意識に読み進めてしまうプレスリリースになっています。プレスリリース下部には、企業情報や問い合わせ先がわかりやすく掲載されています。
サイトオープンのプレスリリースを初めて書く際に参考となる、お手本のようなプレスリリースです。
参考:【革小物】名入れ記念品のECサイト「本革工房 by ARTS」がリニューアルオープン
サイトオープン時に広報PR担当者が行いたい3つの広報PR施策
サイトオープン時にはプレスリリースの配信以外の広報PR施策も行うことで、プレスリリースの配信効果を高められます。基本的な内容が主になりますが、広報PR担当者が行いたい3つの広報PR施策をご紹介します。プレスリリースの配信後、情報が新鮮なうちに広報PR活動ができるように、プレスリリースの準備と並行して、施策の準備も進めておきましょう。

1.自社のSNSアカウントと連携し、SNSからの流入を狙う
サイトオープン時にはプレスリリースの配信に加えて、そのことを自社SNSアカウントで広める広報PR活動が重要な意味を持ちます。
そもそもサイトオープンという情報は、製品リリースやサービスリリースなどの情報に比べて注目されにくい傾向があるため、配信すれば誰かの目に留まるという姿勢ではなく、ほかのツールを使って積極的に広める姿勢を持つことが大切です。SNSのアカウントでサイトオープンについて投稿することで、SNSからの流入が期待できます。
SNSは生活者が多く利用するサービスなので、生活者向けに投稿内容を考えることも意識してみてください。
例えば、日本和装ホールディングス株式会社は公式のSNSアカウントで着物の魅力や豆知識など、フォロワーにとって有益な情報を積極的に発信することで、着物に関心のある一般生活者を集め、サイトへの流入を促すことに成功しています。
参考:ふだんの生活にきものを by日本和装 (@nihonwasou_official) • Instagram photos and videos
2.メディア向けイベントの実施
新サイトオープンのプレスリリースは情報量が少ないことが多い上、話題になりにくいため、記事として取り上げられる可能性が低い傾向があります。プレスリリースを送付するだけでなく、メディア向けイベントを実施すれば、メディア関係者に取り上げられる可能性が高まるだけでなく、メディア関係者との関係構築も期待できます。
イベント内容はさまざま考えられます。例えば、三重県明和町×AVITAのデジタルプロジェクトについての発信では、アバターや生成AIなどのデジタル技術を活用した取り組みを紹介しています。新サイトで取り扱う商品やサービスを実際に体験できるイベント、今回の取り組みについての説明会などもイベント案のひとつです。情報を受け取ったメディア関係者や記者が参加したくなるイベントを実施しましょう。
参考:アバターが接客するECサイトをオープン!三重県明和町×AVITAのデジタルプロジェクトが拡大
3.サイトの内容に関連したキャンペーンを実施する
サイトオープンのプレスリリースは有名な企業やメーカーではない限り、情報が取り上げられる可能性は低いとされています。プレスリリースそのものを読む人も少ないので、読み手を増やすには何らかの施策を用意する必要があります。
その場合に取り組みたい広報PR施策は、サイトの内容に関連したキャンペーンの実施です。読み手がお得に感じるキャンペーンはメディアが積極的に取り上げる傾向があります。
例えば、有限会社いずみは自社ECサイトオープンのプレスリリースの配信と同時に、自社のInstagramとLINEでクーポンが当たるキャンペーンを実施しています。このようなキャンペーンはSNSとも連携ができるので、より多くのアカウントに情報を閲覧してもらいやすくなります。
メディアが必要とする情報から逆算し、情報密度の高いプレスリリースを作成しよう
サイトオープンのプレスリリースは、どうしても情報が少なくなりやすい傾向があります。中には、プレスリリースの配信そのものが目的となっている場合もありますが、プレスリリースの配信は手段であり、本来の目的は自社の新規情報であるサイトオープンをより多くの人に知ってもらうことです。
そのためには、プレスリリースをメディアに取り上げてもらうことが必要。ある程度の情報量がないと記事として紹介されにくいので、プレスリリース作成時にはメディアが必要とする情報から逆算し、情報密度を高める視点を持つことを意識してみてください。
サイトオープンのプレスリリースに関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする