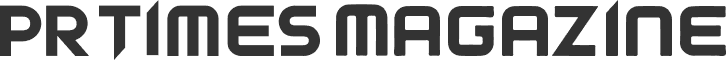すべての企業には競合が存在します。その名の通り、競い合う間柄なので「競合企業とつながるなんて考えられない」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、競合企業の広報担当者同士で接点を持つことは、企業にとって大きなメリットをもたらします。
本記事では、広報担当者が競合企業と付き合いをするメリットをはじめ、合同広報施策の事例や付き合いをするときの注意点を紹介します。
広報担当者が競合企業と付き合いをする5つのメリット
これまで競合企業との付き合いがない場合は「情報や人材が流出させてしまうことになるのでは」と不安が真っ先に頭に浮かぶ方もいるのではないでしょうか。
まずは、広報担当者が競合企業とつながると具体的にどんなメリットが得られるのかを確認していきましょう。自社の業界で取り扱う商品やサービスなどと置き換えるとよりイメージしやすくなるはずです。

メリット1.連携して業界全体の危機的状況を乗り越えられる
広報担当者が競合企業と付き合いをする1つ目のメリットは、連携して業界としての危機的状況を乗り越えられることです。
例えば、急激に拡大したスマホ決済は、2019年に不正アクセス問題が起こり話題となりました。利用者が急スピードで増えてはいましたが、まだキャッシュレスというものに慣れていない生活者が大多数。そんな時期だっただけに、スマホ決済に不安を感じた人もいたのではないでしょうか。
経済産業省が改めて不正利用防止のための各種ガイドラインの徹底を決済事業者に対して求めるなど、市場を拡大していきたいスマホ決済事業を展開する業界の危機的状況でした。
しかし、業界全体で連携し、不正利用防止の取り組みを発表し、啓蒙活動を行ったことで、状況を乗り越えることができました。
参考:今が正念場のキャッシュレス業界、報道されない地道な啓蒙活動もーBCN+R
1社単独で安心・安全の声明を出すよりも、業界全体で連携した方がより大きなメッセージとして生活者に届くでしょう。
このように、業界全体に影響するようなトラブルに見舞われたとしても、競合企業同士で同じ方向に進むことで、その業界のスタンスを示すことができます。自社だけでは解決が難しい問題や時間がかかる問題も、競合企業と連携すれば解決の糸口が見つかるかもしれません。
メリット2.信頼できるメディア関係者との人脈を増やせる
広報担当者が競合企業と付き合いをする2つ目のメリットは、信頼できるメディア関係者との人脈を増やせることです。
広報担当者ごとに過去の取材を経て、親しくなったメディア関係者がいるでしょう。競合企業であっても業界を盛り上げるために、お互いに親交のあるメディア関係者を紹介しあうことで人脈を広げられます。
コロナ禍では、ランチ会や会食といった以前なら当たり前だった交流の場を利用するのは難しいかもしれません。しかし、直接交流できなくてもSNSやオンラインツールなどを使えば、つながることは可能です。まずは、LinkedInやFacebookなどの実名SNSを積極的に活用してみることから始めてみましょう。
広報担当者は新たなメディア関係者との人脈を増やせ、メディア関係者は業界の情報源である取材対象を増やせるので、参加者全員にメリットがあります。
メリット3.競合企業と足並みを揃えたマスコミ対策ができる
広報担当者が競合企業と付き合いをする3つ目のメリットは、マスコミ対策ができることです。
競合企業とは差別化を図ることが重要視されがちですが、時には足並みを揃えるほうが得策になるケースも起こります。業界全体に影響があるような問題が起きた場合、マスコミの取材では他社との違いを指摘されがちです。
業界全体の信頼に関わる場合は、事前に競合企業と連絡を取り合い、情報発信のタイミングや内容の度合いを調整することがマスコミ対策につながります。
メリット4.競合企業の生の声が聞ける
広報担当者が競合企業と付き合いをする4つ目のメリットは、競合企業の生の情報を知れることです。
関わりがある業界の情報収集の方法は新聞やニュースアプリ、プレスリリースなどチェックするなど方法は多岐にわたりますが、その情報の裏側には興味深い話が隠れているものです。広報担当者と付き合いがあると、一歩踏み込んだ競合企業の生の声をキャッチできることも少なくありません。
例えば競合企業のとてもよい記事が公開されたとします。もし広報担当者と面識があれば取材に至った経緯や取材時の裏話、担当記者がどんな人物なのかなど、その記事の背景も知ることができるかもしれません。企業のアイデアの種が得られ、自社の広報施策ができるのか大きなヒントとなることでしょう。
メリット5.励ましあえる広報仲間ができる
広報担当者が競合企業と付き合いをする5つ目のメリットは、仲間ができることです。
大企業であれば広報PRの部署があることが多いですが、中小企業やスタートアップ、個人経営店などであれば、社内の広報担当者は自分ひとり、もしくは他業務と兼務しているケースも珍しくありません。
兼務の種類もさまざまで、企画、マーケティング、広告、バックオフィスなどを同時に担当する場合もあります。それぞれが置かれている立場で、それぞれの悩みを持っています。自社以外の広報担当者と接することで、同じ広報を担う仲間として励ましあえる、よい関係が築けることも大きなメリットだといえるでしょう。

広報が競合企業と合同で行いたい3つの広報施策
競合企業とのつながりを最大限に活かすなら合同の広報施策を行いましょう。異業種のコラボ企画に比べるとまだまだ少ない競合企業同士の広報施策。他業種で行われた施策はすぐに頭に浮かんでも、競合企業では思いつかないかもしれません。
次に、競合企業と合同で行いたい広報施策と、事例を3つ紹介します。
施策1.業界認知を目的としたイベントを開催
競合企業と合同で行いたい1つ目の広報施策は、イベントの開催です。
特に世の中にまだ浸透していない新しい業界や新商品など、合同で認知を目的としたイベントをするとよいでしょう。1社では集客が難しくても、複数の企業が集まれば自ずと規模が大きくなり話題性も高まります。継続開催も視野に入れれば、業界認知にもつながるでしょう。
関連商品を集めた展示販売会や、業界の関係者をスピーカーに迎えトークイベントを開催するなど、さまざまな人や企業を巻き込むとイベントの深みが増します。
また、関わる人それぞれがイベントの告知をしてくれるため、自社だけで開催するのとは比較にならない拡散力が得られることもメリットです。
施策2.ライバル同士のコラボ企画で話題を集める
競合企業と合同で行いたい2つ目の広報施策は、ライバル同士のコラボ企画です。競合企業でありながらも、あえて共同で事業を展開することで話題を集めます。
ミスタードーナツとモスバーガーのコラボ企画は2008年にスタートして以来、現在(2021年7月)まで続く長期企画です。同じ外食産業でありながら「手づくり・できたて」が共通価値の理念だとしMOSDO!の名称で店舗も運営しています。
ミスタードーナツとモスバーガーは知名度のある大手企業であり、生活者からも外食産業の競合であることはわかります。手を組むことだけで意外性は抜群で、注目度を高めることができる施策といえます。
参考:MOSDO!
施策3.SNSでのライブ感ある交流
競合企業と合同で行いたい3つ目の広報施策は、SNSでの交流です。
Twitterなどでの競合企業間のやり取りは生活者の目におもしろく映ります。今まさにストーリーが作られていくようなライブ感が魅力です。
提案から実現までをTwitter上で公開し、ストーリー性を持たせた事例を紹介します。吉野家のTwitter投稿をきっかけに、吉野家と外食産業として競合だといえる松屋・ガスト・モスバーガー・ケンタッキーフライドチキンの5社がコラボした企画です。
企業間が競合関係であればあるほど意外性が高く、見るものをワクワクさせます。このコラボ企画のクライマックスは、吉野家の呼びかけに松屋が応えるという主力商品が同じ牛丼である競合の参加でした。
イラストの制作だけで終わらず各社でニクレンジャーキャンペーンの展開やニクレンジャーの絵本を発売するなど大きなコラボ企画に発展しています。
競合企業とつながりがあり、よい関係性を築けていれば、外部からは刺激的に見える提案も失礼なく行えるのではないでしょうか。
広報が競合企業と付き合いをするときの5つの注意点
ここまで、広報が競合企業との付き合いで得られるメリットを事例も交えながら紹介しました。お互いにメリットのある付き合いとはいえ、付き合い方を誤ると自分だけでなく、自社はもちろん相手先にも迷惑をかけてしまう可能性があります。競合企業間の良好な関係を継続するには、どんなことに気を付けるべきでしょうか。
次に、競合企業と付き合いをするうえで守りたい注意点を5つ紹介します。基本的なことですが人と人、そして企業と企業が関わるうえで重要なポイントです。注意点をしっかり確認し、競合企業との良好な関係を築きましょう。

注意点1.守秘義務を守る
広報が競合企業と付き合いをするときに絶対に注意しておきたいことは、守秘義務を守ることです。
どんなに相手と仲良くなったとしても、競合企業であることには変わりありません。業界問わず、企業に属しているということを常に意識し、社外秘の情報は絶対に漏らさないようにしましょう。
共有しても大丈夫かどうか判断に迷うことがあれば、迷わず上司に確認をし、自社にとっての守るべき情報を把握する必要があります。
注意点2.競合企業の社外秘の情報を探らない
広報が競合企業と付き合いをする2つ目の注意点は、競合の社外秘の情報を探らないことです。
競合企業の動向は気になる情報ですが、社外秘の領域まで探るのはマナー違反です。自社に守秘義務があるように、他の企業にももちろん機密にすべき情報があります。気持ちのよい関係を継続するためにも、相手を困らせるような質問は控えましょう。
注意点3.一定の距離感を保つ
広報が競合企業と付き合いをする3つ目の注意点は、一定の距離感を保つことです。
何度か交流するうちに打ち解けたとしても、友達ではなく競合企業の広報担当者であることは忘れてはいけません。企業の責任者としての自覚を持った距離感を意識しましょう。個人ではなく、企業同士の付き合いとして意識する必要があります。
注意点4.上司に反対された場合の対応策を用意しておく
広報が競合企業と付き合いをする4つ目の注意点は、上司への対応を検討することです。
上司によっては、競合企業の広報担当者と付き合うことを好ましく思われないかもしれません。上司に反対された場合は、該当する競合企業との付き合いで得られる自社のメリットを答えられるように準備したうえ、相談をするようにしましょう。
注意点5.経験の浅い広報担当者だけでつながるデメリットを理解する
広報が競合企業と付き合いをする5つ目の注意点は、経験が浅い広報担当者のみでつながるデメリットを理解しておくことです。
広報としても経験が浅い場合は、競合企業の担当者と付き合う中で、意図せず会社の不利益につながる行動をしてしまう可能性があります。うっかり社外秘を話してしまったり、相手に有益となる情報を提供できなかったりと、気づかないうちに、企業にとってデメリットが生じるコミュニケーションをしてしまう可能性もあることを認識しておきましょう。
競合企業との付き合いの中で判断に迷うことがあれば、上司のサポートを受けるのがおすすめです。最初は上司に同席してもらうなどして、万が一に備えておくなど、対策をして交流をしてみてはいかがでしょうか。
競合企業との付き合い方次第で広報活動のフィールドがぐっと広がる
ライバル関係にある競合企業と付き合うことは、ひと昔前ではタブーだったかもしれません。しかし、変化の激しい現代では業界自体の存続が危ぶまれる事態に追い込まれることも考えられます。ライバルでありながらも、同士として手を取り合って業界の発展に尽力するのがこれから求められる関係性ではないでしょうか。
本記事で紹介した事例のように、競合企業と合同で企画ができれば、自社だけではできないような広報活動が数社集まれば可能になります。
注意点に留意しながら、競合企業との付き合いを検討してみてはいかがでしょうか。
競合企業との付き合い方に関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする