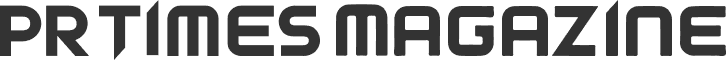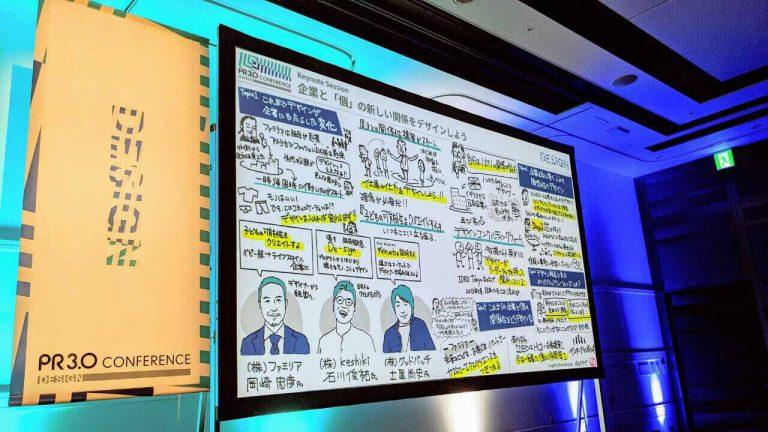メディアのあり方や未来について考えるメディア従事者向けの祭典「MEDIA DAY TOKYO 2023」が、2023年7月20日に開催されました。今回のイベントは、株式会社PR TIMESが主催・企画を担い、CINRA,Inc.が企画・運営を務めます。2018年以来、5年ぶりに開催され、業界の最前線で活躍する多数のメディア関係者が集結。登壇者の熱いトークセッションを聞き、会場は盛り上がりました。
「AIはメディアの味方か?敵か?メディアトレンドの変遷とこれから」をテーマに、株式会社THE GUILD 代表取締役の深津貴之さん、株式会社ゲームエイト代表取締役会長で株式会社Gunosy取締役の西尾健太郎さん、モデレーターにメディアコラボ代表の古田大輔さんを迎えたセッションをお届けします。

株式会社THE GUILD 代表取締役
インタラクションデザイナー。株式会社thaを経て、Flashコミュニティで活躍。2009年の独立以降は活動の中心をスマートフォンアプリのUI設計に移し、株式会社Art&Mobile、クリエイティブファームTHE GUILDを設立。現在はnoteのCXOなど、領域を超えた事業アドバイザリーを行う。執筆、講演などでも精力的に活動。

株式会社ゲームエイト代表取締役会長/株式会社Gunosy取締役
首都大学東京(現 東京都立大学)在学中に株式会社Labit共同創業、2013年代表取締役就任。リクルートホールディングス子会社に事業を譲渡後、株式会社ゲームエイトを創業、現在、代表取締役会長。2015年株式会社GunosyからのM&Aを経て入社。2018年9月より執行役員メディア事業本部を経て、2020年8月より株式会社Gunosy取締役に就任。

ジャーナリスト/メディアコラボ代表
朝日新聞記者、BuzzFeed Japan創刊編集長を経て独立。ジャーナリストとして活動するとともに報道のDXをサポート。2022年に日本ファクトチェックセンター編集長に就任。その他の主な役職として、デジタル・ジャーナリスト育成機構事務局長、ファクトチェック・イニシアティブ理事など。早稲田大、近畿大で非常勤講師。ニューヨーク市立大ジャーナリズムスクール News Innovation and Leadership 2021修了。
プロフィールはプレスリリースより:メディアの未来を考える1日『MEDIA DAY TOKYO 2023』7月20日開催 「エルピス」佐野亜裕美P、「SPY×FAMILY」編集・林士平氏ら登壇!
AIの急成長がメディア業界に与える影響
まず、「AIの急成長による各メディアの変化」についてトークが交わされました。想像を超えるスピードで成長を遂げるAI(人工知能)。ChatGPTをはじめとする最新AI技術の数々が、メディア業界にどのような影響を及ぼすのか、古田さんの問いかけからディスカッションがスタートしました。
メディア業界にとって強烈なインパクト
古田さん(以下、敬称略):おふたりとも仕事はもちろん、個人的な活動でもAIに深く携わっていますが、想像以上の急速なAIの発展はメディア業界に対してどういう影響があるとお考えですか。
深津さん(以下、敬称略):かつて活版印刷が登場し聖書が印刷されたことで、教会の権威や宗教の構造が根本から変わったように、生成AIの登場はそれと同じくらい大きな変化ではないでしょうか。
「情報の即時性」や「1日当たり記事数」など、これまでメディアが誇っていた経済に対する価値は、生成AIの台頭でほぼゼロになる可能性があります。メディア業界の構造そのものが大きく変わる可能性があることを見据え、生き延びる方法を考えていくべきだと思います。
西尾さん(以下、敬称略):生成AIは、スマホやクラウドといった過去の技術トレンドと並ぶインパクトを、確実に社会に与えているのではないでしょうか。使い方によっては、個人の能力を伸ばすことができる技術で、コンテンツを提供するメディア側にとっても、これまで以上にレバレッジをかけられるテクノロジーだと思います。
また、生成AIによって既存メディアのシェアが奪われるという事態を回避するためには、メディア自身が「守り」と「攻め」の両面でAIを使いこなす必要があるかと。今は日々業界の動きを見ながら、急成長する生成AIの波に適切に乗るしかないのかなと思っています。
海外のテック企業が脅威となる可能性も
古田:今、おふたりが注目しているグローバル企業やサービスはありますか。
深津:スピード感では、マイクロソフトはとてもよい仕事をしていると思います。オープンソース戦略で良いポジションを獲得しているのはMetaではないでしょうか。
西尾:メディアでいうと、インスタグラム創業者が手がけた「Artifact(アーティファクト)」という新しいニュースアプリでしょうか。LLM(大規模言語モデル)を駆使して、ユーザーにパーソナライズされたコンテンツを届けるアプリなのですが、このようなサービスが今後も増えていくと予想します。
深津:同じくメディアでは、ブルームバーグが莫大な予算を投じて金融機関向けのLLMを開発中です。将来的にはブルームバーグのような企業が「メディア用言語モデル」の基盤を開発し、全世界の出版社やメディアは利用料を支払いながらLLMを使う未来もあり得るのではないでしょうか。
古田:ブルームバーグは大規模なエンジニアを抱え、メディアのテック企業化に成功した数少ない組織ですよね。こういう企業が本気でAIを活用していくと、多くの企業は吹き飛ばされてしまうんじゃないかと思います。

日本のメディアが取り組むべき対策
西尾:日本のメディアが今取り組むべき対策としては「社内オペレーションの最適化」が大切だと思います。既存の組織の中にAIを取り入れて生産性を上げることで、防御力を高めるべきです。
今回の生成AIの台頭を機に、これまで科学的なアプローチによってコンテンツが作られていなかった部分の見直しを進めることができるのではないでしょうか。
深津:既存の組織の中にAIを取り入れていく際のポイントについては、組織がトップダウン型かボトムアップ型かによって変わると思います。
例えば、ボトムダウン型の組織の場合、まずは経営者にChatGPTなどの生成AIの使い方を教えることが第一歩。その技術の可能性を実感してもらうとともに、経営者自身の生産性を上げることで社員に勧められるようになるのではないでしょうか。
一方、ボトムアップ型の組織の場合は、成果がでないと広まっていかない。トレーニングをしなくても短時間で成果が出やすい分野を見つけ、まずは成功事例をつくることが大切です。
AIによってメディア業界はどう変わるのか
セッション中盤では、AIの浸透が進むことでどのような未来が訪れるかという話題で議論が盛り上がりました。
高度なパーソナライズ化が叶える「AI秘書」
深津:注目すべきは、今後はAIによるパーソナライズ化がさらに進んでいくということ。将来的には、高度になったAIがGoogleカレンダーのようなスケジュール管理ツールと連動することで、過去の予定や当日の予定からその人が今見るべき最適なニュースを提案できるようになると思います。
古田:営業で訪問予定の企業に関する情報や会う予定がある人の直近の発言などから、事前に読んでおくべき記事をAIがインターネット上から探し出し、リコメンドする機能も遠からず実装されるでしょうね。
西尾:以前はGoogleカレンダーの情報をGPTやLLMにつくらせるのはトークンサイズの制限で難しかったのですが、数ヵ月前のアップデートにより、制限が緩和されたはず。スマホがひとりに1台あるように、誰もが自分専用の「AI秘書」を持つような時代が訪れる可能性があると思いますし、新しいビジネスの間口になっていくことを期待しています。
AIの進化で加速する「ひとりメディア」
深津:現在は一問一答しか対応していないChatGPTのプロンプトも、数年後にはそのリミットがなくなると思います。「インターネット上のあらゆる情報の中で信用できるソースのみでレポートを作成してください」「15分ぐらい作業に時間をかけてよいので、終わったらメールをください」ということが可能になるのではないでしょうか。
インターネットの普及によって元記者だった人たちが独立し、「ひとりメディア」として何千人もの客を抱えています。生成AIは、秘書としての役割、下請けの方へのアウトソースなどさまざまな場面で対応してくれるため、今後はさらに「ひとり新聞社」「ひとりテレビ局」など「ひとりメディア」が登場し、大きなメディアと闘う構図が起こるのではないかと予想します。
AIはメディアの味方か敵か
活発なディスカッションが交わされる中、セッションはいよいよ最後の大詰め「AIはメディアの味方か敵か」の話に。古田さんは、高度化したAIにより仕事が奪われてしまう人が出てくることや、メディア業界そのものが吹き飛ぶ可能性に言及しています。そうした事態にどのように立ち向かうべきか。深津さん、西尾さんはどのように考えるのでしょうか。
味方、敵ではなく、使いこなす側に
深津:技術の発展により業界の構造が大きく変化することは歴史上何度も繰り返されてきました。自動車の登場で飛脚業や籠屋が消えた一方で、配送業や郵送業は何十倍にも成長。テクノロジーは単なる様相にすぎません。
新しいテクノロジーが登場したとき、適応する側に回るか、それを拒否する側に回るのかによって結果は大きく異なるのではないでしょうか。これまでの日本のIT技術における歴史を見ると、拒否することは不利になることは明らか。AIと闘うのではなく、使いこなせるようになることが大切だと思います。
西尾:今後AIがさらに進化することは確実ですから味方にするしかないですよね。検索からの流入に頼っているメディアにとっては死活問題ですが、生成AIのコンテンツを活用することで人間の生産性のレバレッジは上がります。また、損益分岐点を超えづらかった特定の人に刺さるようなコンテンツを個人が制作できるようになったり、メリットも多い。味方になり得る可能性が高いといえるのではないでしょうか。
スピード感を持ちAI活用へ着手することが大切
深津:AIを味方につけるためには、「今」というタイミングが非常に大切です。
現在、海外におけるAIのビッグプレイヤーの多くがエネルギーを注いでいるのは、金融や医療、化学の分野。メディアへの注目度が低い今のうちに、メディアに携わる人たちが率先してAIマスターになることでチャンスが生まれる可能性があると思います。
西尾:ChatGPTが話題になっているものの、実際に触ったことがある人はまだ多くはなく、使い続けている人となると少なくなります。そこから工夫して使い続けたり、プロセスや仕事に活用したりする人はさらに少なく、タイミングを逃さずに、仕事や事業に取り込むことを考え続けることが、未来を作るうえで非常に重要です。
人間にしか提供できない価値を見極める
古田:実際に人に会い、話を聞き出すということは、AIがどれだけ発展しても絶対に負けない強みといえる部分だと断言できます。ジャーナリストとしてはAIを活用することでそれ以外の仕事を短時間で終わらせ、人間にしかできない仕事に力を注ぎたいですね。
深津:人間にしか提供できない付加価値は何かを、メディア関係者自身がしっかりと見極めることが大切だと思います。
西尾:自分が大切にしたいものや提供したい価値に向けて、生成AIを上手く使っていくことが何よりも大切。メディアのあり方や世の中全体がよりよいものになるような、そういう動きをしていきたいですね。

AIは味方に、タイミングを逃さず使いこなすこと
AIの浸透がメディア業界に与える影響や活用の可能性について、専門家ならではの観点から話しを聞くことができ、セッション終了後は会場から大きな拍手が送られました。
AIをはじめとする技術革新、生活者が得られる情報量の拡大など取り巻く環境の変化により岐路に立たされているメディア業界。その中で、AIは脅威であると同時に、ビジネスの間口を広げる可能性を秘めていることを再認識したのではないでしょうか。
新しい技術を拒否するのではなく、うまく使いこなす側に回り、味方にする。激動のAI時代を生き抜くヒントがたくさん詰まったセッションは、メディアに携わる一人ひとりにとって参考になる内容だったのではないでしょうか。
【関連記事】
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする