『学ぼう心のサイン 守ろう10代の命』 こどもの自殺対策に関する講演会をこども家庭庁主催で初開催しました
こども家庭庁は、こどもが自ら命を絶つようなことのない社会の実現に向けて、保護者等の大人を対象としたこどもの自殺対策に関する講演会を、1月26日に長野県長野市で開催しました。この講演会は、「こどもの自殺対策の推進に向けたデジタル広報啓発事業」の一環として、こども家庭庁主催で初めて開催しました。

■実施概要
本講演会では、「深刻な悩みを持つこどもが発する心のサイン(SOSのサイン)」をテーマに基調講演とパネルディスカッションの2部構成で開催しました。基調講演では、こどもの自殺の現状や、こどもが持つ深刻な悩みについてNPO法人OVA(オーヴァ)代表理事の伊藤次郎氏が講演を行いました。パネルディスカッションでは、エッセイスト・メディアパーソナリティの小島慶子氏や、NPO法人第3の家族代表の奥村春香氏、長野日本大学高等学校のスクールカウンセラーの宮尾弘子氏が加わり、深刻な悩みを持つこどもの気づき方や気づいた際のサポートの方法などについて来場者と一緒に考えました。
■実施の背景
小中高生の自殺者数は、令和2年以降、高止まりを続け、令和6年は527人(暫定値)と過去最多となっており、喫緊の課題となっています。こども家庭庁では、こどもが自ら命を絶つようなことのない社会の実現に向けて、今年度から「こどもの自殺対策の推進に向けたデジタル広報啓発事業」を開始し、こどもの自殺対策に関わる有識者とともに、どのような対象にどのような広報が必要か、検討を重ねてきました(有識者の一覧は後述)。
初年度の取組として、本講演会に加えて、高校生を対象に悩みを持つ友人への傾聴や寄り添い等を学ぶワークショップや、幅広い年齢を対象にこどもの自殺に関する全国的な意識調査を行い、今後のこどもの自殺対策に関する広報啓発の方向性を検証することとしています。
長野県は、”子どもの自殺ゼロ”を掲げ、『子どもの自殺危機対応チーム』の取組が全国のモデルケースとされるなど、積極的な取組を行っていることから、本講演会とワークショップの開催地として選ばれました。
■主催者挨拶
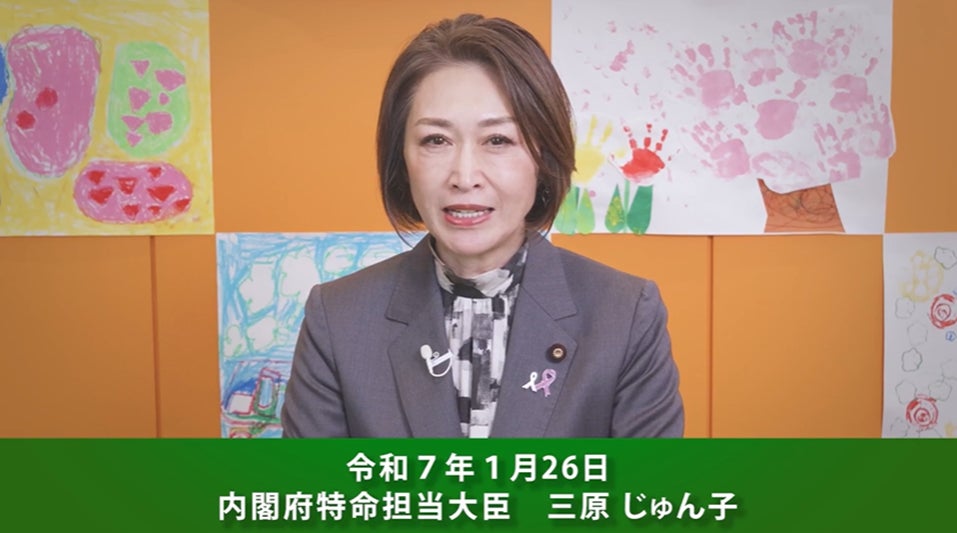
講演会の開会に当たり、三原大臣がビデオメッセージを送りました。
三原大臣は「私たち大人は、不安や悩み、困難を抱えるこどもの声を、しっかりと受け止めているでしょうか。また、受け止めた声に、「解決する」よりも前に、きちんと寄り添っているでしょうか。こどもが伝えているサインやシグナルを見逃してはいないでしょうか。この講演会を通じ、私たち大人はこどもの命を守るために何ができるのか、何をすべきか、ともに考えていければと思います。」と、こどもの自殺対策を進める必要性について述べました。
■県知事挨拶
また、開催地である長野県を代表して、阿部守一長野県知事が挨拶しました。阿部知事は「長野県ではこども(20歳未満)の自殺ゼロを目指し取組を進めていますがまだまだこどもの自殺に歯止めをかけるには至っていません。自殺が心配だ、リスクを抱えているのではないかと気になるこどもがいたら、ぜひ県に直接相談してください。講演、パネルディスカッションを通して、それぞれの立場で、それぞれの地域で、こどもたちにしっかり目を向け、SOSを見逃さない、こどもたちが明るく夢を持って暮らせる長野県にするため、ぜひ力を合わせていければと思います。」と、長野県でも、こどもの自殺対策に全力で取り組んでいく決意を述べ、県民への協力を求めました。

■基調講演
基調講演では、NPO法人OVA代表理事で精神保健福祉士の伊藤次郎氏が、こどもの自殺における現状を踏まえ、SOSのサインに周囲の大人が気付くことの重要性について解説しました。
伊藤氏は「実際、希死念慮を持つ若者が誰に相談したかを確認した調査では、約6割が誰にも相談しなかったと回答しています。だからこそ、いつもと少しでも様子が違うこどもに気づくための知識や、相談を受けた際の望ましい対応は、頭の片隅にでも持っておいてもらいたいと考えています。」と話し、こどもたちが安心して「助けて」と言える社会にするためにも、周りの大人たちによるサポートが重要であると訴えました。

■パネルディスカッション
パネルディスカッションでは、伊藤氏に加え、奥村氏、小島氏、宮尾氏が登壇。深刻な悩みを持つこどもの特徴的な言動や、こどもが自殺を選んでしまうかもしれないほど、深い悩みに至るきっかけ・事象、そのような状況のこどもに対する周囲の大人の望ましい行動・対応といったテーマについて会場の参加者とともに考えました。
ディスカッションの中で小島氏は、自身の10代のころ、希死念慮に悩んだ経験を振り返るとともに、「自分はなんで死にたいのかわからなかったし何を相談していいのかわからなかった。10代のころはその気持ちを表現することができませんでしたが、言語化できたのは30代になってからです。人に聞いてもらえる場所がひとつあるだけでもずっと抱えているよりは楽になります。みなさんひとりひとりが命の恩人になる可能性があります。」と述べ、こどもが発するSOSやサインを拾える周囲の存在の必要性を強調しました。

奥村氏は、「自分たちは“寄り添わない支援”をコンセプトにしています。福祉では寄り添いが大事とされていますが、寄り添いの支援から取りこぼされているこどももいます。相談の機会に来られず、頼る場所がなくなってしまって危険なところに流されてしまうこともあります。」と述べ、自らのWebサイトでも、こどもに煩わしく思われるような支援はせず、寄り添う居場所にたどり着いてもらうために、さりげなく相談窓口を示すなど、若者の声を大切にした自身の活動について述べました。


長野日本大学高等学校のスクールカウンセラーの宮尾氏は、「勤務校には教室に入りづらい生徒のための居場所があります。そこに来る生徒の中で、最初から悩みを打ち明けてくれる生徒はほぼいません。最初は世間話をしたり、トランプをしたりして、一緒の空間にいるだけです。徐々に話してくれるようになり、深く聞けるようになってきます。話してほしいと思いながらもじっくり待つようにしています。」と、学校としてのサポート体制を説明するとともに、傾聴の重要性を訴えました。
■開催概要

|
開催日時 |
令和7年1月26日(日)14:00~15:30 |
|
会場 |
TKPメトロポリタン長野カンファレンスセンター 千曲(ちくま) (長野県長野市南石堂町1346 ホテルメトロポリタン長野 2階) |
|
プログラム |
・主催者挨拶 こども家庭庁 三原じゅん子こども政策担当大臣(ビデオメッセージ) ・開催地代表挨拶 長野県 阿部守一知事 ・基調講演「こどもの自殺の現状や、こどもの持つ深刻な悩みについて」 伊藤次郎氏 ・パネルディスカッション 伊藤次郎氏、奥村春香氏、小島慶子氏、宮尾弘子氏 ①深刻な悩みを持つこどものサインとは? ②こどもが自殺を選んでしまうかもしれないほど、深刻な悩みに至るきっかけ・事象とは? ③深刻な悩みを持つこどもに出会った際、周囲の大人にとって望ましい行動・対応とは? ・閉会挨拶 |
■登壇者情報

講師・パネリスト 伊藤次郎氏(NPO法人OVA 代表理事、精神保健福祉士)
人事コンサルティング会社・精神科クリニックにて働く人のメンタルヘルス対策に従事。2013年より子ども・若者の自殺が深刻な状況にあることに問題意識が芽生え、検索連動広告を用いてハイリスクな子ども・若者にリーチし、インターネットで相談を受ける手法を開発し、OVAを設立(2014年)。主にデジタルアウトリーチ・インターネット相談の実践・研究を行い、SNS事業者と連携したインターネットの安全利用にも関わる。

パネリスト 奥村春香氏(NPO法人第3の家族 代表)
弟の自死をきっかけに活動を始める。LINE株式会社Product Designerを経て、学生時代から続けていた第3の家族を令和5年にNPO法人化。Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023。グッドデザイン・ニューホープ賞最優秀賞、法政大学理系同窓会成績優秀者など数々の受賞歴をもつ。

パネリスト 小島慶子氏(エッセイスト、メディアパーソナリティ)
学習院大学法学部を卒業後、1995年TBSにアナウンサーとして入社。2010年に独立し、各種メディア出演や、執筆・講演活動を精力的に行っている。
母親として二人の息子を育て、昨年までは、10年間オーストラリアと日本の2拠点で生活。子育てと仕事を両立し、現在は日本に定住している。

パネリスト 宮尾弘子氏(公認心理師)
長野県の公立中学校の教員として働き、退職後に長野日本大学学園のスクールカウンセラーに。公認心理師の資格を有する。
有識者検討会委員(敬称略・団体名順)
NPO法人あなたのいばしょ 理事長 根岸督和
NPO法人OVA 代表理事 伊藤次郎
NPO法人Light Ring.代表理事 石井綾華
NPO法人自殺対策支援センターライフリンク 情報デザイングループリーダー 鈴木洋平
一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター(JSCP) 広報室長 山寺香
株式会社官民連携事業研究所 代表取締役 鷲見英利
株式会社大広WEDO チームリーダー 谷本卓哉
日本放送協会 大阪放送局 ディレクター 後藤怜亜
報道におかれましては、WHO(世界保健機関)発行の『自殺予防を推進するためにメディア関係者に知ってもらいたい基礎知識2023年版』を踏まえた対応をお願い申し上げます。
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
