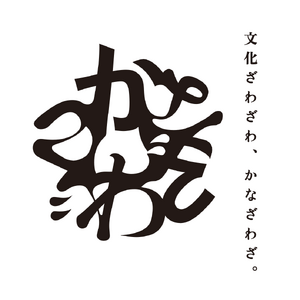【国指定無形文化財】の新たな継承!【能登半島震災】の仮設拠点「インスタントハウス」で行う「農耕儀礼あえのこと」のカタチ
震災を機に文化が減少する反面、復活する兆し。文化とはいったいなんなのか。どう継承されるべきなのか。民間伝承のアップデート版が、12月の珠洲を舞台に繰り広げられます。
2025年12月4、5日の2日間で奥能登農耕文化ツアー事務局(企画運営:合同会社かなざわざ/本社:石川県金沢市、代表取締役:澤田雅美)は、珠洲市で2軒のお宅とともに、ユネスコ無形文化財でもある農耕儀礼「あえのこと」を執り行います。

本プロジェクトでは、年々あえのことの慣習が薄れつつある中で、石川県珠洲市高波地区の納屋(本家は全壊)と、ボランティア拠点となっているインスタントハウスを舞台に、あえのことを復元と変容の2つの形で執り行います。実施にあたっては、珠洲でも忠実に伝承していた珠洲市若山町の田中家の内容をもとに、震災後、実現可能なカタチでの実施。
1人目の継承者
14時から執り行うのは50年以上、珠洲で農業を営む浦野政行さん。母屋は全壊し、現在は仮設住宅で食らいしています。祖父の代までは、あえのことを執り行っていたそうで、なんとなくの記憶しかないと語っています。あえのことは、母屋の隣の納屋を綺麗にし、そこで実施します。


2人目の継承者
15時から行うのは、震災直後から珠洲へボランティアで入り、現在、金沢と2拠点生活を行っている岡嶋健市さん。週の半分は金沢でデザイナーとして、珠洲ではボランティア活動、ボランティアキャンプ運営をしながら、珠洲で有機米の栽培を行っています。あえのことを執り行う場所は、ボランティアキャンプ施設の一角に建てられた「インスタントハウス」です。
そう、名古屋工業大学大学院の北川啓介教授の研究をもとに、LIFULLと名古屋工業大学大学院による産学連携協定にて開発した新しい構築物。あの「インスタントハウス」で行います。


\ 人の想いを継承する文化 /
文化の概要
あえのこととは、一年の豊作の感謝と来年の豊作祈願をするため、田の神様を家に迎え入れ、食事やお風呂へ入れおもてなしをすることです。2009年にはユネスコの無形文化遺産にも登録された、奥能登の伝統的な農耕文化です。
田の神を祀る年間儀礼【あえのこと】
5月 田植え前/柄振り祭(2025年当プロジェクトにて実施)
5月 田植え後/庭まつり(2025年当プロジェクトにて実施)
9月 稲刈り後/刈り上げ祭(2025年11月23日 簡易的に実施予定)
12月5日 神迎え(実施予定)←無形文化遺産登録されている部分
2月9日 神送り(実施予定)←無形文化遺産登録されている部分



文化の課題
時代技術の進化や生活様式の変化により、能登であえのことを行っている家庭はほとんどないとされています。また、この度の能登半島震災により、珠洲で厳格な形式であえのことを行っていた田中家も、執り行う場を失いました。あえのことが持つ「自然への畏敬」と、「感謝の心」は、口頭伝承という形で受け継がれてきましたが、その民間儀礼としての実践は、現代の多忙な生活の中で年々困難さを増していました。
プロジェクトの背景と意義
本プロジェクトは、この農耕儀礼を、単なる「古いしきたり」としてではなく、「震災からの復興と、文化を未来へつなぐ希望の象徴」として位置づけます。特に、母屋が全壊したので隣の納屋や、被災地でボランティア拠点となったインスタントハウスを舞台にすることで、「あえのこと」が、場所や形式に依存せず、人々の心とともにあることを証明し、「現代社会で継承可能な新たな文化財保全モデル」を提示します。
儀礼の実施に向けた連携
合同会社かなざわざの代表でもある澤田雅美はローカルプロデューサーとして活動しており、金沢大学の観光デザイン学科の学生2名(インターン)と共同で、珠洲に伝承される「あえのこと」の儀礼を研究。50年前の資料や、震災前まで儀礼を執り行っていた田中家への取材に基づき、儀礼の精神性を最優先した「短縮プロトコル」を確立。かなざわざは、この新たな継承モデルを浦野様、岡嶋様両家にお伝えし、今回の「あえのこと」を実施いたします。
\\ あえのこと&直会 //
イベントの詳細
アエノコトin珠洲
日時:2025年12月5日(金)14:00-17:00
場所:石川県珠洲市三崎町高波カ部46
参加費:5500円
※震災時、珠洲市在住だった方は3300円
募集人数:12名
現地集合、解散
宿泊希望の方は別途5500円(朝食込み)
直会では、神様のお下がりと日本料理富成による「あえのこと膳」をご用意

今後の展望
あえのことを後世に伝える手段として、田の神様にお供えしていたあえのことの食事に着目し、より身近に文化を体感できるよう、インターンシップとして参加する2名の金沢大学生(金沢大学 観光デザイン学科2年 梅澤日加里、斉藤未郁)とともに「あえのこと弁当」の開発、販売を企画中。奥能登の里山里海に根付いた食事を現代的な解釈を交え再構築し、お弁当の試食会などの新たなイベント開催に向け、この取り組みをさらに発展させていきたいと考えております。
また、来春より、珠洲の農業ボランティアと文化体験をセットにして販売することで、人手と賑わいを生み出し、被災地でのボランティア創出、文化継承へと繋げていきたいと考えます。
奥能登農耕文化ツアー事務局とは
「珠洲ちょんがり研究会」会長の池谷内吉光氏と「合同会社かなざわざ」代表の澤田雅美氏が中心となり運営されています。この事務局は、奥能登の伝統文化を後世に継承することを目的として設立されました。特に、「外部との関わり」を持つ仕組みを取り入れることで、地域内の力だけでなく、外部からの関与を通じて文化継承を支えることを目指しています。
合同会社かなざわざとは
奥能登農耕文化ツアー事務局の企画運営を担う企業です。「文化をエンターテイメントに」をコンセプトに 文化継承の課題に対し、単なる保存ではなく、イベントやツアーといったエンターテイメント性の高い企画を通じて、人々が楽しく、積極的に関わる「新たな継承の形」を創り出すことを行っています。
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像