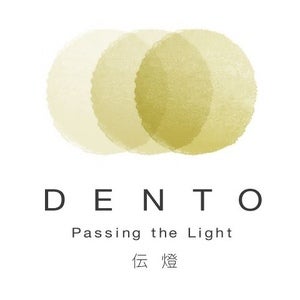伝統を未来に繋ぐ「第2回DENTOサポートプログラム」2025年度受賞者決定!
特定非営利活動法人DENTO(所在地:京都市右京区、代表者:ルガシ・アブラハム)は、日本の伝統工芸における担い手を支援することを目的に、2024年より「DENTOサポートプログラム」を実施しており、本年度第2回目となるプログラムの受賞者を下記のとおり決定いたしました。
2025年5月27日から6月30日までの公募期間において、全国の素晴らしい工芸事業者の皆様から合計21件のご応募を頂き、以下の団体/個人が一次審査を通過され、最終選考に進まれました。
ファイナリスト *50音順:
・井上 みどり(土佐手漉き和紙)
・GLASS-LAB株式会社(江戸切子)
・株式会社金剛組(宮大工)
・須佐 真(鎚起銅器)
・有限会社中村ローソク(和蝋燭)
・有限会社南條工房(京仏具、佐波理製鳴物神仏具)
・MORI KOUGEI(ツキ板工芸)
厳正な二次審査の結果、以下のとおり各賞の受賞者が決定いたしました。
若手職人支援(弟子育成)プログラム受賞者【3社】
株式会社金剛組

受賞者紹介文
金剛組は、1400年以上にわたり神社仏閣の建築に携わってきた、約100名の専属宮大工を擁する、世界最古の企業といわれています。
「宮大工」による伝統建築技術は、ユネスコ無形文化遺産にも登録された高度な技術であり、世界的にも高い評価を得ています。しかし、長年の修行と高度な専門性を要する稀少な技術であることから、現在、後継者不足が深刻な課題となっています。
この技術を未来へつなぐため、当社は2021年に若手職人育成のための「匠育成塾」を開設しました。20歳以下の塾生を対象に、現役の棟梁が講師となり、約6か月間にわたり実技と講義を実施。卒塾後は、各棟梁のもとで弟子入りし、実践を通じて技を深めていきます。 木組み・墨付け・道具の扱いといった基礎を体系的に学べる仕組みにより、塾生の理解と定着率の向上が実感されています。私たちは、日本建築の魂ともいえるこの技術を、これからも世界へ発信し続けてまいります。
審査委員会コメント
世界最古の企業として国内外で広く知られる同社の活動は、日本のサステナブルな企業の象徴とも言え、このような企業の後継者不足は日本にとって深刻な問題と言える。神社仏閣ほか日本の文化そのものを保存するために必要不可欠な技術や知恵を未来に繋いで行くことは、世界に対する日本の責務でもある。同社はすでに企業の将来を見据え、2021年に「匠育成塾」を開設しており、しっかりとしたビジョンを基に後継者の育成活動を行っており、DENTOとしては今回の選考が同社の将来への継続的な歩みの一助となることを祈念する。
有限会社中村ローソク

受賞者紹介文
京都西洞院二条で和蝋燭製造を始め、その地で7代1887年(明治20年)分家創業後、堀川三条の地で3代、昭和52年4月に現在の地、京都伏見で4代目として京都の地で11代、和蝋燭を手掛けております。和蝋燭は灯心と蝋で出来ております。当店が作る和蝋燭は植物蝋と和紙にイ草の髄を巻き付けた芯から出来ております。現在は原材料のハゼの栽培や昔ながらの販売方法からの脱却も進めながら神社仏閣から家庭用を提供致しております。歌舞伎や能・狂言・舞の舞台やお茶席や夜咄の際には数寄屋蝋燭と言う特別な和蝋燭の制作も致しております。絵ろうそくの制作も致しており、火を点さず花の代わりとしての使用や記念品・贈答品としての和蝋燭本来の使用方法などを語り伝える事も行っております。
審査委員会コメント
和蝋燭が代表する日本の灯りの文化は、谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」を引用するまでもなく、日本独自のもので長い歴史の中で醸成され、日本人の空間や光に対する美意識を形成してきた。ただ明治以降の近代化とともに、灯りはより機能的で便利な光源に置き換えられ、和蝋燭の使用は衰退の一途を辿っており、現在はその生産活動すらが、消滅しかねない状況にある。このような中、中村ローソクは現存の数少ない和蝋燭の生産者であるだけでなく、和蝋燭の再興のために孤軍奮闘の活動を行っている。これからも和蝋燭の伝統と日本独自の灯りの文化が継承されるべく、中村ローソクの弟子育成活動を支援することとした。
有限会社南條工房

受賞者紹介文
南條工房は、江戸時代後期の1800年ごろ京都で創業し、「鳴物(なりもの)」と呼ばれる仏具・神具の製作を専門に、200年以上にわたり技術と感性を受け継いできました。すべての製品に銅と錫の合金「佐波理(さはり)」を用い、鋳型づくりから鋳造、仕上げまでのすべての工程を一貫して手作業で行っています。工房独自の配合比率と、薪を使った焼型鋳造により、佐波理の特性を最大限に引き出し、唯一無二の音色を生み出します。現在も国内で唯一、この伝統的な技法でおりんを製作しています。
2019年には、自社ブランド「LinNe(リンネ)」を立ち上げ、暮らしの中で自由に音色を楽しむ製品の開発や、アーティストとのコラボレーション、ワークショップの開催などを通して、伝統の音色を現代に届け可能性を広げる活動を展開。2023年には体験型ギャラリー「LinNe STUDIO」を併設、音色と文化の魅力を広く発信しています。
審査委員会コメント
本工房は鳴物神仏具を独自の伝統的な製法で生産しており、日本の文化に根付く音を担っている。現在では神仏具以外での用途のための商品も提案するほか、ファクトリーショップの開設、工場見学ツアーへの対応など、積極的に多面的な新しい取り組みを行い、事業の安定化を図っている。また製品の性格上、複数の職人が協力して作業を行うことから、計画的な職人確保が事業継続には不可欠で、弟子育成のための体制の構築を進めている。同工房の将来に向けたビジョンと持続可能な取り組みの実現のために、支援を行っていきたい。
DENTOアワーズ:工芸アワード(商品・作品)受賞者【2名】
須佐 真


受賞者紹介文
新潟県三条市にて金工作家として活動しています。 本作は、32年間の鎚起銅器職人としての技術をもとに、干支の巳をテーマに制作しました。摘みは純銀を叩いて成形し、目には18金をろう付け。蓋は黒味銅に透かし模様、胴は銅に錫を塗り、脚は真鍮を使用しています。全体に蛇柄の鎚目を施しつつ、色味と素材の調和に配慮しました。 近年は、伝統技法を生かしながら革新的な作品づくりに挑戦しています。今後も独自の表現を追求し、工芸に携わる方々に刺激を与えられる存在を目指してまいります。このたびは誠にありがとうございました。
審査委員会コメント
鍛蛇の目槌文香炉「巳刻」
伝統的な鎚起銅器の高度な技術を見事に継承しているだけでなく、そこに現代的な感性をスタイリッシュに表現している。素材の持つ特性とその美しさがひとつのオブジェとして際立っており、成熟した作家としての技量の豊かさを物語っている。まさに伝統工芸の現代の形として、今回のアワードに相応しい作品として評価された。これからもこの鎚起銅器の伝統技術を継承しつつ、未来に向けて更に新しい分野での作品づくりへのチャレンジにも期待したい。
MORI KOUGEI


受賞者紹介文
1953年創業、徳島の森工芸は、天然木を紙のように薄くスライスした「ツキ板」を用いた化粧合板の製造を専門に、建具や家具分野で高い技術を培ってきました。2020年より独自ブランドによる製品開発を開始し、伝統と現代の融合を志向する木工プロダクトを展開しています。藍漆PLATEは、徳島の伝統産業である藍と、日本の誇る漆を掛け合わせた新しい表現であり、阿波藍の粉末と生漆を用いた深く複雑な色合いが特徴です。天然素材の可能性を見つめ直しながら、地域に根ざした技術と文化を未来へつなぐ「次世代の工芸」を模索しています。
審査委員会コメント
藍漆 PLATE
森工芸はツキ板の従来の技法の追求にとどまらず、藍漆という独自の塗料との組み合わせによって、今までにない独創的な作品を作り上げた。このように伝統的な技術を更に進化させ新しい価値を生む試みこそは、現代の伝統工芸に今最も必要とされていることであり、大いに評価したい。特に他の伝統工芸の技法との新しい掛け合わせは、日本の伝統工芸に新たな可能性を感じさせる。今回の応募作品は大変高度な技術と共に、今までにない新鮮な風合いをもたらした完成度の高い作品として選出に至った。
DENTOアワーズ:クリエイティブ・アワード(新商品アイデア)
残念ながら、受賞該当者はございませんでした。
DENTOでは、今回の各賞の授与を契機に、少しでも日本の伝統工芸の継承と発展に寄与出来る事を心から願っております。
なお、来年度も同様の支援プログラムを実施予定です。ご関心・ご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。
「第2回DENTOサポートプログラム」2025年審査員:
ルガシ・アブラハム
齋藤 峰明
西堀 耕太郎
特定非営利活動法人DENTO
所在地:〒615-0092 京都市右京区山ノ内宮脇町15-1クエスト御池2F
設立:2021年11月
Mail: info@dento-japan.co.jp
Tel: 080-4134-2606
FAX: 050-3730-9607
すべての画像