読む気のしない紙からの挑戦。草加市広報、全国が注目
人に情報を伝えることの意味を、ゼロから問い直した1年。

かつて、草加市の広報紙は「読まれずに捨てられる紙」だった。
内容は正しく、情報はきちんと載っている。
それでも、読んでほしい市民には十分に届いていなかった。
その現実を、誰よりも悔しく思っていたのは、つくっていた当人たち──広報課でした。
主導したのは、草加市役所広報課の安高昌輝と西田翼。
現場の空気を読み、全体を動かした安高。
構造から仕組みを設計し直した西田。
ふたりの視点と技術が交差したとき、草加市の広報は変わり始めた。
そしてその取り組みが、2025年、全国広報コンクールでの表彰というかたちで評価された。
──だが、それは「成果」ではなく「通過点」だった。
悔しかったのは、伝える責任を果たせないこと
以前の草加市の広報紙には、特集がなく、写真は少なく、余白もなかった。
税や手続き、災害への備え──暮らしに必要な情報は載っていた。
だが、文字だけの情報紙はあまり読まれていなかった。
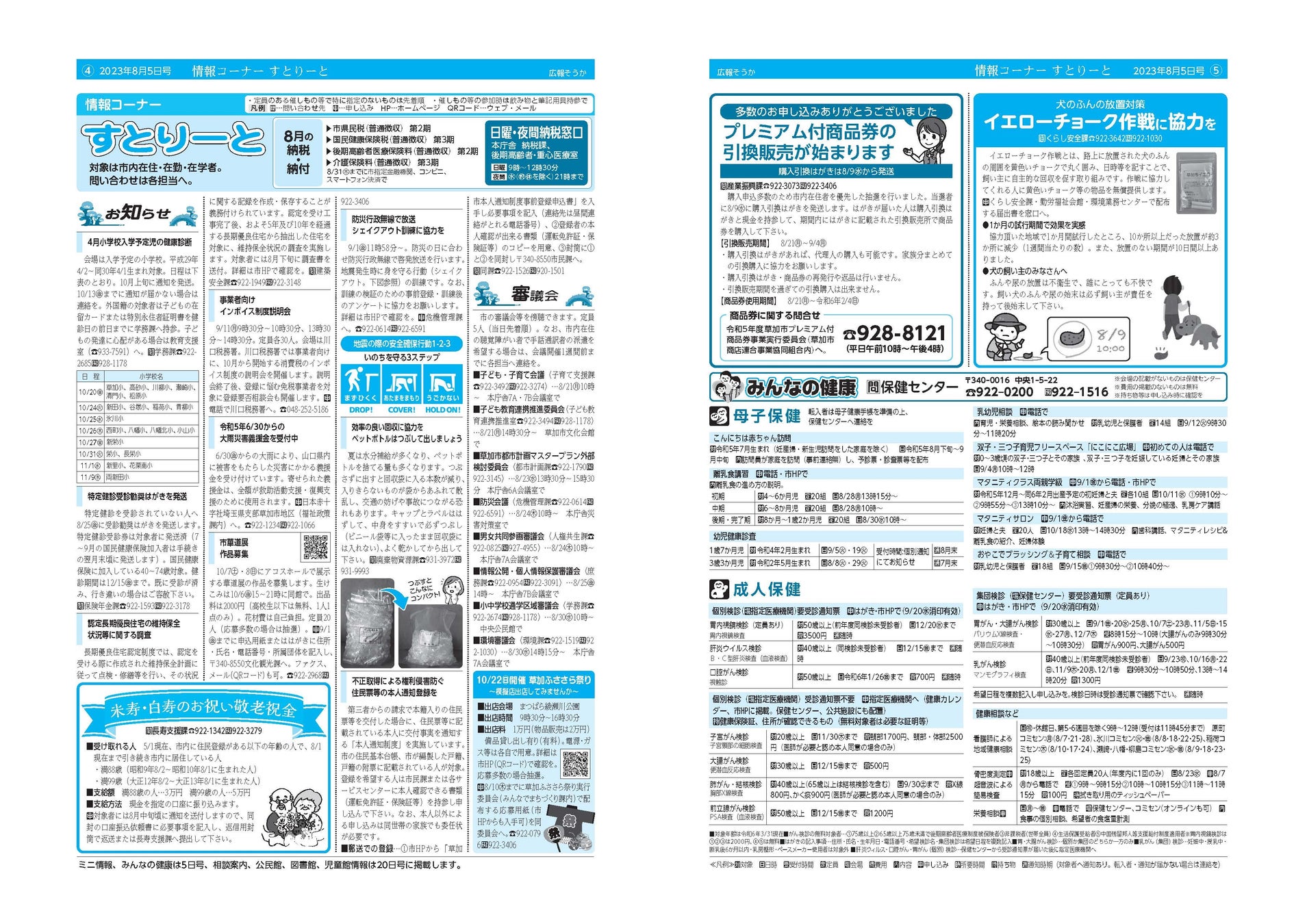
「このままだと、市民にとって不利益になる。
それがいちばん悔しく感じていました。」(安高)
当時の担当者たちは、正確に、丁寧に、すべてを伝えようとしていた。
でも、「伝える」と「届く」は違っていた。
その違和感が、草加市の広報改革の出発点になった。
伝えたのに、届かない──その違和感から始まった
最初に見直したのは、紙面の構成だった。
「なぜこの情報を載せるのか」「誰に届けたいのか」──
そうした問いから、見出し・写真・余白・トーンまですべてを組み直した。
この設計を担ったのが、広報課の西田。

「出すだけでは伝わらない。
“読まれる設計”がなければ、届くことはないと思いました。」(西田)
単なるリニューアルではなく、広報という“設計思想”そのものを問う作業だった。
最初に壊したのは、“これまでの常識”
紙面だけでは足りなかった。
草加市は、「情報の集まり方」自体を変えた。
それまで、全課から依頼のあった記事をすべて掲載していたルールを見直し、
依頼件数に上限を設定。
これにより、「なぜこの情報を出すのか」を問う設計に切り替えた。

「情報は、出せば出すほど伝わるわけじゃない。
戦略なき発信は、“していない”のと同じ。
それを全庁に根づかせるために、あえて制限をかけました。」(西田)
情報を削ることは、勇気のいる決断だった。
でも、それが「伝える力」を生み出すことにつながった。
そして少しずつ、市民からの声が届く
すぐに結果が出たわけではない。
けれど、少しずつ変化はあらわれた。
「今回の特集楽しかった」
「前よりわかりやすい」
「冷蔵庫に貼ってある」
記事の中身だけでなく、「紙面そのもの」に感想が届くようになった。
市民の暮らしの中に、広報紙が“戻ってきた”感覚があった。
全国表彰──でも、そこが終わりではない
草加市は、令和7年全国広報コンクール審査結果において、
-
映像部門:全国2位
-
広報紙部門:埼玉県1位
これは、広報紙のリニューアルから“わずか1年以内”での快挙だ。
紙面の構造を見直し、仕組みを整え、
届け方をゼロから設計し直した日々。
その積み重ねが、初めて“外からも”評価された。
だが、安高はこう語る。

「これは終わりじゃない。
やっと、スタートラインに立てただけです。」(安高)
伝わらない広報には、もう戻らない
2025年度、草加市広報課には専属デザイナーが初めて配属された。
設計、構成、言葉、写真──
“届くための設計”が、体制として本格化した。
情報は、出すだけでは伝わらない。
届けるための構造を、これからも問い続ける。
伝えることの意味を、ゼロから問い直した1年。
そこから始まった広報の挑戦は、今も続いている。
草加市のコンテンツは、以下のとおり
【関連記事】
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像