〜容器の地産地消ならぬ“月産月消”の実現に向けて〜 東洋製罐グループ、月面の砂と同組成の模倣土を基にガラスの生成に成功
東洋製罐グループは、より豊かな社会の実現を目指すプロジェクト「OPEN UP! PROJECT」の一環として、地球と宇宙の食の課題を解決する共創プログラム『SPACE FOODSPHERE』に参画しており、この度、月面の砂と同組成の模倣土を基にしたガラスの生成に成功したことをお知らせいたします。
 月面の砂と同組成の模倣土を基に生成されたガラス。鉄分が多いため光沢のある濃い黒色が特徴。
月面の砂と同組成の模倣土を基に生成されたガラス。鉄分が多いため光沢のある濃い黒色が特徴。
■取り組みの背景
創業100年を超える東洋製罐グループでは、次の新しい100年を創造するべく、様々な課題に向き合うことでイノベーションを起こし、より豊かな社会の実現を目指すプロジェクト「OPEN UP! PROJECT」を2019年より始動しており、その一環として地球と宇宙の食の課題を解決する共創プログラム『SPACE FOODSPHERE』(https://spacefoodsphere.jp/)に参画しております。『SPACE FOODSPHERE』では、月面基地における「循環」・「地産」・「QOL(Quality of Life)向上」の実現を目的として、 2040年代に月面基地に1,000人が居住することを想定し、 地球と宇宙の食の課題解決を目指しています。東洋製罐グループとしては、宇宙環境での生活を、 "容器”の領域でサポートすることを検討しています。
■今回の取り組みについて
この度、これまで培ってきた技術力やノウハウを活用して、月面の砂と同組成の模倣土から、多くの容器に活用できるガラスを生成することに挑戦し、ガラス化に成功いたしました。これにより、地球の枯渇資源を使用することなく、ガラス容器を月で生産できる可能性があることが判明いたしました。ガラス容器は、高温で溶かすことで繰り返し再生できるため高いリサイクル率を実現しています。資源が限られている宇宙環境においては、資源を再利用して循環させる必要があり、ガラスの活用は有効な手段と言えます。
生成に成功したガラスは、鉄分が多く含まれているため、光沢のある濃い黒色が特徴となっています。ガラスの生成過程において鉄などの不純物を取り除く地球上の技術を応用することで、宇宙空間でガラスだけではなく鉄も生成できる可能性があります。資源の限られた宇宙空間で様々な素材を活用したプロダクトの展開も検討しています。
さらに、将来的には容器の地産地消ならぬ、"月産月消”を目指し、月という環境下でどのような容器や食器の開発が実現可能なのか、太陽光の熱などを使ってガラスを作るなど宇宙ならではの製造方法の模索や実験を行い、新たなイノベーションを目指して参ります。ガラスの食器を使用した地球上と同様の食卓を宇宙空間でも実現することで、宇宙での生活のQOL向上にも寄与したいと考えています。
SPACE FOODSPHEREについて
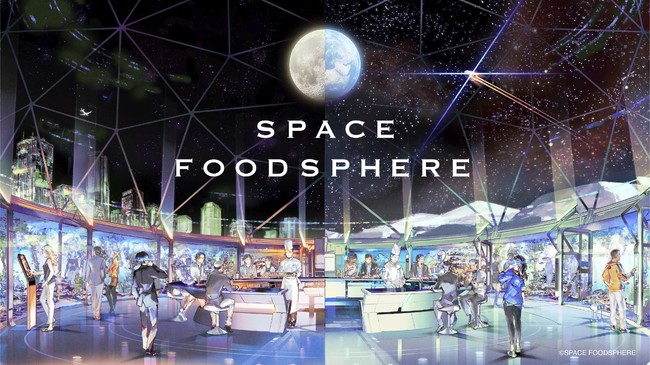
・プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000036405.html
・ウェブサイト:https://spacefoodsphere.jp/
・YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCMTsXSuvhn3WI02V7skEauw
「OPEN UP! PROJECT」について

そして今、人々が同じものを使い、食し、同じ生き方を求める“大衆の時代”から、それぞれが選んだ生き方を求める“個の時代”へと変化しています。その中で東洋製罐グループは、次の100年を創造するべく、大衆にとどまらない細かなニーズと一人ひとりが抱える課題に向き合うことでイノベーションを起こし、より豊かな社会の実現を目指すプロジェクト「OPEN UP! PROJECT」を発足いたしました。
(「OPEN UP! PROJECT」公式サイトURL:https://jp.open-up.tskg-hd.com/ideas/regolith/)
会社概要
会社名:東洋製罐グループホールディングス株式会社
創立 :1917年(大正6年)6月25日
代表者:取締役社長 大塚一男
本社 :〒141-8627東京都品川区東五反田二丁目18番1号大崎フォレストビルディング
URL :https://www.tskg-hd.com/
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
