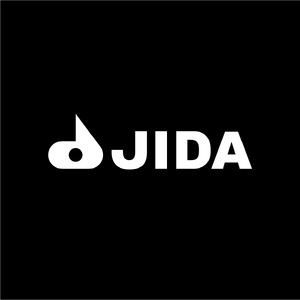デザインで日本を覚醒させる『医療課題と伝えることの難しさ』トークイベントを11月14日(金)開催!医療・工学・デザインの専門家が分野を越えて集結、インダストリアルデザインを社会と産業を動かす力へ
拡張するデザイン領域でデザインを社会に啓蒙するJIDA(公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会)は、医療・工学・デザインの専門家による『医療課題と伝えることの難しさ』トークイベントを開催します。

拡張するデザイン領域でデザインを社会に啓蒙する公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会 (本社:東京都港区、理事長:村田智明、以下JIDA)は、医・工・デザイン連携研究部会による『医療課題と伝えることの難しさ』トークイベントを東京ミッドタウン・タワー5階インターナショナル・デザイン・リエゾンセンターにて、2025年11月14日(金)開催します。
■申込先:https://jida-ikoudesign-seminar2025.peatix.com/view
現代の医療現場では、「正しく伝えること」「相手に届くこと」が大きな課題となっています。医師と患者、開発者と医療従事者、研究者と現場など、立場の違いによって意思疎通が難しくなる場面は少なくありません。本イベントでは、医療・工学・デザインの専門家がそれぞれの立場から「伝えることの難しさ」を語り、今後の協働や改善のヒントを探り、分野を越えて学び合います。
異なる分野から第一線で活躍する専門家が集結し、それぞれの現場で直面している課題や取り組みを共有します。医療の現場は一見特殊に見えますが、そこには、他の分野のコミュニケーション改善にも通じる多くの学びが詰まっています。また、参加者同士によるグループディスカッションを通じて、立場の異なる人と意見を交わしながら課題を共有し、自身の取り組みを新たな視点から見つめ直す機会にもなります。
デザインは、未来を構想し、それを人々に疑似体験させる力を持っています。その力こそが、投資や政策、技術を動かし、社会を前進させる起爆剤となります。JIDAは、これからの時代にふさわしい「社会に効くデザイン」を掲げ、実装と発信の両面からその価値を高め、産業と社会の進化発展に貢献します。
『医療課題と伝えることの難しさ』トークイベント開催概要
現代の医療現場では、「正しく伝えること」「相手に届くこと」が大きな課題となっています。医師と患者、開発者と医療従事者、研究者と現場など、立場の違いによって意思疎通が難しくなる場面は少なくありません。本イベントでは、医療・工学・デザインの専門家がそれぞれの立場から「伝えることの難しさ」を語り、今後の協働や改善のヒントを探ります。
■日時:2025年11月14日(金)13:00〜18:30
■申込先:https://jida-ikoudesign-seminar2025.peatix.com/view
※申込締切: 2025年11月13日(木)17:00
■会場:東京ミッドタウン・タワー5階インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター
(東京都港区赤坂9-7-1)
■定員:50名
■参加費(税込): JIDA会員 3,300円/一般 4,400円/学生会員 1,100円/一般学生 2,200円
■内容:
13:00~13:10 オープニング・趣旨説明 安原 七重(JIDA医・工・デザイン連携研究部会 部会長)
13:10~13:35 テーマ① 医療従事者の立場から:伝わらない現場の実感と限界 松月 正樹(三重大学医学部附属病院 臨床工学部)
13:35~14:00 テーマ② 医療情報システム開発者の視点:電子カルテ開発後の課題と苦悩 宇野 裕(日本電気株式会社 バイオメトリクス研究所)
14:00~14:25 テーマ③ デザイン研究者の視点:患者説明支援ツールの設計と導入事例 渡邊 敏之(東京理科大学 先進工学部)
14:25~14:50 テーマ④ UI/UXデザイナーの実践:現場と設計の“翻訳”に挑む 村木 朋子(株式会社ジャイロ)
15:00~16:10 参加者グループディスカッション&発表
16:20~16:50 パネルディスカッション(登壇者全員)
17:00~18:30 ネットワーキング(ドリンク&軽食提供予定)
■登壇者プロフィール(一部抜粋)
・松月 正樹(三重大学医学部附属病院 臨床工学部 主任臨床工学技士)
医療機器の調達・運用・廃棄計画を含む管理業務に従事。
・宇野 裕(日本電気株式会社 バイオメトリクス研究所 研究員)
医療分野における自然言語処理の応用研究を推進。「MegaOak AIメディカルアシスト」を製品化。
・渡邊 敏之(東京理科大学 先進工学部 機能デザイン工学科 教授)
医療とデザインの融合をテーマに研究。デザイン学・メディアデザイン専門。
・村木 朋子(株式会社ジャイロ ディレクター/デザイナー)
15年以上にわたり医療機器のUI/UXデザインに従事。現場観察を重視した実践的デザインを推進。
■主催: 公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)
プロフェッション委員会/医・工・デザイン連携研究部会
■協力:公益財団法人日本デザイン振興会
■お問合せ先:JIDA事務局 jidasec@jida.or.jp または 03‐3587‐6391
【JIDA医・工・デザイン連携研究部会について】
日本の医療機器・ヘルスケア用品における デザインの質の向上 と 啓発活動の推進を目的としています。医療機器やヘルスケア用品のデザインに実績を持つメンバーを中心に、現場の課題に寄り添いながら活動を進めています。デザインの視点がまだ十分に取り入れられていない業界や開発者に対して、価値を伝えていくことも部会の大切な役割です。また、医療現場の実態を理解するために、医療従事者からの助言を受けられる体制づくりにも取り組んでいます。
JIDA(公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会)について

Designing beyond Design
Create a Mindful Future, Together.
JIDA(公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会)は、1952年に日本で初めての全国デザイン 団体として産業デザイン(インダストリアルデザイン)を振興するために発足された公益社団法人です。インダストリアルデザインは時代の中で常に新たな役割を果たして来ました。その専門性を継承し、変革の針路を探求しつつ、社会環境やビジネスなどに新たな価値を創造することが私たちの使命と考えています。2021年には協会名を現在の公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会に改名、「Designing beyond Design Create a Mindful Future, Together.」というビジョンを掲げました。拡張するデザイン領域の中で、デザイナーの職能にとどまらず、広くデザインを社会と国民に啓蒙する公益社団法人として日々活発なコミュニティをつくって活動しています。

■JIDA会員構成 https://www.jida.or.jp/members
私たちは心豊かな未来を目指し、生活や体験そしてサービスへと拡がるデザイン領域を視野に多分野の 専門家・教育・行政関係・経営者などと連携し、産業と社会の進化発展に寄与する共創活動を行います。
▶正会員:個人約500名、団体・法人約20社
本協会の主旨に賛同し、インダストリアルデザイン及び関連する専門業務に、3年以上携わった経験を 有する個人
▶賛助会員:法人・団体約70社、個人約20名
▶学生会員:年度毎
JIDA入会について https://www.jida.or.jp/about/join
【理事長挨拶】
「プロダクトデザインを、社会と産業を動かす力へ」
長年にわたりプロダクトデザインの分野で社会課題の解決や企業変革に関わってきた中で、今あらため て強く感じているのは、デザインが社会に与えるべき本質的なインパクトとは何かという問いです。
JIDAは1952年、戦後復興と高度経済成長のさなかに、日本の工業製品の質的向上とデザインの社会的 価値の確立を目的に設立されました。以来70年以上にわたり、製品デザインの専門家集団として、工 業、流通、生活文化、教育、行政と多様な領域に働きかけ、日本の産業と生活を支えるプロフェッショ ナル・ネットワークを築いてきました。これまで歩んできた歴史の延長線上にあるのは、「よりよい未来をデザインによって実装する」という揺るぎない使命です。
世界を見渡せば、プロダクトデザインがイノベーションの起点となり、経済や文化の変革を牽引している事例が数多く見られます。その原動力は、未来の暮らしや製品、サービスの姿をビジュアルに可視化し、人々に共感と行動を促す力にあります。日本でも、そうしたデザインの本質的価値をもっと社会全体に浸透させていく必要があります。
いま求められているのは、造形や演出にとどまらず、複雑な課題に応答する統合的な「知と感性」を備 えたデザイナーです。JIDAは、こうした次世代型のハイブリッド人材を育成する環境づくりにも注力 し、社会を変えるためのビジョンと行動力を持った仲間を増やしてまいります。
デザインは、未来を構想し、それを人々に疑似体験させる力を持っています。その力こそが、投資や政策、技術を動かし、社会を前進させる起爆剤となります。JIDAは、これからの時代にふさわしい「社会に効くデザイン」を掲げ、実装と発信の両面からその価値を高めていきたいと考えています。未来を描き、行動を誘発するデザインの力を、会員の皆さまと共に育んで、広げていきましょう。
公益社団法人 日本インダストリアルデザイン協会 理事長 村田智明

大阪市立大学工学部応用物理学科卒。三洋電機デザインセンター退 社後、1986年ハーズ実験デザイン研究所を設立。現在はデザイン思 考から企画デザイン開発をサポートするデザインシンクタンクとし て活動。「デザイン思考」の実践的なメソッドとして「行為のデザ イン思考法」のSSFB法や「感性価値ヘキサゴングラフ」などを提 唱している。Gマーク金賞、DFAグランプリ、RED DOT BEST OF BEST、ジャーマンデザインアワードWINNER賞、iF DESIGN AWARD GOLDなど国内外のデザインアワードで219点を受賞。またオムロンの血圧計「スポットアーム」やMicrosoft「Xbox360」の実績が評価され、Newsweekの「世界が注目する日本の中小企業100社」に選定される。コンソーシアムブランド「METAPHYS」では、技術のデザイン化から販売までを実践している。また、経産省・中小企業基盤整備機構の「感性価値創造ミュージアム」や東京都美術館の新伝統工芸プロデュース事業「TOKYO CRAFTS & DESIGN」、越前打ち刃物コンソーシアム「iiza」など、伝統工芸や地域振興にも多く携わる。「ソーシャルデザイン」という言葉を生み出しその啓蒙に努めている。 2024年7月、CJIDCの協力で蘇州市に「行為のデザイン博物館」が常設開設された。著書に『ソーシャルデザインの教科書』、『問題解決に効く行為のデザイン思考法』、『感性ポテンシャル思考法』、『バグトリデザイン』などがある。
「JIDAデザイン検定」について

JIDAデザイン検定(旧:PD検定)は「プロダクトデザインを中心としたデザインに関する基礎知識習得の指標」としてJIDA(公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会)により運営されている検定です。
https://jida-design-kentei.studio.site/




このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像