ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展と同時開催で「GO FOR KOGEI」が挑む新展『身体と物質のエスノグラフィー―加速社会における遅さと深さ』
秋元雄史キュレーションのもと「工芸的アプローチ」を通じて現代美術の新たな視座を提案

2020年から毎年北陸で開催し好評を博してきた「GO FOR KOGEI」を主催する認定NPO法人趣都金澤は、第61回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の開催にあわせ、GO FOR KOGEI アーティスティックディレクター・秋元雄史のキュレーションによる展覧会『身体と物質のエスノグラフィー―加速社会における遅さと深さ』を、2026年5月9日(土)から11月22日(日)まで、イタリア・ヴェネチアのパラッツォ・ピザーニ・サンタ・マリーナにて開催します。
はじめに
秋元雄史(本展キュレーター、GO FOR KOGEIアーティスティック・ディレクター)
本展は、情報と消費が加速度的に拡大する現代社会において、「つくること」という行為に内在する、もう一つの時間感覚と身体的な知覚を回復しようとする試みである。ここで扱われるものは、「工芸的アプローチ」あるいは「工芸的感性」と言い換えることができるだろう。
本展は、工芸を一つのジャンルとして位置づけるのではなく、あえて工芸的な態度を批評的なレンズとして用い、現代美術そのものを読み替え、再解釈することを目指している。
本展には、国内外で活躍する10名の日本人アーティストが参加する。彼ら/彼女らの多様な実践を通して、本展は、物質との深い関与、身体に根ざした知、そして身振りの緩やかな蓄積に基づく、現代美術の新たな理解を提示する。それは、速度、可視性、即時的な流通を重視する支配的な価値体系に対する、静かながらも確かな問いかけとなるだろう。出展アーティストは、沖 潤子、川井雄仁、桑田卓郎、コムロタカヒロ、シゲ・フジシロ、舘鼻則孝、中田真裕、三嶋りつ惠、牟田陽日、綿 結である。
開催概要
展覧会タイトル|身体と物質のエスノグラフィー―加速社会における遅さと深さ
会期|2026年5月9日(土)‒11月22日(日)(休場:火曜)
時間|11:00-19:00(5月9日‒9月30日)、10:00-18:00(10月1日‒11月22日)
会場|パラッツォ・ピザーニ・サンタ・マリーナ ヴェネツィア市カンナレージョ地区6104(イタリア)
入場|無料
プレビュー|2026年5月6日(水)-5月8日(金)11:00-19:00
キュレーター|秋元雄史 GO FOR KOGEI アーティスティックディレクター
アーティスト|沖 潤子、川井雄仁、桑田卓郎、コムロタカヒロ、シゲ・フジシロ、
舘鼻則孝、中田真裕、三嶋りつ惠、牟田陽日、綿 結(五十音順)
主催|認定NPO法人趣都金澤
助成|クリエイター支援基金
特設サイト|https://venice.goforkogei.com/jp/
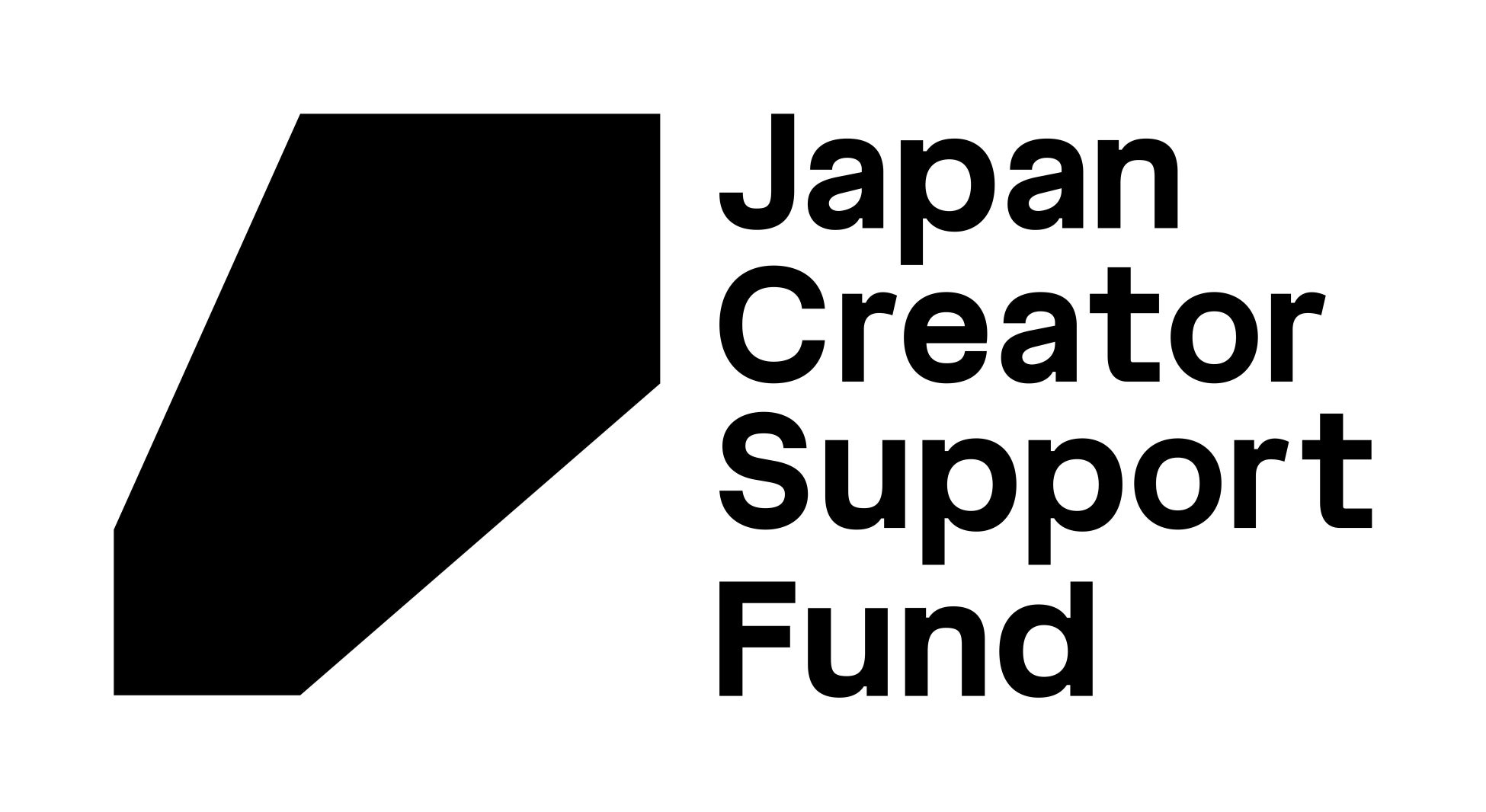
展覧会の見どころ
1.コンセプトと作品
本展『身体と物質のエスノグラフィー――加速社会における遅さと深さ』は、情報と消費が瞬時に循環する現代において、「つくること」に宿るもう一つの時間感覚と身体的知覚に光を当てる展覧会である。本展が掲げる「エスノグラフィー(民族誌)」とは、素材に向き合い、手を動かし、時間をかけて制作を行う作家たちの実践を、文化的・社会的な営みとして読み解く視点を指している。
出品作家は、陶、ガラス、漆、繊維、刺繍、木彫といった多様な素材を扱いながら、それぞれ異なる「遅さ」や「深さ」を作品に刻み込む。
桑田卓郎は、磁器に生じる偶発性や破綻をあえて引き受け、完成と崩壊のあわいを可視化する。川井雄仁は、土と重力、身体のバランスの関係を通じて、形が生まれる瞬間の緊張を彫刻として定着させる。
コムロタカヒロは、都市文化やサブカルチャーのイメージを拡張された彫刻として立ち上げ、崇拝と消費の境界を揺さぶる。
また、牟田陽日は絵付けの工程を通して自然への感情を陶に描き込み、沖 潤子は刺繍という反復行為によって布に生活の時間を縫い込む。綿 結は糸の撚りや重力を手がかりに、身体的スケールを超える繊維彫刻を生み出し、中田真裕は幾層にも塗り重ねた漆の中に、記憶の揺らぎと時間の沈殿を可視化する。
ガラスという透明な物質を用いる三嶋りつ惠は、光そのものを彫刻化し、空間と一体化する作品を提示する。シゲ・フジシロは、ガラスビーズによる膨大な手作業を通して、消費社会の記憶や労働の時間をきらめく表層に刻み込む。さらに舘鼻則孝は、伝統的装飾文化を現代的に再構築し、身体と装い、儀礼と時間の関係を問い直す。
本展の見どころは、これらの作品が「すぐに理解される意味」を提示するのではなく、鑑賞者に時間をかけた関与を求める点にある。歩き、立ち止まり、視点を変えながら素材と向き合う体験を通して、鑑賞者自身の身体もまた、この小さなエスノグラフィーの一部となるだろう。
2.建築を読む展示

本展の会場となる パラッツォ・ピザーニ・サンタ・マリーナは、ヴェニスの旧市街サンタ・マリーナ地区に位置する歴史的な貴族邸宅であり、水の都ヴェニスが育んできた都市構造と建築文化を現在に伝える建物である。ヴェニスの街並みは、運河と路地が複雑に絡み合う有機的な構造を特徴とし、建築は単体として完結するのではなく、都市の流れや人の移動と密接に結びついてきた。パラッツォとは、そうした都市の中で、居住、社交、商業、政治が重なり合う場として機能してきた存在である。
本展では、このパラッツォが内包する「建築の時間」を積極的に読み込み、展示の前提条件として捉える。空間をホワイトキューブ化するのではなく、建築に刻まれた歴史や素材の触覚性をそのまま引き受けることで、工芸的な制作態度がもつ遅い時間や身体に根ざした知覚が、建築と共鳴する場を立ち上げる。
3.建築家と展示デザインの特徴

本展の展示構成は、世界各地の美術館建築や展示デザインを手がけてきた建築家 クラパット・ヤントラサスト(Kulapat Yantrasast)が担当する。彼は近年、メトロポリタン美術館やディブ・バンコクなどにおいて、既存建築の歴史性を尊重しながら、鑑賞者の身体的な移動や視点の変化を重視した展示空間を構築してきた。本展においても、その設計思想は、ヴェニスの歴史的パラッツォがもつ空間の層と時間性を読み解くことから始まっている。
クラパットは、会場に足場(スキャフォールド)という仮設的な構造体を挿入することで、床面だけに限定されない立体的な動線を生み出す。この視点の連続的な移動は、固定された展示順路や一方向的な鑑賞体験を解体し、空間そのものを読み替える行為へと鑑賞者を導く。足場は単なる機能的装置ではなく、建築に新たなレイヤーを一時的に重ねる存在として機能する。工芸的な制作に内在する「途中であること」「積み重ねられる時間」と、歴史建築に沈殿した時間とが交差することで、本展は、完成された展示空間ではなく、生成し続ける場として立ち現れる。クラパットの展示構成は、建築・作品・身体の関係を再編し、時間を体験するための装置として空間を再定義する試みである。
アーティスト紹介
沖 潤子
沖 潤子は、刺繍という反復的な手仕事を通して、布に生活の時間と身体の記憶を縫い込む作家である。その制作は、長らく家庭の内部に属するとみなされ、可視化されにくかったフェミニンな労働の時間を、作品として静かに立ち上げる。本展では、パラッツォ2階のかつて居間として使われていた空間に作品を展示し、大きな窓から差し込む自然光、鏡やシャンデリアと呼応させる。
親密で私的な空間において、刺繍された布は装飾ではなく、日々の生活の中で積み重ねられてきた感情や記憶の堆積として知覚される。光の移ろいと鑑賞者の移動に伴い、布の陰影や質感は変化し、家庭という場に内在する静かな労働の時間が、身体的な感覚として呼び覚まされる。沖の作品は、居間という空間を通して、ケアや反復、沈黙を含んだ制作行為の価値を、あらためて問いかけている。


川井雄仁
川井雄仁は、陶を単なる素材としてではなく、欲望や虚構、アイデンティティの揺らぎを投影する媒体として用い、過剰な色彩と量感を伴う造形を展開してきた。その背景には、1990年代の原宿文化やストリートファッション、マスメディアが生み出したイメージへの強い影響がある。消費的で甘美な表層と、現実との乖離が生む違和感や不安定さが、川井の作品には常に併存している。
本展では、装飾的な内装をもつ部屋が連なるパラッツォの中にあって、あえて倉庫として使用されていた簡素な室内空間を展示場所として用いる。華やかな装飾を欠いたこの空間において、川井の作品は、重厚な壁や床と直接対峙しながら配置される。液体を滴らせる陶磁作品は、固体であるはずの陶に流動
性と湿度を与え、欲望が滲み出し、循環するプロセスを可視化する。装飾性を抑えた空間だからこそ、作品の過剰な色彩や質量感は強調され、鑑賞者は甘美さと不穏さのあいだを往還することになる。


桑田卓郎
桑田卓郎は、陶芸における伝統的技法や形式を意図的に過剰化し、器と彫刻、日常と非日常の境界を攪拌する実践を続けてきた作家である。貫入、石はぜ、釉薬の流動や破裂といった、通常は欠点や失敗とみなされがちな現象を積極的に引き受けることで、完成と崩壊が同時に立ち現れる造形を生み出してきた。その作品は、用のための器でありながら、制度化された陶芸の枠組みを逸脱する彫刻的存在として振る舞う。
本展では、足場によって分節化された展示空間の中で、桑田の作品がパラッツォの漆喰壁や石床と直接対話する。ひび割れや釉薬の奔流は、建築に刻まれた経年の痕跡と共鳴し、制作行為に内在する「事故」や「破綻」を、建築が抱え込む老いの時間と重ね合わせる。均質な展示空間では見過ごされがちな不安定さや歪みは、ここではむしろ可視化され、作品はパラッツォそのものが孕む不均質な時間性を浮かび上がらせる装置として機能する。桑田卓郎の実践は、陶芸という制度の内側から、その価値と時間の在り方を根源的に問い直している。


コムロタカヒロ
コムロタカヒロは、ソフビ玩具やSF的イメージ、アメリカンコミックスといった視覚文化を起点に、木彫彫刻と量産フィギュアを横断する独自の彫刻表現を展開してきた。本展では、グランドフロアの入口空間を舞台に、高低差のある足場が組まれ、その上にコムロの世界が立ち上がる。鑑賞者は、見上げ、見下ろし、回り込むという身体的な移動を通して、作品と出会うことになる。
足場によって生まれる高さや俯瞰の視点は、作品を単なる「玩具の拡大」から、崇拝や神話を想起させる像へと変容させる。歴史的なパラッツォの中に突如出現する巨大なキャラクターは、信仰像と消費アイコンの境界を曖昧にし、鑑賞者の身体感覚と価値判断を揺さぶる。パラッツォに堆積した時間の層と、ポップで人工的な造形が正面衝突することで、「像を見る」「像を仰ぐ」という行為そのものが問い直され、現代における崇拝と欲望の構造が立体的に浮かび上がる。


シゲ・フジシロ
シゲ・フジシロの作品は、ガラスビーズと安全ピンという、装身具や交易品としての歴史をもつ素材を用い、膨大な手作業の集積によって日常の風景を幻想的に変容させる。本展では、パラッツォの2階に残るかつての居住空間を展示の舞台とし、運河に面した窓から差し込む自然光、天井のシャンデリアや室内に残る家具と呼応するかたちで作品が配置される。足場を用いないこの階では、鑑賞者は建築本来のスケールと親密さの中で、ビーズの微細な輝きと時間の密度を身体的に感じ取ることになる。
バスケットコートを想起させるモチーフは、水の都ヴェニスの文脈において「滝」へと読み替えられ、コートのラインは水の落下や流れとして立ち現れる。そこでは、汚水と清い水が循環する都市ヴェニスの構造が、労働と夢、自由と制約のあわいを象徴するイメージとして重ね合わされる。シゲ・フジシロの作品は、装飾的な美しさの背後に、都市と身体、浄化と滞留という相反する要素を内包し、建築とともに「見ること」と「想像すること」の関係を静かに更新する。


舘鼻則孝
舘鼻則孝は、「装うこと」を身体の外観的な装飾ではなく、社会的役割や儀礼、価値観を身体に刻み込む行為として捉え、日本の伝統文化を現代的に再構築してきた作家である。本展では、代表的な《Heel-less Shoes》を、江戸組紐の高度な技法を用いて制作し、パラッツォの2階に残るかつての居住空間に展示する。
装飾性の強い天井や壁、室内意匠を備えたこの空間において、履物は単なるファッションや工芸品としてではなく、身体の姿勢や重心、歩行を規定する彫刻的存在として立ち現れる。ヒールを欠いた構造は、身体の安定と緊張を同時に強い、装いが身体の感覚や行為をいかに変容させるかを可視化する。歴史的建築の内部において、江戸期の技法と現代的造形が重なり合うことで、装いは時間と文化を媒介する装置となり、身体が制度や儀礼と結びつく場そのものとして再定義される。


中田真裕
中田真裕は、蒟醤(きんま)を中心とする伝統的な漆技法を出発点に、漆を単なる「装飾」から解き放ち、時間や記憶の揺らぎを受け止める現代的なメディウムとして再定義してきた作家である。数十層に及ぶ漆の塗り重ねと研ぎの工程によって生まれる色層は、表面に現れる図像よりも、むしろ内部に蓄積された時間そのものを可視化する。彫り、塗り、研ぎという反復的なプロセスは、制作期間が数ヶ月から一年に及ぶこともあり、その長い時間が物質の内部に沈殿していく。
一方で、中田の作品の基本的な造形は、極めてシンプルで幾何学的である。過剰な形態や物語性を排したフォルムは、見る者の注意を表層の装飾ではなく、漆の層が生む微細な色の変化や奥行きへと向ける。本展では、パラッツォ2階の親密な雰囲気が残る室内に作品を配置する。生活の記憶を宿す空間の中で、漆の層に蓄えられた時間と、建築に沈殿した時間とが静かに重なり合い、作品は「記憶が沈殿する物質」として、穏やかに鑑賞者の身体感覚へと浸透していく。


三嶋りつ惠
三嶋りつ惠は、ガラス産業の中心地として長い歴史をもつムラーノ島の熟練職人との協働を通じ、無色透明のガラスのみを用いた彫刻作品を制作してきた。ヴェニスにおいてガラスは、光と水、交易と技の象徴的な素材であり、三嶋の作品はその歴史的文脈を現代に引き寄せる。炎の中で刻々と変化する素材の状態を読み取り、即興的な判断によって導かれる造形は「火の果実」とも呼ばれ、意図と偶然のせめぎ合いから必然的に立ち現れる。
本展では、パラッツォ2階の最初の部屋に35点からなる作品群を配置し、特別に制作された展示台そのものが柔らかな光を発する構成によって、光のインスタレーションが展開される。展示台は光を蓄え、拡散させる装置として機能し、ガラスはその光を受け止め、屈折や反射、影として空間に放つ。作品は単体の彫刻を超え、光の循環を可視化する存在として、建築と一体化しながら、ヴェニスの光の記憶を静かに呼び覚ます。


牟田陽日
牟田陽日は、九谷焼に学んだ色絵の技法を基盤に、日本文化において周縁化されてきた女性像や自然観を、陶磁器という媒体を通して再解釈してきた作家である。近年の制作において重要な主題となっているのが「山姥(やまんば)」である。山姥は、母性と暴力、祝福と恐怖、聖と俗といった相反する要素を内包する存在として、日本の民間伝承の中で語り継がれてきたが、同時に、制度や秩序から逸脱した女性性の象徴でもあった。
牟田の色絵に描かれる女性像は、外部から客体化された「見るための女性」ではなく、女性である作家自身の内側から立ち上がる視点によって構成されている。そこでは、自然は背景ではなく、身体や感情と連続する存在として描かれ、現実と虚構、実在と想像が溶け合う。手捻りによる不均質な造形や、工程を重ねる絵付けは、女性の身体や経験がもつ揺らぎや多層性を可視化する行為でもある。
本展では、グランドフロア奥、運河に面した小さな空間に作品が展示される。天井の低い、無骨な木材が露わになったこの場は、都市と水、内と外の境界に位置し、牟田の作品がもつ周縁性や両義性を際立たせる。ここで立ち現れる山姥のイメージは、抑圧や恐怖の象徴ではなく、女性の身体と自然が再び結び直されるための、静かで力強いヴィジョンとして、ヴェニスの時間と共鳴する。


綿 結
綿 結は、糸を撚り、染め、織るという原初的な工程から制作を始め、布の内部構造や重力そのものを立体として立ち上げる作家である。本展では、天井高のあるグランドフロアに作品が広がり、足場の高低差をもつ階段動線からは距離を保って眺められる一方、フロアに立つ鑑賞者は、空間に展開する作品を仰ぎ見る体験へと導かれる。
遠景からは、織物が描く全体の構成や量感が把握され、フロアからは、糸の重なりや張力、垂れ下がる布が生む重力の気配が身体的に迫ってくる。糸と糸のあいだに潜む微細な空間は、パラッツォに内在する空隙や構造と呼応し、平面と立体、支持体と彫刻の境界を曖昧にする。歴史的建築に堆積した時間の層と、反復的な手仕事によって生成された時間が交差することで、綿 結の作品は、視点の変化とともに異なる知覚を呼び起こし、素材と身体の関係を空間全体で体験させる。


※本展覧会は「クリエイター支援基金」の助成を受けて開催するものです。
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
