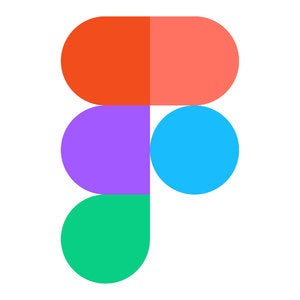FigmaのAIツール「Figma Make」、日本を含む全世界で提供開始
Figmaのプロンプト入力によるアプリ生成機能を活用すれば、高精度なプロトタイプの作成や、デザイン・コードの細かな調整も可能に。
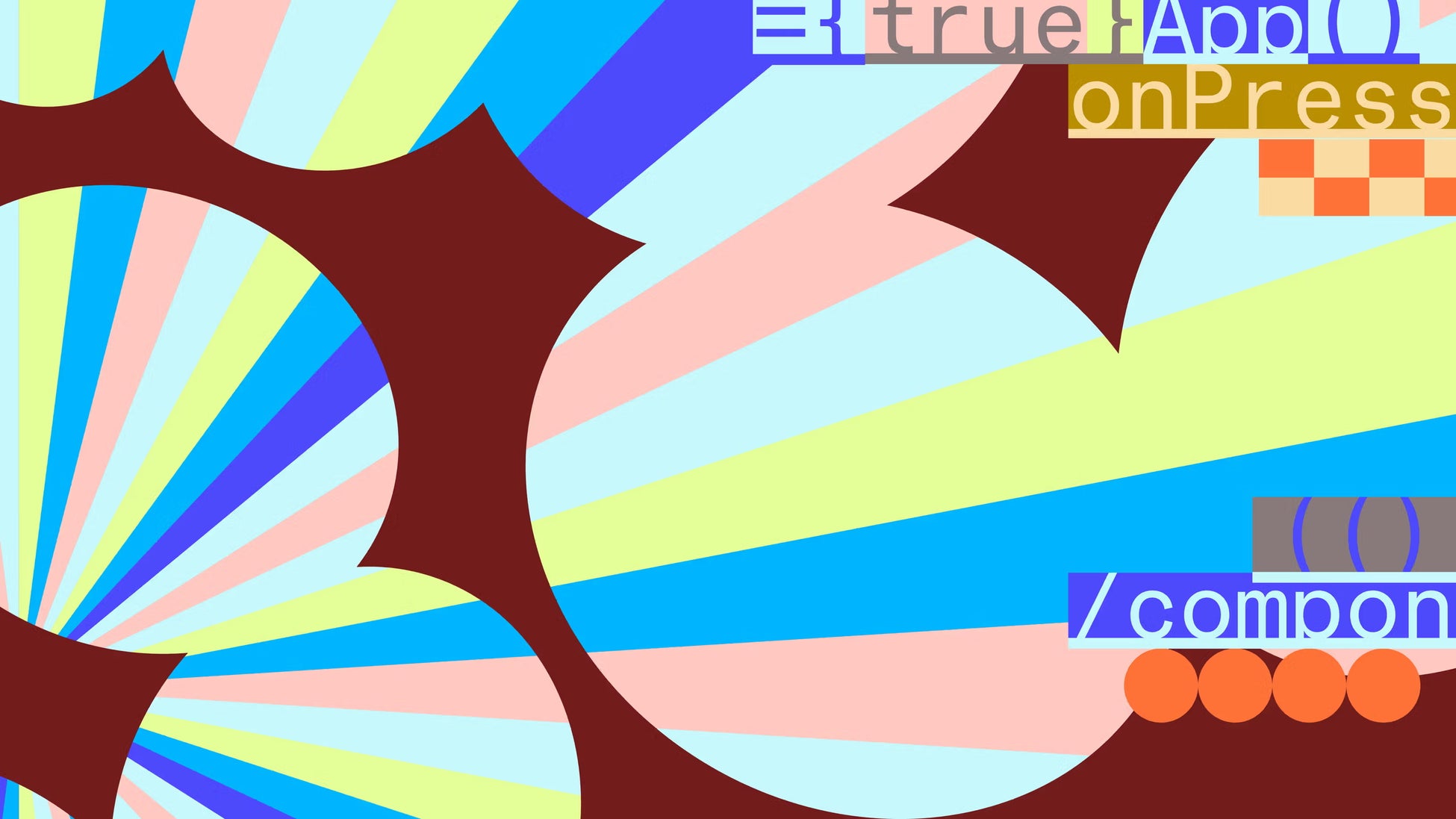
ブラウザ上で共同編集可能なデザインおよびプロダクト開発プラットフォームを提供するFigma(本社:米国サンフランシスコ)は、プロンプトからアプリを生成できる新しいツール「Figma Make」を、日本を含む全世界のユーザーに向けて提供開始したことを発表しました。
Figma Makeは、今年5月にFigmaの年次カンファレンス「Config」で発表されたもので、自然言語によるプロンプトや、既存のFigmaデザインを貼り付けるだけで、機能するアプリやプロトタイプを作成できるツールです。これにより、より素早く解決策を模索し、ビジョンを共有し、デザインを繰り返し改善することが可能となります。
Figma Japan カントリーマネージャー 川延浩彰のコメント:
「AIは、技術的なスキルの有無に関わらず、誰もがアイデアを実際に動くプロダクトやプロトタイプに変えることを可能にし、プロダクト開発のあり方を変えつつあります。Figma Makeは、より多くの人々が開発に参加できるようにするだけでなく、デザイナーや開発者が自身のスキルをさらに高められるツールや機能へのアクセスを提供することで、Figmaとして日本のものづくりの可能性をさらに広げていきます。」

Figma Makeは、アイデアから製品のリリースまでを一つの場所で完結できるFigmaの包括的なプラットフォームの一部として、チームの既存のデザインおよび開発ワークフローと統合することができます。また、既存ブランドと一貫した見た目や操作感をもつプロトタイプを生成するために、FigmaライブラリからスタイルのコンテキストをFigma Makeに取り込むことができ、そのライブラリからCSSスタイルを抽出することで、生成されるコードがデザインのコンテキストを正確に反映するようにします。
Figma Makeは、無料のStarterプランを含むすべてのユーザーが利用可能です。誰でも自由にFigma Makeを試すことができます。また、Figma Makeの提供開始にあわせて、レイヤー名変更、画像生成・編集、コンテンツ差し替えなどのFigma AI機能がベータ版を終了し、すべての有料プランで一般提供開始されました。さらに、Figmaは最近「Dev Mode MCP サーバー」をリリースしており、開発者はVS CodeのCopilot、Cursor、Claude Codeなどのエージェント型コーディングツールにFigmaのコンテキストを取り込むことが可能です。
Figmaは2022年に日本での展開を開始し、日本語にも完全対応しています。現在では、サイバーエージェント、みずほ銀行、LINEヤフー、みんなの銀行、SmartHRなど、日本を代表する先進的な企業に導入されています。
Figmaのプロダクト
Figma Makeは、日本のお客様が利用できる数多くのFigma製品のひとつであり、他にも以下のような製品があります。:
-
Figma Design:チームがアイデアを出し、反復しながらデジタル製品をプロトタイピングする場
-
Dev Mode:デザインとコードの橋渡しを行うための開発者向けモード
-
FigJam:チームで集まり、ブレインストーミングし、業務を進めるためのオンラインホワイトボード。
-
Figma Slides:チームが共同でインタラクティブなプレゼンテーションを作成・発表できるツール
-
Figma Draw:より豊かなビジュアル表現のための強化されたベクター編集機能とイラスト機能を備えたツールセット
-
Figma Buzz(ベータ版):ブランドの一貫性を損なうことなく大規模にビジュアルアセットを作成
-
Figma Sites(ベータ版):コードとAIを活用した無制限なインタラクションとカスタマイズによって、デザイナーが動的なウェブサイトを構築・公開できるようになるプロダクト
他のユーザーが Figma Make や Figma Sites をどのように使っているかは、こちらのギャラリーをご覧ください。 https://www.figma.com/blog/figma-make-general-availability/
Figmaについて
Figmaは、アイデアを世界最高のデジタルプロダクトや体験へと形にするためにチームが集まる場所です。2012年に設立されたFigmaは、単なるデザインツールから、アイデアから製品リリースまでを一貫してサポートする、連携性とAIを備えたプラットフォームへと進化してきました。アイデアの発想、デザイン、構築、リリースまで、Figmaはプロダクト開発のすべてのプロセスを、より協働的に、効率的に、そして楽しくしてくれます。同時に、チーム全体が常に同じ認識を共有できるようにします。
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像