大阪・関西万博 北欧パビリオン、未来へつなぐ北欧と日本の対話の集大成 10/10(金)&10/11(土)にサステナビリティと北極圏をテーマに閉幕イベントを開催
ヴィクトリア皇太子殿下が初来場し、サステナビリティをテーマに若い世代・ビジネス層と交流 万博のレガシーとして北欧5か国の在日商工会議所が連携し「北欧・関西ビジネスアライアンス」発足

デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンの北欧5か国による共同出展で注目を集める北欧パビリオンは、大阪・関西万博の閉幕を目前に控えた10月10日(金)と11日(土)の2日間、2つの国際イベント「スウェーデン・日本 サステナビリティサミット2025」および「Nordic Arctic Day(北極圏のビジネスデー)」を開催しました。北欧パビリオンは、日本と北欧をつなぐ架け橋として、閉幕までの半年間にわたり、王室や大統領、閣僚級をはじめとするハイレベルなゲストを迎えた国際イベントをはじめ、200件を超える企業イベントを実施しました。来場者数は延べ160万人以上に達し、多くの対話と新たなプロジェクトの芽を育んできた半年間の活動を締めくくる、フィナーレにふさわしい2日間となりました。
両日を通じて、ヴィクトリア・スウェーデン王国皇太子殿下が7年ぶりに来日し、大阪・関西万博へ初来場。10月10日付で国連開発計画(UNDP)のグッドウィル・アンバサダー(UNDP親善大使)の任期を2年間延長することが発表された皇太子殿下は、国連パビリオンでの若い世代との交流、国際シンポジウムへのご出席、そしてビジネス界へのメッセージを通して、「次世代との共創による持続可能な未来」を力強く発信しました。
また北欧5か国の在日商工会議所と関西商工会議所連合会は、北欧と関西地域の新たな連携の礎となる「北欧・関西ビジネスアライアンス(NKBA)」の正式発足も発表し、半年間にわたる北欧パビリオンの取り組みのレガシーを未来へとつなぐ節目となりました。
■7年ぶりの来日となるヴィクトリア皇太子殿下
ヴィクトリア皇太子殿下は、環境・気候・海洋保全などの分野に長年強い関心を持ち、国際的な活動を続けてきました。2016〜2019年には国連の「SDGs推進の17名のアドボケイト」の一人に任命され、現在も「Global Goals Advocate Emerita」として活動を継続しています。さらに、国連パビリオン訪問当日の10月10日には、UNDP親善大使の延長が発表されました。
特に海洋資源の保全と持続可能な漁業(水産)はヴィクトリア皇太子殿下の関心が深いテーマであり、北欧諸国と同様に長い海岸線を持つ日本との連携に強い意義を感じていらっしゃいます。こうした背景から、今回の訪問でも特にSDGs「海の豊かさを守ろう(目標14)」を軸に若者と対話し、持続可能な未来への意識を共有しました。
<10月10日(金):北欧パビリオン、日本館ご訪問>
北欧パビリオンへのご訪問では、北欧パビリオンのガイドたちがヴィクトリア皇太子殿下を笑顔でお出迎えしました。北欧パビリオンでは廃棄される米を活用したスクリーンに北欧5か国の日常やサステナビリティ、ウェルビーイング、そして自然との深い関わりを映し出し、来場者に「信頼の輪」というメッセージを伝えてきました。スウェーデン出身のガイドがこのコンセプトや展示の背景を説明し、ヴィクトリア皇太子殿下は熱心に耳を傾けられていました。

さらに、北欧パビリオンはその独創的な展示とメッセージ性の高さが評価され、万博参加国を対象としたThe Experiential Design Authority(TEDA)主催の「ワールド・エクスポリンピック(Expolympics)」のディスプレイ部門において最優秀賞を受賞。北欧5か国が一体となって築いた展示のアイデアと、持続可能な未来への力強いビジョンが来場者にも伝わったことを実感できる結果となっています。続いて日本館にも足を運ばれ、技術と文化について理解を深められました。

<10月10日(金):若い世代と未来を語る、ヴィクトリア皇太子殿下を招いた国連パビリオンでのパネルディスカッション>
北欧パビリオンの訪問に続いて、ヴィクトリア皇太子殿下は大阪・関西万博会場内の国連パビリオンを訪問し、日本の高校生やガールスカウト、スタートアップ企業とのパネルディスカッションに参加。SDGs、特に「海の豊かさを守ろう(目標14)」をテーマに活発な意見交換が行われました。皇太子殿下は、
「皆さんのストーリーや強い関心を伺うことができ、本当に素晴らしい時間でした。若い世代との対話に感銘を受けました。皆さんの情熱は、若い世代として、またコミュニティの一員として、何ができるのかを力強く示してくれました。 その姿勢は非常に意義深く、心から敬意を表します。世界はいま、まさに皆さんのような人たちを必要としています。 どのようなコミュニティにいても、どんな課題に直面しても、ぜひこれからもこのような事象に関心を持ち、積極的に関わってくださることを心から願っています。」とコメントを寄せました。


<10月10日(金):関西で初開催となるスウェーデン・日本 サステナビリティサミット 2025>
午後の「スウェーデン・日本 サステナビリティサミット 2025」は、2021年から毎年都内で開催されている取り組みで、関西では初めての開催となりました。スウェーデン政府、Business Sweden、IKEAなどの在日スウェーデン企業が連携して企画されたもので、「循環型ライフスタイル」、「未来のモビリティ」、「ネットゼロ医療」という3つのテーマで構成されました。

それぞれのセッションでは、スウェーデンと日本の専門家や企業リーダーが登壇し、両国が直面する課題と未来へのアプローチについて議論を展開。持続可能な社会の実現に向けて、テクノロジー・ビジネス・ライフスタイルの各視点から多角的な対話が行われました。
登壇者には、スウェーデンのエリック・スロットネル民生大臣、IKEA Chief Sustainability Officer のカレン・フルーグ氏、そしてスウェーデン北部サーミ地域出身のアーティストのサーラ・アインナク氏などが名を連ねました。特に、アインナク氏によるサーミ民族の伝統歌唱「ヨイク」に電子音響や現代的アレンジを融合させ、音楽と映像を組み合わせたパフォーマンスは、サミット全体に強い印象を残し、参加者に持続可能な未来のイメージを心に響く形で訴えかける内容となりました。

ヴィクトリア皇太子殿下も終始セッションを熱心にご覧になり、登壇者と直接意見を交わす場面も見られました。経済・社会・文化の枠を超えた本サミットは、スウェーデンと日本のサステナビリティ分野における連携を一段と深める機会となりました。
ヴィクトリア皇太子陛下は、「まず初めに、日本が本年、ひとつではなく二つの大きな栄誉を受けられたことに、心よりお祝い申し上げます。そのうちの1つであるノーベル生理学・医学賞の受賞者は、大阪大学の教授でいらっしゃいます。改めておめでとうございます。この偉業は、日本が長年培ってきた「科学とイノベーションの伝統」の強さを示すものであり、その精神はこの万博の場にも表れているように感じます。」とノーベル賞受賞についてお祝いの言葉を述べました。

また閉幕を間近に控える大阪・関西万博について触れながら、「4月の開幕以来、この万国博覧会は、スウェーデンが日本との自然な絆をさらに深めるための重要なプラットフォームとなってきました。この万博を見事に運営し、持続可能な成長とイノベーションに取り組む多くのパートナーを結びつけてくださった日本の皆さまに感謝申し上げます。5月には、私の父であるカール16世グスタフ国王陛下が、ここ万博会場で開催されたスウェーデンのナショナルデーにご臨席されました。その際には、過去最大規模のスウェーデン経済使節団が日本を訪れました。この半年間、スウェーデンが万博で展開してきたすべての活動の根底には、「持続可能性」と「イノベーション」というテーマが流れており、本日の「スウェーデン・日本 サステナビリティサミット」で締めくくられることは決して偶然ではありません。それは、日本、そして関西地域との長期的な協力関係を象徴するものです。今回の万博で私にとって特に印象的だったのは、「自然への敬意」です。本日訪れた日本館では、その想いが随所に感じられました。また、「テクノロジーの力によって、私たちが直面する数々の課題を乗り越えられる」という強い信念も印象的でした。さらに、国連パビリオンで出会った日本の学生たちが、持続可能な開発目標(SDGs)に関する研究に真摯に取り組む姿にも深く感銘を受けました。彼らの熱意は私に希望を与えてくれる一方で、次の世代が私たちに「今、行動すること」を期待しているという現実も思い起こさせてくれました。皆さま、私たち両国の人々は、自然への敬意と、持続可能な社会を支えるイノベーションへの情熱を共有しています。共に歩むことで、私たちは持続可能な未来を築く「世界のリーダー」となる可能性を秘めています。」とご挨拶されました。


<10月11日(土):Nordic Arctic Day 北極圏のビジネスデー。北極圏を舞台にした国際連携の最前線>
翌11日、北欧パビリオンでは「Nordic Arctic Day:北極圏のビジネスデー」を開催。北欧5か国共催によるジョイント・ノルディック・イベントの最終回として、北極圏をめぐる地政学・気候変動・デジタル化といったテーマで北欧と日本の閣僚、研究者、企業が国際的な議論を重ねました。
開会にはヴィクトリア皇太子殿下とダニエル王子殿下がご臨席。北極圏を舞台にした国際協力の新たな可能性が示される一日となりました。

スウェーデンのヴィクトリア皇太子殿下はスピーチの中で、「創造性、協力、そしてコミットメント——これが北欧の価値観です」と述べ、スウェーデンと日本が持続可能性とグリーントランジションを推進するために築いてきた連携の歩みを振り返りました。さらに、地球規模の気候や生態系にとって極めて重要な北極の現状に触れ、「北極は私たち全員をつなぎ、協力して行動することを私たちに呼びかけています」と強調。北欧と日本の協力を通じて、北極圏を未来の世代にとっても命とインスピレーションの源であり続ける地域にしていく決意を示されました。
続いて、フィンランドのアンデシュ・アドレクルッツ教育大臣が開会の挨拶を行いました。同大臣は、北欧と日本の長年の協力関係に触れたうえで、今回の大阪・関西万博の北欧パビリオンは、この関係をさらに発展させる理想的な場です」と述べました。
また、北極が戦略的にも気候的にも国際社会の安全保障の焦点となっている現状を指摘し、サイバーセキュリティやレジリエンス(回復力)、若者政策などを含む包括的安全保障の観点から、北欧地域が連携して課題に取り組んでいることを紹介。北欧閣僚理事会が進める北極圏の研究・協力の枠組みや、臨界点への備えに向けた国際的議論の重要性を強調しました。
午前の地政学セッションでは、安全保障や緊急対応を含む北極圏の国際秩序の変化が議論され、午後の気候変動・極地研究セッションでは、急速に進む環境変化への対応と、北欧と日本による研究協力の強化が主要なテーマとなりました。続くデジタル化・コネクティビティのセッションでは、北極圏を経由した海底光ファイバーケーブルなどの戦略的インフラ整備に焦点が当たり、テクノロジーと地政学の両面から議論が深まりました。
北極圏は、欧州とアジアを最短距離で結ぶ新たな物流・通信ルートとして注目されており、エネルギー、海運、デジタル通信、環境研究など多岐にわたる分野で、日本にとっても新たなビジネス機会を広げる可能性を秘めています。近年の気候変動により航路開発やインフラ整備が進む中、北欧諸国は長年にわたる知見と技術を有しており、日本にとっては北欧との連携が北極圏進出のカギとなります。
登壇者には、スウェーデンのエリック・スロットネル民生大臣、北欧閣僚理事会 事務総長のカレン・エレマン氏、北欧および日本の極地研究者やデジタル政策関係者など、多彩な顔ぶれが揃い、政策・科学・ビジネスが交わるハイレベルな国際プラットフォームとなりました。終日のプログラムを通じて、北欧と日本が協力しながら北極圏の未来を形づくるための多角的な可能性が示され、今後の国際連携に向けた重要な一歩となりました。

■北欧・関西ビジネスアライアンス(NKBA)が正式発足
万博のレガシーを未来へ ― 地域と北欧の持続的な連携を推進
11日のプログラム内では、北欧5か国の在日商工会議所が連携し、関西商工会議所連合会と「北欧・関西ビジネスアライアンス(Nordic Kansai Business Alliance/NKBA)」の発足を正式発表しました。


NKBAは、大阪・関西万博を通じてより一層深められた北欧と関西の企業・自治体・研究機関間のネットワークを未来に引き継ぎ、エネルギー、都市デザイン、観光、教育など幅広い分野で中長期的な協働を推進していくことを目的としています。
北欧閣僚理事会 事務総長のカレン・エレマン氏は、「北欧企業が日本をはじめとする国際的なパートナーと連携し、持続可能なソリューションやイノベーションを広げていくためには、適切な協力の枠組みが不可欠です。この半年間、パビリオンを拠点に展開された数多くの活動は、まさにその好例といえます。今回のアライアンス発足は、地域間の相互利益と協力の新たな一歩です」と述べました。
フィンランドのアンデシュ・アドレクルッツ教育大臣は、「北欧は“持続可能性・イノベーション・未来への信頼・平等・安定”といった共通の価値観を世界に発信する地域です。本日の発表は、北欧各国の商工会議所や企業が一体となって日本との連携をさらに深める重要な節目であり、400社以上の企業が有するネットワークを活かし、共通の価値を推進していく大きな可能性を示しています」と語りました。
スウェーデンのエリック・スロットネル民生大臣は、「大阪・関西万博は、北欧と日本の強固なつながりを築く国際的な舞台となりました。特に関西地域は、北欧企業にとって今後の協力を拡大する上で極めて重要な拠点です。今回のビジネスアライアンスは、北欧の長期的な関与と地域への強いコミットメントを示すものであり、イノベーションと持続可能な成長、そしてさらなる関係強化を力強く後押しするものになると確信しています」と述べました。
また、関西地域の代表として、大阪府 商工労働部長の馬場広由己氏、大阪市経済戦略局理事の和田彩氏からも祝辞が述べられました。
「北欧諸国は、イノベーションや環境技術、持続可能なソリューションの分野で世界をリードしてきました。一方、大阪・関西は長年にわたり技術革新の拠点として、多様な取り組みを推進してきました。両者が力を合わせることで、新たな経済成長の原動力となることを期待しています。共に、より良い未来を築いていけることを願っています。」
■大阪・関西万博閉幕に向けて:北欧パビリオンから未来へ
2025年4月の開幕以来、北欧パビリオンは半年間にわたり、日本と北欧の対話・連携を深める数々のハイレベルなプログラムを展開してきました。
各国のナショナルデーでは、王室や大統領、閣僚級といったハイレベルなゲストを迎え、両地域の長年の友好関係と未来への協力の意志を強く印象づけました。また、北欧5か国が重点を置くライフサイエンス、エネルギー、ジェンダー平等、文学・文化などのテーマを軸に、各国が単独での発信にとどまらず、5か国共催で多彩な国際イベントを実施。北欧および日本の専門家・研究者・企業を招き、シンポジウムやネットワーキング、実務レベルの対話を通じて両国間の連携と関係強化を進めてきました。
さらに、民間パートナー企業による独自のイベントも数多く開催され、ビジネス、技術、文化、社会といった多層的な分野で、北欧と日本の協働の可能性を具体的に示す場となりました。半年間で実施された企業イベントは200件を超え、来場者数は延べ160万人以上に達しました。
こうした活動を通じて、北欧パビリオンは単なる展示空間を超え、北欧と日本を結ぶ持続可能な対話と共創のハブとしての役割を果たしてきました。以下では、この半年間を締めくくるにあたり、北欧5か国の政府代表から寄せられたメッセージをご紹介します。
スティーネ・グルマン(Stine L.Guldmann)デンマーク政府代表
「大阪・関西万博では、持続可能性、イノベーション、そして高い生活の質といったデンマークの強みを世界に発信する素晴らしい機会となりました。多くの新たな友情や価値あるネットワークが生まれ、デンマークのソリューションに対する国際的な関心も高まりました。ご来場いただき、交流してくださったすべての皆さまに心より感謝申し上げます。」
ニタ・ピルカマ(Nita Pilkama)フィンランド政府代表
「大阪・関西万博の運営および大阪地域の皆さまに、心から感謝申し上げます。このプロジェクトを通じて、私たちは多くの新しいつながりを築き、国同士が協力しながらグローバルな課題に前向きに取り組むことができるということを世界に示すことができたと思っています。」
ラグナル・ソルバルダルソン(Ragnar Þorvarðarson)アイスランド政府代表
「この6か月間、日本で北欧諸国と共にアイスランドを紹介できたことは大変貴重な機会でした。参加を通じて、アイスランドのイノベーション、持続可能性、創造性、そして北欧諸国間の強い絆を発信することができました。イノベーションから観光、食産業まで幅広い分野の6社の企業パートナーと、50社を超える協力企業の皆さまに深く感謝しています。大統領や産業大臣による訪問を通じて日本市場への関心もさらに高まり、この万博への参加が非常に意義深いものとなりました。今後は、この成果を基盤に、日本の皆さまとさらに連携を深めていきたいと考えています。」
フィン・クリスティアン・オーモット(Finn Kristian Aamodt)ノルウェー政府代表
「大阪・関西が万博の開催地となったことに、心から敬意を表します。この万博は、北欧諸国にとって“信頼”と“協働”という価値を発信する貴重な機会となりました。パビリオンへの多くの来場者数は、北欧のストーリーが日本と強く響き合っていることを示しています。ビジネスセミナーには多数の参加があり、北欧およびノルウェー企業との連携・取引への関心の高さも実感できました。さらに、大阪における北欧商工会議所の設立は、関西地域における私たちの存在感が一段と大きくなったことの証です。万博開催期間中の日本のみなさんの多大な支援に心より感謝いたします。」
セシリア・エクホルム(Cecilia Ekholm)スウェーデン政府代表
「この6か月間は、協力と信頼を祝福する素晴らしい旅でした。スウェーデンは、北欧パビリオンおよび大阪・関西万博の一員として参加できたことを誇りに思います。私たちは、万博で築かれたレガシーを、日本そして世界でこれからも発展させていけることを楽しみにしています。」
半年間にわたる挑戦と協働を経て、北欧パビリオンは日本と北欧をつなぐ架け橋として、多くの出会いと対話、そして新たなプロジェクトの芽を育んできました。私たちの活動は、万博という特別な時間と空間の中で終わるものではなく、ここから未来へと続いていきます。
北欧パビリオンのオフィシャル素材のダウンロードはこちらから。
本イベントのオフィシャル素材のダウンロードはこちらから。
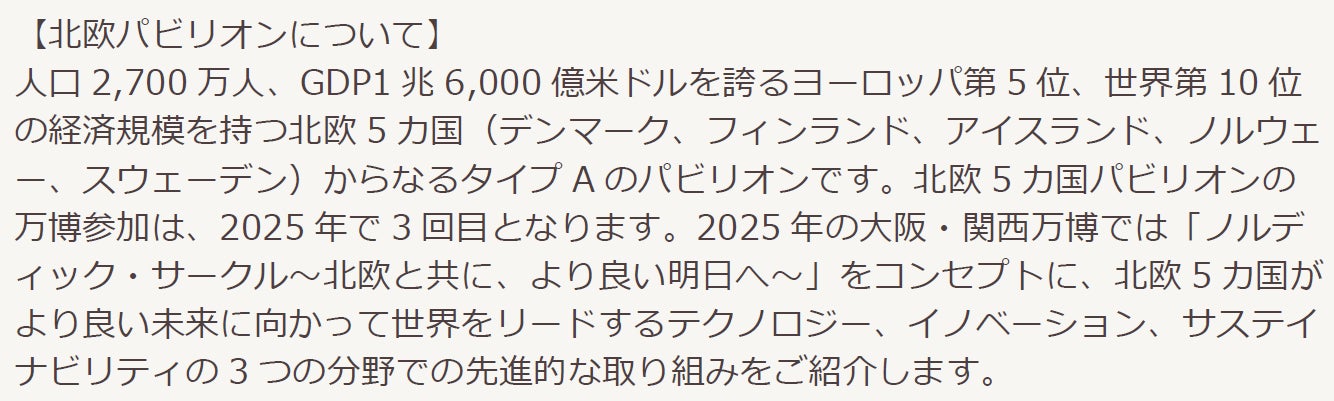
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像