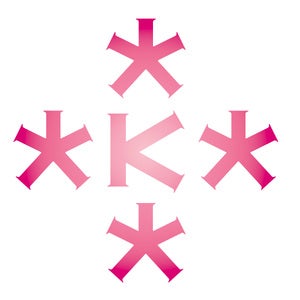水難事故を防ぐ第一歩は“浮く力”―若吉教授(水球元五輪代表)が指導法を伝授

2025年6月24日、大阪府豊能郡能勢町にある義務教育学校「能勢ささゆり学園」で、小中学校教員約20名を対象にした水泳指導研修が行われました。講師を務めたのは、人間科学部の若吉浩二教授。1984年ロサンゼルス五輪に水球日本代表として出場し、現在は学校現場に即した水泳教育の実践・研究に取り組んでいます。
本研修では、若吉教授が開発した水泳補助具『フラットヘルパー』を活用し、段階的な指導法を実践的に学ぶプログラムが展開されました。泳ぎが苦手な児童にも無理なく「浮く感覚」を身につけさせることに重点を置いた内容が特徴です。
学校水泳の縮小と泳力格差への対応をめざして
学校水泳を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。猛暑による熱中症リスクの高まりにより、一定の気温を超えると授業が中止されることも多く、年間の水泳授業時間は10時間程度に限られている学校も少なくありません。
また、民間のスイミングスクールに通う児童とそうでない児童との間で、泳力の差が広がっているという課題もあります。
限られた時間の中で、泳ぎが苦手な子どもにどう教えるか。こうした状況に対し、若吉教授は「水難事故の予防の観点からも、“浮いて待つ”技術を身につけることがすべての子どもにとって重要です」と語ります。
そのために開発されたのが、独自の水泳指導法「大阪“大の字”泳法」と補助具『フラットヘルパー』です。
手軽な補助具『フラットヘルパー』で「浮く感覚」を実感

『フラットヘルパー』は、メッシュ素材の補助パンツの両脇にビート板素材の浮力体を装着して使用する簡易的な水泳補助具です。浮力体には500mlのペットボトルも代用可能。特に沈みやすい下半身の浮力を補い、水面での水平姿勢を自然にサポートします。
研修では、教員たちが実際にこの補助具を装着して水中での感覚を体験。「浮く感覚」の体得が水への恐怖心の軽減につながることを実感しました。あわせて、海水と真水の浮力の違いを体験する環境教育や、水難事故時の基本動作を学ぶ安全水泳、さらには泳法習得まで、理論と実技が連動した内容が展開されました。

子どもたちが「楽しく・安全に」水に親しめるように
現在の学習指導要領では、低学年で「水慣れ」を重視し、中学年からは「浮く・沈む・潜る」といった基本的なスキル、さらに泳法の習得へと進む流れが定められています。しかし、泳ぎが得意ではない子どもにとって、このステップは高いハードルになることもあります。
若吉教授は、そうした壁を乗り越えるため、指導法をやさしく、段階的に設計。研修で示されたカリキュラムは、まず「水慣れ」から始まり、「浮き身」「呼吸法」「姿勢づくり」へと進行。最終的には「大の字浮き」「伏し浮き」「背浮き」といった安全水泳技術の習得を通して、自然に泳法へとつながっていく構成となっています。

指導フローには、「浮く感覚」を中心に据え、体の重心や浮力、呼吸、水の抵抗といった基本原理もわかりやすく整理されており、教員が児童に段階的に伝えやすい工夫が施されています。
「能勢モデル」から全国へ広がる水泳教育のかたち
若吉教授は、2019年から能勢町教育委員会と協働し、同町の子どもたちの体力向上に取り組んできました。今回の研修もその一環であり、教員たちが現場で実践した成果は、アンケートや実地観察を通して蓄積されています。
「能勢のような山間地域でも取り組めたモデルだからこそ、他の地域にも展開できるはず」と若吉教授は語り、「能勢モデル」として全国への波及を目指しています。

研修に参加した教員からは、「浮きながら安心して呼吸の指導ができそう」「すぐに授業に取り入れたい」といった前向きな声が多く寄せられました。
水に浮かぶ身体の仕組みを理解する3つの視点
本研修では、水泳における基本動作や浮き方の理解を深めるため、以下の3点が紹介されました。
(1)重力と浮力の関係
水中で体が浮くのは、体積分の水の重さと体重が釣り合う状態による。息を吐くと体積が減り、沈みやすくなる。呼吸の仕方が浮き沈みに大きく影響する。
(2)重心と浮心の関係
「だるま浮き」のように体を丸めると、重心と浮心が一致して安定。空気の入れ方や姿勢で重心・浮心がズレると、浮き方も変化する。
(3)水の抵抗と慣性
姿勢が乱れると抵抗が増え、泳いでもすぐに止まる。良好な水平姿勢では慣性が働き、少ない力でスムーズに進む。
このような基礎理論を、教員自身が体感を通して学ぶことにより、より実感を持って指導に取り組むことができるようになります。

子どもたち一人ひとりの「水とのつきあい方」を支える教育へ
水泳教室に通えなくても、身近な学校のプールで「浮く」ことから始められる――。若吉教授の実践は、水との向き合い方を見つめ直す水泳教育の新たな可能性を示しています。泳げるかどうかではなく、水に親しみ、自らの命を守る力を育むこと。その第一歩を支える教育モデルとして、今後の広がりが期待されます。
関係者の声
若吉浩二 教授(人間科学部)
水に慣れ、浮く体験を通して、子どもたちが水を楽しめるようになることが何より大切です。水泳は特別なものではなく、もっと気軽に触れ合ってほしい。その第一歩として、“浮く感覚”を育てることを重視しています。
能勢町教育委員会(担当者)
“速く泳ぐ”よりも“長く、安全に泳ぐ”ことに重点を置いた若吉先生の方針は、子どもたちの心理的抵抗感を下げ、泳力や姿勢の向上にもつながっています。今後も『フラットヘルパー』を活用しながら、子どもたちの安全と成長を支えていきたいと考えています。
大阪経済大学
▼本件に関するお問い合わせ先
大阪経済大学 企画・総務部 広報課
住所:大阪府大阪市東淀川区大隅2-2-8
TEL:06-6328-2431
E-mail: kouhou@osaka-ue.ac.jp
すべての画像