お城好き必見!国指定史跡 伊豆長浜城跡開園10周年記念講演会の様子を沼津市公式YouTubeチャンネルにて公開!
伊豆長浜城跡・韮山城跡・能島城跡。3つの国指定史跡の最新研究成果から長浜城跡を深掘り!

【「駿河湾の海の城と海賊~韮山外張先之城二候~」と題した講演会の様子をあますことなく、動画で公開】
駿河湾を代表する海城の長浜城跡。1988年に国史跡に指定され、2015年に史跡公園としてオープンしました。本年8月には開園10周年を記念した講演会を実施。
史跡整備に伴う総合調査によって明らかになった成果とともに、小田原北条氏の伊豆の本拠である韮山城の最新の発掘調査成果から見えてきた長浜城の役割や、同時代の日本最大の海賊とされる西国海賊の代表、村上海賊との比較研究から見えた東国の海賊の姿など、それぞれの研究者の視点から、海の城である長浜城跡の魅力に迫ります。
小田原北条氏の祖、伊勢新九郎盛時(北条早雲)は、興国寺城(沼津市根古屋)から堀越公方足利茶々丸の館を急襲・追放後、韮山に城を構え戦国大名としての第一歩を踏み出しました。その後小田原を手中におさめ、二代氏綱・三代氏康の頃には領地を武蔵から下総まで広げ、関東一円を支配する大大名へとなっていきます。
北条氏は三崎や浦賀を根拠地とする三浦水軍を組織し、江戸湾から里見氏の勢力を駆逐する一方、今川義元亡き後の駿河に侵入してきた武田氏に対しても、伊豆の水軍を組織しその脅威に備えました。その伊豆における北条水軍根拠地の一つが、この長浜城でした。 このような情勢の中、天正7年(1579年)には北条水軍の事実上の統括者である海賊、梶原備前守が長浜城におかれ、翌天正8年(1580年)、武田・北条両氏水軍による駿河湾海戦が行われました。
1985年に実施された市教育委員会による詳細分布調査の結果、長浜城は4つの曲輪と15の腰曲輪、曲輪上の土塁跡や6基の堀切などが確認されました。各曲輪は小規模ながら、戦国時代後半に見られる特徴的な防御構造をよく残しており、豊富な文献資料と合わせて、戦国末期の城郭として高い学術的価値が認められ、1988年に国指定史跡となりました。その後の調査・復元整備を経て、2015年度には海城として国内でも珍しい形態の歴史公園が整備され、約400年前の城跡の姿が復元され公開されています。
今回の講演会は、史跡公園開園10周年を記念したもので、伊豆の本拠である韮山城跡の最新の発掘調査成果や、戦国時代に宣教師らによって「日本最大の海賊」と称された村上海賊との比較研究などから、最新の伊豆の地域研究や中世日本海賊研究の成果について解説しました。戦国時代の海上防衛や勢力に関心のある方にとって、最新の知見に触れる貴重な機会となっています。
【動画の視聴はコチラ】
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/kyoiku/kyoiku/bunka/kouenkai.htm

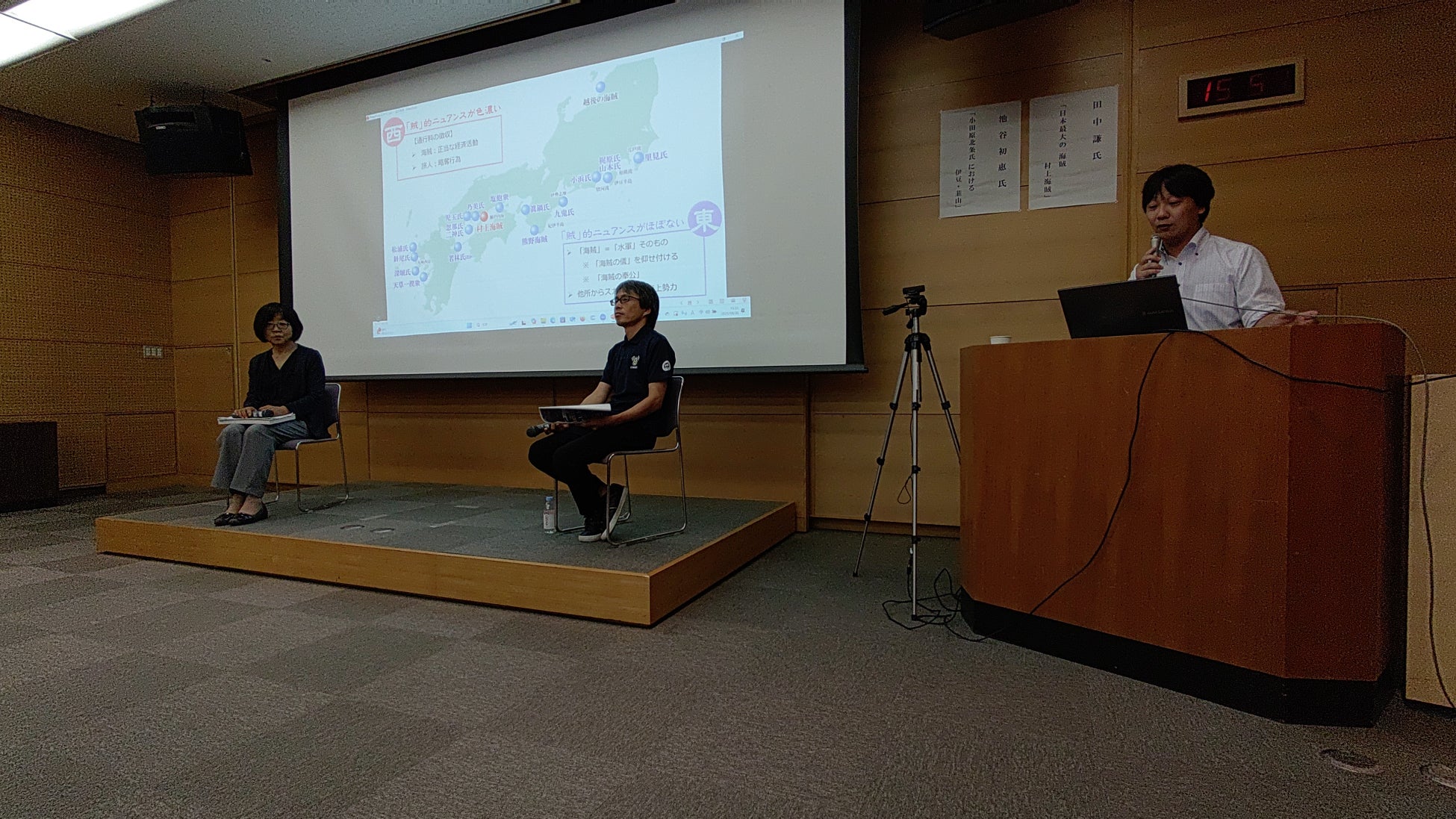
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
