【創業5周年リリース 第4弾】環境移送ベンチャーイノカ、「イノカ・アカデミア・パートナーシップ制度」を運用開始。東大・関西大・埼玉大・科学大(旧東工大)の5つの大学研究室との連携を公表
〜 イノカ独自の「環境移送技術®︎」を活用した学術研究の促進、新たな課題解決領域の発見、次世代研究者との共創を目指す。パートナー研究室の募集も開始 〜

株式会社イノカ(本社:東京都文京区、代表取締役CEO:高倉葉太、以下「イノカ」)は、大学研究室とのパートナー制度として「イノカ・アカデミア・パートナーシップ制度」の運用を開始しました。
2025年2月現在、5つのパートナー研究室として、東京大学 安田仁奈 教授、関西大学 上田正人教授、埼玉大学 蔭山健介 教授、東京大学 水野勝紀 准教授、東京科学大学(旧東京工業大学) 中村隆志 准教授の研究室との連携を公表します。
イノカの「環境移送技術®︎(※1)」はこれまで、主に民間企業および自治体との共同研究に活用されており、従来型のフィールドリサーチ等ではアプローチがしにくかった海洋課題の解決の糸口として、ラボ内で人工的に制御された先進性の高い実験・研究環境を提供可能であることが評価されてきました。(※2)
本制度の導入により、新たにアカデミアとの連携を強化し、学会発表や共著での論文執筆を加速することにより、学術的にも国際的にインパクトのある共同研究成果の創出を目指すとともに、各研究室に所属する若手研究者を技術・知識面でサポートし、地球環境問題の解決において重要な役割を担う次世代の研究者との共創にもコミットしてまいります。(※3)
※1 環境移送技術:天然海水を使わず、水質(30以上の微量元素の溶存濃度)をはじめ、水温・水流・照明環境・微生物を含んだ様々な生物の関係性など、多岐に渡るパラメーターのバランスを取りながら、自社で開発したIoTデバイスを用いて、任意の生態系を水槽内に再現するイノカ独自の技術のこと。2022年、時期をずらしたサンゴの人工産卵に世界で初めて成功。
※2 これまでの活用事例および背景課題の説明については、下記リリースをご参照ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000047217.html
※3 本制度は「環境移送技術」を用いた各研究室との連携やサポートを促進するためのものであり、共同契約締結を指すものではありません。
「イノカ・アカデミア・パートナーシップ制度」について
本制度の目的
本制度の運用を開始した目的は大きく下記の3点です。
・目的①:環境移送技術®︎の応用により、学術研究への貢献を促進するため。
・目的②:多様な知の交換による、新たな課題解決領域を発見する機会創出のため。
・目的③:環境課題の解決を担う次世代の研究者人材との共創のため。
本制度の概要
本パートナー制度のポイントは主に下記の3点です。
1. 環境移送技術®️を活用した新規性の高い研究テーマの発掘
パートナー研究室の指導教員である教授陣・所属学生とのディスカッションを行いながら、環境移送技術®️を用いて深化を図ることのできうる研究領域を絞り込み、新規性の高い研究テーマを発掘することを目指します。
2. 修士課程・博士課程の大学院生が主な対象
主には各研究室に所属する修士課程・博士課程の大学院生との共同研究を想定しており、学会発表や論文化を目指します。
3. イノカの研究スタッフによる技術面での研究サポート
イノカは環境移送技術®︎に関連する技術やノウハウを提供し、研究計画や実験系の組み方、実験のオペレーション等についてアドバイスし、研究に伴走します。
パートナー研究室(2025年2月時点)ご紹介
① 東京大学 大学院農学生命科学研究科 生圏システム学専攻 水域保全学研究室(安田仁奈 教授)
研究室HP:http://www.suiiki.es.a.u-tokyo.ac.jp/
<想定する共同研究領域>
・サンゴの形態の可塑性に関する研究(群体系が環境によってどのくらい変わりえるのか)
・北限環境のサンゴ群集と藻類の競争を水槽内で再現して、さまざまな環境変動シナリオをためして、何が起きるか比較
・絶滅危険度の高いサンゴや希少性のサンゴを活かし続ける場として

<安田仁奈 教授 コメント>
一般的に長期で飼育することが難しいサンゴを活かし続けることに長けたイノカの技術は、例えば、野外で絶滅の危険度が高いサンゴや遺伝的に希少なサンゴの保全や、急速な温暖化に伴って変化する沿岸生態系の変化を再現できれば、将来予測に役立つなど、様々な可能性を秘めていると思い期待しています。
② 関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 環境材料研究室(上田正人 教授)
研究室HP:https://wps.itc.kansai-u.ac.jp/matt
<想定する共同研究領域>
・再生医療技術を応用したサンゴ礁の早期再生研究

<上田正人 教授 コメント>
サンゴの軟組織であるポリプを単離し、これを起点としたサンゴの高効率増殖技術を開発しています。本技術により、サンゴの初期発生段階を大量に確保することが可能となる一方で、ポリプは極めて脆弱であり、安定した飼育環境の維持が重要な課題となります。イノカの環境移送技術は、精密な環境制御を実現することで、ポリプの生存率および成長率の向上に寄与すると期待されます。また、閉鎖系における厳密な環境制御が可能となることで、海洋フィールドでは取得困難な高い再現性を有するデータを取得でき、基礎生物学的研究および応用研究の双方において有益な知見を得ることができると考えています。
③ 埼玉大学 大学院理工学研究科 機械科学専攻 / 工学部 機械工学・システムデザイン学科 材料工学研究室(蔭山健介 教授)
研究室HP:https://materialeng.mech.saitama-u.ac.jp/
<想定する共同研究領域>
・エレクトレットセンサを用いた海洋生物のアコースティックセンシング
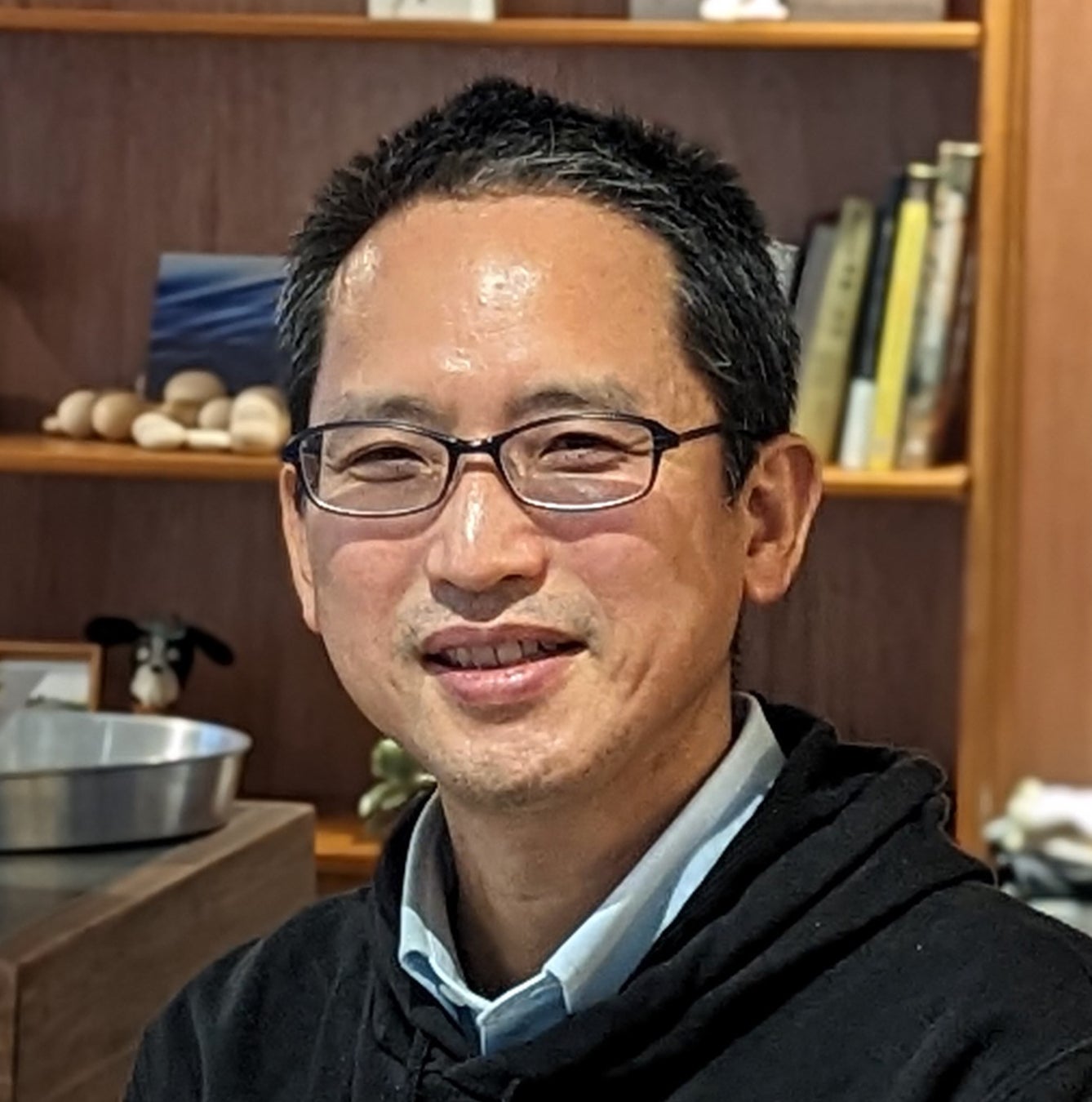
<蔭山健介 教授 コメント>
私は,触れるだけで微細な音や振動を検出するセンサを開発し,音で多様な生き物の動きを捉えるしくみをつくっています。イノカの環境移送技術とは親和性が高いと感じており,例えば藻類の光合成やマングローブの体内水分動態で生じる音響放射から環境変動が生態系に及ぼす影響を把握できるのではと期待しています。
④ 東京大学 大学院 新領域創成科学研究科環境システム学専攻 水野研究室(水野勝紀 准教授)
研究室HP:https://webpark2264.sakura.ne.jp/mizu/
<想定する共同研究領域>
・センシングデバイスによる、底質中におけるアサリ等の生物の移動状況の捕捉

<水野勝紀 准教授 コメント>
海底堆積物の中に生息している底生生物の分布や生態を「超音波」を用いて調べる技術の開発を行っています。イノカの環境移送技術によって、現場で調査する前に、ラボで様々な実験を実施できます。また、生物飼育に関する知識や実績がなくても、実験環境の構築やその後のフォローなど、幅広くサポートしていただけますので、異分野融合(例えば、工学×環境)の観点からも、その進展が期待されます。
⑤ 東京科学大学 環境・社会理工学院 中村(隆志)研究室(中村隆志 准教授)
研究室HP:http://www.nakamulab.mei.titech.ac.jp/
<想定する共同研究領域>
環境制御化でのサンゴ飼育による環境に対する生物応答のモデル化と将来予測

<中村隆志 准教授 コメント>
サンゴの環境に対する応答を数理モデル化し、数値シミュレーションによって環境変化に対するサンゴ生態系の将来予測をするための研究を行っています。イノカの環境移送技術によって環境をモニタリング/制御しながら生物応答を調べることによって、将来予測に必要な生物応答プロセスをより深く理解できると期待しています。
パートナー研究室の募集について
本パートナー制度を活用したイノカの環境移送技術®️とコラボレーションにご関心のある大学教員および学生の方々との幅広い意見交換の窓口を設置します。
環境移送技術®️の活用余地やご自身の研究への応用について、イノカスタッフとのカジュアルミーティングをご希望の方は、下記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:info@innoqua.jp
テーマ例
・海洋流出の可能性がある物質の各種海洋生態系への影響評価
・生育方法の発見
・遺伝資源の保存(生物資源ライブラリー)
・遺伝資源の利活用 / バイオリソース
※上記に限らず、幅広いテーマでの意見交換の機会を歓迎いたします。
株式会社イノカについて

イノカは「自分たちが好きな自然をみつづける」をフィロソフィーに掲げ、国内有数のサンゴ飼育技術を持つアクアリスト(水棲生物の飼育者)と、東京大学でAI研究を行っていたエンジニアがタッグを組み、2019年に創業したベンチャー企業です。
「人類の選択肢を増やし、人も自然も栄える世界をつくる」をミッションに掲げ、自然を愛し、好奇心に基づいて飼育研究を行う人々の力と、IoT・AI技術を組み合わせることで、任意の生態系を水槽内に再現する『環境移送技術®️(※1)』の研究開発を推進しています。2022年2月には世界初となるサンゴの人工産卵実験に成功しました。
当社は、遺伝資源(※4)を含む海洋生物多様性の価値を持続可能にすることを目的として、「自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:以下「TNFD」)」の「TNFDデータカタリスト」にも参画しています。
※4 遺伝資源:生物多様性条約においては「遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物、その他に由来する素材のうち、現実の、又は潜在的な価値を持つもの」と定義される。全ての生物は遺伝子を持っており、医薬品開発やバイオテクノロジーの素材として役に立つ可能性がある。
会社名 株式会社イノカ
代表者 代表取締役CEO 高倉 葉太
設立 2019年4月
所在地 東京都文京区後楽2丁目3番地21号
すべての画像
