能登官民連携復興センターの取り組みについて
~2024年10月の設立から1年~
能登の創造的復興に向けた広域的な中間支援組織として、2024年10月に「能登官民連携復興センター」(以下「センター」)が設立されてから1年が経ちました。
これまで、全国から寄せられる様々な支援の受け皿となり、ロックユニット「COMPLEX」からの寄附金の活用や、LINEヤフーや経済同友会との連携などの取り組みを通じて、復興に取り組む地域団体等に対し、「資金」「人材」「ノウハウ」といった支援を効果的に結びつけてきました。
組織は、8名体制で発足して以降、徐々に拡充し、現在は、藤沢烈センター長のもと、地域団体の伴走支援を担う「事業推進部門」、企業・団体等からの支援調整を担う「広域連携部門」、庶務等を担う「管理運営部門」の3部門、計16名体制で運営しています。
職員は、石川県職員のほか、民間企業、JICA、地域おこし協力隊など、官民多様な分野から参画しています。
センターの具体の取り組みとしては、
■「資金支援」の取り組み
ロックユニット「COMPLEX」などからの寄附金を活用した「能登復興支援事業」では、能登の未来を創る先導的な取り組みを支援しています。
1次公募では、253件の応募の中から、「アーバンスポーツを中心とした子どもたちの居場所づくり」、「宝立七夕キリコ祭り復興プロジェクト」など、6件の取り組みを支援します。
また、7月から9月にかけて実施した2次公募では、123件の応募があり、現在、外部有識者等による審査が行われています。
クラウドファンディングの活用支援については、復興に向けた様々なプロジェクトの資金調達手法として、クラウドファンディングの活用を後押ししています。
クラウドファンディング事業者に支払う手数料等について、最大100万円まで助成しており、地元住民による地域コミュニティの拠点となるマルシェの整備など、6件のクラウドファンディングが実施され、今後、更に増えていく見込みとなっています。
休眠預金を活用した支援として、休眠預金の資金分配団体である(一社)RCFと連携し、まちづくりや生業再建の取り組みを支援しており、11件を採択し、各団体につき1,500万円程度を助成し、その活動を伴走支援しています。
例えば、地元金融機関である「興能信用金庫」と「のと共栄信用金庫」が連携した「しんきん能登復興コンソーシアム」では、被災した小規模事業者の商品を詰め合わせたギフトセット「NOTO TSUMUGU.(のと つむぐ)」の開発・販売を支援しています。
■「人材支援」の取り組み
スポットワークの活用による被災事業者の人手不足の解消支援については、(株)タイミーが提供するスポットワークのマッチングサービスを活用し、被災事業者のスポット的な人材確保を支援しています。
センターがILAC(いしかわ就職・定住総合サポートセンター)や金融機関等と連携し、能登のスポットワーク需要の掘り起こしを行い、センターが呼びかけた事業者において、新たに500回以上のスポットワークの求人が行われ、約5割がマッチングしました。
大手求人サイトを活用した地域団体等の人材確保支援については、地域団体等の組織づくりや事業全体の企画・管理を担う「中核的な人材」の確保に向けた採用活動の支援として、大手求人サイトを活用して、能登の復興に関心のある全国の人材に幅広くアプローチし、また、面接や採用手続きの支援も行うなど、採用までの総合的なフォローアップを実施するもので、事業開始に向け、準備を進めています。
■「ノウハウ支援」の取り組み
LINEヤフーと連携したプロボノ支援として、専門性やノウハウを活かした社会貢献活動「プロボノ」支援のマッチングを行っており、これまでに22名の同社社員の方々が、10事業者に対し、SNS運用のサポートなどを実施しています。
また、今月からは、LINEヤフーに加え、6社の企業が社員のプロボノ派遣に参画していただくこととなり、例えば、NECとLINEヤフーの社員の方々が協働し、事業者のシステム構築を支援するなど、各社のノウハウを活かしたプロボノ支援を展開し、支援の輪を更に拡大していきます。
■「広域連携」の取り組み
(公社)経済同友会との連携について、能登の復興に向けて経済同友会の会員が能登内外のプレイヤーや自治体等と対話し、支援プロジェクトのあり方を議論する「のとマルチセクター・ダイアローグ」にセンターも参画し、各種プロジェクトの実現に向けた議論を推進しています。
これまでに全2回開催され、関係人口、子ども・教育、復興拠点、アート、食、ディザスターシティなどのテーマに分かれて議論が行われています。
■「支援体制の強化」の取り組み
今後本格化する地域の復興まちづくりに向けて、センターを核とした中間支援機能を強化するため、地域の実情をよく知り、様々なノウハウを持つ団体をセンターの「連携パートナー」として選定し、連携パートナーとセンターがタッグを組み、様々な関係者と協働しながら、各地の取り組みを支援する体制を構築していきます。
また、地域の課題や取組状況を関係者間で共有する場を設置し、県内自治体や地域団体など、関係者同士の関係構築にも取り組んでいくこととしており、事業開始に向け、準備を進めています。
センターの取り組みは始動したばかりであり、今後、被災地の復興が本格化していく中で、センターが担う役割や県民の方々の期待は一層高まっていくと考えられます。
センターが、県内の自治体や関係者との連携をさらに強化し、地域を支えていくことにより、創造的復興を加速させる原動力となるよう、石川県としてもしっかりとサポートしていきたいと考えています。

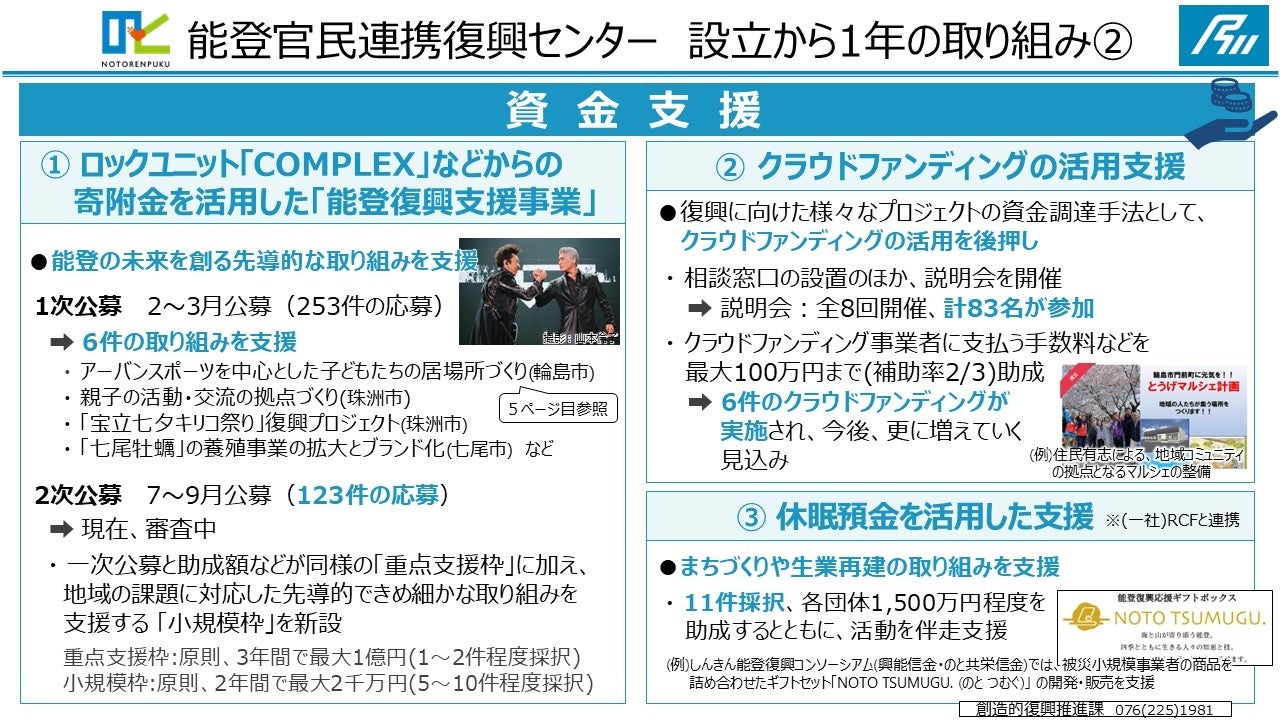
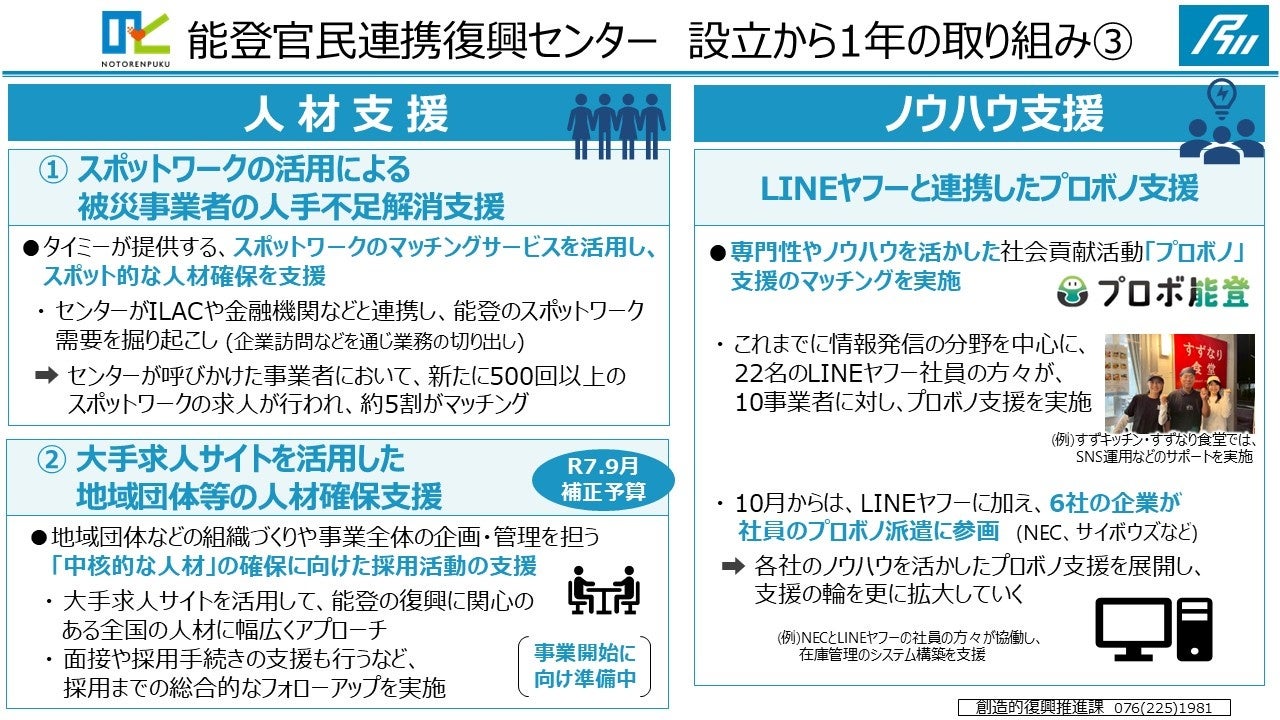
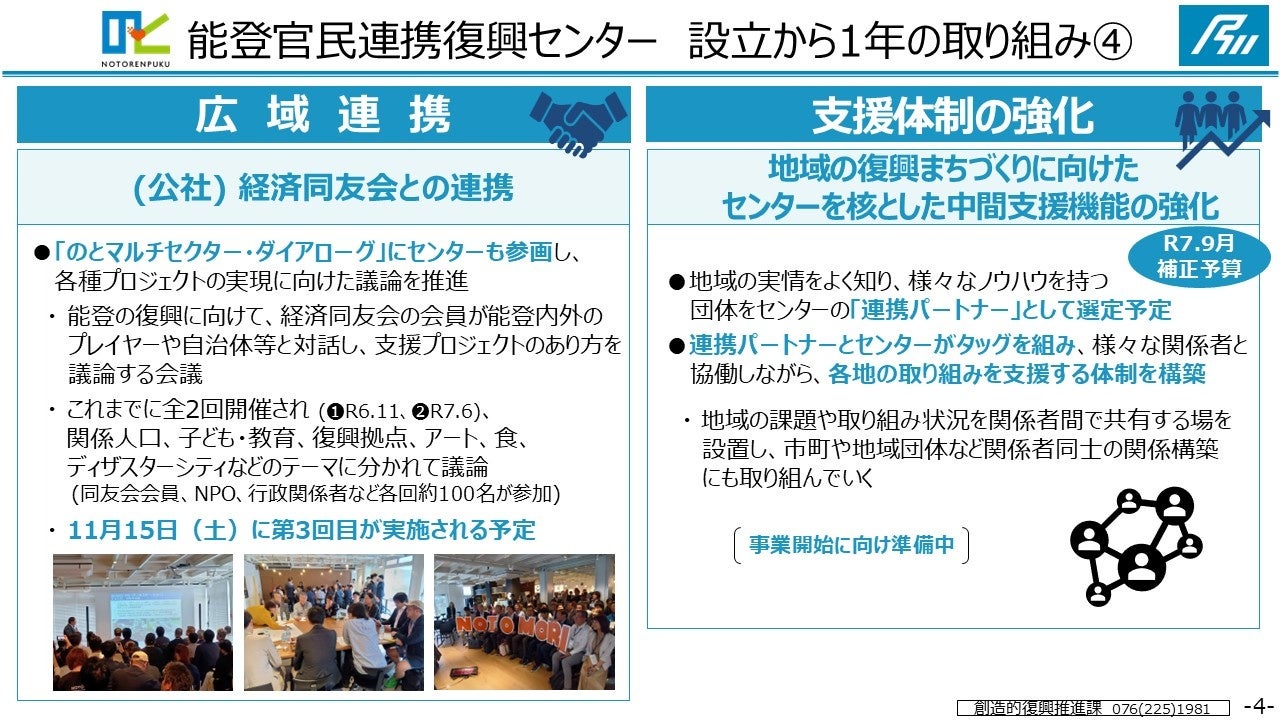
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
