第1回『医師・地域連携 子ども支援助成』採択団体を決定 小児科医が「子どものこえ」を聴き、職種や立場をこえて取り組む活動を支援
小児医学・医療・保健の発展のため、小児医学研究者への研究助成や小児医学を志す医学生への奨学金給付などを行う公益財団法人川野小児医学奨学財団(所在地:埼玉県川越市、理事長:川野幸夫/株式会社ヤオコー代表取締役会長)は、2025年6月からスタートした新助成事業「医師・地域連携 子ども支援助成 -子どものこえからはじまるアドボカシー活動-」の第1回採択団体を決定しました。

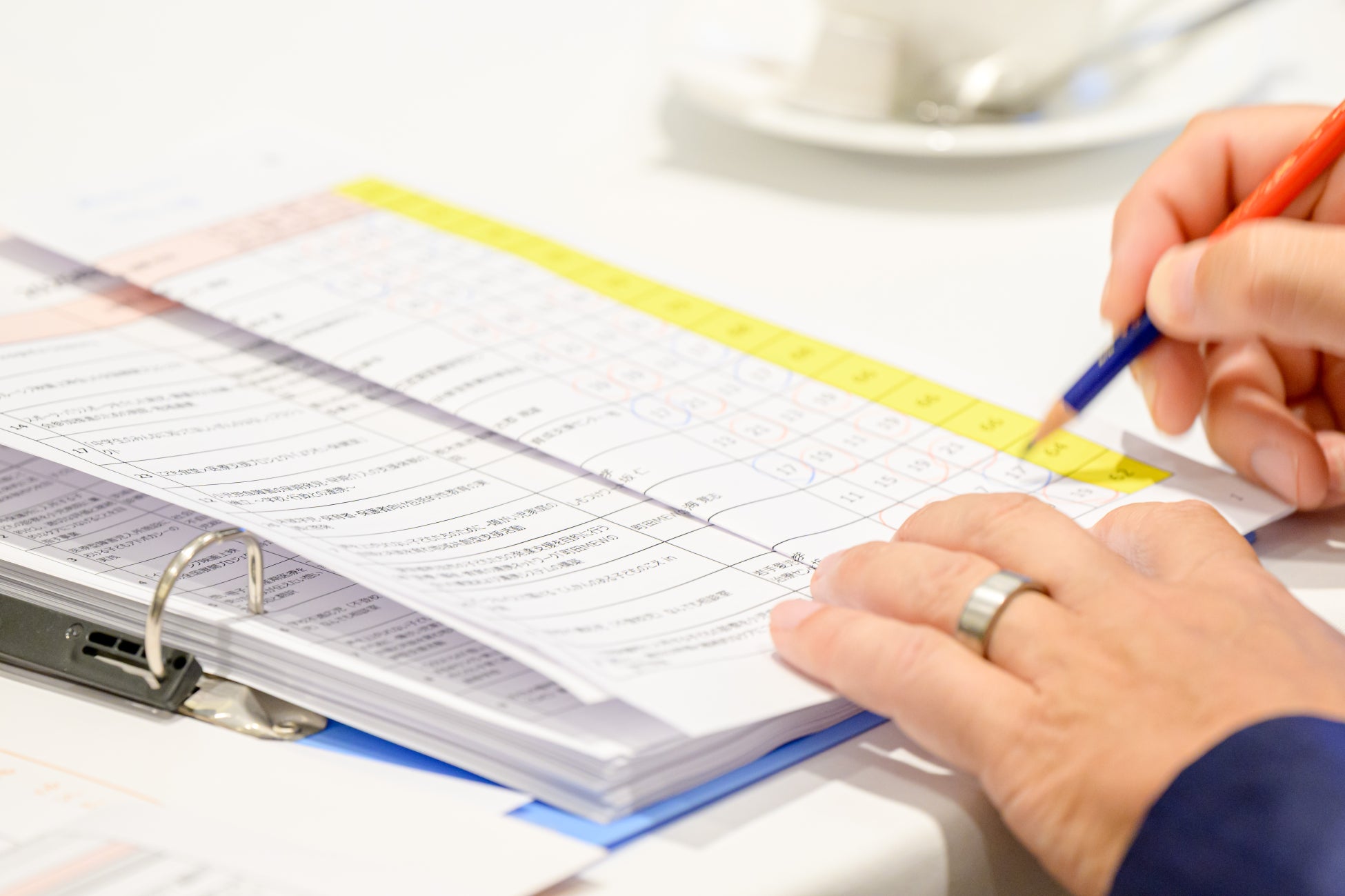
■本事業の概要と特徴
本事業では、小児科医を中心とする医師が「子どものこえ」を通じて明確化した問題について、地域と連携して解決にむけ取り組む活動に対して、1件あたり最大70万円を助成いたします。
資金面の支援に加え、各採択団体が目標とする成果を確実に達成できるよう、伴走支援を行っていきます。定期的な面談を通じて課題や進捗を把握し、財団としてサポートしていく予定です。また、2027年には活動の成果や学びを共有し合う成果報告会の開催も予定しております。
■本事業のねらい
近年、子どもを取り巻く問題はますます複雑で多様化しています。
こうした問題に向き合い、子どもたちの健康をこれまで以上に支えていくためには、職種や立場を問わず、子どもに関わるすべての人が「子どものこえ」に耳を傾け、連携して取り組むことが重要になっています。医療においても、社会に働きかけて変化を促す「アドボカシー」というアプローチが求められています。
小児科医や子どもに関わる医師は、日々の診療の中で「子どものこえ」に接し、子どもたちが抱えるさまざまな問題に直面しています。だからこそ、彼らが「子どもの代弁者」として、他の専門職や地域と連携しながら問題の解決に取り組むことは、大きな意義があります。
しかし、日本では小児科医によるアドボカシー活動への理解や認知はまだ十分とは言えず、活動の開始や継続に必要な資金的な支援もほとんどありません。アドボカシー活動を促進し子どもたちを取り巻く問題の解決につなげるため、2025年度より本事業を開始いたしました。
■2025年度「医師・地域連携 子ども支援助成」採択団体一覧
採択件数:5件 助成総額:2,999,181円

|
団体名もしくは代表者名 |
具体的な活動内容 |
助成額 |
|
社会医療法人天神会まどかファミリークリニック 小児科医 丸山 大地 |
「VOICE(Voices Of Insightful Children's Expressions)」 取り組む課題: 在宅医療的ケア児の多くは移動や発話が困難であり、本人の意思や感情をうまく伝えることができない。一方、支援現場では、限られた時間や人的資源の中で家族の負担軽減が優先され、子ども本人の「声」が十分に受け止められていない現状がある。 成長に伴って成人医療や福祉へと移行する際の「ケアの崖」を乗り越えるためにも、本人の意思を起点とした支援体制の整備が急務である。 具体的な活動予定: 在宅医療・福祉・教育の関係者が集まり、多職種連携カンファレンスを開催。それぞれの立場から受け取った医療的ケア児の「声なき声」を共有・可視化し資料を作成する。資料は子どもの「好き・嫌い・安心できること・不安なこと」などを言語・非言語的表現を含めて整理し、支援現場でも即座に活用できるようにする。さらに、専門家による講演会や対談を通じて支援者が「子どもの声」の捉え方を学ぶ機会を設ける。 |
348,301円 |
|
豊川市HPVワクチン接種検討委員会 (豊川市医師会内) |
「『中学生のみんなに知ってほしいがんのはなし』プロジェクト」 取り組む課題: HPVワクチンの定期接種対象者である小6~高1相当の女子と保護者は、正しい情報へのアクセスが十分ではなく、ワクチン接種に対して不安や迷いを抱えている実態がある。正しい知識を丁寧に伝え、命の大切さと、若い世代のがん・子宮頸がんはワクチンで予防できることを学び、ワクチン接種を促していきたい。 具体的な活動予定: 市内の希望する中学校にて生徒・保護者・教職員対象に、医師会、保健センター、教育委員会、外部講師が連携して、がんサバイバーによるがん出前講座を実施する。「がんの原因として感染症がありワクチンで予防できるがんがある」、「HPVワクチンの有効性と安全性」等を伝える。 また、学習用小冊子も作成し、市内全中学生、全教職員及び学校医等関係者に配布を行う。 |
630,880円 |
|
地方独立行政法人大阪市立総合医療センター 小児脳神経・言語療法内科 医長 温井 めぐみ |
「パープルバスで届ける てんかんのある子どものこえin 大阪」 取り組む課題: てんかんは小児期における慢性疾患の中でも頻度が高い疾患である一方で、誤解や偏見が根強く残っており、過度な行動制限は子ども達の成長や自己肯定感に深刻な影響を与えている。てんかんのある子どもや家族は、診断や日常生活のなかで「言い出しにくさ」や「社会との断絶」を感じることが多い。 地域の教育機関・企業との協働により、てんかんのある子どもや家族の「こえ」を地域・社会への届ける代弁者となり、「私はてんかんです」と安心して言える社会の実現に取り組んでいきたい。 具体的な活動予定: てんかんのある子どもや家族の「こえ」をデザインしたマグネットシートで車体を装飾した車いすリフト付きのバスで大阪府内を巡回する。途中、協力企業(近鉄百貨店など)の敷地や公共空間に停車し、子どもや家族の「こえ」を届けるパネル展示、交流イベントを行う。SNSでの動画配信も企画する。 |
700,000円 |
|
熊本大学大学院生命科学研究部 小児科学講座 |
「食物アレルギーと向き合う子どもたちの声から始める -ともに歩む支援のかたちを考える」 取り組む課題: 食物アレルギーを持つ子どもたちは、食べられないことへの不安や、アレルゲンを含む食物を恐怖感とともに摂取しなければならない葛藤を抱えている。一方、子どもたちの声が十分に反映されておらず学校や家庭での支援体制には不十分な点がある。子ども自身の語りから支援のかたちを捉え直し、医療・教育・家庭がよりよいかたちでつながるための実効性ある支援体制の構築を目指したい。 具体的な活動予定: 食物アレルギーの子どもや卒業生へのアンケートを通じて、子どもたちの日常生活や食事に関する思い・経験を聞き取る。学校現場の実情や支援状況を把握し、子どもの声と合わせて多面的に分析・整理し、「子どもの声に学ぶ支援のヒント」として資料化。医療者、教育関係者、保護者間で共有し、誰もが安心して「食べられる」環境づくりをめざし、地域全体で理解と支援を広げる。 |
700,000円 |
|
愛知県医療療育総合センター中央病院 |
「先天性遺伝性疾患の成人移行期支援及び成人期医療の実態調査と支援」 取り組む課題: 先天性遺伝性疾患を持つ子どもは、多くの身体的な合併症や知的障害も伴い、小児期及び成人期に医療や福祉の支援を必要としている。一方で、成人期の健康管理の情報は不足しており、医療体制も整っていない。 「子どものこえ、家族のこえ」を聞き現状把握した上で、先天性遺伝性疾患の子どもが成人期も必要な医療福祉を受け、子どもとその家族が充実した生活が送れるように、医療者としてできることを取り組んでいきたい。 具体的な活動予定: 当事者や支援者の移行期医療に関するニーズと課題についてアンケート調査を実施。結果を分析し、医学的妥当性と当事者視点の両面から疾患フォローアップガイドを作成する。 外来にて患者・家族を対象に早期移行準備支援を試行的に実施するほか、他の希少疾患の患者会や講演会などで継続して発信していく。 |
620,000円 |
■採択団体決定までのプロセス
事業を開始して第1回目の募集となりましたが、全国の大学病院や地域のクリニック、非営利団体などから26件の申請がありました。厳正な書類選考を経て、本事業選考委員による選考委員会を開催いたしました。選考委員は、医師が地域と連携して行う活動の特性を踏まえ、多職種から構成された4名の専門家で構成されています。
選考委員会では、「子どものこえが適切にすくい上げられているか」「地域との連携の度合い」「当財団の助成の必要性」などの多角的な視点から選考が行われましたが、いずれの団体の活動も子どもたちにとって非常に重要であることから選考は困難を極めました。
今年度は5つの団体が採択され、社会的意義と実現可能性の高さが特に評価されました。

■皆さまからの声
<申請者>

地域連携や当事者の子どもを大切にした研究課題の募集は大変ありがたいと思いました。これからも子どもたちのために頑張ってください。

このような助成金支援活動があることを知り申請いたしました。大変勇気づけられました。これからも地域で生活するすべての子どもたちのために、様々なアドボカシー活動に取り組んでいきたいと思いました。仲間の小児科医へも紹介させていただきました。
<選考委員会議長> 国立成育医療研究センター 総合診療部 緩和ケア科 診療部長 余谷 暢之
小児科医が日常診療で直面する医療のみでは解決できない課題について、他の医療者や地域社会と連携し、社会全体で捉え取り組むことは、小児医療の専門家として重要な責務です。この活動を支援すべく、当財団が本助成事業を立ち上げました。
初回26件の申請は、関心の高まりと、多くの小児科医がこれまで積極的にアドボカシー活動に取り組んできた証です。厳正な審査で5件を採択しましたが、残念ながら採択に至らなかった課題の中にも、重要なものが多く含まれていました。本事業が、子どもたちの未来に向けた力強い第一歩となることを心から願っています。
<財団事業担当者>
事務局の当初の想定を大きく上回る26件の申請が寄せられ、全国での関心の高さと期待の大きさを実感いたしました。申請を通じて、当財団でも予想をしていなかった見過ごされがちな課題が存在することを知り、活動の社会的価値の高さを感じております。
また申請者アンケートでは、75%が「当財団の助成金で初めてアドボカシー活動に対する助成事業を知った」と回答しており、多くの課題、また小児科医のアドボカシー活動がこれまで十分に支援されてこなかった事を改めて認識しました。
■財団概要
財団名:公益財団法人川野小児医学奨学財団(〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-10-1)
理事長:川野 幸夫(株式会社ヤオコー 代表取締役会長)
設立:1989年12月25日(行政庁 内閣府)
URL:https://kawanozaidan.or.jp/
TEL:049-247-1717
Mail:info@kawanozaidan.or.jp
事業内容:研究助成/奨学金給付/小児医学川野賞/医学会助成/小児医療施設支援/
ドクターによる出前セミナー/医師・地域連携 子ども支援助成
<創業ストーリー>
財団の創業ストーリーや事業のエピソードをPR TIMES STORYで紹介しております。
どうぞご覧ください。
失われた息子の命をきっかけに設立した「川野小児医学奨学財団」
ー小児医療をめぐる課題に取り組む中で感じた、子どもたちの心と体を守るために必要なこと
https://prtimes.jp/story/detail/rX5NvZs7GXb
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
