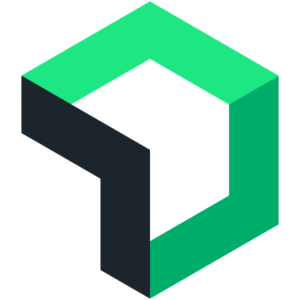三菱UFJ eスマート証券、オブザーバビリティ(可観測性)プラットフォーム「New Relic」の導入により、システム障害の検知・対応能力を向上
膨大な証券取引のトランザクションを支える中核システムを可視化し、システム開発・運用に携わる全技術者がシステムの状態やログを確認できる体制を確立
デジタルビジネスにオブザーバビリティ(可観測性)プラットフォームを提供するNew Relic株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小西 真一朗、以下「New Relic」)は、三菱UFJ eスマート証券株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役会長兼社長:二宮 明雄、以下「三菱UFJ eスマート証券」)が、オブザーバビリティプラットフォーム「New Relic」を導入し、システム障害の検知・対応能力を向上したことを発表します。
導入の背景と経緯
三菱UFJ eスマート証券は、長年にわたって、ネット証券の市場を牽引する企業として成長と発展を続けてきました。2019年からは、三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」)とKDDIグループが共同出資する「auカブコム証券」として事業を展開。近年も堅調に証券口座の数を増やし、2025年度(2025年3月期)も、月平均約1万のペースで新規口座を獲得(*1)、2025年1月時点の証券口座数は179万以上に達しています。2025年2月には、三菱UFJ銀行の100%子会社となり、社名を現社名「三菱UFJ eスマート証券」へと変更し、新たなスタートを切っています。
三菱UFJ eスマート証券では、ネット証券事業の核となるシステムとして、「新スマホシステム(現「三菱UFJ eスマート証券アプリ」のシステム)」を提供しています。同システムでは、「国内株式」「米国株式」「投資信託」「先物」「オプション」「NISA」「つみたてNISA」「クレカ積立」といった各種商品の取引ができるほか、180銘柄を登録できるリアルタイム株価ボードや高機能チャート、資産状況・投資成績が一目で確認できる仕組みを提供しています。2023年、この新スマホシステムにおいて、アクセスが集中する取引開始時刻の午前9時に障害が発生しましたが、同システムは、多種多様な外部システムとフロントエンドの各機能が複雑に連携するシステムであったため、それまでのログを中心とした監視の仕組みでは、障害原因を特定することができませんでした。同社では、この出来事をきっかけに、システムの状態を可視化するとともに、システムに関する属人性を可能な限り低減させ、このような問題を抜本的に解決するソリューションとして、オブザーバビリティプラットフォーム導入の検討を進めました。
New Relicの導入と効果
オブザーバビリティプラットフォームの選定においては、複数のツールを比較検討した結果、豊富な機能をシンプルな料金体系で利用可能なことから、New Relicの導入を決定しました。特に三菱UFJ eスマート証券では、システムだけではなく、その開発を行うための多数のステージング環境も本番環境と同様に観測したいと考えていたため、サーバー単位の課金では料金がかなり膨らむことが予想されました。これに対してNew Relicは、ユーザー数やデータ転送量をベースにした分かりやすい料金体系となっており、同社の環境や目的に合致するものでした。
同社は、2023年11月からNew RelicのPoC(概念実証)を実施、2024年2月に本格導入に至りました。導入当初の観測対象は新スマホシステムのみでしたが、その後、PC上で株価情報やニュースを配信する投資情報ツール「kabuステーション」や法人向けAPIサービス「kabu.com API」へと観測対象を広げていきました。
三菱UFJ eスマート証券では、New Relic活用における第一段階の目標をシステム技術者に対するシステムの見える化に設定しています。従来は、システムに問題が発生した際、当該システムの開発チームから基盤グループにイベントログの確認依頼があるのが標準的なフローであったため、初動が遅れてしまうという課題がありました。New Relic導入後は、無料提供される「ベーシックユーザー(*2)」ライセンスを活用することで、システムの開発・運用に携わる全技術者が、共通のプラットフォームを通じて、システムの状態やログを自ら確認できるような環境が確立されました。また、これまでは外部の協力会社に依頼して人手で行ってきたシステムの外形監視(*3)もNew Relicに置き換え、社内で効率的に完結できるようになりました。今後は、障害の早期発見に向けたアラートの活用なども進めていく予定です。
三菱UFJ eスマート証券 システム技術部 基盤グループ グループ長 池浦將登(まさと)氏 コメント
「今後は、お客様向けに提供する全てのシステムや新スマホシステムなどにつながる多種多様なシステムに、New Relicによる観測対象を広げていく予定です。最終的には1つの画面を通じて『システム上のどの処理が障害の原因になっているか』『どの処理がパフォーマンスのボトルネックになっているか』を突き止められるようにする計画です」
New Relic 代表取締役社長 小西真一朗 コメント
「高い信頼性が求められるネット証券事業のコアシステムの安定運用に、New Relicが貢献できることを大変うれしく思います。三菱UFJ eスマート証券様が、さらに高度な障害検知・対応能力を確立できるよう、今後もご支援してまいります」
*1 2024年4月~2025年1月の約10カ月間の実績。
*2 ベーシックユーザー:New Relicのオブザーバビリティツールの設定、データクエリの実行、ダッシュボードの利用、基本的なアラート機能などが使用できる無料のライセンス。
*3 外形監視:WebサイトやWebアプリケーションを、システムが稼働するネットワークの外側からアクセスし、ユーザー視点で利用可能な状態にあるかどうかを機械的に監視すること。
■「三菱UFJ eスマート証券」New Relicご採用事例の詳細は以下をご参照ください。
https://newrelic.com/jp/customers/mitsubishi-ufj-esmart-securities
■ 本プレスリリースのURLはこちらです。
https://newrelic.com/jp/press-release/20250326
■ その他のお客様によるNew Relic採用事例は以下からご覧いただけます。
https://newrelic.com/jp/customers
■ New Relicのファクトシートやロゴ等は、以下からご確認いただけます。
https://newrelic.com/jp/about/media-assets
■New Relicについて
2008年に創業したNew Relicは、業界におけるリーダーとして、デジタルビジネスのあらゆる重要指標を観測可能にする「オブザーバビリティ(可観測性)プラットフォーム」を提供しています。デジタルビジネスを構成するアプリケーションやインフラストラクチャだけでなく、ユーザー側の顧客体験状況までをも観測可能にするため、企業はデジタルサービスの障害検知、顧客体験の低下検知、潜在的な問題やボトルネックを早期特定し解決するDevOpsチームを生み出します。これにより、企業は取り組むべきデジタル変革を、計測可能な戦略へと変化させることができます。New Relicの全世界顧客数は16,000以上、Fortune 100企業の過半数で採用されており、日本でも数百社を超えるお客様のデジタル変革を支援しています。New Relicが支持されている理由は、newrelic.com/jp をご覧ください。
■オブザーバビリティ(可観測性)プラットフォーム「New Relic」の特長
New Relicはオブザーバビリティのリーダーとして、優れたソフトウェアの計画、構築、デプロイ、実行に対するデータドリブンなアプローチでエンジニアを支援しています。New Relicは、エンジニアがあらゆるテレメトリー(メトリクス、イベント、ログ、トレース)を取得できる唯一の統合データプラットフォームを提供し、強力なフルスタック分析ツールとの組み合わせにより、エンジニアが意見ではなくデータを用いて最高の仕事をできるよう支援します。New Relicは、シンプルで透明性の高い価格体系を採用しています。開発サイクルタイムの計画、変更失敗率、リリース頻度、平均復旧時間(MTTR)の改善を支援することにより、エンジニアに高い費用対効果をもたらします。
※New Relicは、New Relic, Inc.の登録商標です。
※本文書内の製品名および会社名は全て、それらの登録名義人の商標である場合があります。
将来予想に関する記述
本資料は関係情報の開示のみを目的として作成されたものであり、有価証券の取得または売付けの勧誘または申込みを構成するものではありません。本資料は、正確性を期すべく慎重に作成されていますが、完全性を保証するものではありません。また本資料の作成にあたり、当社に入手可能な第三者情報に依拠しておりますが、かかる第三者情報の実際の正確性および完全性について、当社が表明・保証するものではありません。当社は、本資料の記述に依拠したことにより生じる損害について一切の責任を負いません。本資料の情報は、事前の通知なく変更される可能性があります。本資料には将来予想に関する見通し情報が含まれます。これらの記述は、現在の見込、予測およびリスクを伴う想定(一般的な経済状況および業界または市場の状況を含みますがこれらに限定されません)に基づいており、実際の業績とは大きく異なる可能性があります。今後、新たな情報、将来の事象の発生またはその他いかなる理由があっても、当社は本資料の将来に関する記述を更新または修正する義務を負うものではありません。
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。