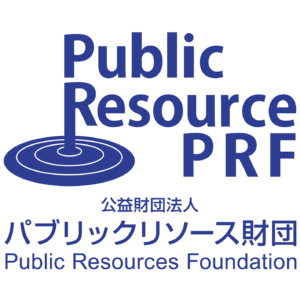【11/26(水) 13時30分ー オンラインセミナー第5弾 申込受付中】「これからの女性支援のあり方 ― 制度と現場をつなぐ視点から」
ウィメンズネット・こうべは兵庫県内にて「六甲ウィメンズハウス」を運営し、生活再建と社会的孤立の防止を柱とした支援を展開。本セミナーは、その取組成果を報告し、制度運用との接点を議論する。
女性の非正規雇用比率は半数を超えており、単身世帯で勤労世帯(20歳~64歳)の女性の約4分の1、65歳以上の女性の約半数が相対的貧困状態にあります(内閣府ホームページより)。さらに、コロナ禍により、不安定な職につく単身女性やシングルマザーが失業や収入減に陥る、虐待やDV被害などを受けている若年女性が家庭に居づらくなり居場所を失うなど、脆弱な環境下にある女性ほど、深刻な経済的困窮状態に陥る悪循環が生じています。
各都道府県に設置されている女性自立支援施設、女性相談支援員が受け付けた来所相談をみると、 20歳以上 では「夫等からの暴力」が、18~20歳未満及び18歳未満では「子・親・親族からの暴力」など の暴力を受けたことによる相談が最も高いとされています(厚生労働白書より)。
また昨今では物価高騰による生活圧迫も問題となっており、生活の基本が脅かされている実態が浮き彫りになっています。
そうした中、パブリックリソース財団(東京都中央区、代表理事・理事長久住剛)では、2022年度休眠預金活用事業※「様々な困難で困窮する女性の経済的自立支援事業」に採択され、実行団体(助成先団体)6団体を選定、2023年11月からこの課題解決を目指すため、プロジェクトを実施しています。
https://www.public.or.jp/project/f1017
DV、性暴力、孤立、経済困窮など複合的な困難を抱える女性に対し、「緊急期から居住・生活・就労まで切れ目ない支援モデル」の構築を目的とし、資金助成に加え、専門家による伴走支援、事業評価支援、全国ネットワーク形成支援を通じて、地域に根ざした包括的女性支援の体制づくりを推進しています。
今回、以下のとおり、実行団体による活動報告、および分野の専門家をお呼びしてのディスカッションを行う予定です。ぜひ多くの方にご参加いただき、困難な状況にある女性たちの現状を知っていただき、解決に向けての後押しをしていただければ幸いです。
「これからの女性支援のあり方 ― 制度と現場をつなぐ視点から」
◆お申込みフォーム
https://forms.gle/KBtVk7vDCSvKQWvJ9
※オンライン参加orアーカイブ配信希望、どちらかにチェックを入れてください。
◆開催概要
-
日時:2025年11月26日(水) 13時30分~15時30分
-
場所:オンライン配信(ZOOMウェビナー) ※アーカイブ配信有
-
参加費:無料
-
主催:公益財団法人パブリックリソース財団
共催:認定NPO法人 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ
◆開催趣旨
近年、困難な問題を抱える女性への支援をめぐる制度や体制は大きな転換期を迎えています。
2024年には「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行され、地域の女性支援団体や行政機関には、制度理解と実践力の双方を備えた支援体制の構築が求められています。
認定NPO法人女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべは、公益財団法人パブリックリソース財団による休眠預金活用事業「様々な困難で困窮する女性の経済的自立支援事業」に採択され、支援付き住宅「六甲ウィメンズハウス」を拠点に、居住支援・生活再建支援・就労支援等の多層的支援を展開してきました。
本セミナーは、当該助成事業の活動報告を兼ね、現場で明らかになった課題を踏まえて、行政・民間の現場の両視点から「これからの女性支援のあり方」を検討することを目的とします。
◆当日の流れ
-
開催のご挨拶
・公益財団法人パブリックリソース財団
-
基調講演
・有本 晃子 氏(兵庫県 福祉部 児童家庭課 家庭支援対策官)
└「兵庫県の女性支援の取組について」
└行政からの報告、困難女性支援法を踏まえた兵庫県の取組
-
講演
・正井 禮子氏(認定NPO法人 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ 代表理事)
└ 「現場から見た女性支援の現在地と今後の展望」
└ 困難を抱える女性支援の現場動向、居住支援・自立支援における課題、制度設計と現場実践のギャップについて
-
実行団体より活動報告
・鈴木 幸恵 氏(認定NPO法人 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ 事務局長)
・下園 美保子 氏(秋田看護福祉大学 教授/保健師・看護師/日本評価学会 認定評価士)
└事業名:困難を抱える女性のための「六甲ウィメンズハウス」整備と生活支援、就労支援
└六甲ウィメンズハウスにおける居住・生活支援の実践と課題、本事業の成果及び課題分析
-
パネルディスカッション
テーマ :「現場と制度のギャップをどう埋めるか」
└制度と現場の接点に焦点をあて、支援体制の継続可能性、専門職確保、行政・民間の協働体制構築に向けた課題を検討する。
<登壇者>
(1)正井 禮子 氏 (認定NPO法人 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ 代表理事)
(2)下園 美保子 氏 (秋田看護福祉大学 教授/保健師・看護師/日本評価学会 認定評価士)
(3)近藤 恵子 氏 (NPO法人女のスペース・おん 理事/NPO法人全国女性シェルターネット 理事/北海道ウイメンズ・ユニオン 執行委員長)
<モデレーター>
・山本 恵子 氏 (ジャーナリスト、元NHK解説委員)
◆休眠預金活用事業、実行団体プロジェクトの紹介
困難を抱える女性のための「六甲ウィメンズハウス」整備と生活支援、就労支援
(実行団体:認定NPO法人 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ)
事業の背景・社会課題としては、困難を抱える女性の住居取得の難しさがある。本事業では、民間遊休施設を借りうけて女性たちが安心安全に住める場へと改修・整備を行い、困難を抱える女性やその子どもたちを対象とした「六甲ウィメンズハウス」を開設する。そして、住居取得が難しい女性たちに対して住宅として、提供する。同時に、共有スペースを設置することによって就労支援や子どもの託児、相談支援等包括的な支援を提供する。
本活動によって、困難を抱える女性やその子どもたちに対して、包括的な支援付き住宅の提供が可能になる。さらに本事業をモデル事業としてノウハウ等を提示することによって、全国に同様の支援付き住宅の提供を可能にする。このことによって、最終的には、本事業の直接的受益者だけでなく、全国の困難を抱える女性に対して貢献することが可能である。
<ご参考>
-
休眠預金活用事業「様々な困難で困窮する女性の経済的自立支援事業」 サイト
-
NPO法人くまもと相談所 HP
-
セミナー開催報告(過去分)
第1回 『女性支援に求められるもの:研究と支援の現場より』(NPO法人ささえる/愛媛県)
https://www.public.or.jp/post/women-kyumin_seminar-1
第2回 「全国の母子ハウスネットワークを活用した伴走自立支援プログラム」(NPO法人全国ひとり親居住支援機構/神奈川県)
https://www.public.or.jp/post/women-kyumin_seminar2_houkoku
第3回 「若年女性の包括的支援の実践から見えた、持続可能な支援モデルとは」 (NPO法人さくらんぼ/神奈川県)
https://www.public.or.jp/post/women-kyumin_seminar3_houkoku
第4回 『くまもとにおける、官民協同で進める女性支援の未来について考える ~ 困難を抱える女性たちが私らしく生きていくために ~』(NPO法人くまもと相談所/熊本県)
<団体情報>
主催(資金分配団体):公益財団法人パブリックリソース財団
2000年に非営利のシンクタンク、NPO法人パブリックリソースセンターとして発足し、NPO など非営利事業体のマネジメント強化、SRI(社会的責任投資)にかかる企業の社会性評価やCSRの推進支援、そしてオンライン寄付をはじめとする寄付推進事業などを展開。2013年1月、これらの成果と蓄積を踏まえ、「誰かの力になりたい」という人びとの志を寄付で実現するために、個人や企業の資金力を社会的事業への投資につなぐ寄付推進の専門組織「公益財団法人パブリックリソース財団」として新たにスタート。「意志ある寄付で社会を変える」ことをミッションに、オンライン寄付サイト、テーマ基金、オリジナル基金、遺贈、相続財産による寄付など様々な寄付の方法を提供し、人生を豊かにする寄付、未来を切り拓く寄付の仕組みづくりに取り組む。
WEBサイト:https://www.public.or.jp/
共催(実行団体): 認定NPO法人 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ
男女が互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、その能力を発揮することができ、安心してのびやかに生きることができるよう、すべての人に対して、女性や子どもの人権の擁護や福祉の増進に関する事業を行い、男女共同参画社会の形成と子どもの健全育成の推進に寄与することを目的とする。女性や子どもが安心して自分らしく生きられる社会を目指し、DVなど多様な要因から困難な状況にある女性や子どもの支援を行っている。
WEBサイト:https://wn-kobe.or.jp/
<登壇者紹介>
基調講演
有本 晃子 氏
(兵庫県 福祉部 児童家庭課 家庭支援対策官)
・令和6年度から児童家庭課 家庭支援対策官として勤務。
・本県におけるDV対策及び家庭福祉対策に関する担当管理職として、令和6年4月の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行に伴う、県基本計画のスタートや県支援調整会議の立ち上げ等に尽力。WEBサイト:兵庫県/福祉部 児童家庭課
講演、パネリスト
正井 禮子 氏
(認定NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ 代表理事)
1992年に、市民グループ「ウィメンズネット・こうべ」を発足させ、男女共同参画社会の実現と女性の人権を守るため、さまざまな活動を行なってきた。1994年、女性が本音で話せて元気になれる場として「女たちの家」開設する(震災で失う)。
震災直後、「女性支援ネットワーク」をたちあげ、物資の配布、「女性のための電話相談」を開設、女性だけで語り合う「女性支援連続セミナー」などを毎月開催し、被災女性の支援を行った。女性の視点で震災を記録する活動も行う。
震災以降は主に「女性に対する暴力」の根絶、特にDV被害者支援に力を注ぎ、2004年には民間シェルターを開設、以降、現在まで400組以上の支援を行う。更に、居場所支援や居住支援など先駆的な取組みを行うほか、デートDV防止授業など暴力のないジェンダー平等な社会づくりに向けて啓発活動も行っている。
活動報告、パネリスト
下園 美保子 氏
(秋田看護福祉大学 看護福祉学部 教授/保健師・看護師/日本評価学会 認定評価士)
奈良県出身・在住。山間部の市町村で保健師として10年間勤務したのち、山梨大学大学院で疫学を、元日本社会事業大学教授の大島巌先生のもとで評価学を学ぶ。以後、東京・愛知・大阪の大学で保健師教育に携わり、現在は秋田看護福祉大学にてオンラインで教育・研究を行っている。
研究テーマは、セルフ・ネグレクト、高齢者の閉じこもり、精神障害のある方の地域生活支援、DV被害女性の居住支援など、SOSが出しにくい人々への支援体制の整備とその評価である。
日本評価学会認定評価士として、休眠預金等活用事業における実行団体支援や、成果評価・事後評価計画の設計支援に携わり、「アウトカムの可視化」「効率性」「出口戦略」の3観点を中心に、実践と理論をつなぐ評価を推進している。現場に寄り添いながら、事業の成果を社会に伝え、次の挑戦へつなげる評価の在り方を探求している。
パネリスト
近藤 恵子 氏
(NPO法人女のスペース・おん 理事/NPO法人全国女性シェルターネット 理事/北海道ウイメンズ・ユニオン 執行委員長)
1947年 香川県生まれ。
1993年 札幌市に女性の人権ネットワーク事務所「女のスペース・おん」開設。
1995年 第四回世界女性会議(北京)NGOフォーラム参加
1997年 道内初の民間サポートシェルターを開設運営
1998年 北海道シェルターネットワーク、全国女性シェルターネット設立。2001年のDV防止法制定および5度の改正作業に貢献。2011年より「よりそいホットライン」「DV+」など、DV・性暴力24時間全国フリーダイヤルに参加協力。暴力根絶をめざし、直接支援から政策提言まで幅広い活動をネットワークしている。
2018年 厚生労働省「困難な問題を抱える女性への支援に関する検討会」検討委員
2024年 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」制定
モデレーター
山本 恵子 氏
(ジャーナリスト、元NHK解説委員)
1995年NHK入局。金沢放送局、東京・社会部を経て、2014年からNHKの国際放送「NHK WORLD JAPAN」で世界に向け英語でニュースを発信。
2019年6月より、名古屋放送局報道部 副部長(コンテンツセンター チーフ・リード)。
2017年7月より、NHK解説委員を兼務(ジェンダー・男女共同参画担当)。夕方のニュース番組「まるっと!」の「KYジャーナル」で身近なジェンダー問題を解説。
2024年9月 フリージャーナリストとして独立。
2001年女性ジャーナリストの勉強会を設立し、 1000人を超えるメンバーとともに、教育、働き方改革、ジェンダー問題など、世の中のよい変化につながる発信をつづけている。
2009年アジアソサエティより、アジアの若手リーダー「Asia21フェロー」に選ばれる。
東京大学大学院情報学環客員研究員。高校生の母。
WEBサイト:https://keikoyamamoto.jp/
<お申込みフォーム>
https://forms.gle/KBtVk7vDCSvKQWvJ9
※オンライン参加orアーカイブ配信希望、どちらかにチェックを入れてください。
※本会は休眠預金活用事業による助成金によって開催いたします
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。