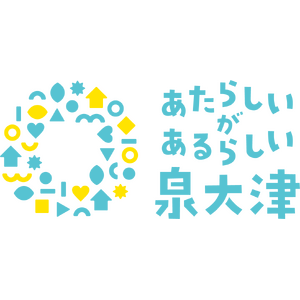“フルーツの町”和歌山県かつらぎ町で、泉大津市のこども特派員が農業体験に挑戦!
~みかん狩りや木工体験を通じて、“食”と“ものづくり”の魅力を学ぶ~
泉大津市(市長:南出賢一)では、「市民の健康増進」および「食料危機への備え」を目的に、令和6年10月より和歌山県かつらぎ町と農業連携協定を締結し、本市の学校給食でかつらぎ町産みかんを提供するなどの連携を進めてきました。今回は新たな連携として、泉大津市のこどもたちが連携先に訪問し、現地で直接生産者から「食」について学び・体験し・発信する「こども特派員」事業を実施します。
「こども特派員」事業とは、こどもたちの健全な育成に繋がる地域間交流活動を通じた原体験機会の創出を図るとともに、こどもたちが自ら市の魅力を発信し、他地域との交流から学ぶことによる市民としてのシビックプライドの醸成を図ることを目的としています。毎回定員を超える申込みがあり、特に今回は、募集定員の7倍を超える72組の申込みがありました。
訪問先となるかつらぎ町は、温暖な気候を活かしたみかんの名産地として知られています。泉大津市の学校給食において、昨年度かつらぎ町産の「みかん」を提供しており、今回のこども特派員では、みかん農園を訪問し、収穫体験や生産者へのインタビューにも挑戦。普段食べている果物がどのように育てられているかを、自分の目で確かめ、味わい、生産者から直接お話を聞きながら学びます。
また、かつらぎ町は、北を和泉山脈、南を紀伊山地に仰ぐ山間・丘陵地帯であり、山地の森林資源が豊富であることから、「木育」や「森林環境教育」も推進しています。今回のこども特派員では、地元の木工職人の指導のもと、木工体験も実施。地域資源を活かした「ものづくり」の魅力にもふれ、持続可能な暮らしや環境への理解を深めます。
泉大津市は、市域に占める農地面積が2.2%と非常に小さく、市内のこどもたちが直接、自然や農林業とふれあう機会が限られています。このような背景から、未来を担うこどもたちに自然豊かな地域との交流を通じ、こどもたちが「食」や「環境」、「地域文化」について五感を使った多様な学びを得てもらうことが狙いです。
〈イベント概要〉
■日程:令和7年11月29日(土)
■場所:和歌山県かつらぎ町
■主なプログラム:
• みかん狩り(雨天時は柿の渋抜きまたはつるし柿体験)
• MYお箸づくり(木工体験)
• 生産者への取材
• 取材記事の作成・発表会
(参考)泉大津市の「食」に関する主な取組み
①安全・安心な食糧の安定的確保に関する構想
令和5年3月に策定。生産地との「共存共生の関係性」による独自の食糧サプライチェーン構築を目指した構想。農地の少ない泉大津市は、将来的な不測の事態が発生した際に市民の暮らしを守れるだけの安定的な食糧確保が困難である一方、生産地では、農業従事者の減少・高齢化、農地面積の減少といった状況が続いており、食糧生産基盤の強化が喫緊の課題となっている。給食など一定の食糧需要がある都市部の自治体と生産地の自治体が相互のリソースを活用し、泉大津市にとっては食糧の安定的な確保を、生産地にとっては生産者の所得安定や休耕地の活用、新たな担い手確保など、それぞれの課題を補完できるような連携を創出しながら、「市民の健康増進」及び「食料危機への備え」に取り組む。
②かつらぎ町との連携
泉大津市では、「安全・安心な食糧の安定的確保に関する構想」の実現に向けた農業連携先となる自治体を募集し、令和6年10月にかつらぎ町と連携協定を締結。
同町は、温暖で恵まれた気候から年間をとおして果樹栽培が行われる“フルーツ王国”で、「かき」や「すもも」などの様々なフルーツ(一部有機JAS認証を取得)が栽培・収穫されている。
今回の連携における具体的な取組みとして、「みかん」を泉大津市の学校給食で提供するところからスタートさせ、子どもの健全な育成発達や食育を図る。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
- 種類
- イベント
- ビジネスカテゴリ
- 政治・官公庁・地方自治体
- ダウンロード