「気候変動、ユース世代により深刻な影響ー進学・就職選択に加え、女の子が直面する特有の不安も」~ガールズ・リーダーシップ調査2026 速報結果~
防災月間に寄せて、SDGsの実現を目指し、若者と女性の声の反映を
国際NGOプラン・インターナショナル(所在地:東京都世田谷区 理事長:池上清子 以下、プラン)は、2025年8月に全国の15〜39歳の若者2,070人を対象に「気候変動の実感」に関してオンライン調査を実施。今回の速報では、ユース世代(15〜29歳)と30〜39歳を対比し、気候変動が教育・就労・キャリア設計に与える影響を明らかにしています。
気候変動への取り組みは「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標13「気候変動に具体的な対策を」として定められている国際目標
です。
9月の防災月間に本速報を発表することで、若者と女性の声を施策に反映させる必要性を提言します。
≫プランのSDGsへの取り組みについてはこちら

<調査概要>
≫調査名:ガールズ・リーダーシップ調査2026 速報
≫実施主体:公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン(調査実施協力:マクロミル)
≫実施時期:2025年8月
≫対象:全国15〜39歳の若者2,070人
≫区分:ユース世代(15〜29歳)1,242人/30〜39歳 828人
≫方法:オンライン調査
≫性別構成:女性50% / 男性50%
<速報ポイント>
① 8割超が気候変動を実感
15〜19歳および30~39歳で「非常に感じる」の割合が高い。年齢が低い場合“将来への不安”としての実感が強く、年齢が上がると“生活上の実体験”としての実感が強まる傾向が見られる。
② 直近5年の被災・影響経験は多数、ユースほど家族単位の被災意識が高い
ユース世代、特に15〜19歳で「自分と家族の両方が影響」を受けた割合が高い。最も多い経験は「高温・猛暑(熱中症、屋外活動制限、授業中止など)」。避難経験の主因は「大雨・集中豪雨・洪水」「台風・強風」「降雪・大雪」。
③ 進学・就職など人生計画にも影響ー若年男性で変更・検討が相対的に高い
15〜19歳は「志望校・進学先の変更」が突出して高く、進学段階にある若者にとって、通学の安全性や災害リスクが進学先選びに直接影響していることを示している。30代では「柔軟な働き方の選択」や「移住の検討」など、ライフスタイル全体を見直す傾向が強い。
④ 災害時の負担や配慮にジェンダー差ー10代女性で安全・プライバシー不安が高い
災害・復旧時の役割分担や、避難環境での安全・プライバシー不安、意思決定参加の不均衡を指摘する声がある。女性20代では「気候問題に関する自分の意見が軽視・無視された」との経験が突出。15〜19歳女性では「生理用品・着替えを言い出しにくい」など特有の困難が相対的に高い。
⑤ 若者の行動意欲は高いが機会不足も
15〜19歳男性は行動・行動意欲が全体平均を上回る一方で、「何もしていない」回答も多く、機会不足の可能性。
⑥ 情報源はSNS・メディアが中心ー10代は学校での学びが多い
年齢が上がるほどメディア(TV・新聞など)からが多く、10代では学校からの取得が多い。
⑦ 政策・防災計画への反映実感は乏しいー「とても反映」は3.2%
若年層ほど「反映されていない」との認識が強く、政策決定プロセスからの疎外感がうかがえる。
≫調査速報の詳細はこちら
d12939-279-df07369678f942870be0cca02d762d43.pdf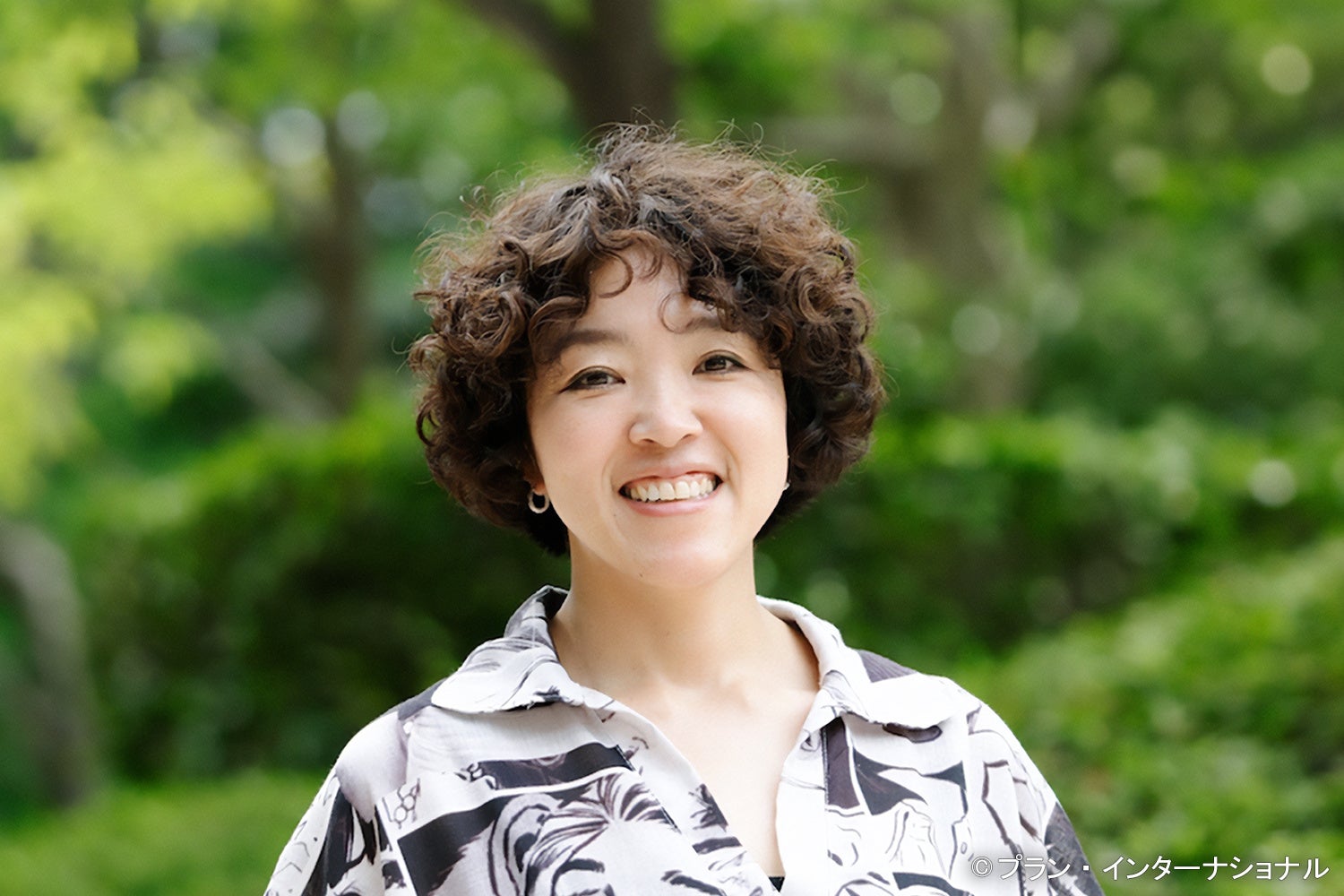
長島美紀(アドボカシーグループリーダー、政治学博士)のコメントおよび提言:
9月の防災月間にあたり、今回の調査結果は、気候変動が単なる環境問題にとどまらず、教育や就職、そして若者の将来設計にまで深く影響していることを改めて浮き彫りにしています。
特に、ユース世代、なかでも10代・20代の若者たちは、将来への選択肢が制限されたり、自らの声が政策に反映されにくいと感じたりしている現実があります。災害時におけるジェンダーによる負担の差や、安全・プライバシーに対する不安の声も見逃せません。
私たちは、若者や女性の声が防災・気候政策の中で当たり前に尊重され、反映される社会を目指さなければなりません。教育、行政、メディア、そして私たち市民社会がそれぞれの立場でできることを今、問い直すべき時です。
本調査が、多くの方々にとって“聞くべき声”に耳を傾けるきっかけになることを願っています。
※本調査のフルバージョンは、2026年1月に公開を予定しています。
※本レポートについてご取材をご希望の場合は、広報担当までご連絡ください。
国際NGOプラン・インターナショナルは、誰もが平等で公正な世界を実現するために、子どもや若者、さまざまなステークホルダーとともに世界80カ国以上で活動しています。子どもや女の子たちが直面している不平等を生む原因を明らかにし、その解決にむけ取り組んでいます。子どもたちが生まれてから大人になるまで寄り添い、自らの力で困難や逆境を乗り越えることができるよう支援します。
すべての画像
