葡萄屋kofu 金子 博文 グランシェフ等が山梨県産果物に対する溢れる想いを語る 山梨県富士川町産の柚子をメイン食材にスイーツスキルアップ講習会を開催
山梨県(知事:長崎幸太郎)は、令和7年1月19日(日)、山梨県立博物館内(山梨県笛吹市)にある Museum café Sweets lab 葡萄屋kofu(運営:株式会社プロヴィンチア(山梨県甲府市) 代表取締役 古屋 浩)において、山梨県富士川町産の柚子をメイン食材にしたスイーツスキルアップ講習会を開催しました。

当講習会は、本県の観光消費額の向上を目指し、県産果実を活用したスイーツの県内での提供品数や提供場所の拡大を図るため、県内のスイーツの製造や創作に関わるパティシエ等を対象に、昨年度から回を重ねて開催しているものです。
今回は約10人が参加し、金子グランシェフによる素材の扱い方のデモンストレーションに加え、有識者による柚子の伝来や食文化に関する説明も行われ、参加者は素材に対する理解を一層深めることができました。
1.イントロダクション
株式会社プロヴィンチア 古屋 浩 氏
昨年、「Museum café Sweets lab 葡萄屋kofu」の開店メニュー開発をきっかけに、県産果実である富士川町産の柚子に関わるようになり、その素材の素晴らしさに感銘を受けたことを紹介。柑橘に関わる活動を取り組む金子グランシェフの繋がりで、京都大学の北島宣名誉教授と合同会社EKR(高知県香美市)の百田美知氏をお招きし、研究成果や取組の説明、富士川町穂積地区の柚子に関連した講義をあわせた講習会を開催することとなったと挨拶しました。
2.講義『ユズはどこから来たのか?』
講師:京都大学 名誉教授 北島 宣 氏
一般的なユズの特徴やその利用方法などの話から始まり、DNA解析に基づいた在来柑橘の起源や派生についての講義がありました。また、渡来人や修験道の修行僧、平家の落人の移動とともに日本国内にユズが伝播したという諸説や、山梨県も縁のある「富嶽三十六景」の葛飾北斎が病に倒れた際にユズを利用した薬により回復したという昔の利用方法についても紹介されました。
富士川町のユズについては、修験道に関連する寺があることから、その修行僧により伝播してきた可能性があることを説明。講習会前日に視察した推定樹齢200年のユズが実生(接ぎ木でなく種から生育したもの)であることから、DNA解析によるルーツ調査をしたいとの話もありました。


3.講義『山梨県産ゆず活用 高知県の香酸柑橘とその食文化を例として』
講師:合同会社EKR 百田 美知 氏
ゆずの生産量全国1位を誇る高知県から来県した百田氏が、高知県の「酢みかん(香酸柑橘(果汁の酸味や果皮の香りを楽しむカンキツ類))」について講義を行いました。高知県では各家庭に、塩入り、塩無し、新酢、古酢など様々な「ゆのす(柚子の果汁)」が調味料としてあり、多用されることから「ゆのす」の一升瓶サイズも存在するとのことです。百田氏お手製の「ゆずの皮の辛子煮(「ひめいち」とみかんの辛子煮)」の試食も交えながら、高知県の食文化に思いを馳せるようなプレゼンテーションが行われました。
また、来県後、北島名誉教授と一緒に山梨県立図書館を訪れ、本県の料理本などの文献調査を実施。その中で見つけた「甲州盆唄」の歌詞「何たる江戸の絵かきでも平岡の柚子の木や絵には書けまい」から、富士川町近隣のゆずには、絵には表現できないほど素晴らしい香りがあり、昔からその価値が認められていたと解説しました。

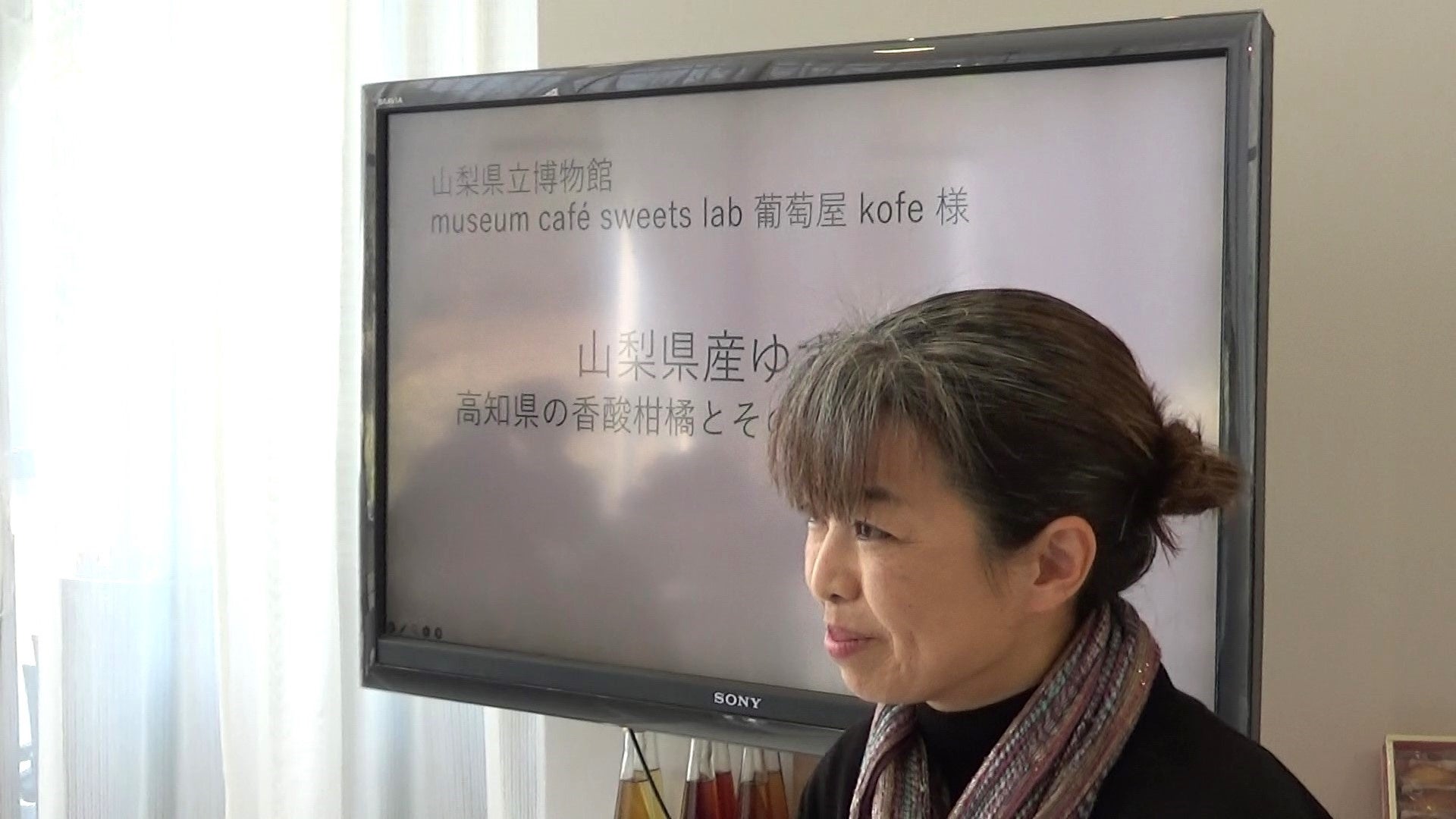
さらに、北島名誉教授と百田氏からは、実生の柚子は接ぎ木で育てられたものと異なり、どこから来たのか分かり、その土地ならではの特徴があるので大事にして欲しいという強い思いを伝えられました。
4.『柚子のアシェット』の説明 ※参加者による試食会
講師:銀座ウエスト青山ガーデンシェフ、葡萄屋kofu 顧問 金子 博文 グランシェフ
本日のアシェットには、講習会の前日に視察した貴重な柚子が使用されました。柚子を食べるイメージがあまりない中、スイーツにすると七色に変化することを表現したといいます。具体的には、柚子と白餡を合わせ、タルト生地に枯露柿と柚子を刻んで混ぜたとのことです。
また、今回使用した「すがき糖」の香りを活かすため、組み合わせる素材のバランスを考えたこと、柚子のパティシエール(クリーム)については、フレッシュ感を残す製法から他の果物でも汎用できることの説明もありました。
「スイーツは作り手の想いが反映されるもの。扱い方の違いにより生まれてくる変化をよく考えることで、アレンジが増えていく」と話がありました。


5.『柚子を使用したパン・ド・カンパーニュ』の紹介 ※参加者による試食
説明者:Conaファクトリー 開発サポートチームリーダー 森田 政士 氏
県・農政部の紹介で、山梨県内の多くの生産者に出会い、その中の食材を使用して本日のパンを作ったと説明。県産小麦粉の「かいほのか」と全粒粉、県内で手で炊かれた塩、地元の水、それから県産柚子で和え、苦みを残して作った自家製ピールをパンに使用。即興で添えた金子シェフ特製の柚子のクリームによく合っているといいます。また、素材の特徴を活かした拘りのある製法の説明や、様々な県産食材を使用したパン2種類の紹介もあり、「山梨県は素材の宝庫」と強調しました。


6.『柚子のアシェット』のデモ、技術用語と解説
講師:銀座ウエスト青山ガーデンシェフ、葡萄屋kofu 顧問 金子 博文 グランシェフ
料理・菓子ジャーナリスト 各国食文化研究家 並木 麻輝子 氏
キッチンの中で、参加者が講師を取り囲み、講師の作業を間近で見学。金子シェフは、柚子を使用した様々なクリームやソースなどのレシピ、柚子の分解方法、ママレードへの加工方法など技術的な説明を行いました。また、素材やその扱い方による変化から感じるものを自分なりに解釈し、表現することの大切さを伝えていました。
並木氏は、専門用語や金子シェフによる技術製法の説明について、参加者に分かり易く解説。また、複雑な食材の組み合わせ、例えばタルト生地に複数の砂糖が使用されていることを指摘し、金子シェフならではの拘りにフォーカスするとともに、各種食材が持つ特徴をどのようにスイーツに表現したのかを引き出していました。今回のスイーツには、並木氏のアレンジも加わっているといいます。


7.若手パティシエ伴走支援プログラム開発品紹介
『柚子とそば粉のビスコッティ』
説明者:プログラム参加者 西野 歩 氏、外川 愛理 氏
県産柚子と忍野村のそば粉を使用したビスコッティを開発。堅さの異なる2種類が用意されました。山梨県にある昔ながらの菓子「紅梅焼き」を意識したとのことで、懐かしさの中に二人の拘りを感じるものでした。さらに、ミュージアムカフェでの販売開始に合わせ、「焼き菓子 Pinna(やきがし ぴな)」というブランド名を披露。「Pinna」は、英語で「羽、翼」という意味があることから、ほっとひと息、羽休めの時間のおともになれたらという想いから名付けたとのことです。


参加者からは、「柚子の扱い方に対する苦手意識が払拭できた」「生産者やパティシエの想いに感動し他にはない講座だった」という感想がありました。
また、「柚子の歴史や特徴に触れることで県内の素材の大切さを実感できた」「素材の理解を深める講義やデモ形式など多方面から学べる講習会の構成に満足した」という講座構成への高い評価をいただきました。
当講習会は、講師と参加者の距離が近く、参加者が質問をしやすいアットホームな雰囲気も好評です。今後は3月末までに、イチゴやレモン等をテーマにした講習会を3回開催する予定です。
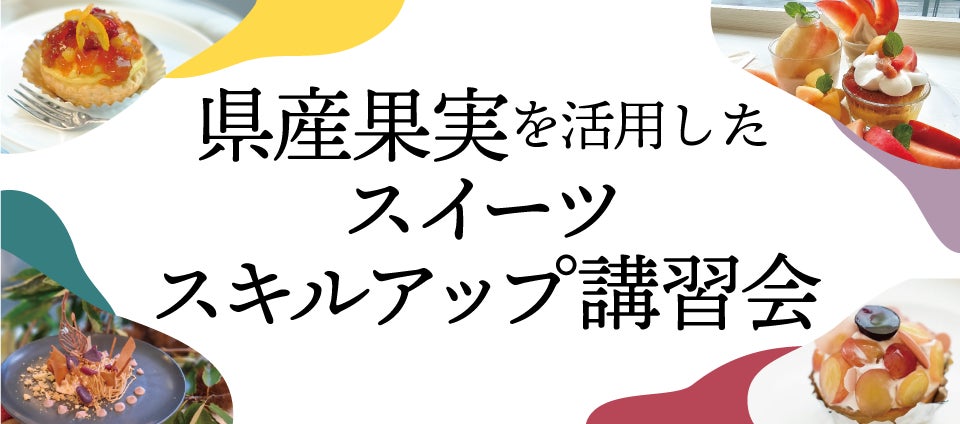
今後の開催予定とこれまでの実績は、山梨県公式ホームページでご覧ください。
https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sk/sweets/koshukai.html
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
