【投票開始】「AIコンパニオン」は孤独対策になる?行政による導入の是非を問う
スマホと生成AIが融合した「AIコンパニオン」が、孤独・孤立対策の新たな切り札として注目されています。あなたは、行政がAIコンパニオンを正式に導入することに賛成ですか?反対ですか?
生成AIの社会実装を推進するPolimill株式会社(本社:東京都港区/代表取締役:伊藤あやめ・谷口野乃花)は、2025年11月19日、当社が運営するデジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」にて、【「AIコンパニオン」を孤独・孤立問題に取り組む行政の対策として採用すべきか?】というイシューの意見募集を開始しました。
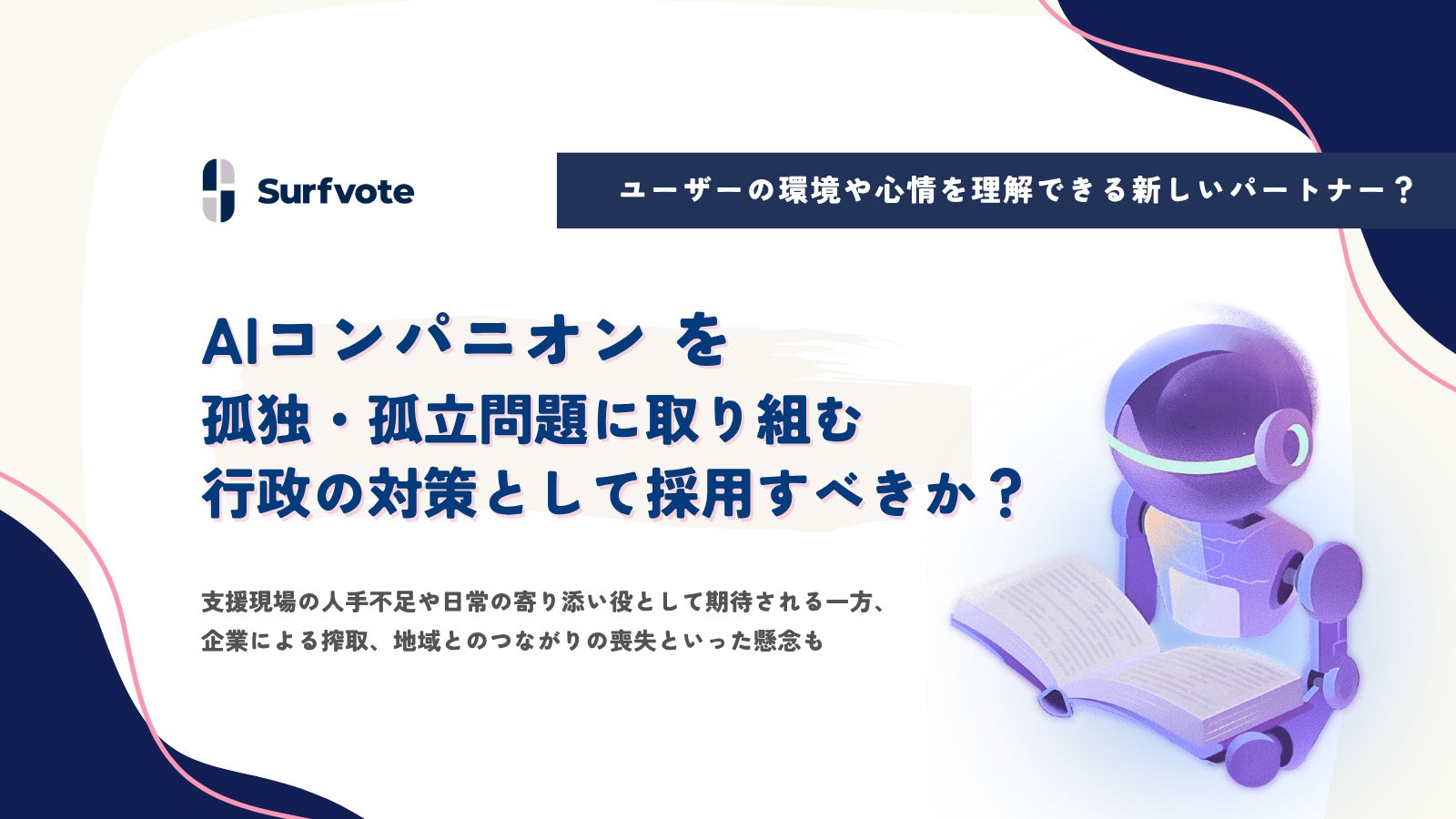
Surfvoteとは?
Surfvoteでは、社会のあらゆる課題や困りごとを「イシュー」として、ほぼ毎日掲載しています。 これらのイシューは、大学の先生や専門家、全国の地方自治体など、多様な立場の方々によって提起されています。Surfvoteを訪れれば、誰でも気軽に社会課題に触れ、学び、考えることができます。 アカウント登録をすることで、自分の意見に近い選択肢を選んで投票したり、コメントを投稿して他のユーザーと意見を交わしたりすることも可能です。私たちは、社会の分断や対立をあおるのではなく、さまざまな意見や立場を持つ人々が共通の価値観を見つけられる場を目指して、日々サービスの改善・開発を進めています。
この記事の一部をご紹介
スマホと生成AIが融合した「新しい相棒」の登場
「AIコンパニオン」とは、ユーザーの会話や環境を理解し、共感性すら示そうとする小型のAI端末。日々の孤独に寄り添う「パーソナルAI」としての可能性が注目されています。
行政の孤独対策として活用する声も
高齢者の見守りや心のケア、限られた支援人材の補完手段として、「AIコンパニオン」を行政サービスに取り入れる動きも一部(八王子市など)で始まっています。
対話は進化?それとも退化?人とAIの境界
便利さの裏で、「人間関係を築く力が弱まるのでは」という懸念や、「AIとの関係に依存しすぎるリスク」も指摘されています。公的支援にAIをどう位置づけるか、社会的な議論が求められています。
Surfvoteで投票してみませんか?
人とAIが共に生きる未来について、あなたはどう考えますか?
本当に必要なのは、人間の代替?それともヒトとのつながりの再構築?
あなたの視点で意見を投票してください。
「AIに支えられることで、生きる希望を持つ人もいると思う」
「本来の課題は人との関係性の構築であり、AIはあくまで補助的手段にすべき」
「高齢者など話し相手がいない人にとって、AIコンパニオンがパートナー的存在になるなら意味があると思う」
「孤独に苦しんでいるのは人との関係を望んでいるからではないか?」
「税金でAIコンパニオンを導入するなら、その対象者の声を丁寧に聴いて活用してほしい」
👉 投票ページはこちら
「AIコンパニオン」を孤独・孤立問題に取り組む行政の対策として採用すべきか?(Surfvote)
執筆者プロフィール
小宮信夫さん
立正大学教授。社会学博士。日本人として初めてケンブリッジ大学大学院犯罪学研究科を修了。国連アジア極東犯罪防止研修所、法務省などを経て現職。「地域安全マップ」の考案者。警察庁の安全・安心まちづくり調査研究会座長、東京都の非行防止・被害防止教育委員会座長などを歴任。代表的著作は、『写真でわかる世界の防犯 ――遺跡・デザイン・まちづくり』(小学館)。NHK「クローズアップ現代」、日本テレビ「世界一受けたい授業」などテレビへの出演、新聞の取材(これまでの記事は1700件以上)、全国各地での講演も多数。公式ホームページとYouTube チャンネルは「小宮信夫の犯罪学の部屋」。
Polimill株式会社
Polimill株式会社は、各専門領域に特化した行政サポート生成AI「QommonsAI(コモンズAI)」と、誰もが安心して簡単にまちづくりに参加できるSNS「Surfvote(サーフボート)」を開発・運営する、創業4年のICTスタートアップです。
QommonsAIは300を超える地方自治体や省庁で導入されており、Surfvoteでは、全国の社会課題に加えて、各自治体が抱える地域課題(Surfvoteローカル)も掲載。誰もが意見を届けられる場を提供しています。
私たちは、すべての人がルールづくりに参加できる、理性と感性を備えたデジタル駆動型社会の実現を、AIとSNSの力で目指しています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
