『広告白書2025-26年版』発売!
日本経済新聞社グループの日経広告研究所は、『広告白書2025-26年版』を2025年9月19日(金)に全国の書店・オンライン書店にて発売しました。
デジタル社会の進展により、広告・マーケティングの構造は大きく変化しています。生活者が自ら情報を選び取る時代となり、広告は単なる情報伝達手段ではなく、企業と生活者の関係性を築く「経営の中核的な戦略機能」として再定義されつつあります。本書は、こうした転換期における広告の意味と役割を問い直し、今後の広告戦略の立案に必要な知見を集約しました。
広告の役割の変化や新しい価値、生活者の情報行動やSNS利用の実態、広告コミュニケーションの手法や組織の変革、インターネット・テレビ・新聞・雑誌など主要メディアの現状、クリエイティブの潮流や広告賞の動向、さらには最新の広告研究・広告法規・広告関連データまで幅広く取り上げています。実務担当者、経営層、研究者など多様な立場の方が実践に活かせる内容です。
最新の調査データと豊富な事例をもとに、広告の進化と構造的変化を体系的に整理。図書館や企業の資料室に常備される定番書として、また広告・マーケティングの現場で「広告戦略の羅針盤」としてご活用いただけます。
【書籍概要】
書名:『広告白書2025-26年版』
編集:日経広告研究所
発売日:2025年9月19日(金)
定価:5,500円(税込)
仕様:A4判並製/255ページ
ISBN:978-4-296-12374-2
発行:日経広告研究所
発売:日経BPマーケティング
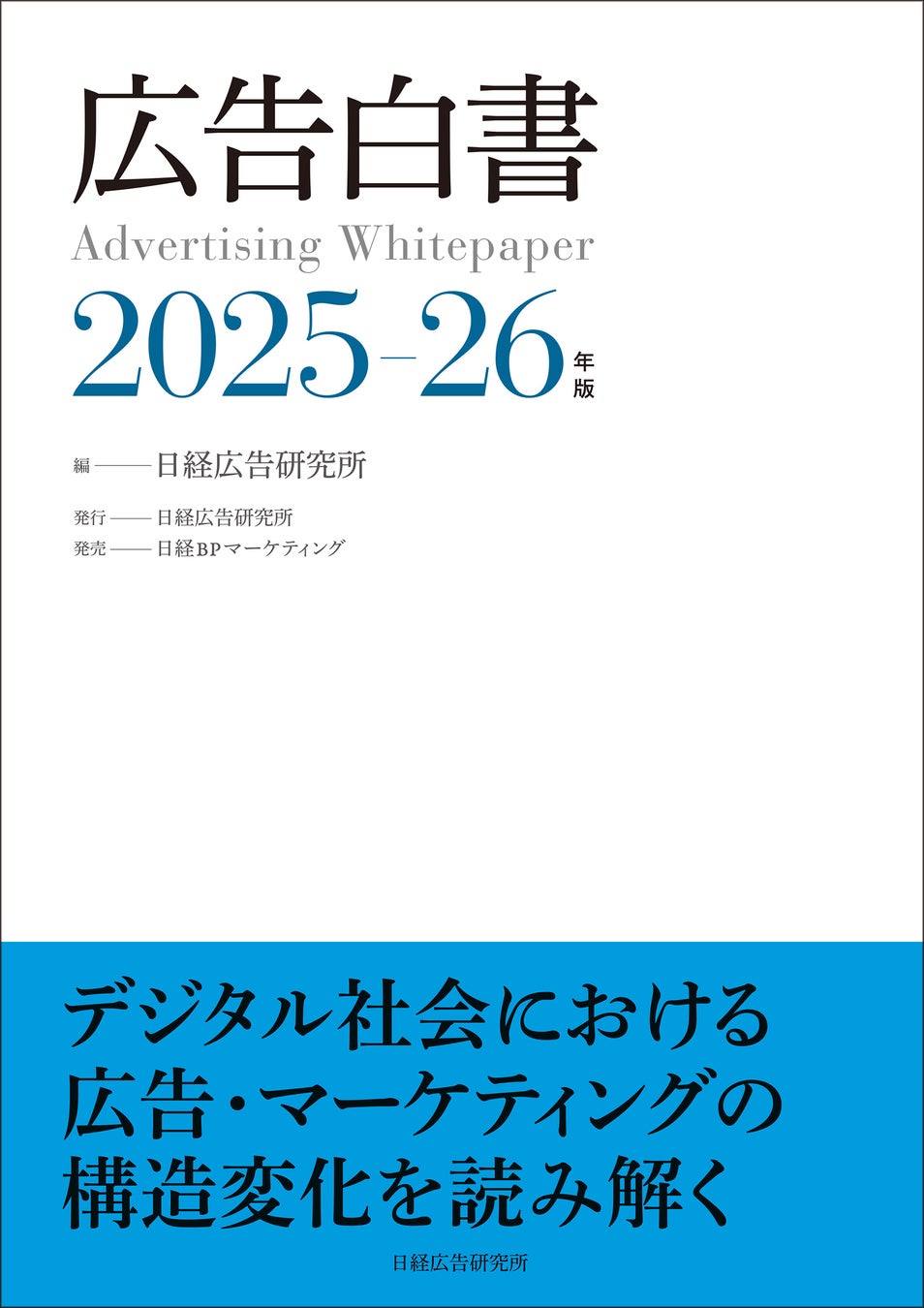
【お問い合わせ先】
日経広告研究所 広報担当
TEL: 03-5259-2626
Mail: koken_toiawase@nex.nikkei.co.jp
<参考情報>
広告と生活者の関係性から読み解く「実務に役立つ10の視点」 (広告白書2025-26年版より)
1. 広告は“接点設計”から“関係設計”へ
広告は媒体出稿を起点とする従来型から、企業と生活者がともに「場」を形成する関係性設計へと進化。情報伝達だけでなく信頼構築を目的とした活動へと位置づけが変化している。
2. 統合型コミュニケーションが常識に──部門横断と全社連携
広告・広報・販促・SNSなどの区分を超え、生活者接点を軸とした統合的な設計が主流化。広告部門が経営企画・営業・商品開発と連携する体制へと変化している。
3. 広告は経営課題と直結し、戦略推進の中核を担う活動へ
広告はもはや販促手段ではなく、生活者との信頼構築を通じた中長期戦略の中核に位置付けられている。KPI設計、人材育成、説明責任が広告部門の実務課題として浮上している。
4. 自社メディアとインフルエンサーが生活者の判断材料に
自社SNSやWebサイト、YouTubeなどの継続的な発信が広告効果を高める一方、インフルエンサーとの協働も一般化。生活者が自然に接触・判断できる情報環境の設計が重要視されている。
5. 生活者参加型のブランド形成──ファンダムマーケティングの台頭
ファンコミュニティの形成や、ユーザーによる自発的コンテンツ創出がブランドの認知や好意を高めている。生活者と共に価値をつくる発想が、関係構築の基盤として注目される。
6. インターネット広告は関係性を繋ぐ“起点”に
SNSや検索連動広告など、生活者の情報探索と感情接点をつなぐインターネット広告が、購買プロセスの中核に組み込まれている。効果測定と即応性を活かした設計が求められる。
7. テレビは“共体験メディア”として再定義される
見逃し配信やコネクテッドTVの普及により、テレビは「選んで見る」「共に見る」メディアへと変化。運用型TV広告の伸長とあわせ、家庭内スクリーンの戦略的価値が再認識されている。
8. 新聞は信頼の起点、“第三者性”を担保するメディアへ
広告表現が信頼されにくい時代において、新聞・報道記事の活用や戦略PRの組み合わせが再評価されている。情報源としての信頼を背景に、広報・広告連携の動きが加速している。
9. 媒体選定は“拡散構造”まで設計する時代に
各メディアのそれぞれが担う「共体験」「信頼性」「拡散性」の特性を横断的に組み合わせ、シェア・再発見を前提としたメディアプランが定着している。
10. KPIと広告評価は“生活者視点”へ再設計が進む
単なるリーチやクリック数ではなく、「好意形成」「再生完了率」「ブランド想起」など、中長期かつ質的な指標での評価が重視されるようになっている。
すべての画像
