昭和に遊び、昭和に抗い続けた「最も過激な個人主義者」文豪・永井荷風の鮮烈な生涯を辿った『荷風の昭和』前後篇が本日発売!
私娼と戯れつつ、軍人を「肥満豚」と呼び、やがて反時代的傑作『濹東綺譚』を完成させた荷風。戦後はストリップを楽しみ、新憲法を嗤った文豪の素顔に迫りながら「昭和」を丸ごと描き出す「昭和百年」記念作品。
関東大震災から、激しく揺れ動く「昭和」は始まった。モダン都市東京の誕生、昭和恐慌、226事件、満州事変、太平洋戦争、東京大空襲、地方への疎開、敗戦、戦後民主主義、性の解放……。激動の昭和を微細に書き留めた『断腸亭日乗』をはじめとする荷風作品を徹底的に読みこんだ評論家・川本三郎さんが、荷風とその時代の足跡を辿り、「これを書きあげたら思い残すことはない」とまで語った、執筆6年余、1900枚に及ぶライフワーク『荷風の昭和』前後篇(新潮選書)が「昭和百年」の今年、5月21日(水)に同時発売されます。
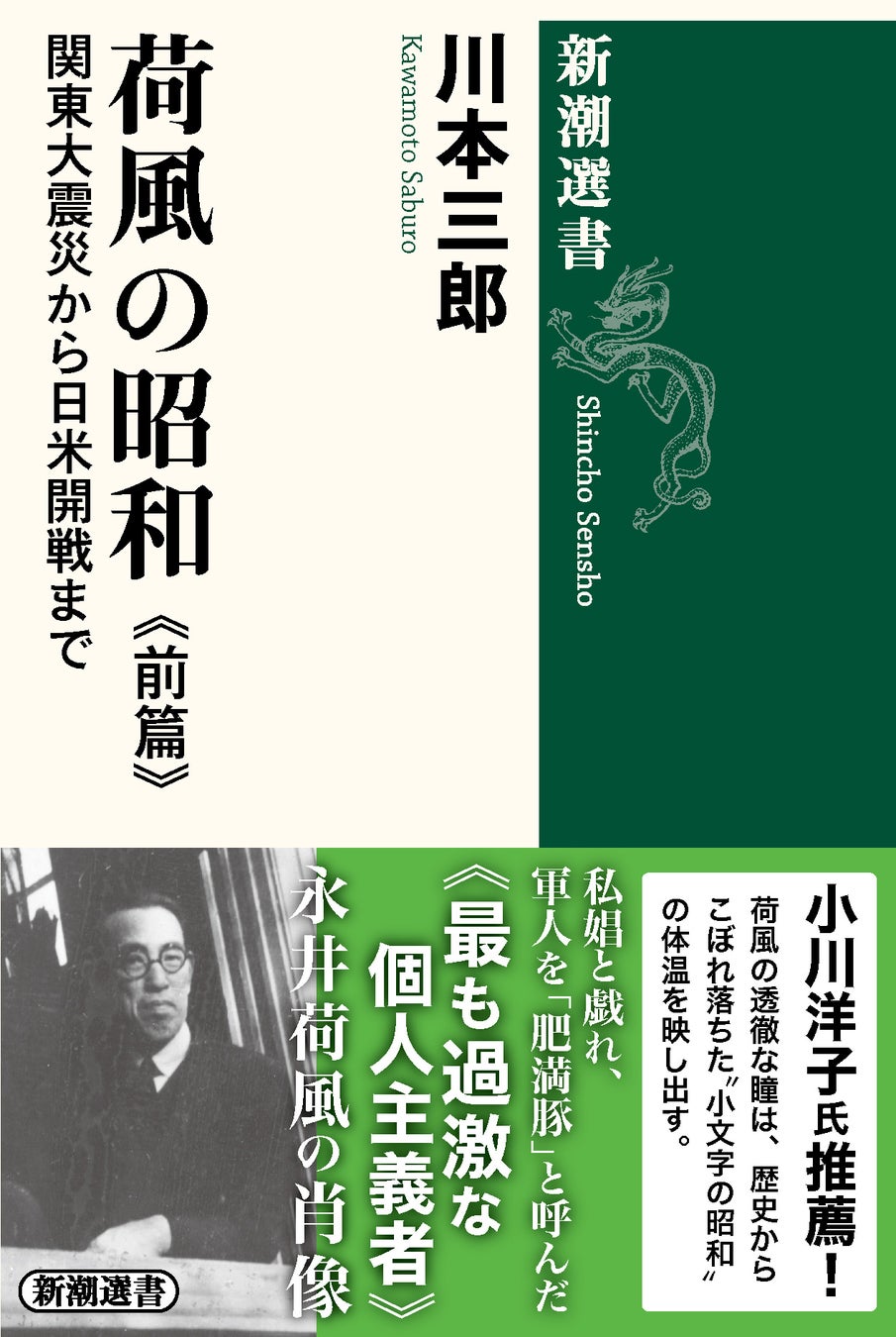
戦前は軍国主義に反発する軟派の作家として、娼婦との交流を『濹東綺譚』などで抒情豊かに謳い上げた永井荷風。荷風の強靭な精神を支えた膨大な蔵書は東京大空襲で焼き尽くされたが、戦後もなお、奇人と見なされながらも反骨精神を保ち続けた。そんな荷風の素顔と昭和の核心を浮かび上がらせる文芸評論の到達点にして、昭和論の金字塔。
【刊行記念イベント決定】
『荷風の昭和』刊行記念×昭和百年トーク&サイン会が、5月23日(金)18時30分から東京堂ホール(東京堂書店は6階)で開かれます。
川本三郎さんの講演「ひとり暮しの老人の昭和」のあと、本書のサイン会となります。参加費1500円。お申込みについては東京堂書店ホームページをご覧ください。
■目次
【荷風の昭和 前篇 関東大震災から日米開戦まで 目次】
1 偏奇館で関東大震災に遭う
昭和の起点/良き隠れ家、偏奇館/大震災後の東京を歩く/林芙美子の被災/大曲駒村の被災/荷風が「自警団」と遭遇する
2 食と共に復興する東京
「この度の災禍は実に天罰なり」/東京の盛り場が移っていく/復興は食から始まる/銀座の「陳列館」「勧工場」へ
3 作家になるまで
「恋愛と文芸」の底に/「閑文字を弄ぶ」放蕩息子/母恋いの記/文学が認められていない時代に/憧れのフランスで/「変わった人間」として生きていく
4 花とオペラと反骨精神
タンポポの種を蒔く/帝国劇場の亡命ロシア・オペラ団/「今日は帝劇」の時代/大震災後のプラトン社「女性」/日記だから書きえたこと
5 学ぶ荷風――柳北日記との出会い
漢詩の添削を請う/図書館で急死した老人/成島柳北への傾倒/柳北日記を書き写す
6 円本ブーム
曝本の楽しみ/金融恐慌で預金を移す/不況下の円本ブーム/改造社との縁/「大衆」が台頭する
7 私娼という新しい女
銘酒屋が並ぶ盛り場で/「私娼の肩を持つわけじゃないが」/荷風の私娼取材/もっとも艶麗な一夜
8 私娼への思い――「かし間の女」と「ひかげの女」
散娼、「自活」する女たち/「テヨダワことば」の女たち/カフェの女給か、活動の女優か/裏通りの詩情/世の隅にいる二人を
9 銀座復興
時代観察者が市中を散歩する/復興した町の活気と殺気/銀座が繁華街の王者となる/愛妾と提灯行列を見る/
10 中州病院から隅田川へ
荷風のかかりつけ医/復興の魁としての橋/荷風の下町発見/東京、第二の陣痛/共産党への弾圧
11 市川左團次との親交
サラ・ベルナールを見た二人/共同作業への憧れ/ソ連が自由だった頃/エイゼンシュテインも影響を受けた
12 カフェ通い
「カッフェー」の時代始まる/「女給」という新しい女性/不況と「ガールの時代」/「文壇カフェー常連番附」大関の弁/教え子に一本取られる
13 「つゆのあとさき」に描かれた銀座
アドバルーンのある風景/銀座通りの歩き方/カフェの女たち、客たち/アイスコーヒー始めました
14 モダン都市へと出てゆく女たち
交詢社ビル地下「サロン春」/チャップリンと女給の結婚話/小文字の「昭和」/女給と甘味処で/溝口健二が山田五十鈴に重ねたのは
15 郊外住宅地の誕生
東京が西へ広がっていく/水道の水はまずい/西の郊外を歩く/新開町、渋谷/やがて消えゆく小さな桃源郷
16 犬を飼う、探偵に依頼する
すでにペット霊園がある/ポチの文学史/荷風がシロを飼う/秘密探偵岩井三郎/モダン都市の新しい言葉
17 見え隠れする「暗い昭和」
佐分利公使の自殺/松本清張が推理する/満州へ、満州へ/世の中は明るくなった!/そしてテロとクーデターが始まった
18 小名木川への道
いまも残る江戸の運河/「水の東京」ゆえの工業地帯化/川から川へ/芭蕉の古碑を見つける/現在の向こうに歴史を見る
19 荒川放水路のほうへ
「限りなくもわたくしを喜ばせる」/お化け煙突を発見する/放水路という新風景/葛西橋への思い入れ/小津安二郎のアングル
20 満州事変始まる
デパートの商戦にも/ゲンポーとグンシュクの日々/「最高に恰好いい姿」だった/こうして朝日新聞は変化した/天皇への直訴という考え方/荷風が日の丸を買う
21 城東電車が走った町、砂町
世界第二の都市に/路面電車に乗って/城東地区の興亡/モダニズム作家の見た江東/砂町で発見したもの/墨田川以東の地への思い
22 戦争の隣りの平和
小春日和のような日々/「暢気眼鏡」の奥さんのアルバイト/パーマネントが禁止されるとき/文士と麻雀/紙芝居の登場
23 軍人たちの時代
待合とクーデター/「武断政治を措きて他に道なし」/テロリストが賛美されてゆく/五・一五事件とポピュリズム/軍人を太った豚と呼ぶ
24 貧しい東京、悲惨な東北
「強兵」重視のかげで/荒川、四ツ木橋を渡って/「欠食児童」という流行語/三陸大津波ふたたび/不受不施の生き方
25 私娼たちに「パリ」を見る
「性」を売る町/「ひかげの花」のモデル/パリの娼婦たち/フランスへの「亡命」/時代に背を向ける秘かな楽しみ
26 玉の井への道
玉の井観察/おはぐろどぶバラバラ事件/猟奇的世界から遠く離れて/あらかじめ失われた町へ
27 隠れ里、玉の井
二・二六事件の戒厳令下を/「最低の遊び場」へ通いつめる/荷風の「詩人的配慮」/迷宮を通り抜けた先に/国外脱出の夢、そしてミューズ
28 「ミューズ」、お雪
過去を懐しむ先に/「井戸か水道か」/過去の幻影が立ち現れる/美女と茶漬け/おためごかしの後の自己嫌悪/モーパッサン原作の映画?
29 日中戦争始まる
天皇機関説問題/「個人の覚醒せざるがために」/元愛妾と阿部定の噂話をする/私家版『濹東奇譚』始末/出征兵士の別れの挨拶
30 日中戦争下の日々
アッパッパを着た女性/写真機を片手に/ニュース映画の上映館/作家への弾圧が始まる
31 吉原出遊
三十年ぶりの吉原登楼/遊ぶ、見る、書く/「なか」が通じなくなった/没落の遊里取材/「荷風散人墓」/廓内の女たちへの尊敬
32 浅草オペラ館への道
東武電車が浅草に/松屋デパートの屋上から/軽演劇の人びとと交わる/浅草の観客/エノケン、ロッパの去った街で/「一味の哀愁をおぼえたり」
33 浅草で、歌劇「葛飾情話」上演
「写真を撮ってくれるおじいさん」/オペラへの愛情/ドビュッシイのレコード/荷風歌劇、大入満員/一九九九年の「葛飾情話」
34 第二次世界大戦まで
幻の映画「浅草交響曲」/戦死者が日常的になる/軽演劇のヒトラー/同調圧力にさからって
35 「非国民」の悲しみ
金の国勢調査/パーマの髪と短いスカート姿/「非国民」同士の共感/パリ落城
36 昭和十五年、「紀元二千六百年」
米穀通帳が始まる/荷風が炭を失敬する/口を開けば「新体制、新体制」/「駅馬車」日本公開の年に/「祝賀」のあと/ひそかな荷風ブームがおきる
37 太平洋戦争まで
遺書を書く/朝鮮の踊子たちが歌う/ある舞姫の物語/荷風の覚悟/「模倣ナチス政治」の世で
【後篇 偏奇館焼亡から終焉まで 目次】
38 鰹節と日米開戦
防空演習始まる/米と鰹節と梅干あらば/開戦に熱狂する知識人たち/「スミス都へ行く」/徴用令時代の文士たち
39 太平洋戦争下の日々
甘い物がほしい/ドゥリットル隊来襲/南京にいた慶應の卒業生/ひとりでジャムを煮る/山本五十六も象のトンキーも/「白紙」が来る恐怖
40 戦時下にも「別天地」あり
谷崎と会食の日に/浅草の釣竿屋老主人を眺めて/戦時下のフランス映画/踊子の家のお漬物/鷗外先生墓所掃苔の一日/戦時下の楽興の時
41 建物疎開続く
玉の井でも防火訓練/建物疎開促進の「国策映画」/「疎開ト云フ新語流行ス」/東京の市中が臭くなる/軍部が『腕くらべ』を注文する
42 空襲下の日々
最初で最後の偏奇館訪問/サン・テグジュペリと特攻隊/疎開児童、欠食児童/本格的な空襲へ/この世の涯で珈琲を飲む
43 偏奇館燃ゆ
空襲下で本を読む/文学青年と素人の女性/多くの死体がすばやく片づけられる/観潮楼焼亡す/生まれ育った東京への鎮魂歌
44 偏奇館を焼かれたあと
燃えあがる蔵書の炎/向田邦子の三月十日/大佛次郎と高見順の場合/「人種が違うの」/大空襲翌朝の焚出し/それでも鉄道は走る
45 東中野で五月に十五日の大空襲に遭う
ヒヤシンスの芽、桜の花/大空襲ふたたび/東中野の国際文化アパートへ/荷風を支えた人たち/可憐な少女に会った日に
46 明石での束の間の平穏
二度目の焼け出され/明石への疎開を決心する/ドビュッシイの取りもつ縁/三度目の空襲
47 岡山で四たび空襲に遭う
岡山での八十日が始まる/戦時下のピアノコンサート/「この銀行は安心出来ない」/牧歌的な軽便鉄道が往く/言葉によって描かれた絵/死を覚悟する
48 岡山空襲のあとで
雨のなかを歩く/岡山の親切な女性たち/「待つ人もなく燈火もなけれど」/「S氏夫婦」との距離感/流転の日々の支え
49 終戦まで――勝山で谷崎に会う
あの頃の郵便事情/谷崎潤一郎の場合/谷崎が町の物価を上げる/「焼け出され」の負い目/八月十五日、荷風は列車に乗る
50 戦時下に書かれた小説「踊子」「浮沈」など
発表のあてもなく/忌み嫌われた作家の「最後の別天地」/滅びゆく町への挽歌/山の手への帰郷/作者に似た世捨人たちの肖像
51 戦時下に書かれた「問はずがたり」のこと
山田風太郎が荷風を読む/末期の目で世界を見るように/思想よりも信仰よりも大切なもの/戦争の時代の新しい少女たち/みごとな非国民ぶり
52 岡山を去る日
荷風の戦後が始まる/「余は今は心賤しき者になりぬ」/〝自由〟を盾にする同居人たち/村田武雄を頼る/岡山の人びとの親切
53 岡山から熱海へ
貨物列車に乗って/田辺聖子と河野多惠子の大阪空襲/ひとまず熱海に落ちつく/軍国主義も民主主義も/余計者の作家が求められる時
54 熱海での日々
着るものも食べるものも/RAAが作られる/天皇に同情する/荷風全集の刊行決まる/思い切って古くなってみせた
55 大家の復活
新興出版社の原稿料/青山虎之助の思い/鎌倉文士が作った貸本屋/荷風の礼儀正しさ/「印税成金」となる
56 熱海から市川へ
突然の立ち退き要求/終焉の地、市川へ/荷風復活の評価/ズボンのMボタン
57 占領下の市川
闇市で百三十円のビールを飲む/「にぎり飯」のたくましい男の女/闇商売の少年たち/与えられたる自由の下で/「パンパン」から日本を見る
58 市川の人々
疥癬に悩まされる/一番湯にムトウハップを/正岡容、そして吉井勇/市川で文学を語り合う/露伴先生逝く/幸田文、父の葬儀のあとさき
59 市川での日々
露伴が文に『濹東綺譚』を薦める/ラジオの音との戦い/避難所で生まれた短篇/側近、相磯凌霜/下町の商家の別荘地
60 「四畳半襖の下張」騒動
秘密出版で高値を呼ぶ/「来訪者」の二人/震える手で調書に署名する/「この裁判それ自体がすこぶる滑稽」/戯作のスワン・ソング
61 二人の閨秀作家、深尾須磨子と林芙美子
円地文子の荷風頌/深尾須磨子の巴里/荷風も愛したフランスの閨秀作家/南京郊外の『濹東奇譚』/林芙美子の戦後
62 「菅野はげにもうつくしき里」
隠れ住むのにうってつけの地/牧場と梨のある風景/花薫る里で/葛飾八幡宮で見たもの/昭和二十二年五月三日、「笑ふ可し」
63 「真間川の記」と大田南畝
川をめぐる「奇癖」/川べりの孤影/南畝の碑を発見する/正宗白鳥への猛反駁/似ているのは偶然ではなく
64 「歩く荷風」、再び
日蓮宗の大本山散策/「人間の幸福これに若くものなし」/健脚老人が今日もゆく/焼跡での地図作り/新たな私娼窟、東京パレス
65 困った同居人
老いてもなお我がまま/「正気の沙汰に見えず」/ついに引越す/五叟一家をののしる/文学者荷風と同居人荷風
66 「五叟日誌」に見る戦後の世相
奇行の人として/住友令嬢誘拐事件/弱者に優しい町/荷風が描いた買出しの女性/「同盟罷業」が禁止される/東京裁判と公職追放と
67 被害が大きかったキャサリーン台風
人災としての水害/洪水見物に行く/戦後の浅草通いが始まる/「婦女の裸体」の「展覧」/玉の井焼失から七十日で
68 戦後の色町、鳩の街のこと
木の実ナナの回想/水辺の女たち/米兵相手の街になる/吉行淳之介の「借金のカタ」/自作「春情鳩の街」に沸かせる/「初日を見る。大入満員」
69 浅草、出遊のこと
失われた東京/知識人が背を向けた街へ/桜むつ子の回想/浅草舞台劇三部作/あるカストリ雑誌との縁
70 老翁、ストリップ劇場にあり
京成本線沿線の踊子たち/新聞記者を避けてロック座へ/井上ひさしの浅草時代事始/ストリッパーたちとの座談会/ある踊子の回想
71 欲望の解放と、老人の諦念
「猟奇」に魅かれる女性/快楽を求める女性像/春本「ぬれずろ草子」/理想的な世の去り方/酔狂老人の文化勲章受章
72 老いのあとさき
得意料理は五目飯/四書、そして聖書を読む/荷風をとらえた写真/大金持だとバレる/お金を出すとき/「正午浅草。アリゾナに飰す」
73 フランス映画を見る
そば屋で倒れる/映画史家からの指摘/ラジオで大いに語る/映画監督になりたかった/ジッドやゾラの原作映画を/女給とロートレックの伝記映画を見る
74 市川の荷風を訪ねた人々
昔の愛妾からの年賀状/歌の見た荷風の暮し/文人来訪/東京を愛したフランス人/荷風の話した日本語
75 最後の日々
中央公論社との紐帯/没後全集の出版元/清楚で美しい謎の女性/晩年の散人点鬼簿/小林青年、来る/「正午大黒屋」ののちに
■著者コメント
本書は、都市の作家である荷風が、ことの多い激動の昭和をどう生きたかを検証した。
震災後のモダン都市東京の誕生、昭和恐慌、二・二六事件、日中戦争、太平洋戦争、東京大空襲、地方への疎開、戦後の混乱期……次々に襲いかかる大事件のなかで、群れることを嫌い、個として生きようとした荷風の悪戦苦闘ぶりには、近代日本の知識人の苦難の姿があらわわれている。
軍国主義の時代が息苦しくなるなかで、荷風が玉の井の娼婦や浅草の踊子たち、あるいは戦後の浅草のストリッパーたちと交流したことは、柔らかで優しい女性文化への愛情から生まれたものといっていい。生涯、女性たちを愛し続けた荷風は、軍人たちの武に対し、女性たちの美にこそオマージュを捧げた作家だった。そのことを明らかにすることも本書の眼目である。

■小川洋子氏、推薦!
荷風の透徹な瞳は、歴史からこぼれ落ちた“小文字の昭和”の体温を映し出す。(『荷風の昭和』前篇オビより)
■書籍内容紹介
『荷風の昭和 前篇 関東大震災から日米開戦まで』
関東大震災から急激に復興したモダン都市東京、カフェーの女給や私娼などの新しい女たち、テロとクーデターに奔走する軍人……。激変する時代に何を見て、この「最後の文人」は反時代的傑作『ぼく東綺譚』を書き始めたのか? 『断腸亭日乗』など永井荷風の全作品を徹底的に読み込み、昭和をまるごと描き出した文芸評論の到達点!
『荷風の昭和 後篇 偏奇館焼亡から最期の日まで』
荷風の精神を支えた大量の蔵書と共に、偏奇館は空襲で焼け落ちた。戦後、老文士は戦災のトラウマに悩まされ、奇人として有名になる。しかし尚も権威を嫌い、新憲法を嗤い、ストリップを楽しんで、市井の男女の情愛を描き続けた。著者自ら「これを書きあげたらいつ死んでもいい」と筆を振るった荷風論にして昭和論の金字塔!
■著者紹介:川本三郎(かわもと・さぶろう)
1944年東京生まれ。文学、映画、漫画、東京、旅などを中心とした評論やエッセイなど幅広い執筆活動で知られる。著書に『大正幻影』(サントリー学芸賞)、『荷風と東京』(読売文学賞)、『林芙美子の昭和』(毎日出版文化賞・桑原武夫学芸賞)、『白秋望遠』(伊藤整文学賞)、『マイ・バック・ページ』、『いまも、君を想う』、『成瀬巳喜男 映画の面影』』、『「男はつらいよ」を旅する』(共に新潮選書)、『陽だまりの昭和』など多数。訳書にT・カポーティ『夜の樹』、『叶えられた祈り』(共に新潮文庫)などがある。
■書籍データ
【タイトル】荷風の昭和 前篇 関東大震災から日米開戦まで
【著者名】川本三郎
【発売日】2025年5月21日
【造本】新潮選書/四六判変型ソフトカバー
【定価】2860円(税込)
【ISBN】978-4-10-603927-0
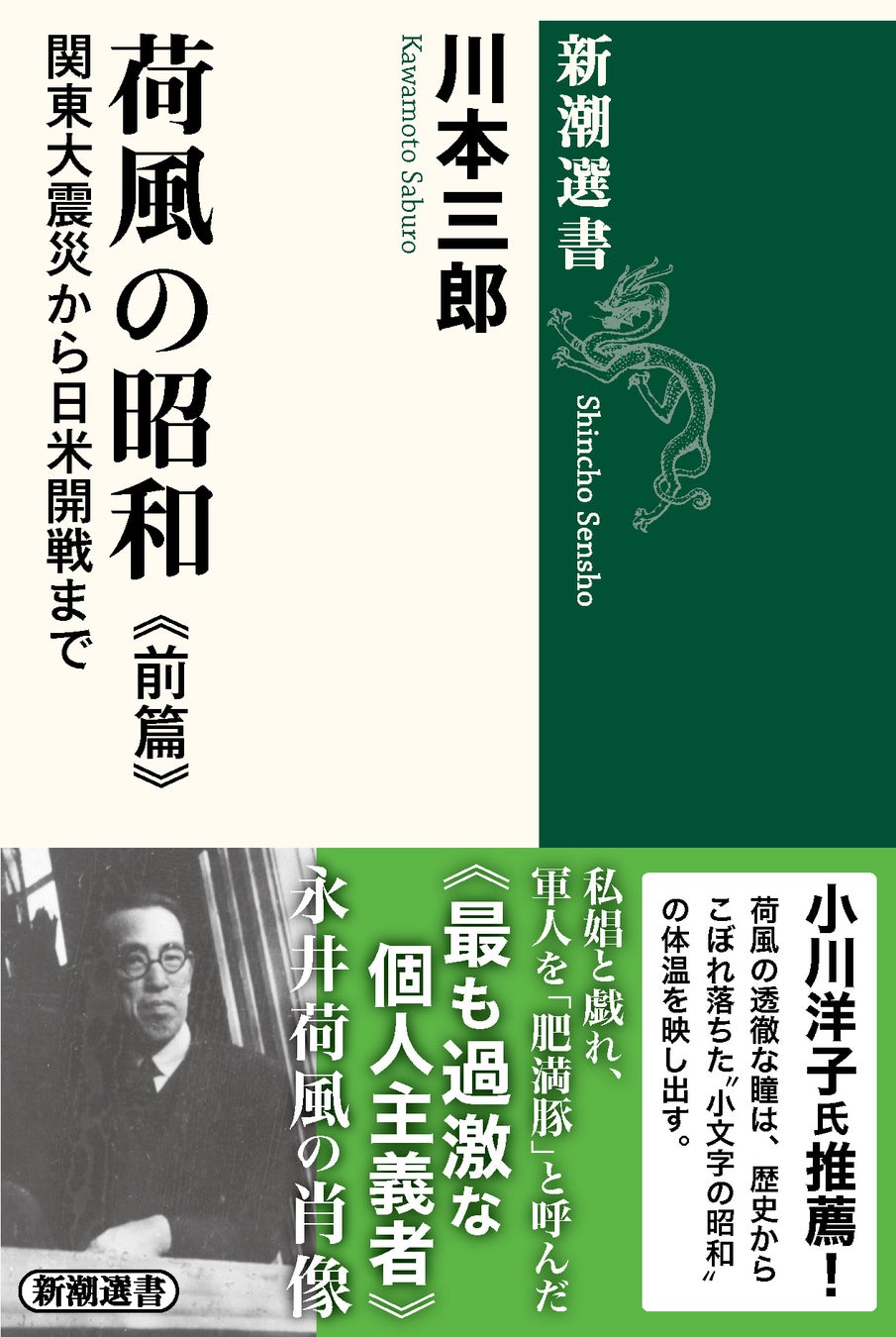
【タイトル】荷風の昭和 後篇 偏奇館焼亡から最期の日まで
【著者名】川本三郎
【発売日】2025年5月21日
【造本】新潮選書/四六判変型ソフトカバー
【定価】2860円(税込)
【ISBN】978-4-10-603928-7
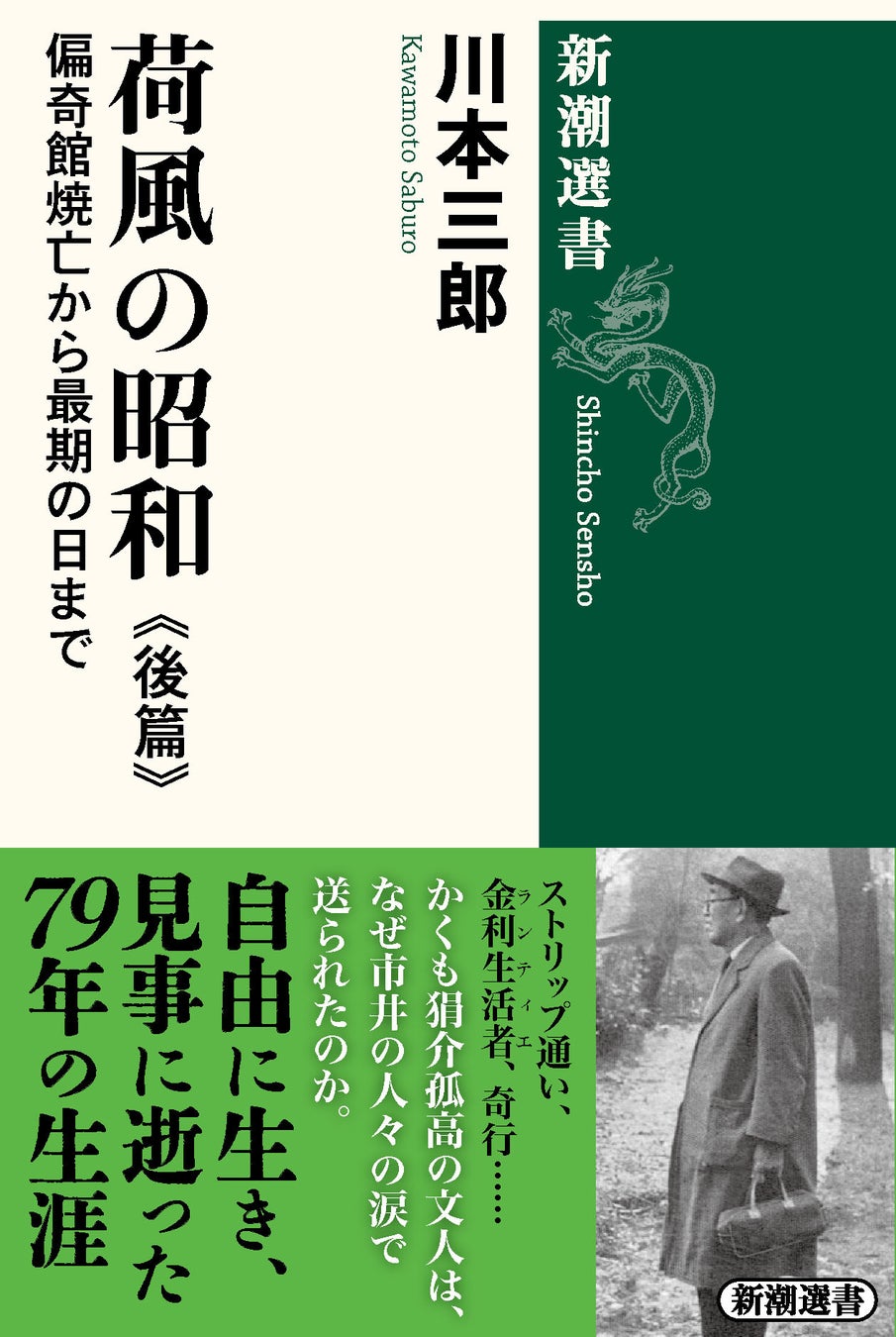
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
