ジーズ開校10周年記念エッセイコンテスト授賞式を開催、受賞作品を発表!|テーマは「こわそう、つくろう、ジブンを、セカイを。」
グランプリは『光の向こうに見えたもの』/Ryoさん(リアル部門)、『生きるための一歩』/横山 シシファ美麗さん(ミライ部門)

IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を展開するデジタルハリウッド株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:春名 啓紀、学長:杉山 知之)が運営する、エンジニアと起業の学校『G's』(ジーズ)は、開校10周年を記念してエッセイコンテストを初開催し、11月21日(金)にG's TOKYO(東京・原宿)にて授賞式を行いました。
リアル部門のグランプリには、Ryoさんの「光の向こうに見えたもの」、ミライ部門のグランプリは横山シシファ美麗さんの「生きるための一歩」が受賞されました。横山シシファ美麗さんは本コンテスト最年少(16歳)での受賞となりました。
取り巻く環境や経験、年代も様々な個性あふれる受賞者の皆さんのコメントと、授賞式の様子、トークセッションの詳細は下記をご覧ください。
【エッセイコンテスト 開催概要】
コンテスト名:G's 10周年記念「こわそう、つくろう、ジブンを、セカイを。」エッセイコンテスト
作品募集期間:2025年8月19日(火)~2025年9月30日(火)
授賞式日程:2025年11月21日(金)
授賞式会場:G's TOKYO(東京・原宿)
特設サイト:https://g-s.dev/essay/
【審査員について】
審査員には、アーティストとして幅広く活躍する和田彩花さん、そして作家として注目を集める樋口恭介さんをお迎え致しました。
お二人による厳正な選考、白熱した審査会を経て、各賞の受賞作品が決定しました。
【授賞式】
授賞式は、G's TOKYO(東京・原宿)にて開催。
主催者であるG'sより挨拶ののち、各賞の表彰、そして審査員によるトークセッションをおこないました。
審査員からのコメントや、受賞者の想いを交えながら、それぞれの挑戦を称え、より深く共有する時間となりました。




【受賞作品紹介】
■リアル部門
審査員コメント:
淡々と冷静に綴られていく一変した人生の話。軽やかな表現で示される言葉と情景の数々に魅了されました。しかし、綴られているのは、きっと読んでいるだけでは想像することすらできていないだろう大きな出来事と、その後の孤独と社会との壁について。諦めなかった日々を通して紡がれる力強い言葉と物語、しっかりと受け止めたいです。(和田彩花さん)
どんなに絶望的な状況であっても、あるいは一般にはディスアドバンテージととらえられるような要素をかかえていたとしても、希望を捨てず、よりよく生きようということを必死で考え続け、試行錯誤を続ければ、明るい未来は見えてくる――と、このようにまとめてしまえば陳腐な紋切り型になってしまい、誰の心も打たないどころか読者を白けさせてしまうということは明白であるが、そうしたリスクとつねに隣合わせでありつつも、ギリギリのところで読者の感動を呼び起こすところに着地する、というような、困難なアクロバットを文章によって成し遂げるのが優れたエッセイの特性である。
単なるお涙頂戴にとどまらず、希望を読者に伝えきるという難しい橋を渡りきった作品となっているという点において、「つくろう、こわそう、ジブンを、セカイを」というテーマが冠されたコンテストのグランプリにふさわしいものであると考え、これを推す。(樋口恭介さん)
受賞者コメント:
今回はグランプリという大変光栄な賞を頂き、誠にありがとうございます。
この賞は私一人のものではなく、息子と二人で頂けたものだと思います。
今日息子は会場には来られなかったのですが、今この瞬間をオンラインで見てくれています。息子もとても喜んでくれていました。私は実はパニック障害があり、人前に立つのが苦手です。けれど、事故後にすべてを失った息子が、あきらめずに挑戦している姿を毎日見ているなかで、私もやりたいことに挑戦したいと思い、このエッセイを書きました。私たちは現在障がい者専門芸能事務所に所属しており、障がい当事者だからこそ伝えられることを、活動を通してひとつひとつの挑戦に込めています。
最後に、この場をお借りして日々支えてくださっているすべての方々へ心から感謝いたします。


審査員コメント:
「聞こえないことで周囲とのつながりがなくなるのはもったいない。交流を通して楽しい時間を共有したい」冒頭に綴られた一文に驚きました。そして、こんなにも力強い言葉をサラッと書いてしまえるまっこさんの行動力もやはり凄まじいものでした。周囲とのつながり、楽しい時間を作るために何ができるのか、音を聞くことのできる私こそ、考えを壊し、作り直さなければいけないと感じました。素晴らしい経験をこうしてエッセイにまとめて、伝えてくれてありがとうございます。(和田彩花さん)
受賞者コメント:
私は自分自身の声が全く聞こえないので、声がしっかり通っているか全く分からない状態で話します。もし分かりにくい部分があったら申し訳ないです。非常に嬉しいお言葉をいただき感激しております。(和田さんが)言ってくださったように、自分が障がいという壁を持っている立場ではありますが、その壁を壊したことによって新しい世界が広がっていた、その経験を読んでいただいた方に新しい気づきとか頑張れるような何かのきっかけになる、そういうエッセイにしたい、という気持ちを込めて書いたので、頂いた一言一言が本当に嬉しくありがたいと思っています。今回このような貴重な機会を頂き本当にありがとうございます。


審査員コメント:
優れたエッセイには、徹底的に私的であることと、そしてそれが文芸表現という技術をもって第三者によって追体験可能となり、それによって公共性を帯びる、という二つの条件がある。そして本作にはそれがあった。
むろん、ここで描かれている希望の経験は、医学的には疑問が付されるものであり、そうした意味では危険な結末であるという留意は必要であるが、一方で、科学的には妥当とは言えないものであっても、優れた作文技術によって書かれてしまえば、読者はそれによって心が打たれ、心が動かされ、科学とは異なる仕方で納得が得られてしまう。そのような、言葉や物語の力が持つ恐ろしい側面も含めて世に問うことで、多くの人々に当事者として考える機会が与えられることには一定の価値があるはずである、という願いも込めて、本作を推したいと考えた。(樋口恭介さん)
受賞者コメント:
この素晴らしい賞をいただけて本当に嬉しいです。エッセイ応募のテーマを見て、「ああ自分のことだ」とまず思って書いてみたいと思ったのと、応募条件の中に「授賞式に参加できる方」と書いてあって、「今だったら人の前に立てるかもな」と思い、応募するきっかけになりました。去年の今頃でしたら暗黒の中におり、人の目を避けて過ごしていて、そもそも文章を書くという挑戦も出来なかったので、本当にこの場に来られて嬉しいです。アトピーに限らず(樋口さんが)仰っていただいたように、自分がなったことのない病気や他の方の悩みに、なかなか寄り添うことが出来なかったりしますが、例えば私の文を読んでいただいて、少しでも自分のことのように思ってくださる方が増えるなら、今回応募してよかったと思います。「ジブンをこわしてつくって」という……私の見えている世界がどんどん鮮やかになっていく感じがしました。
日常のなかでたくさんの方に感謝が沸いてくる時間も増えましたし、病気というのはとても辛いことではあるんですが、この過程でしか出会えなかった自分がいたと思うので、本当にいい体験だったなと思っています。


■ミライ部門
審査員コメント:
異なる場所で経験した出来事を通して考える今こそが、未来に繋がる力だと強く感じさせられました。たくさんの社会問題を抱え、明るい将来を想像しにくい現代において、横山さんのような若い世代の方が日常で見逃してしまいがちな出来事に疑問を呈してくれることが未来の明るさだと思うと同時に、成人した大人こそが現代社会をきちんと見つめ未来に続く今をつくっていかなければいけないのではないかと思いました。年齢や立場に関係なく、あなたのやりたいことに突き進んでください。あなたのやりたいことができる社会であることを大人である私から心がけます。(和田彩花さん)
未来を考えるヒントは二つある。一つは時間軸で考えること、もう一つは空間軸で考えることだ。時間軸は未来と過去に分解できるが、実のところゼロベースで未来をいきなり考えるのはかなり訓練していないと難しい。おすすめしたいのは過去について考えることだ。そして次に空間軸。空間軸というのは国や、人種や、性別や、年齢や、他の生物種や、あるいは非生物や、海や、山や、空や、宇宙について考えることだ。そして両者の射程は長ければ長いほどいい。過去は遡れば遡るほどいいし、空間は自分から遠ければ遠いほどいい。人は想像力を飛ばすこともできるし、想像力以外のものを飛ばすこともできる。だから外国に身を置くのは未来について考える助けになるし、経験した悲劇に深く分け入っていくことも、眼の前の現実に補助線を引くことになる。本エッセイは、トンガと日本の両方で育った少女が、両方の国で大きな災害を経験するという、ただそれだけの話なのだが、トンガの噴火は日本の地震を呼び起こし、日本の地震はトンガの噴火を呼び起こし、トンガの生活は日本の生活を前景化し、日本で感じたことはトンガの生活を前景化する。つまるところ、思考とは離散的であると同時に円環的なのだ。そして、そうした散り散りの思い出の発光の過程に、あるいはその間隙に、未来の思考は横たわっているのだと僕は思う。(樋口恭介さん)
受賞者コメント:
グランプリをいただいて、今回(自分が応募した)最初のコンテストなので、グランプリを獲るとは思っていなかったのですごくありがたいです。「こわそう、つくろう、ジブンを、セカイを。」が、すごく自分のやりたい活動に繋がっていて、自分の気持ちや自分の目標などを、一人でも多くの人に伝えたかったです。子どもでも大人でも、自分で自分の未来は変えられる、ということを伝えたかったので、このエッセイコンテストに参加させていただき、こんな賞をもらえて本当に感謝しています。ありがとうございます。


審査員コメント:
丁寧に綴られた日本語誤用に関する問題提起が印象的でした。しなやかな強さのなかにある揺らぎがとても素敵な作品でもあると思いました。言葉のコンテストでもある場所で疑問を投げかけてくれてありがとうございます。1人でも多くの人にこのメッセージが届くといいなと思っています。(和田彩花さん)
受賞者コメント:
本日はこのような素晴らしい賞をいただけて本当に嬉しく思います。私は今回書いた作品の中で「伝わればいいという価値観が得意ではない」ということを書きましたが、どうしても今のSNSですと音が先行するやりとりが多いので、日本語の意味や正確性があまり重要視されなくなってきてると思っています。それがすごく悲しいというか、寂しいと思っていました。今回、このエッセイコンテストで、それを少しでも共感してほしいし、そういう人もいるなあと思ってもらえたらいいなと思い、今回書いたので、すごく嬉しいです。改めて本日はありがとうございました。


審査員コメント:
僕は今年で36歳になる。中年で、ヘテロ男性で、社会的立場があり、家族がいる。要するに、権力勾配を意識しなければすぐに裸の王様になりうる人間ということだ。だからこのエッセイは、僭越ながら当事者として読んだ。
現代はしばしば、倫理的で公共的な人間ほど口をつぐみ、反倫理的で反公共的な人間ほど大きな声で話し続け、結果的に善なる言説が継承されず、陳腐な悪ばかりが跋扈する時代と言われる。
自分で自分がそのどちらに属する人間なのかを判断することは困難だが、本作を読みながら、あるいはその困難を引き受けつつ、善なるものを試行して話すこと、ためらいながら決断することの倫理を信じること、それこそが真に公共的な意味なのではないかと思い至った。
非常に現代的なエッセイで、新たな公共の可能性に開かれた、本コンテストのコンセプトにある意味最も合致した、広く問われるべき良い作品だと感じ、これを推す。(樋口恭介さん)
受賞者コメント:
この(エッセイ)コンテストを何で知ったかというと、おじいちゃんのSNS、Facebookに、盛んに広告が表示されるようになり、「これは、どんなコンテストなんだ」とちょっと気持ちが動きました。ジーズを調べてみると、どうも事業を立ち上げる人たちを育成する教育機関だなと知りまして。「おいおい、おじいちゃんはスコープの外だぞ」と思いましたが、同時に、日本には相当数のおじいちゃんがいますので、彼らもみなさんの商売のターゲットにしたらいかがですか、という意味合いも含めて応募してみました。評価いただき、賞をいただけたのは大変嬉しいです。どうもありがとうございました。


【トークセッション】
授賞式の後半では、審査員と受賞者によるトークセッションを開催。
「リアル部門」と「ミライ部門」に分かれ、各回30分のセッションを行いました。
それぞれの作品に込められた背景や、言葉を通して見えてきた“こわす・つくる”の体験を深堀し、自己表現やこれからの生き方について語り合う場となりました。
■リアル部門トークセッション

《作品の中でご自身が一番気に入っている文について》
Ryoさんは、「『夢を語る息子の姿』は、私にとって世界に光が差す感動だった。」と述べ、長い闘病の末に息子さんが未来を語った瞬間、色のなかった世界が一変し、親子の再生が動き出したと振り返りました。
まっこさんは、生まれつき音声が全く聞こえないという聴覚障がいを持ちながらも、文字起こしツールを使用し、自らの声ですべてのコメント、コミュニケーションを行いました。「壁を壊せば壊すほど人のつながりは豊かになることを証明していた。」という一文を選び、手話や工夫を通じて広がった人との繋がりを語りました。
和田さんは今日のために動画で手話を少し学習されたとのことで、手話という新たな言語への関心を寄せられていました。
直さんは、「生かされている」っていうのをこの経験で思いました」、と自身の身体の変化や生存感覚を切実に語り、そのエッセイ本文の描写の粒度の変わらなさ、深さは圧倒的だったと樋口さんがコメントしました。
《この体験をもとに次に挑戦したいこと》
Ryoさんは、親子の物語を作品として形にし、書籍化・映像化に挑戦したいと述べ、人前に立つことへの恐怖を越え、トークにも挑戦したい気持ちが芽生えたと語りました。
まっこさんは、「自分だからこそできること」を軸に、聴覚障がい者の可能性を広げる国際協力の現場で世界へ発信していきたいとコメント。
直さんは、「地球にありがとう」という思いから身近な環境活動を始め、優しさが循環する世界を目指して小さな行動を続けていきたいと話しました。
《このエッセイを読んでくれた人に伝えたいこと》
Ryoさんは、「絶望の中にも光はある」とし、恐怖や諦めを越えた先にある優しさと生きる力を信じてほしいと伝えました。
まっこさんは、壁は可能性の入り口であり、小さな一歩が未来を開くと強調。
直さんは、「うまくいかないなら一度こわしてみるのもいい」と自身の体験から背中を押したいと語りました。

■ミライ部門トークセッション

《作品の中でご自身が一番気に入っている文について》
横山さんは「恐怖を敵ではなく道標として見る」との一文を挙げ、恐怖に向き合うことで自分の使命が見え、NPO活動の原動力になったと語りました。
樋口さんは、ネガティブな感情は創作の味方であり必要なものだと共感を示しました。
法月さんは、「遠い未来で、私たちが使用していた文字が、とっつきにくいものにならないように」という一文を選び、日本語の難しさと愛しさを語りました。
和田さんは、彼女が揺れ動く心情を描いた別の一文を絶賛し、樋口さんは日本語が本来もつ“ねじれ”の自由さが作品に表れていると評価。
井端さんは「語ることは過去を差し出すこと」との一文を選び、語る行為の姿勢を示しました。
《描いた未来へ向けて挑戦したいこと》
横山さんは、沖縄で行うNPO活動を世界へ広げ、子どもたちをもっと笑顔にしたいと述べました。
法月さんは、日本語表現への関心を深め、文章として発信する活動に挑戦したいと語りました。
井端さんは、副業サイトで文章の仕事を得た体験を紹介し、今後もnoteやSNSで意図的に発信を続けながら、文章表現を広げていきたいと述べました。
《このエッセイを読んでくれた人に伝えたいこと》
横山さんは、大人には「過去のやり方が常に正しいわけではない」という気づきを、子どもには「行動こそが変化を生む」と伝えたいと語りました。
法月さんは、日本語は思っているほど難しくなく、誰の中にも豊かな表現の可能性があることを知ってほしいと話しました。
井端さんは、「人生は思い通りにはならないが、やった通りにはなる」と述べ、やらずに後悔するより挑戦する大切さを伝えたいと締めくくりました。

【審査員統括】
統括として、和田彩花さんは「受賞はきっかけ」という言葉に対し、これまでの苦労や違和感が報われる日でもあってほしいとお話され、審査を通して多くの経験に触れることで自身の視野も広がる貴重な時間だったと振り返り、感謝を述べていただきました。

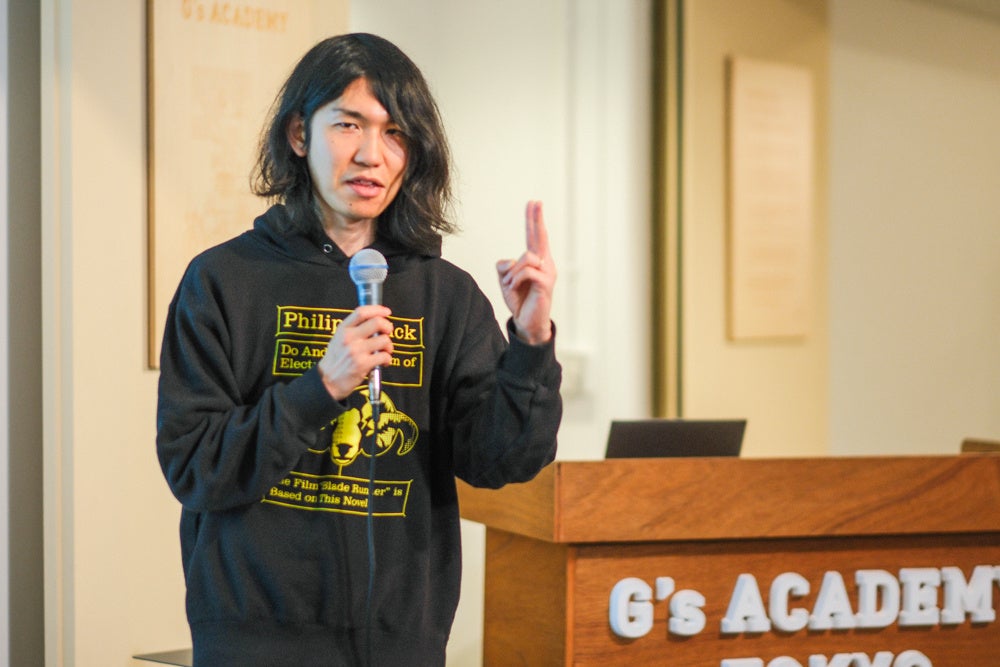
樋口恭介さんは、個々の体験が響き合う場になったと評価した上で、「インクルーシブデザイン」の概念を紹介。社会の「端っこ」にいる人のためのデザインは全体にも有益であると説き、賞という競争原理の外にある、人々の隠れた「弱さ」や「悩み」を可視化し、他者の発信を促していく活動こそが、今回表彰された人たちの使命ではないかと語り、審査員としてそのような願いを持っていると伝えていただきました。
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
