アート×イノベーション シンポジウム at 京都大学 / 12月20日, 21日
無言の声を聞く: 解放とイノベーションのアート Listening to the Silent Voices: Art of Liberation and Innovation

本シンポジウムでは、現在サンパウロ・ビエンナーレで総合キュレーターを務めるボナベンチュール・ソー・べジェン・ンディクン(Prof. Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung)を迎え、アートとイノベーションの可能性を探ります。沖縄のヒップホップアーティスト、DJ、笛奏者、現代アーティスト、茶人など多様なゲストとともに時の流れを止め、アート、政治、イノベーションについて考える場を創出します。
社会には、どの声が“聞こえる”のかを決める感性のシステムがあり、そこからこぼれ落ちる声は排除されがちです。イノベーションとは声にならない声を掬い上げ、そのシステムを揺さぶる創造の行為です。アートはこうした実践の最前線にあり、既存の意味体系を一度宙吊りにし、純粋な形式から新たな創造を生み出します。日本の茶の湯もまた、その静寂の中で唯一無二の出会いと創造の瞬間を生み出してきました。
このイベントは、京都大学がリードし、京都市立芸術大学および京都工芸繊維大学と共同で推進している、文部科学省受託事業・価値創造人材育成プログラム「京都クリエイティブ・アッサンブラージュ」による主催で開催します。国内に社会人の創造性育成拠点を作るという政府の取り組みです。京都大学ならではの人文学やアートの学問を、イノベーションに応用しています。12月21日には、京都市立芸術大学にてボナベンチュール教授によるキュレーション講義も予定しています。
1. 開催日時:令和7年12月20日(土)10:15~18:00
2. 場所:京都大学百周年時計台記念館1階 百周年記念ホール
3. 対象:どなたでも参加できます
4. 参加費:無料(企業から業務として参加の場合は3,000円)
5. 定員:500名(先着順)
6. イベント詳細ページ: https://artxinnovation-kyoto.peatix.com (参加申込もこちらから)
連絡先:京都大学 経営管理研究部 山内研究室
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
Tel: 080-4325-3528
E-mail: yamauchi.yutaka.3r@kyoto-u.ac.jp
登壇者

Prof. Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung ボナベンチュール・ソー・べジェング・ンディクン, 第36回サンパウロ・ビエンナーレ・総合キュレーター
キュレーター、文筆家、バイオテクノロジストであり、現在ドイツ・ベルリンの文化・アート交流施設「世界文化の家(HKW)」のディレクター兼チーフキュレーター、ならびに第36回サンパウロ・ビエンナーレのチーフキュレーターを務めている。ベルリンのSAVVY Contemporaryの創設者兼芸術監督を務めたほか、オランダ・アーネムで4年ごとに開催される現代美術展「sonsbeek20–24」の芸術監督も歴任。また、2017年にアダム・シムチクが企画したドクメンタ14(ギリシャ・アテネとドイツ・カッセル)では客員キュレーターを務め、2018年にはセネガル・ダカールで開催されたダカール・ビエンナーレのゲストキュレーターを務めた。さらに、マリで開催される写真ビエンナーレ「バマコ・エンカウンターズ」の第12回(2019年)および第13回(2022年)の芸術監督を務めた。2019年の第58回ヴェネチア・ビエンナーレにおけるフィンランド館のキュレーションも担当。また、フランクフルトのシュテーデルシューレにてキュレーション研究とサウンドアートの客員教授を務め、現在はベルリンのヴァイセンゼー美術大学にて空間戦略修士課程の教授兼学部長を務める。2020年にはトロントのOCAD大学国際キュレーター・レジデンシー・フェローシップの第1期生に選出された。著作多数。
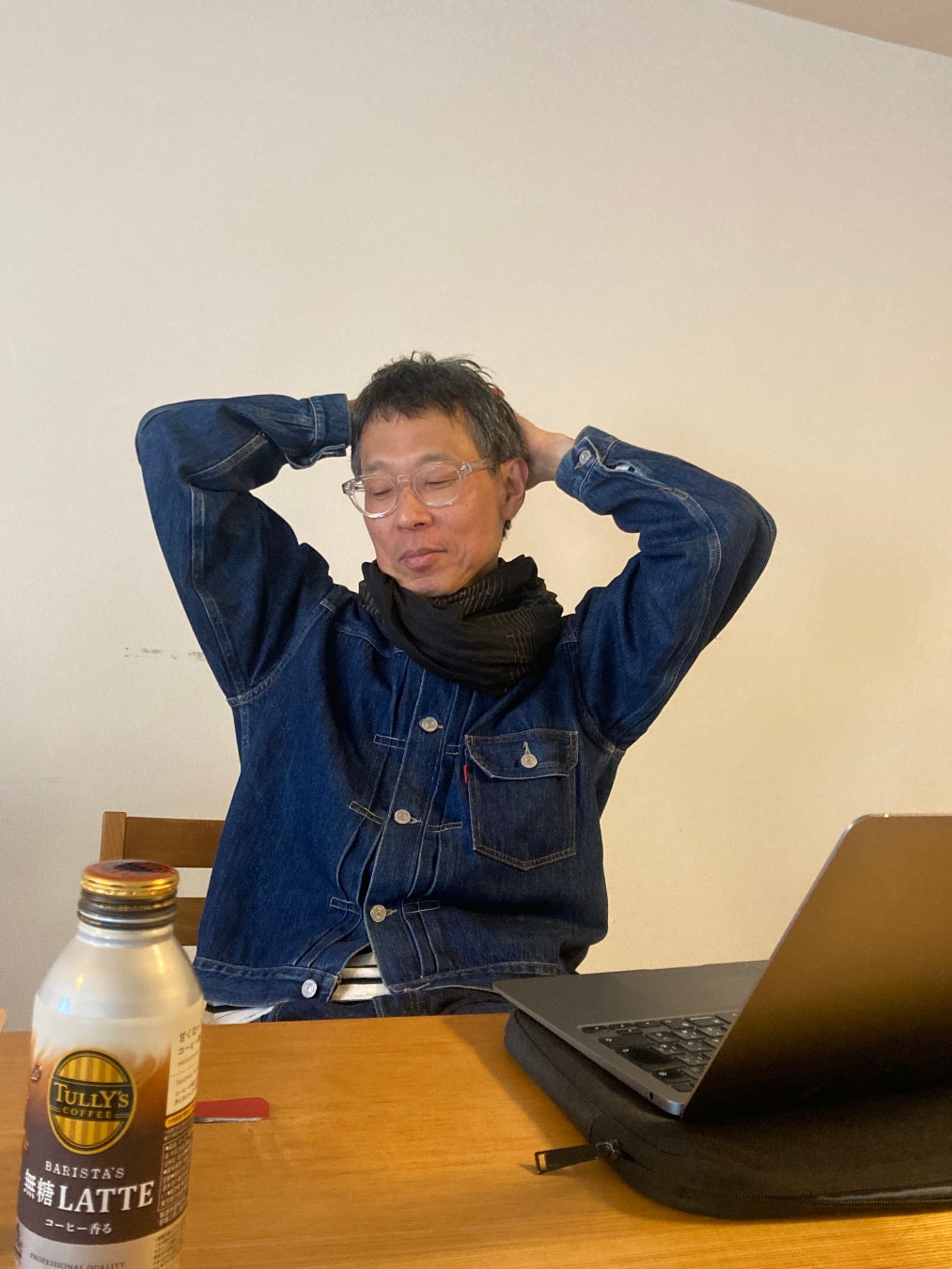
荏開津広 Hiroshi Egaitsu, 執筆家・DJ
東京生まれ。東京の黎明期のクラブでDJを、以後主にストリート・カルチャーの領域で国内外にて活動。2010年以後はより批評的な活動へ移行。PortB 『ワーグナープロジェクト』音楽監督。立教大学兼任講師。

BIG KNOT, Records/Clothing/Café (沖縄)
琉球、日本、USAの3カ国がちゃんぷるー(混ざった)小さい島から生まれたBigknot。大きく(Big)繋ぐ(Knot)大きな輪のユイマールをテーマにこの島のアイデンティティを縁で繋いで沖縄から日本、世界に発信。今回はレーベルから”TOYOMU“、”ARAHA YUNTA”など古典や民謡を新たなビートで解釈したシンガーKUNIKOがパフォーマンスを披露。

KUNIKO, シンガー (沖縄)

TECH NINE, Hiphopアーティスト, 石垣島出身のラッパー
石垣島(八重山諸島)出身のラッパー、15歳からスケートボードを始めたのをきっかけにヒップホップにのめりこむ。現在は音楽活動の範囲を広げるために京都ベースで活動中。沖縄の訛りを生かしたラップと温かみのある声に定評あり。

dj sniff, ターンテーブリスト、京都精華大学非常勤講師、東京藝術大学特任助教
ターンテーブルと独自の演奏ツールを組み合わせながら実験音楽/インプロビゼーションの分野で活動。近年は玉音放送や戦時下におけるレコードおよび聴覚文化を題材にした作品を発表。また2014年からは大友良英らとともにAMF(アジアン・ミーティング・フェスティバル)のコ・ディレクターを務める。これまでにオランダ・アムステルダムSTEIM電子楽器スタジオ(ArtisticDirector 2009-12)、香港城市大學創意媒體學院 (Visiting Assistant Professor 2012-17)、京都精華大学(特任准教授 2020-2022)に在籍し、国際交流基金、札幌国際芸術祭、ゲーテ・インスティトゥート東京、アーツカウンシル東京、日本財団 DIVERSITY IN THE ARTSの主催事業の企画・制作・監修など。2022年からはアメリカ・ロサンゼレスを拠点にしている。2025年から東京藝術大学キュレーション教育研究センターに所属。

矢野原佑史 Yushi Yanohara, 神戸大学国際文化学研究科
音楽人類学者・DJ。地域研究博士(京都大学)。2005年よりカメルーン共和国にて、森の民Bakaの音楽と社会、都市部のポピュラー音楽(特にヒップホップ)を調査。乳幼児から大人まで、音で遊びながらアフリカ文化を学ぶワークショップや公演を多数実施。現在、神戸大学アフリカン・コンヴィヴィアリティ・センター特命助教、京都大学アフリカ地域研究資料センター特任研究員。

田中功起 Koki Tanaka, アーティスト, 京都市立芸術大学
1975年生まれ。アーティスト。映像や執筆などによって「共に生きるとは何か」をテーマに、人々の協働や共同体のあり方を問い直す芸術実践を行う。近年は、育児とケアの視点からアートを捉え直す制作、執筆活動を続けている。主に参加した展覧会にあいちトリエンナーレ(2019年)、ミュンスター彫刻プロジェクト(2017年)、ヴェネチア・ビエンナーレ(2017年)など。2015年にドイツ銀行によるアーティスト・オブ・ザ・イヤー、2013年に参加したヴェネチア・ビエンナーレでは日本館が特別表彰を受ける。著作、作品集に『リフレクティブ・ノート(選集)』(アートソンジェ、美術出版社、2020年/2021年)、『Precarious Practice』(Hatje Cantz、2015年)、『必然的にばらばらなものが生まれてくる』(武蔵野美術大学出版局、2014年)などがある。

蔵屋美香 Mika Kuraya, キュレーター, 横浜美術館 館長, 京都大学経営管理大学院 客員教授
千葉県生まれ。女子美術大学卒業。千葉大学大学院修了。1993年より東京国立近代美術館勤務。2020年より横浜美術館館長。2025年より京都大学経営管理大学院客員教授。主な企画に、「ぬぐ絵画:日本のヌード1880-1945 」(2011-12年 東京国立近代美術館/第24 回倫雅美術奨励賞)、第55回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館キュレーター (田中功起「abstract speaking: sharing uncertainty and collective acts」/特別表彰)、「おかえり、ヨコハマ」(2025年 横浜美術館)他。主な著作に『もっと知りたい 岸⽥劉⽣』(2019年 東京美術)他。イラストレーター、暗☆闇香としても活動。

木村宗慎 Soshin Kimura, 茶人, 京都大学経営管理大学院 客員教授, 芳心会主宰
茶人。1976年愛媛県宇和島市生まれ。神戸大学卒業。少年期より茶道を学び、1997年に芳心会を設立。京都・東京で同会稽古場を主宰。その一方で、茶の湯を軸に執筆活動や各種媒体、展覧会などの監修も手がける。また国内外の建築家やデザイナーなどさまざまなクリエイターとのコラボレートも多く、多角的に茶道の同時代性の理解と普及に努めている。

雲龍 Unryu, 笛奏者・音楽家・細野晴臣 with 環太平洋モンゴロイドユニット
鞍馬山、吉野、富士山ほか、さまざまな「場」で横笛をはじめ土笛、磐笛、コアガラスの笛、息吹之笛、ネイティブ・フルートなど様々な笛を 演奏。1997年より細野晴臣with環太平洋モンゴロイド・ユニットのメンバーとして活動。NHK土曜ドラマ「ウォーカーズ」、龍村仁監督映画 「地球交響曲第六番」虚空の音の章に出演。平城遷都千三百年記念平城物語 “まほろば”インド医療支援コンサート、天河大辨財天社 復興音楽祭、出雲大社大遷宮奉祝コンサートに参加。奈良フォーラム・第三回アジアコスモポリタン賞授賞式式典で祝奏。2020年には、日本アーユルヴェーダ学会大阪研究総会でオンラインによる講演・演奏を行う。薬師寺・天武忌法要、比叡山延暦寺根本中堂での奉納、神社・仏閣、インド・釈尊の聖地、ネパール、ミャンマー、台湾、韓国、カナダ、米国・グランドキャニオン、ハワイ島、英国・ダートムアの聖地 他での献奏を行い活動の場を広げている。演奏にあわせて、2012年より「陶笛・息吹之笛」の創作活動を始め、各地で「息吹之笛の集い」を行い、一つ穴、一音の響きの世界を伝えている。◎日本アコースティックレコ−ズより『遮那・水のながれ光の如く』を再リリース (NARP-8001)

杉山加奈子 Kanako Sugiyama, 文化・アート起業家、キューレーター、プロデューサー
兵庫県出身、独ベルリン在住。日本、オランダ、イギリスで国際法、EU法、移民法等を学んだ後、スイスのUNHCR、タイのNGO、外務省、在ベルギーEU連合日本政府代表部、ドイツの弁護士事務所に勤務。2023年にベルリンでKAIKÔを立ち上げる。伝統工芸品の販売、コンサル、ブランディングのセミナー等行う。2025年9月からは、大館市まげわっぱの意匠開発を、パリの芸術大学とコラボして行うプロジェクトも開始。また、現代アートと伝統工芸を繋げるため、現代アート分野でも活躍。第36回サンパウロビエナーレ(2025年)の日本エディションであるTokyo Invocation(アート、学術、伝統を凌駕した学際的イベント)を、草月会館、東大にて、共同企画。2026年には、ブラジル・サンパウロの有名美術館Instituto Tomie Ohtakeにて、日本人アーティストのキューレーション・展示を行う予定。また、アートを通じて地方創生、お年寄りも子供も繋がるコミュニティビルディングにも関心があり、2025年1月から、石川県の能登で、著名ガーナ人アーティストのTーマイケル設立のアートレジデンシー・コミュ二ティ文化施設であるTーWabisatoの文化マネージャーを務める。アートは人々をつなぐ媒体であり、世代や国境、文化の違いを超えて共感や対話を生み出す力を持っていると信じている。また、アートは教育でもあると考え、次世代へのアートを通じての教育にも力を入れている。

山内 裕 Yutaka Yamauchi, 京都大学経営管理大学院
1998年京都大学工学部情報工学卒業、2000年京都大学情報学修士、2006年UCLA Anderson Schoolにて経営学博士(Ph.D. in Management)。Xerox Palo Alto Research Center研究員を経て、京都大学経営管理大学院に講師として着任。2021年4月より現職。現在は、人文学的視点から「文化の経営学」に注力して研究している。文部科学省 価値創造人材育成拠点形成事業 京都クリエイティブ・アッサンブラージュ主宰。
主催
京都大学エステティック・ストラテジー・コンソーシアム
共催
京都大学経営管理大学院
京都大学経営管理大学院 CHA寄附講座 (Creativity, Humanities & Aesthetics)
京都大学経営管理大学院 キュレーション理論・実践とマネジメント寄附講座
京都市立芸術大学美術学部美術科構想設計専攻田中功起研究室
京都大学 大学院教育支援機構デザイン学大学院連携プログラム(京都大学デザインスクール)
後援
京都市
共創HUB京都コンソーシアム(大阪ガス都市開発、コミュニティ・バンク京信、学校法人龍谷大学)
協力
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像