【10選】オウンドメディアの失敗事例!意味ない運用にならないコツまで徹底リサーチ
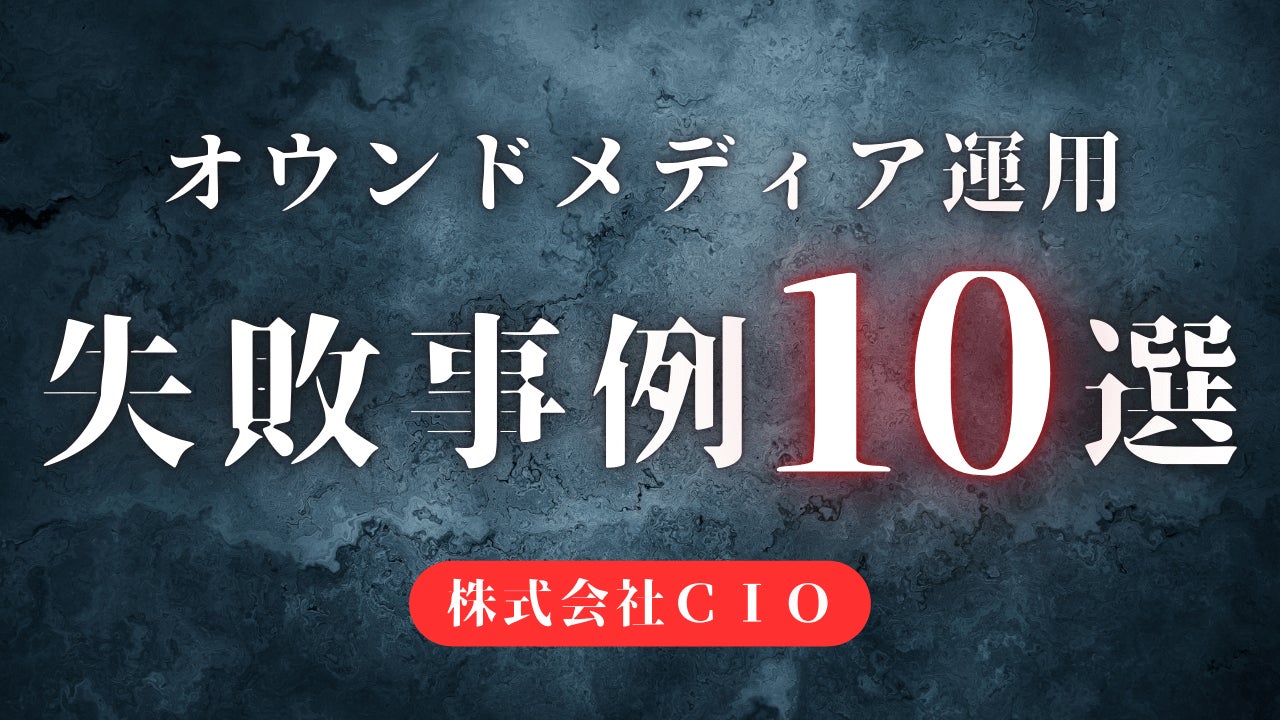
株式会社CIOは、オウンドメディアの失敗事例を30社を対象にインタビュー形式で調査、および失敗要因を10個にまとめました。
また、失敗したオウンドメディアから、弊社が介入することで「どのように成功へと舵切りしいったのか?」も解説しています。
失敗事例を学ぶことで、同じ轍を踏むリスクを回避できますので、オウンドメディア運用をしている方はぜひ最後までご覧ください。
※具体的な社名やメディア名を出さないことを条件に許諾したケースのみ掲載
オウンドメディアの失敗事例

オウンドメディアの失敗事例を10個にまとめると以下の通りです。
-
運用効率が悪い
-
セールスストーリーが甘い
-
短期間で成果計測してしまう
-
運用の目的定義ができていない
-
記事を書くことしかしていない
-
メディアの記事に関連性がない
-
狙うキーワードの競合が強すぎる
-
コンバージョンに繋がる記事がない
-
社内で運用意義を理解されていない
-
CVR改善のノウハウが欠如している
順番に詳細を解説していきます。
|失敗事例①:運用効率が悪い
▼参照メディア情報
・記事数:15本
・インデックス数:12本
・月間アクセス数:約3,000pv
・月1,2本しか更新できない
↓弊社介入後
運用体制を再構築し、月5本以上を更新できるように。
失敗事例1つ目は運用効率の悪さ。
オウンドメディアは、WordPress等のCMSで運用するケースもあれば、フルスクラッチで完全オリジナルの箱を運用するケースもあります。
WordPressであれば、運用難易度が低いため、記事更新にそこまで工数はかかりません。しかし、フルスクラッチの癖のある箱の場合、記事更新の度に、エンジニアサイドと連携する必要があり、「下書きだけ増えていき、なかなか思うようなスピード感で記事を出していけない」そんな企業も多いです。
他にも、記事へのこだわりが強く、内容チェックを他部署で行うため、記事を書いても更新まで2週間以上かかる企業もありました。
なので、オウンドメディアを運用する場合は、
-
運用難易度を下げること
-
運用体制を構築してから推進すること
この2点を意識すると良いでしょう。
|失敗事例②:セールスストーリーが甘い
▼参照メディア情報
・記事数:24,000本
・インデックス数:19,500本
・月間アクセス数:約2,500,000pv
・メディア経由のCV件数が少ない
↓弊社介入後
メディア導線を改善、およびリライトと新規記事の作成により、CV件数を2.3倍へ。
SEO対策ができていても、コンバージョンするか否かは、また別の話です。
読者が記事を読んだ際に、「どのような心情で記事を読み進めていくのか?」「最後にはどのような感情になるのか?」「その結果としてどんな行動をとってほしいのか?」などは最低限 把握しておく必要があります。
要するに、SEO対策はできていても、SEOマーケティングができていないと、オウンドメディアの効果は最大化できないわけです。そもそもSEOはマーケティングの手段であり、目的ではありません。
キーワード選定を実施する際に、周辺キーワードも含め、読者の検索意図(顕在ニーズ・潜在ニーズ)を想定し、どのようなCTAを敷くべきか?は1記事ごとに考えていく必要があります。
ちなみに..
株式会社CIOでは、記事の骨格部分のみを指示書という形式で納品するパッケージがございます。「キーワード選定、キーワードグルーピング、骨格作成、検索意図の深堀り、セールスストーリー設計」まで落とし込むパッケージなので、記事の上座設定に課題感のある企業様はぜひご活用ください。
|失敗事例③:短期間で成果計測してしまう
▼参照メディア情報
・記事数:30本
・インデックス数:27本
・月間アクセス数:約5,200pv
・ライターさんへ文字単価1円で30記事を外注し、費用対効果を見て運用停止
↓
リスティング広告が集客のメインチャネルなこと、コアなtoC商材なこと、などを加味して弊社から無理な提案は差し上げず、壁打ちのみで終了。
SEOは中長期的な施策です。
広告であれば、ショットで打つことができるため、費用対効果を計測しやすいでしょう。しかし、SEOはすぐに成果が出るわけではないので、費用対効果を計測しにくいです。
「何記事書けば何件CVするのか?」といった短期的な推測には、あまり意味がありません。どのジャンルで書くのか?どのキーワードで書くのか?によっても、CTRやCVRは激変します。加えて、オウンドメディアはコンテンツに資産性があるので、1回の投資で中長期的な成果を享受できるもの。
実際、オウンドメディアで成功されている事例を見ていくと、最初は中長期的な投資として割り切っているケースが多いです。逆に、費用対効果を徹底的に検証している企業ほど、スタートが遅くなり割く費用も少なくなり、短期的に見切りをつけるため、失敗してしまいます。
オウンドメディアは、記事からの直接的なコンバージョン以外にも、指名検索が増えることによる間接的なコンバージョン、ブランド認知度向上によるリードジェネレーションなど、他にも画面上では計測できないようなメリットも多々あります。
|失敗事例④:運用の目的定義ができていない
▼参照メディア情報
・記事数:100本
・インデックス数:79本
・月間アクセス数:約1,500pv
・とりあえず100記事書きましょうと提案され、その通りに任せてみたが、何もメリットがなかった。
↓弊社介入後
運用目的を再定義し、新規ドメインへ切り替え。半年で70記事ほどを投下し、月間12万のメディアへ成長、事業売上は2倍にグロースアップ。
繰り返しですが、SEOは手段であり目的ではありません。
そのためオウンドメディアを運用する目的が定義できていないと意味は半減してしまします。「なぜオウンドメディアを運用するのか?」は、一番最初に考えておくべきです。
多くの場合、オウンドメディアの運用目的は下記2つに帰結します。
-
採用を促進するため
-
コンバージョンを生むため
ブランディングや信頼性担保のため運用するケースもありますが、その場合はオウンドメディアというより、ルートドメインのコーポレートサイトを強化する方がコスパが良いでしょう。
|失敗事例⑤:記事を書くことしかしていない
▼参照メディア情報
・記事数:100本
・インデックス数:83本
・月間アクセス数:約5,000pv
・ドメイン評価が低く、メディアが伸びにくい
↓弊社介入後
弊社クローズドサービスを実施し、DAを「2→23」まで向上。記事の骨格を正しいものにリライトし、月間アクセス数が2倍へ。
オウンドメディアのSEO対策は、ざっくり内部対策と外部対策の2つがあります。
記事を書くことは、内部対策の中のコンテンツSEOにあたる部分。つまり、記事を書く以外にも、オウンドメディアにて実施すべき施策は多数あるわけです。
なので、記事を書きつつ、外部対策にも注力していく必要があります。その一環として相互リンクを実施する企業も多いですが、弊社ではおすすめしていません。
一定の相互リンク活動は有効ですが、リンク形式やリンク元ページ、メディアとの関連性、リンク元のドメイン評価、タイトルタグ、ページ内設置個所、など考慮すべきことがかなり多いので注意が必要。Googleも公式に推奨はしておらず、やりすぎは逆効果です。
実際、被リンク代行サービス(相互リンク数をKPIにするもの)を活用した結果、アクセスが激減したケースを何件か確認しています。
弊社では、相手先のメディアだけから適切な形式で発リンクをもらえる、かつ指名検索やサイテーション、AIO等の外部対策に有効なクローズドサービスがございますので、外部対策にお困りの際はお問い合わせくださいませ。
|失敗事例⑥:メディアの記事に関連性がない
▼参照メディア情報
・記事数:20,000本
・インデックス数:350本
・月間アクセス数:28,000pv
・何となく自社に関連のありそうな記事を量産している状態。
↓弊社介入後
無駄な記事を削除、統合、もしくはリサイクル(弊社クローズドサービスを活用し、アクセス0の記事群で、月間5万pvのメディアをゼロから構築)し、インデックス率を1.75%→50%へ改善。月間アクセスが約1.5倍に。
SEOは団体戦です。
個々の記事で勝負するのではなく、メディア単位の記事群で勝負するもの。ゆえに、ただ記事を書いていくだけでは、なかなか勝ち切ることが難しいです。
まずはオウンドメディア運用の目的を定義し、そのうえで「どのようなメディア方向性にするのか?」「なぜこの記事を書くのか?」などを考えていく必要があります。
とりあえずビックキーワードで記事を量産していく、といった運用をしていると、成果を見込むことは難しいでしょう。
|失敗事例⑦:狙うキーワードの競合が強すぎる
▼参照メディア情報
・記事数:15本
・インデックス数:12本
・月間アクセス数:約3,500pv
・とりあえず思いつくビックワードで記事を書いてみた状態。
↓弊社介入後
キーワード選定、骨格作成、ストーリ設計の上座を握り、月間アクセス数を「3,000pv→30,000pv」へグロースアップ。
キーワード選定は最重要のSEO対策。
コンバージョン(もしくは採用)に繋がるキーワードの中で、検索ボリュームが大きいが、自社のドメインで勝ち筋があるものを選定していくのが基本の流れです。
そして、核となる記事群を作っていき、その強化の一環として周辺キーワードを取得していきます。
最初から、検索ボリュームが1万や10万を超えるようにビックワードを狙っても、まず勝つことは不可能。そもそもビックワードほど検索意図がぼやけるので、そこまで良質なコンバージョンは得られません。
メディアの状況や競合によりけりですが、ロングテールキーワードでコツコツ勝ちを積み重ねていくことで、徐々にミドルキーワード→ビックワードと勝てるようになっていきますよ。
関連記事:【保存版】自分でできるSEO対策23選!何をすればいいのか?やり方を初心者向けに徹底解説
|失敗事例⑧:コンバージョンに繋がる記事がない
▼参照メディア情報
・記事数:300本
・インデックス数:285本
・月間アクセス数:約30,000pv
・アクセス数をKPIにSEOベンダーに動いてもらったが、アクセスは伸びたもののコンバージョンに繋がっていない。
↓弊社介入後
アクセスをKPIとしない方針へ転換。30記事で既存のCV件数の2倍以上のパフォーマンスを発揮。
よくあるオウンドメディアの失敗が、いわゆるKnowクエリ(「○○とは?」「○○ 使い方」など)で記事を量産してしまい、アクセスは増えたがコンバージョンに繋がっていないケース。
確かに、「○○ 使い方」等のキーワードは上位表示の難易度が低く、アクセスを確保しやすいです。しかし、どのような読者が読む記事でしょうか。
多くの場合、商品・サービスを買った後に検索しますよね。つまり、自社の見込み客ではない層に情報提供をしているだけで、コンバージョンに繋がるケースは少ないわけです。
なので、内製する場合でも外注する場合でも、オウンドメディアの運用目的を定義したうえで、目的に沿ったキーワード選定や記事作成を進めていきましょう。
|失敗事例⑨:社内で運用意義を理解されていない
▼参照メディア情報
・記事数:50本
・インデックス数:48本
・月間アクセス数:約6,600pv
・担当者ベースではやりたいが、経営者レイヤーから反対がある。
↓
お打ち合わせをし、資金繰りの問題から予算を割けないことを理解。集客の優先順位を整理し、無理な提案はせず、費用対効果の高い短期的な一時集客の手法を共有して終了。
地味に多いケースが、社内で運用意義を理解されていないケース。
担当者はオウンドメディアの意義を理解しているものの、経営者レイヤーが意義を理解しておらず、どうしても優先順位を下げざる負えないケースです。
この場合、予算も降りにくく別の仕事を回されるため、オウンドメディアにリソースを割くことができません。そして、多くの場合は、担当者単位で話をひっくり返すことは難しいです。
とはいえ、すべての会社がオウンドメディアをやる必要はありません。別の集客チャネルが適しているケースも多々あるので、「オウンドメディアをやらない」という判断は正しいケースもあります。
|失敗事例⑩:CVR改善のノウハウが欠如している
▼参照メディア情報
・記事数:12,000本
・インデックス数:8,900本
・月間アクセス数:約890,000pv
・コンバージョンは生んでいるものの、CVRがそこまで良くない。
↓弊社介入後
メディア内部のCTRを調整、新規記事を作成していき、CVRを1.3倍へ改善。
CVR改善には、セールスストーリー設計以外にも、細かい部分の調整が大切です。
例えば、リンク形式にしても「ボタンが良いのか?」「テキストが良いのか?」、はたまた「何色が良いのか?」「アニメーションはつけるべきか?」「どの場所に設置すべき?」「どのくらい設置すべきか?」「前後のマイクロセールスは最適なのか?」など、考えるべき観点が盛りだくさん。
また、コンバージョンが増えれば良いわけでもありません。敷居を下げればコンバージョンは増えますが、ホットリードの割合が低ければ、人件費の観点でマイナスを生むだけです。
また、無理くりにコンバージョンを増やしていくと、本来の想定ペルソナと異なるリードにまでリーチしてしまい、レピュテーションリスクを高めてしまいます。
なので、「ペルソナを定義したうえで、ホットリードをいかに増やしていく?」といった考え方が非常に重要です。
意味ないオウンドメディア運用にならないコツ

最後に、「オウンドメディア運用が意味のない施策」にならないコツをまとめます。
下記3つの流れで考えるのがおすすめです。
-
オウンドメディアをやるべきか?を考える
-
自社で運用すべきか?外注すべきか?を考える
-
中長期的な視点を持ちつつ、成果を計測していく
順番に解説していきますね。
|運用のコツ①:オウンドメディアをやるべきか?を考える
まずオウンドメディアをやるべきか?否か?を考えましょう。
オウンドメディアをやる目的を定義、自社の状況と照らし合わせることで、そもそもオウンドメディアをやるべきではないという決断をするべきケースもあります。
勝ち筋がないのに、何となくオウンドメディアを運用しても、無駄な予算が消えていくだけですので、大前提「本当にやるべき施策なの?」という観点を持ちましょう。
ちなみに、弊社では毎月10社限定で、60分1万円のスポットコンサルを実施しています。SEOセカンドオピニオン、SEOの壁打ちとしてご利用いただけますので、お悩みの方はご活用ください。
|運用のコツ②:自社で運用すべきか?外注すべきか?を考える
仮に、オウンドメディアを運用する場合は、内製か?外注か?を考えましょう。
SEOのノウハウとライターリソースがあれば、内製化しても問題なし。ただ、どちらもない場合は、外注する方が結果的にコストパフォーマンスが高くなることが多いです。
弊社は、再委託なしで現役のアフィリエイターが一気通貫で対応するスタンスです。受注後にクラウドソーシングで文字単価1円で再委託したり、現場経験のない新卒2年目3年目の若手人材をアサインしたり、などは一切していません。
また、上座は人間が徹底的に設計し、ライティング部分のみAIに任せる、『スマートAIライティング』というサービスも提供しています。
文字単価2円~にて、キーワード選定から記事制作まで一気通貫で巻き取る高コスパサービスですので、予算的にオウンドメディアが難しい会社様にもおすすめです。
|運用のコツ③:中長期的な視点を持ちつつ、成果を計測していく
最後は、短期的な費用対効果でオウンドメディアの成果を判断しないことです。
SEOはすぐに成果が出るマーケティング手法ではありません。例えば、検索ボリュームが1,500のキーワードで1位を取得すれば、継続的に1回の投資で効果を享受することが可能。
リスティング広告だと、1クリック当たりの課金なので、課金し続けないと成果は出ません。そして、競合が増えるにつれて、1クリック当たりの金額は増加する傾向にあります。
実際、100%リスティング広告に頼っている企業様から、下記のようなご相談をよくいただきます。
-
「クリック単価が高くなってしまい、別チャネルでの集客が必要になった」
-
「コスパ良くリードを確保できているが、リスティング広告だけでは獲得リード数に上限がある」
なので、継続的に成果を享受できる別軸の集客チャネルとして、オウンドメディアを育成していくのが効果的と言えるでしょう。
以上3つの観点を踏まえつつ、前述したオウンドメディア失敗事例と同じ轍を踏まないようにすれば、適切な方向性で運用していくことが可能です。
オウンドメディアの失敗事例:まとめ
株式会社CIOは、ドメイン立ち上げ~マネタイズまで会社の資本を活用せず、1人で達成し切れる人材しか役務提供をしていません。
そして、役務提供する人材は、あえて個人事業主の人格を有しており、そちらで毎月1回以上は新規ドメインの立ち上げからマネタイズまでを実施し、常に最前線の情報をキャッチアップしております。
そのため対応できる法人様数には限りを設けておりますので、必要な場合はお早めにお問い合わせくださいませ。
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
