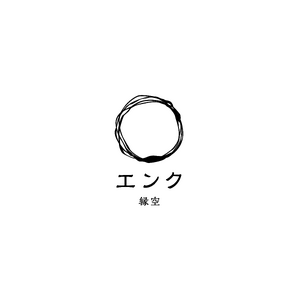今年のお盆こそ、親族に切り出そう! 「墓じまい」や「遺言」のこと
TikToker僧侶&葬祭カウンセラーの行政書士が〝看取り〟の無料相談サイト 「ハスノミ」 をOPEN
今年のお盆こそ、 親族に切り出そう! 「墓じまい」や「遺言」の話
TikToker僧侶&葬祭カウンセラーの行政書士が
看取りの無料相談サイト 「ハスノミ」 をOPEN

TikTokで18万人超のフォロワーをもつ古溪光大僧侶(ふるたに・こうだい。曹洞宗/群馬県安中市・龍峩山雲門寺副住職)が、『いいお坊さん ひどいお坊さん』(ベスト新書、2011年)著者の勝桂子(すぐれ・けいこ。墓じまいや遺言相続に特化した特定行政書士)とタッグを組み、2023年10月に設立した縁空(えんく)合同会社。
同社はこのほど、〝看取り〟とその前段階である〝人生の秋〟について無料相談できるQ&Aサイト「ハスノミ」を立ち上げました。

「ハスノミ」の回答者は、葬祭の歴史や民俗学的な意義について動画講座で学び、縁空の認定を受けた葬祭カウンセラー。縁空の葬祭カウンセラー認定実用講座は2024年4月に開講し、現在までの認定者は25名(創始者の二村祐輔と勝桂子を含む。https://enc-llc.jp/sousai-list/)。いまの構成メンバーは僧侶と士業者が目立つが、受講資格はとくに設けておらず、今後は介護・医療・葬祭周辺事業者やいつか親族を看取る一般市民などへもひろげてゆきたいと企図しています。
葬祭界と寺院界には、「その価格、妥当なの?」を市民が考える基準もリテラシーもない! 縁空がリテラシーを伝え、葬祭とお寺の〝不透明〟の闇に斬り込みます
■葬儀と寺の世界には「価格ドットコム」のような比較サイトがない

Q 僧侶の立場で、仏事や葬祭をはじめ死後事務や遺言相続など、看取り周辺のことをきける無料相談サイトを立ち上げたきっかけは?
古溪:親の葬儀を出さなければならなくなったとき、昔は電話帳で「わが町の葬儀社」を探せばそれでよかったと思います。いまは「地域名、葬儀」でインターネット検索すれば、葬祭会館などの情報はたくさん出てきますが、大手は広範囲にサービス展開しているので、本社はぜんぜん違うエリアにあったりします。「価格ドットコム」のような比較サイトもないので、じっさいどの企業がほんとうに親身になってくれるのか、評判がよいのかということもまったくわからない。だけど皆さん、喪主になるなんて一生に一度か二度のことなので、ひどい思いをしたとしても「しょうがなかった」で済ませてしまっている人がほとんどです。この状況をなんとかしたいと思いました。
Q お寺の世界も不透明で、昨今は「葬儀に僧侶を呼びたくない」という人も増えていますよね?
古溪:私の寺は群馬の山中ですから、まだ「呼びたくない」という声は幸いにして多くはないように思いますが、都市部はそうですね。多くのお寺は、お布施の目安を僧侶自身の言葉で伝えることもしていない。よくわからないから無理せず出せる金額を包んだら、黙って突き返されたという話も聞きます。しかし、檀家総代に気軽に聞けた時代と違い、いまは檀家さんも離れてバラバラに住んでいてお互い疎遠ですし、目安を言ってもらわなければ払いようがありません。
いまほんとうに生きづらい人がたくさんいて、精神科はどこも予約が一杯。生老病死苦について考えぬいたお釈迦さまの教えがいまほど人びとの役に立つ時代はないのに、この国では「お寺へのお布施の相場がよくわからないし、墓じまいをして離檀しよう」と、なんとなくの理由で、お寺から離れていく人が続出している。これはなんとかしなければ、との思いで、まずは皆さんのリテラシーを向上してもらおうと、ハスノミを立ち上げました。

■お寺が〝看取り〟のハブになれば
Q 勝(すぐれ)さんは『いいお坊さん ひどいお坊さん』の著者として、全国さまざまな宗派の僧侶研修に登壇し、〝お寺を看取りステーションに〟を提唱してきたと聞きます。なぜお寺ではなく、葬祭カウンセラーの普及に転向したのですか?
勝:15年間、全国の僧侶研修に登壇してきました。お墓を管理するお寺が中心となって、遺言相続業務をこなす士業者や、介護施設、医療機関、社会福祉協議会とも連携し、地域の看取りの輪をつくってゆけば、「看取ってくれる子どもがいない」、「子どもはあるが、遠くに住んでいて私が危篤になってもすぐに駆けつけることができない」といった市民も安心して過ごせると提案しつづけてきました。
ところが15年たっても、実現できている事例が数えるほどしか増えなかったんです。地方のお寺のご住職は月~金は市役所や学校に勤務しているかたも多く、とても新たなことに着手する余力はないんですね。そこで、お寺に企画を持ち込める市民を増やすことが先決だと思いました。
たとえば「認知症カフェ」や「介護について語らう会」、「余命宣告を受けた人のわかちあいの会」でも「ひきこもりの親族の会」でもなんでもいいのです。学校や会社では話題にしづらい、生きづらさや死にかかわる話題について、お寺であれば切り出しやすい素地があります。年に数回でも、そうした生きづらさや人生観に関する話題を定期的に語らう企画を、市民がお寺へ持ち込んでいく。そうすることでやっと、「お寺に人生相談してみよう」とか、「菩提寺(お墓のある寺)の和尚さんに親戚代わりのようになっていただいて、私の死後事務を任せてみよう」といった人が出てくると考えました。
わからないことをハスノミで無料相談。親族と話すための基礎知識をつけよう!
■毎月22日20時~、縁空月例Zoomを開催(どなたでも参加可)
社長の古溪は今年2月、ABEMA Prime「僧侶不要論」に出演し、「お布施の目安もいえない僧侶は、これからの時代には不要」と明言しました(リンク先動画19分28秒)。
お布施や葬儀のことは、どうして不透明なのか? これを解決すべく、縁空の葬祭カウンセラーたちは毎月22日の20時~の月例Zoomで「TVCMに出てくる格安葬儀を依頼すると、どんな葬儀になるのか」、「樹木葬墓地見聞録」、「生前葬ってどんな感じ?」など、さまざまなテーマで事例発表や意見交換を行っています。
僧侶の参加者には「難しい話を説くだけでなく、お布施についても、どういえば市民に理解してもらいやすいのか」を。一般市民の参加者には、わからないことを何でも聞ける場を提供し、ハスノミ回答者として適切な回答をできるよう、日夜研鑽を積んでおります。
この月例Zoomは縁空公式LINEに登録したかたであれば、どなたでも参加可能。「葬祭カウンセラーに興味はあるけど、まずは雰囲気を見てみたい」というかたも歓迎です。
■今年のお盆こそ、親族と語らおう! そのためにまず、知識の蓄積が重要
☑お盆や年末年始、GWが来るたびに、「今年こそはお墓の話を切り出さないと……」と思うのに、けっきょくうまく切り出せないまま旅程が過ぎてしまう。
☑切り出してはみたものの、核心にふれる話はできずに流されてしまった。
多くのかたが、こうした経験をお持ちではないかと思います。そうなってしまう根本原因は、基礎知識がないことにあります。
-
お墓をしまうには、どんな手順がいるの?
-
お寺との話がこじれてしまったら、どうすればいいの?
-
葬儀の生前予約をしたほうがいいと思うけれど、どんな業者を選べばいいのかわからない
-
親に遺言を書いてもらいたいけれど、何から切り出せばよいのかわからない
縁空が新設するウェブサイト「ハスノミ」では、いつでも無料で、こうした〝人生の秋〟に関することを質問できます。
■「ハスノミ」は、お坊さんが必ず答えてくれる人生相談サイト「ハスノハ」の姉妹サイトです

ハスノミと聞いて、「そんな名前の相談サイト、ほかにもあったよ」と思ったかたもいらっしゃるでしょう。縁空は創業当初から、お坊さんが必ず答えてくれる相談サイト「ハスノハ」(2012年~)の堀下剛司代表とタッグを組んでおり、今回の相談サイト「ハスノミ」はその姉妹サイトという位置づけでオープンしました。
内面の相談は「ハスノハ」へ、手続き面を中心とした相談は縁空の「ハスノミ」へ。どちらも、生きづらさや人生観といった〝答えのない問い〟に向き合うサイトです。
これまでの資本主義社会では、インプットとアウトプットが得意な人が偏差値を評価されてきました。しかし、インプット&アウトプットで出せる答えは、AIが得意とするところ。これからの社会に必要な資質は、〝答えのない問い〟に答えるスキルや経験であると、縁空は考えます。
人生観や死生観といった〝答えのない問い〟を、お坊さんや葬祭カウンセラーとともに感じ考えてゆきたい人々のため、ハスノハ&ハスノミは連携して「学校や会社では話しづらいことを相談できる場」を提供しつづけます。
葬祭カウンセラー認定実用講座が、よくある終活系資格と異なる理由
■年会費負担なく、生涯「葬祭カウンセラー」を名乗れる
終活カウンセラー、お墓ディレクター、終活士、終活アドバイザー、供養コンシェルジュ、看取り士などなど、終活系の民間資格は乱立しています。そのいずれもが年会費を収めている間だけ資格者を名乗ることができ、「取得はしても、ほとんど仕事にならない」と言われています。
縁空の葬祭カウンセラー認定実用講座は、動画10本の試聴と効果測定で認定を受けられます。その後の入会金や年会費は必要なく、生涯「葬祭カウンセラー」を名乗っていただくことができます。半世紀前の日本人なら、誰でも肌で感じていたことをお伝えしているので、会費を払いつづけなくとも、一度コツをつかんでいただいたら知識がブレることはないと考えているからです。
現在のデモサイトでは、「質問ができ、回答がつく」というシンプルな機能のみですが、秋には回答者のマイページ機能を追加予定。回答者は、良質の回答をたくさんつけることにより、自身が得意とする別のサービスや有料相談へと誘導することも可能となりますので、〝食べられない民間資格〟にはならないと自負しております。
■70代以上になっても相談に乗れる稀少な資格
また葬祭カウンセラーは、友人や知人の葬儀に出る回数が増えれば増えるほど、カウンセリングの腕に磨きがかかるため、80代、90代になっても、頭さえしっかりしていれば相談に応じることができます。
「年金生活になって、10万円以上稼ぐ必要はないけれど、月に数回でも有料相談に応じることで、孫と食事にいくための小遣いが稼げたら……」
といった需要に応え、中高年の生きがいを下支えすることのできる資格といえます。
■リカレント教育の一環としても注目できる「葬祭カウンセラー認定実用講座」
社長の古溪光大がTikTokerであることから、縁空はSNSでの発信等にも長けており、個々の葬祭カウンセラーが個別相談を受けるためのSNSアカウント作成からファネル構築(申し込みまでの導線確保)まで、個別指導することもできます。
高齢になっても相談者を募り、相談を受けることのできる有望な資格である葬祭カウンセラー認定実用講座。リカレント教育の一環としても、ぜひ縁空の「葬祭カウンセラー認定実用講座」をご検討いただきたいと考えております。

■〝生きがい危機〟をなんとかしたい
いま終活セミナーにみえるかたの関心の大半は、お金の心配です。
しかし、子育ても終わり、あくせく働く必要のなくなった老後の時間はほんらい、人生をふりかえり、残りの時間どのように生きるべきか? を考える濃密的で哲学的な思索の時間であるべきと縁空では考えています。
それを実現するため、葬祭カウンセラーを全国に増やし、「親の葬儀をどうする」、「親族の墓をどうする」から遺品整理、遺言相続、ひいては「生きがいとは?」まで、ひとりでも多くの皆さんが葬祭を起点として人生観を確立してゆくお手伝いがしたいのです。
今後予定している縁空の活動:オリジナルのハニワキャラクターを用いた葬祭ネタの普及
「葬祭」と聞くと、親の葬儀を出す予定でもない限り、「自分にはまだ関係ない」、「暗い話だ」と感じてしまいがちです。しかし縁空では、大人たちが何時間も語らう昔ながらの通夜葬儀こそ、若い世代の倫理意識を育成する場であったと確信しています。
昔の葬儀では、幼い子どもたちは眠い目をこすりながら、「死んだときあんなに人が集まって噂話をするんじゃ、人さまに後ろ指をさされるようなことはできないな」と心に刻んだはず。じっさい保護司をしている僧侶らからは、「特殊詐欺集団に加担してしまう少年たちの大半は、成人するまで葬式に出た経験がほとんどないと話している」などと聞きます。
なんとしても、敬遠されがちな葬祭の話に向き合う人を増やしたい。人は、ゴールテープを見なければ全速力で走ることなどできないのだから、ひとりでも多くの人に葬祭の重要性を理解していただき、そしてゴールをみすえることで、人生観を確立してよりよく生きていただきたい。その願いから、オリジナルのハニワキャラクターによる葬祭知識などの普及を企画しました。

秋以降には、これらのキャラクターを配したオリジナルグッズも開発してゆく予定なので、乞うご期待です。
【会社概要】
社名:縁空合同会社
本社所在地:東京都板橋区赤塚2―12-6
代表:古溪光大
事業内容:「葬祭カウンセラー認定実用講座」や「人生物語」といった無形コンテンツの販売、 関連セミナー、関連グッズの販売
設立: 2023年10月17日
ウェブサイト:https://enc-llc.jp/
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像