南大阪地域の居場所づくりや拠点強化に取り組む5団体を決定
「南大阪地域子育て支援ハブ形成プロジェクト」実施期間は2028年2月まで
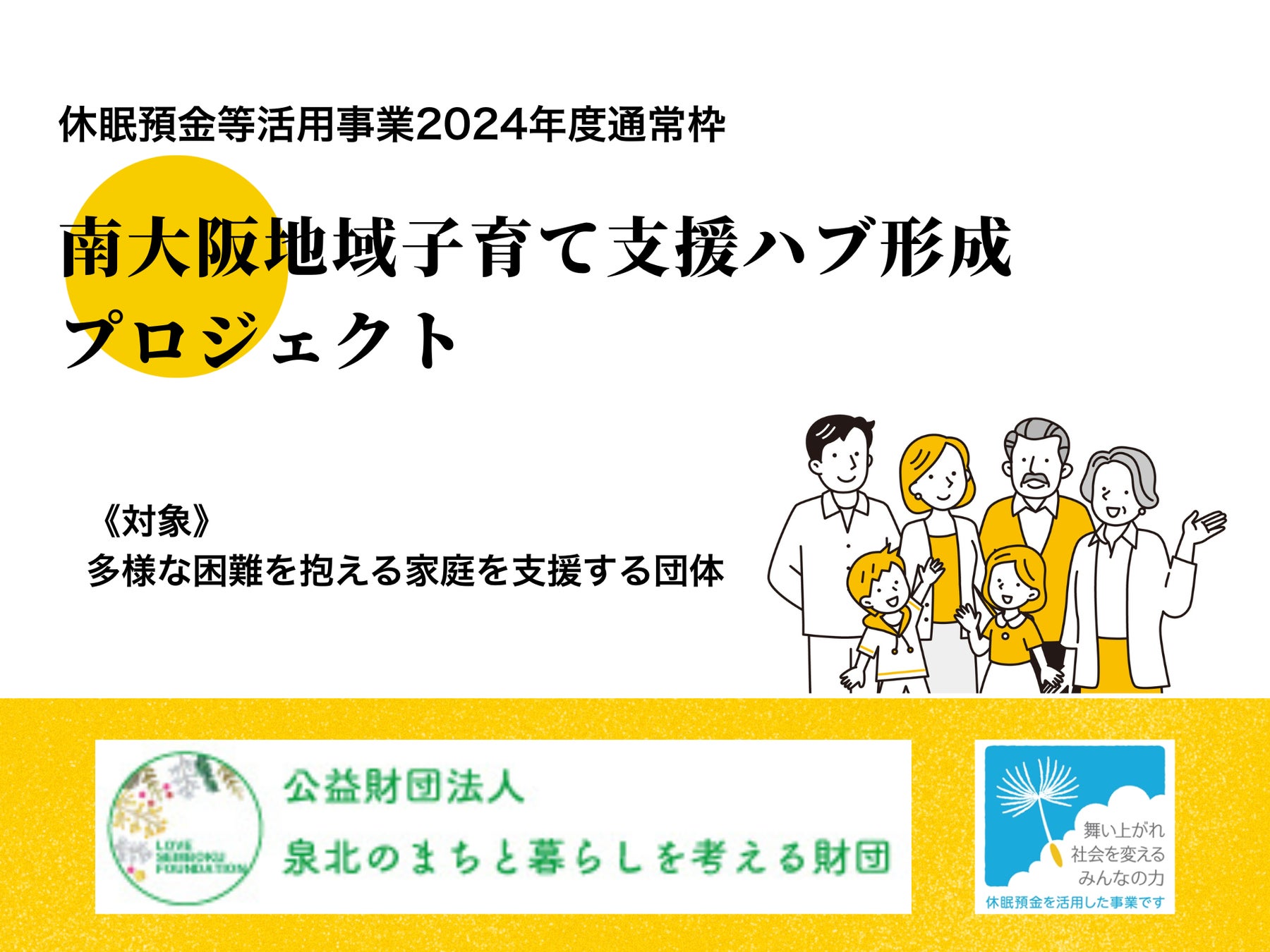
公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団が取り組む「南大阪地域子育て支援ハブ形成プロジェクト」において、5団体が採択・発表されました(https://semboku-fund.org/archives/3869)。2025年10月~2028年2月(約2年5ヶ月)を事業期間とする予定です。
■南大阪地域子育て支援ハブ形成プロジェクトとは
公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団では、2021年度休眠預金活用事業(通常枠)において、泉北ニュータウン地域の『社会的孤立』解決のため、多様な世代への支援を行う3つの居場所事業を3年間のべ65,278人へ提供してきました。
居場所事業の運営から見えてきた個人の抱える社会課題を包括的に捉え、当事者だけではなく多様な主体の協働を推進する仕組みづくりとして、「地域版重層的支援」とも言える「実行会議(ケース会議)」の場を設け、これまでに80件を社会資源に接続するなど、成果を達成してきました。
しかし南大阪地域に目を向けると、子ども・若者を取り巻く環境は依然厳しく、常設型の居場所が不足しており、地域単位でのモデル確立が求められています。
本事業では、「実行団体が、南大阪地域において、自ら居場所を運営できること」を目標に、ファンドレイジング力、情報戦略、人材育成の3点を支援し、基盤強化を図ります。
具体的には組織診断の実施と個別伴走支援計画の策定、事業設計図(ロジックモデル・セオリーオブチェンジ等)の作成、クラウドファンディングなどを通じたファンドレイジングを支援します。また、地域に開かれた敷居の低い居場所に当事者が繋がることができる情報戦略構築を支援します。さらに、居場所を通じて発見された地域課題を地域内で連携し協働できる体制整備のために実行会議の開催支援、ファシリテーターの派遣、開催のための研修会を当団体が主体となって支援します。
当団体は、本事業における上記一連の支援活動を通じ、これまでの泉北ニュータウンでの取り組みの成果をもとに、南大阪の各地域において、当団体の提唱する『自走型自治モデル』が構築されることを目指しています。
■実証実験を行う課題と採択団体
採択団体①:東深井つどいば食堂ふらっと
事業名:誰もが学び集える居場所づくりと地域の相談窓口
誰もが学び集える居場所と地域の相談窓口をつくりたい!
従来の活動(みんなの居場所づくりとこども食堂)は平日週2回と土日月1回であるが、今後は常設型を目指し平日週3回~4回、土曜日 月2回と回数を増やし、不登校児童の居場所や学習支援、大人の集いばなどをより参加人数を増やす為に内容を強化していく。不登校児童の居場所の成果の向上としては、週1回の開催は変わらないが現状の参加人数を倍に増やして、学習の定着、学習意欲を高めていき、自己肯定感を上げることで、将来の選択肢を増やしていく。漢検や英検受験も検討。晩ごはん提供は現在月2回程度だが、週1回に増やし参加人数を増やす。土曜日は他団体とも連携でワークショップやイベントなどを開催し、こどもの居場所の周知や活動を応援してくれる人や企業を増やす。現状の開催日数より開催頻度を増やしていくことは、現在参加している 又は参加できていない人からの希望として声が出ており、日数を増やすことで、より多くの人が自分のニーズに合った内容や時間帯などで参加できるようになり、支援や見守りの人数を増やすことができる。そして、地域の中で気軽で安心安全な相談窓口として認知が増えていくことで、より多くの人の拾い上げが可能となる。休眠預金で従来より幅の広い取り組みをすることができれば、この居場所事業に専属で従事できるスタッフが増え(現在は全員本職の傍らでの作業)より安定した居場所運営が可能になる。
採択団体②:あたごプラザ協議会
事業名:舞校区 みんなの居場所プロジェクト
あたごプラザにあらゆる世代が集まる拠点をつくりたい!
自治会や子ども会等への参加者が減少し、子ども会については2025年度で終了することが決まる中、これら地域活動の衰退を改善することは喫緊の課題と認識し、『あたごプラザ』を拠点として、これまでの高齢者を中心とした「地域住民の生涯学習と地域福祉の増進を図る場」に加え、①「楽しい地域交流を体験することで、将来、地域に参加することが当たり前と認識し、地域の中で自立していく子ども世代を育成する場(子ども食堂や子ども会的なイベント)」、②「親世代が安心して楽しく暮らすために集まり情報提供・交換など共助する場(子育て支援ハブ)」、③「子育てを終えた世代が次世代のためのボランティアとして参加できる第二の活躍の場」、そして④「子ども、親世代同士や参加するボランティアスタッフなどあらゆる世代が安全安心にワイワイ楽しく過ごす交流の場」を構築することで『あたごプラザ』に集まる関係人口を増やし、その結果、①→②→③のサイクルを経て④を維持し、定定住人口を維持することで、舞校区を再活性化していく。
採択団体③:特定非営利活動法人青少年自立支援施設淡路プラッツ
事業名:南河内地域に点在する様々な社会資源とひきこもりの若者を繋ぎ社会参加のための出番創出を行う事業
南河内地域に点在する社会資源、ひきこもり、生きづらさを抱えた若者と家族をつなぎたい!
コロナ禍以降の不登校の数は34万人に倍増し、ひきこもりの数は146万人、中でも8050問題と呼ばれる親が80歳子どもが50歳の高齢ひきこもりの増加を含め大きな社会問題となっている。大和川以南の地域においても、支援機関や居場所が不足していると言われており、ひきこもり支援においても例外ではない。このような状況を踏まえ本事業では、行政や社会的に支援の受け皿の少ない学齢期以降の20歳代~概ね40歳代までの若者で、ひきこもり・ニート・不登校状態にある方々とその家族を主な対象とした支援を行う(10代および高齢ひきこもりも含む)。同時に、地域に不足している拠点としての居場所を拡大し若者の出番を創ることで、地域のハブ的な役割を担うことを目指す。取組の方向性として、以降の「5つの柱」を軸に遂行する。柱①居場所のリフォーム、柱②居場所による「相談事業強化」、柱③「組織基盤強化」および「人材育成」、柱④居場所を拠点とした「出番の創出」、柱⑤地域連携創出(実行会議の開催)、である。これらを通じて、南河内地域に点在する様々な社会資源とひきこもりや生きづらさを抱えた若者と家族を繋ぎ、社会参加のための出番創出事業とする。また、事業開始時から終了後を見据えた組織基盤強化を図り、地域のステークホルダーと連携協力しながら、終了後の自走型の伴走的な若者支援の継続と地域共生の実現に取り組む。
採択団体④:NPO法人モモの木
事業名:堺市地域子育て支援ハブ形成プロジェクト
ひとり親家庭やヤングケアラー家庭への家事支援ヘルパー部門を立ち上げたい!
NPO法人の立ち上げから4年経ち地域の居場所として根づいてきたが、深く関われば関わるほど、行政制度の狭間で孤立し生きづらさを抱える家庭が非常に多い。生活課題が複雑化し1つの制度だけでは解決できない、支援が必要だが制度を利用できる要件を満たしておらず生活が困窮する家庭がある。なんとか支援したいが現在の体制では金銭面、組織体制(人手不足)の面でも継続することだけで精一杯で、加えて専門性を持つ人材も不足している。本事業では①重層的支援②既存事業の継続ができるよう運営の基盤を強化することを柱とする。①は専門性を持つスタッフ(保育士、社会福祉士、ソーシャルワーカーなど)を配置し、潜在的に支援が必要な家庭を見つけ出す。ひとり親家庭やヤングケアラー家庭への家事支援ヘルパー部門の立ち上げ、モモの木と信頼関係を構築しながら行政に繋げ、支援家庭と伴走していく。また定期的なスタッフ研修会やケース会議を開き重層的に支援できる体制を作る。②は継続のために事業運営の組織基盤を強化していく。各部門ごとに専任のメンバーを配置し、代表以外の中心メンバーも経営に携わっていく。これまで地域で継続的に活動してきた強み・信頼を生かし誰でも来ていい場所、相談しやすい地域のハブ拠点として存在を高める。モモの木の重層的支援により、問題が深刻化する前に相談してもらい生きづらさを軽減させ、子どもたちを取り巻く環境が改善される。
採択団体⑤:一般社団法人カンデ
事業名:美加の台みんなの居場所づくり事業ー多様な主体の恊働による地域まちづくり活動拠点整備と持続的なまちづくり活動環境構築のための関係づくりー
スーパーの空きテナントを活用して誰もが立ち寄れる居場所をつくりたい!
本事業は、1984年分譲のニュータウン美加の台において深刻化する少子高齢化、人口減少、地域のつながりの希薄化、子どもや若者の孤立といった社会課題に対応するため、スーパーの空きテナントを活用し、誰もが立ち寄れる常設型の居場所拠点を整備するものである。拠点の基本業態としてカフェを運営し、日常的に住民が利用できる収益基盤を確立させ、その収益を原資に、子どもの学習支援や子育て世代の相談支援、高齢者や生活困難者に対する有償ボランティアによる生活支援など、地域の多様なニーズに応える公益的事業を展開する。また、地域住民・大学・行政・民間事業者による「実行会議」を設置し、定期的に課題を共有・検討することで、地域の課題解決を継続的に推進する体制を整える。収益面では、カフェ売上を安定的な事業収入としつつ、イベント実施やワークスペースとしての利用など、複数の事業を重ね合わせたり、生活支援の一部を有償化することで利用者の負担能力に応じた費用負担を組み込み、助成金終了後も収支相償以上で運営できる持続的な環境を形成する。将来的には行政・大学との連携による事業受託を進めることで、複数の収入源を確保し、持続的な事業展開を可能にする。本事業では、社会課題の解決と自立的な収益構造の確立を両立させ、地域に根差した持続可能な活動拠点を創出し、孤立防止や子どもの育成支援、安心して住み続けられる環境形成を目指す。
■公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団とは
公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団は、泉北ニュータウンの少子高齢化をはじめ、児童虐待、子どもの貧困、不登校、教育格差、子どもの自殺、ひきこもり、認知症、老老介護、買い物困難者などの当事者やその家族など、多くの「社会的孤立」を解決したいと取り組んできました。さらにエリアを拡大し、今後は南大阪(など)の課題解決に取り組んでいきます。
▼これまでのメディア掲載
https://semboku-fund.org/archives/category/media
▼公式ウェブサイト/公式アカウント
・公式ウェブサイト:https://semboku-fund.org/
・YouTube:https://www.youtube.com/@semboku-fund
・Facebook:https://www.facebook.com/semboku.fund.org/
・Instagram:https://www.instagram.com/lovesenboku/
・X(旧Twitter):https://x.com/semboku_fund
・note:https://note.com/semboku_fund
■ 本件に関するお問い合わせフォーム
すべての画像
