全健会・JCA顧問の小林豊病院長と、JCA海外特別講師のラリー・スミスD.C.が対談
日米の医療とカイロプラクティックをテーマに意見交換

全健会・JCA顧問であり、さくら総合病院病院長を務める小林豊氏と、JCA海外特別講師でテキサスカイロプラクティック大学講師の、ラリー・スミスD.C.による対談が行われました。本対談では「日米の医療とカイロプラクティック」をテーマに、予防医療や病院とカイロプラクティックの関わり、医療制度の違い、そしてカイロプラクティックの未来について幅広く意見が交わされました。
対談内容
〈病院でのカイロプラクティック〉
小林:「アメリカでは、総合病院の中にカイロプラクティック科があると聞きます。集中治療室で施術が行われることはあるのでしょうか?」
ラリー:「集中治療室でカイロプラクティックを行うことはありません。ただ、医師や看護師の多くが個人的にカイロプラクティックを受けていて、特に整形外科医には好んで利用する人が多いですね。」
小林:「整形外科医も受けているのですか?」
ラリー:「はい。表向きには懐疑的な人もいますが、実際にはカイロプラクティックを好む整形外科医は少なくありません。」
小林:「信じていないと言いつつ、実際には受けているのですね。病院はもっとカイロプラクティックを取り入れるべきだと思います。その方が患者にとっても病院経営にとっても効率的であり、医療費削減にもつながるはずです。」
ラリー:「たしかに、カイロプラクティックを受けることで、脊柱に関わる疾患では病院受診率が約50%も減少します。さらに、手術の頻度や処方薬の使用も減り、結果として患者さんが病院にかける費用も大きく抑えられるのです。」

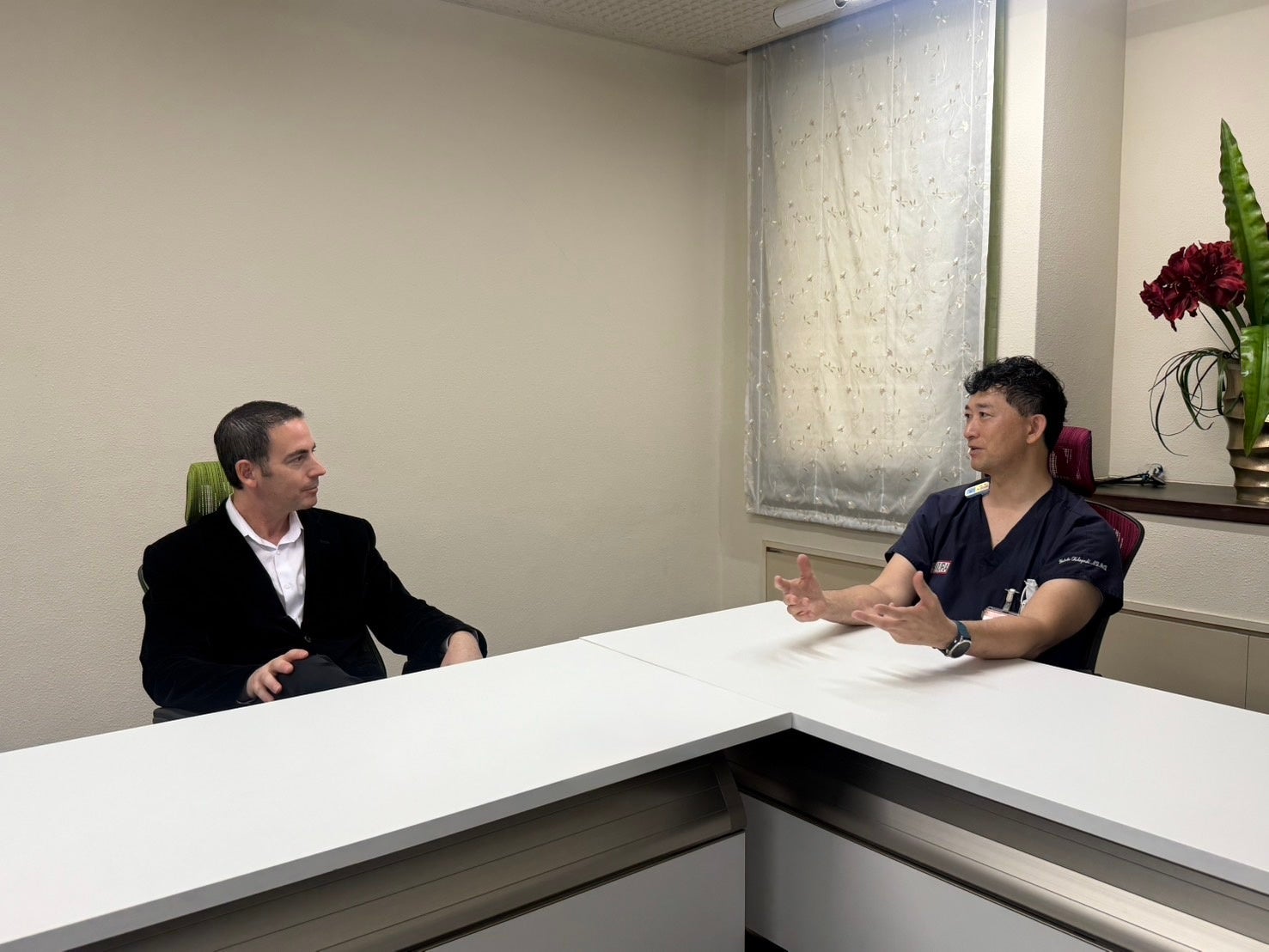
〈予防医療とカイロプラクティックと医療の違い〉
小林:「日本では予防医療の一環として健康診断が広く行われています。癌の早期発見を目的に、胸部X線、心電図、マンモグラフィーなどが一般的で、非常に人気があります。アメリカではどのような取り組みがあるのでしょうか?」
ラリー:「アメリカでは、高リスクの人に限って大腸内視鏡検査を行ったり、保険を利用して予防目的のCT検査を受けるケースがあります。」
小林:「日本とアメリカでは医療制度が大きく異なります。日本は国民皆保険ですが、アメリカはそうではありません。日本の社会保障制度はすでに十分に機能しているとは言えず、医師の収入も10年以上ほぼ横ばいです。アメリカの病院はビジネスとしてどのように成り立っているのですか?」
ラリー:「アメリカでは、病院の多くはビジネスとして運営されており、医師以外の経営者が管理することも少なくありません。さらに保険会社が患者管理に強い影響力を持っています。医療費も日本と大きく異なり、例えば“タイレノール”は日本では約100円ですが、アメリカでは約2,000円します。ただし共通点もあり、医師と理学療法士(PT)の役割が明確に分けられている点や、ケースマネジャーが入院や通院のケアを担当する点は日本と似ています。」
〈日本のカイロプラクティックの未来〉
小林:「カイロプラクティックは、今後どのように発展していくとお考えですか?」
ラリー:「アメリカでは国家資格として認められていますが、日本ではまだ正式に認可されておらず、一般の認知度も高くはありません。課題は“どうやって知ってもらうか”です。そのためには、メディア発信の強化や一般の方への啓蒙活動、キャッチフレーズやSNSを活用した情報発信が重要です。また、効果が実感しやすい商品やサービスをつくることも必要だと思います。」
小林:「確かに、最終的には会員一人ひとりがどのように成長していくかにかかっていると思います。」
ラリー:「その通りですね。制度や資格の整備に加えて、個々のスキルアップとレベルアップが非常に大切だと感じています。」

今後の展望
今回の対談を通じ、小林豊病院長が全健会・JCA顧問に就任したことにより、日本におけるカイロプラクティックの社会的地位向上に向けた動きが具体化しつつあることが示されました。JCAでは今後も、医療とカイロプラクティックの橋渡し役として国際的な視点を取り入れながら活動を展開してまいります。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
