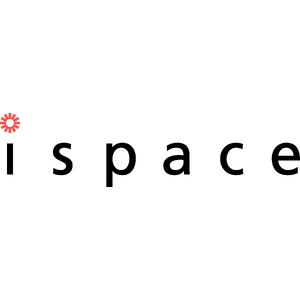【イベントレポート】ispace女性宇宙エンジニアによる、女子中高生向け「Girls Meet STEM」開催!月面探査の最前線、管制室で月ミッションのオペレーター体験
未来を担うリケジョの可能性は宇宙へ!

株式会社ispace(東京都中央区、代表取締役:袴田武史、以下ispace)(証券コード9348)は2025年9月20日(土)に東京・日本橋にあるX NIHONBASHIにて、初参画となる公益財団法人山田進太郎 D&I 財団が主催する「Girls Meet STEM」において、「月面探査の最前線!月ミッションの 現場を見に行こう!~リケジョがはまる宇宙の魅力~」ツアーを開催いたしました。本プログラムは、女子中高生が STEM(科学・技術・工学・数学)領域の企業や大学の提供するツアーに参加し、現場で活躍する女性たちとの交流を通じて、自身がやりたいことを見つけ、進路選択の幅を広げることを目的としています。将来の、女性理系人材育成の機会創出につながる取り組みに賛同したispaceは、月面資源開発に取り組む宇宙スタートアップならではの特別なワークショップ体験を用意しました。
イベントには、120名以上の応募の中から抽選で選ばれた、都内在住の女子中高生30名とその保護者が参加しました。ispaceからは、ミッション1およびミッション 2 の二度の月ミッションで実際に管制室からランダーを運用したフライト・ディレクターや、ランダー開発に携わったアビオニクス担当、推進系担当、熱工学担当のエンジニアや、そしてルナ・サイエンティストなど、まさにSTEM領域で活躍する多国籍な女性エキスパートを中心に、計8名が参加しました。
初めは、緊張な面持ちで不安げな表情をしていた参加者の皆さんも、ワークショップを通じて、グループの他の参加者と一緒に課題を考えたり、フレンドリーなエンジニアと一生懸命英語で会話をしていくうちに、徐々に自然な笑顔を見せ始め、楽しい時間を過ごすことが出来ました。
■ イベントハイライト
初めてispaceという会社を知った参加者も多く、ビジョンや会社概要の説明から始まりました。そして、事前に募集した質問に答えていく質疑応答の時間には、代表女性エンジニア4名が自身の経験やストーリーを交えて丁寧に回答していきました。参加者は時にうなずきながら、それぞれの話に聞き入っていました。
(例)
Q:宇宙関連の仕事に就きたいと思った理由や決め手を教えてください。
A:学生の頃、ヒューストンにあるスペースセンターを訪れたとき、NASAで働くたくさんの人たちと交流する機会がありました。目の前で実際に宇宙での仕事をする人たちを見て、この仕事に就きたいと強烈な憧れを抱きました。
A:エンジニアを目指していましたが、システムや開発など多くの種類があり決めきれずにいました。そんな時、ある大学の授業中、教授が1枚の写真を見せてくれました。それは、宇宙飛行士が「ハッブル望遠鏡」を整備している写真でした。教授は、これは若かりし頃の自分だと言いました。それが私の宇宙航空工学との出会いであり、今日ここに居るきっかけになりました。

また、参加者は5名一組のグループに分けられ、6つのグループで本イベントのために考案された、ispaceでしか体験できない3つのワークショップ/アクティビティに挑戦しました。
① 月面の着陸地点を探してみよう!
このアクティビティでは、月面探査を実施するために最適な着陸地点を、月面の地図に記載されている情報を基に探し出します。参加者は、Mare Tranquillitatis(静寂の海)というエリアの傾斜角や高度、地形などが示された地図を見比べながら、傾斜角10度未満、2000メートル以下、マイナス2900メートル以内で、且つ、科学的に興味深い特徴(洞窟や尾根、溶岩流のような岩)がある場所を探し出します。初めて目にする月面の地図をじっと見つめながら、「こっちが良いかな?」「あ、でも傾斜があり過ぎると着陸出来ないか…」などと会話をしながら、全員が適切な場所を見つけ、選定理由と併せて発表しました。ispaceのルナ・サイエンティストからは「全員合格です!」と拍手が送られました。

② 月着陸船(ランダー)を設計し、組み立ててみよう!
このアクティビティでは、ランダーの技術開発から構造、システム設計、製造、そして統合して試験を行うまでのプロセスを理解し、さらに様々なシステム運用を、実際に設計に携わった担当者から学びます。その後、3Dプリンターで作成した、ランダーの構成部品をマニュアルに従い組み立てていく体験をしました。各システムが、ランダーのどこに取り付けられていて、どんな役割を果たすのか、ispaceが実際に使用したランダーをイメージしながらグループで協力しながらランダーを完成させました。

③ 管制室でランダーの運用シミュレーションを体験してみよう!
このアクティビティは、参加者が特別に、ミッション1およびミッション2の運用を行ったミッションコントロールセンター(管制室)でシステムオペレータとなり、実際の運用シミュレーションを体験しました。
参加者は、11の管制室での役割*¹の中から興味のあるシステムを1つ選び、宇宙を航行するランダーの運用を担当します。各システムの“状態”がPC画面に映し出され、オペレータとなった参加者は、配布されたマニュアルに記載されている“正しいシステムの状態”と“実際の状態”を見比べ、システムに起きている異常を見つけ出します。その異常により、ミッションにどんな影響が起こりえるのか、そしてどのように異常を解決すべきなのかを、マニュアルの中から探し出し、運用チームのリーダーである「フライト・ディレクター」へ報告します。フライト・ディレクターの担当者は、異常の内容を精査し、運用全体を鑑みた解決の優先順位をつけます。オペレータから提示された解決方法を実施するためには、管制室からランダーに指令(コマンド)を送信する必要があり、その役割を担うことが出来るのは、「スペースクラフト・コントローラー」となります。担当する参加者は、数多くのコマンドの中から、最適を選び、実際にPCでコマンドを送信して、異常が解決し、正常となることを確認します。
積極的にエンジニアに質問をしたり、同じ担当者同士真剣に話し合う姿、正常を確認出来たときに喜び合う姿など、まるで実際のミッション運用を見ているかのような雰囲気が多く見られました。

■ 参加者の声
(学生)
・ 宇宙に興味があり参加した。いつか月に行ってみたい。
・ エンジニアの人たちはみんな親切で優しかった。こんな会社で働いてみたいと思った。
・ 英語で会話するのが難しかったのでもう少し勉強頑張ろうと思った。
・ 理系に進むかは決めてないが、宇宙は好き。月にも興味が沸いた。
(保護者)
・ とても貴重な体験をさせてもらえた。見学している親も楽しめた。
・ 子どもが英語でコミュニケーションする姿は誇らしかった。
・ 期待以上のイベント内容だった。
今回、初参画となった「Girls Meet STEM」では、社内で一から考案した様々なアクティビティを通じて、学生の皆さんととても貴重な時間を過ごすことが出来ました。参加した女性宇宙エンジニアたちもかつて、同じように進路について考え、迷いながら学生時代を過ごし、今ispaceで共に月を目指しています。宇宙と同じく、可能性は無限大に広がる学生の皆さんが、今後未来を考えるとき、ispaceでの体験が選択の幅を広げるきっかけとなれれば幸いです。そして、今よりもっと月が身近な存在になっているその時、ispaceが目指す地球と月がひとつのエコシステムとなる持続性のある世界にまた一歩近づけることを願っています。


■ 株式会社ispace ( https://ispace-inc.com/jpn/ )について
「Expand our planet. Expand our future. ~人類の生活圏を宇宙に広げ、持続性のある世界へ~」をビジョンに掲げ、月面資源開発に取り組んでいる宇宙スタートアップ企業。日本、ルクセンブルク、アメリカの3拠点で活動し、現在約300名のスタッフが在籍。2010年に設立し、Google Lunar XPRIZEレースの最終選考に残った5チームのうちの1チームである「HAKUTO」を運営した。月への高頻度かつ低コストの輸送サービスを提供することを目的とした小型のランダー(月着陸船)と、月探査用のローバー(月面探査車)を開発。民間企業が月でビジネスを行うためのゲートウェイとなることを目指し、月市場への参入をサポートするための月データビジネスコンセプトの立ち上げも行う。2022年12月11日には SpaceXのFalcon 9を使用し、同社初となるミッション1のランダーの打ち上げを完了。続くミッション2も2025年1月15日に打上げを完了した。これらはR&D(研究開発)の位置づけで、ランダーの設計および技術の検証と、月面輸送サービスと月面データサービスの提供という事業モデルの検証および強化を目的としたミッションであり、結果、ispaceは月周回までの確かな輸送能力や、ランダーの姿勢制御、誘導制御機能を実証することが出来た。2027年には[i]、米国法人が主導するミッション3(正式名称:Team Draper Commercial Mission 1)の打ち上げを予定しており、ミッション1、2で得られたデータやノウハウをフィードバックした、より精度の高い月面輸送サービスの提供によって、NASAが行う「アルテミス計画」にも貢献する計画。さらに、同年、経産省SBIR補助金を活用し、現在日本で開発中のシリーズ3ランダー(仮称)を用いたミッション4(旧ミッション6)の打ち上げを予定している。
i 2025年9月時点の想定
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像