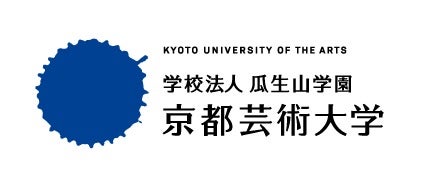令和7年度大学における芸術家等育成事業「受け継ぐ、伝える、伝統文化を地域・未来へ生かす実践型アートマネジメント・人材育成プログラム -藍の學校-」
~伝統文化を未来へつなぐ、実践型アートマネジメント育成事業~

京都芸術大学(京都市/学長 佐藤卓)は、文化庁「令和7年度大学における芸術家等育成事業」として、実践型アートマネジメント・人材育成プログラム「藍の學校」を実施します。
「藍の學校」とは?
これからの作家、アートマネジメントを行う人材には『環境に配慮した持続可能な物作りの思考』が資質として不可欠です。工芸は長い年月をかけてその地域に最適化された歴史を持ち、環境に対する配慮や多様な生物との共存への試みの蓄積があります。それらを文化、技術、科学など様々な視点から改めて捉え直すことで『環境に配慮した持続可能な物作りの思考』を抽出できると考えました。世界各地で文化を形成している「藍」を通して工芸の文化を再考し、日本の工芸から世界の工芸へと視点を移しながら現代社会に求められている新しい思考を見出します。本事業は4つのプログラムで構成。知識を身につけ実践を通して技術を学びそれを生かして作品を制作するスタイルです。スキルアップの効果と共に考えをカタチにする構築力と行動力が身につくことを目指します。
座学や実践を通し、工芸における知識・技術の向上を目指す為の4つのプログラム

2025年度のテーマは「産地と作家」。阿波藍の産地・徳島県を舞台に、フィールドワークも交えながら、座学と実践を通して工芸への理解を深めます。
藍の學校では、次の4つの柱からなるプログラムを通じて、知識と技術を育み、未来へとつなぐ工芸のあり方を探ります。
■知識
工芸に携わる作家やデザイナーを招いたレクチャー・講演会を通じて、視野を広げます。
■実践
ものづくりのプロセスを体験し、技術の習得だけでなく、次世代へ継承する視点を学びます。
■ 材料
素材は“つくる”ところから。種をまき、育て、原材料になるまでを自らの手で。
自然と向き合うことで、物づくりの思考を深めます。
■ 成果展
学びの集大成として、プロダクト・映像・写真・材料・道具などを展示。
ギャラリーツアーやワークショップも開催し、来場者とともに「つくること」を考える場をひらきます。
*プログラムの詳細は藍の學校HPよりご確認ください。
https://ai-no-gakko.kyoto-art.ac.jp/program-2025
育成対象
伝統工芸作家・芸術家・芸術・美術系大学生・芸術系メディア(書籍・webメディアなど)編集者・教育関係者・大学教員をはじめとした研究者・自治体・企業の芸術企画担当者・文化施設担当者・美術館・博物館の学芸員など
実施期間
令和7年4月~令和8年3月
※詳細は藍の學校HPをご覧ください。
https://ai-no-gakko.kyoto-art.ac.jp/program-2025
申し込み
申込締切:6/1(日)
藍の學校HPより受付をしています。
https://ai-no-gakko.kyoto-art.ac.jp/
京都芸術大学 https://www.kyoto-art.ac.jp/
京都芸術大学は、10学科24コースからなる国内最大規模の総合芸術大学です。芸術を通して社会で必要な力を育成しています。芸術を学んだ学生が社会を変える「藝術立国」を教育目標に掲げ、通学課程では特に “社会と芸術”の関わりを重視した芸術教育を推進。企業や自治体などが抱える課題を、学生たちがアート・デザインの力で解決する「社会実装プロジェクト」が年間100件以上あります。学科を超えたグループワークや実際の仕事を通して、社会性を備えた表現者を育成しています。
所在地:〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116
学科編成:10学科24コース(美術工芸学科、キャラクターデザイン学科、情報デザイン学科、プロダクトデザイン学科、空間演出デザイン学科、環境デザイン学科、映画学科、舞台芸術学科、文芸表現学科、こども芸術学科)
在籍者数:4,114名(芸術学部 正科生、2024年5月現在)
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像