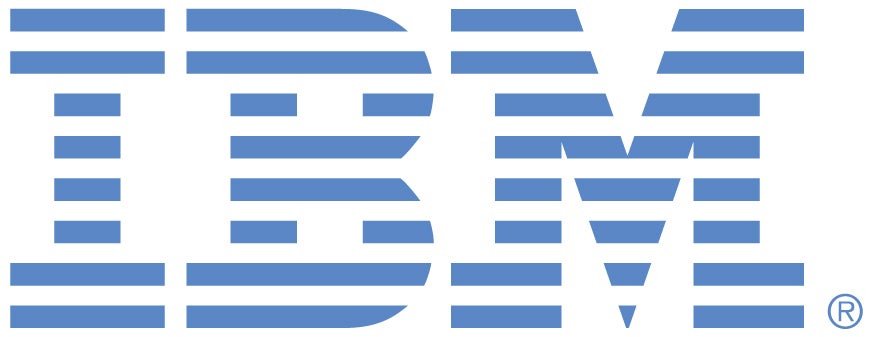CMOスタディ2025「CMOが導く、AI時代の5つの成長策」日本版を公開
-
CMOの54%が、「AI戦略を具体的成果に結びつけるための運用上の複雑さを過小評価していた」と認めている
-
AIによる意思決定の自動化に関し、明確なガイドラインやガードレール(安全対策)を設けている組織はわずか22%
-
64%のCMOが利益率を、58%のCMOが収益成長を牽引する責任を担っている

日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBM)は、本日、IBM Institute for Business Value(IBV)が実施した最新の調査であるCMOスタディ2025「CMOが導く、AI時代の5つの成長策」の日本版を公開しました。
日本を含む世界の最高マーケティング責任者(CMO)および最高営業責任者(CSO)1,800名(以下、一律CMOとして定義)を対象とした本調査によると、CMOはAIの戦略的重要性を広く認識している一方、自身に課せられる大きな役割の変化に適応する中で、主に断片化されたシステムに起因する「構想と実行のギャップ」に直面していることが明らかになりました。
具体的には、世界のCMOの81%が、AIは既存のオペレーションを抜本的に再構成し、戦略の実行力を飛躍的に高めるゲーム・チェンジャーだと認めている一方で、同じく8割強(世界84%、日本88%)のCMOはオペレーションがあまりに硬直、分断しているために、AIテクノロジーを活用しきれずにいると述べています。CMOの54%(世界、日本とも同割合)が、「AI戦略を具体的成果に結びつけるための運用上の複雑さを過小評価していた」と認めており、自社の組織が、「意思決定と業務効率を向上させるために、エージェント型AIをプロセスに組み込む準備ができている」と答えた割合は、わずか2割でした(世界17%、日本19%)。
本調査によると、AIエージェントがもたらす文化とオペレーションの変化に従業員が十分に準備できていると考えるCMOはわずか4分の1程度(世界23%、日本30%)で、CMOの6割以上(世界67%、日本66%)が、生成AIのような新興テクノロジーをうまく受け入れられるように、企業文化のさまざまな面を変える責任を自身が負っていると考えています。さらに、6割強のCMO(世界64%、日本63%)が利益率を高める責任、6割弱のCMO(世界58%、日本51%)が収益成長を牽引する責任を担っていると認識しており、業績向上に向け、テクノロジーの統合と部門横断的な連携を強化する必要性を強調しています。実際に、社内のオペレーションにおいて、部門の枠を越えた連携を十分に実現できていないと回答したCMOは、2024年に12%の収益成長を報告した一方、企業全体の運用効率を最適化できている先進的なCMOの企業は13%の成長を達成しています。このわずか1ポイントの差は、平均年商140億ドル規模の企業にとっては、1億4,000万ドルの潜在的な利益向上に相当します。
IBMのマーケティング&コミュニケーションズ担当シニア・バイス・プレジデントであるジョナサン・アダシェク(Jonathan Adashek)は、次のように述べています。「次の10年で優位に立つ企業は、AIを組織の中核に据え、その上にオペレーティング・モデルとチームを構築し、深く統合していく企業です。多くのCMOに、今のマーケティング・モデルが十分ではないことを認める覚悟が求められます。それがどれほど快適で使い慣れたものであり、変え難いものであっても、もはや必要なものを提供していないばかりか、将来を積極的に妨害しているとすら言えるからです」
その他の主な調査結果は以下のとおりです。
CMOはAI戦略を採用する一方、成果に結びつける準備はまだ整っていない
-
「AIリテラシーを備えた人材」は望ましいだけでなく、ミッション・クリティカルな存在だと理解しており、実際、CMOの約6割(世界65%、日本60%)が優先度の高い目標を達成するための欠かせない要素だと回答。しかし、今後2年間に目標を達成するための必要な人材が揃っていると考えるCMOはわずか2割(世界21%、日本22%)
-
わずか2割(世界22%、日本21%)の組織しか、AIによる意思決定の自動化に関し、明確なガイドラインやガードレール(安全対策)を確立していない。つまり、およそ10社中8社が、AIを活用した新たな働き方に対応するための指針を社員に示しきれていないということになる
-
CMOの6割以上(世界62%、日本68%)が、絶え間ない変化のスピードによって、オペレーションに課題を抱えていると認めている
-
自社のテクノロジー・プラットフォームが部門間の一貫した連携を支えるように整備されている、と回答したCMOは約4分の1(世界24%、日本26%)にとどまる。現時点で、需要計画やオペレーションを支援する統合テクノロジーを実際に導入していると回答したCMOは、半数以下(世界44%、日本46%)であった
-
マーケティングの状況が変化する中で、約7割(世界69%、日本61%)のCMOが「新たなプライバシー規制へ対応するために、データ戦略を見直す必要がある」と認めている
業務のサイロ化と断片化されたテクノロジーがパフォーマンスを阻害している可能性がある
-
エンドツーエンドの顧客体験を提供するための、部門横断の効果的な体制が構築できていると報告した組織は3割未満(世界28%、日本23%)にとどまり、これは財務パフォーマンスに影響を与える可能性がある
-
多くのCMOが、マーケティング、営業、オペレーションを完全に連携させることで、収益が最大20%向上する可能性があるとみている
-
データ関連のマーケティング・インフラストラクチャーの主な課題として、世界のCMOは、複数のシステムをまたぐワークフローの同期と自動化、データの断片化、管理すべきツールやプラットフォームが多すぎることを挙げている。日本のCMOは、特定のタスクやキャンペーンにどのツールを使用すべきかが不明確であること、データやレポートから実用的な洞察を引き出すのが難しいこと、データの断片化、を課題の上位として挙げており、世界のCMOと異なる課題認識を持っている
-
6割以上(世界68%、日本61%)が、マーケティングの技術インフラストラクチャーを簡素化することが、業務の効率と有効性の向上につながることに同意している
-
今後3年間における最大の課題について、世界のCMOが挙げた課題の1位はサイバーセキュリティーとデータ・プライバシーであり、続いてテクノロジーの最新化、予測精度の向上、人材の採用と定着が挙げられた。一方、日本のCMOは、課題の1位として同じくサイバーセキュリティーとデータ・プライバシーを挙げているが、続いて挙げたのはマーケティングとセールスの効果、サプライチェーンのパフォーマンスなどビジネス成果に直結する課題であり、世界のCMOとは異なる
レポートの全文は以下よりご覧いただけます:
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/jp-ja/c-suite-study/cmo
調査方法
IBM Institute for Business Valueは、オックスフォード・エコノミクス(Oxford Economics)社の協力を得て、2025年の第1四半期に24業種・33地域の1,800人の最高マーケティング責任者(CMO)および最高営業責任者(CSO)を対象として調査を実施しました(本レポートでは、一律CMOとして定義)。調査では、属性、組織のパフォーマンス、戦略的な優先事項、イノベーションおよびオペレーション上の課題といった複数の重要領域について調査しました。また、変化の管理、AIやクラウドのようなテクノロジーの導入、意思決定を企業がどのように行っているかを探りました。加えて、リーダー層のアプローチや人材戦略、変革への文化面での準備態勢のほか、連携の取り組みや規制への懸念についても評価しました。
IBM Institute for Business Valueについて
IBM Institute for Business Value(IBV)は、IBM のソート・リーダーシップ・シンクタンクとして、ビジネス・リーダーの意思決定を支援するため、世界の調査とパフォーマンス・データ、業界の専門家や学者の専門知識に裏付けられた戦略的洞察を提供しています。詳しくは、以下をご覧ください。
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/jp-ja
当報道資料は、2025年6月17日(現地時間)にIBM Corporationが発表したプレスリリースの抄訳の一部をもとにしています。原文はこちらを参照ください。
すべての画像