「旅人たちと巡る、世界の“認知症” 」第3弾【アジア編】を開催しました!
今回のアジア編では台湾とシンガポールから、それぞれの現場で活躍する実践者の方々をゲストとしてお迎えしました。本イベントへの申し込みは86名を超え、多くの方にご視聴いただきました。
7月1日(火)に、世界8カ国でのクラウドファンディングのスタートを記念したオンライントークイベント「旅人たちと巡る、世界の“認知症” 」の第3回目が開催されました。
今回は、アジア編ということで台湾とシンガポールから、それぞれの現場で活躍する実践者の方々をお招きし、彼らが実施しているユニークな取り組みと、それにかける熱い思いを語っていただきました。地域ごとに異なる背景やアプローチを学ぶことができ、認知症に対する理解が深まるイベントになりました。
※前回のイギリス編はこちら。初回の欧米編のレポートはこちらからご覧いただけます。
※ issue+designは、認知症とともに幸せに生きるヒントを届けるため『認知症世界の歩き方』の実写映画化にチャレンジしています。映画についての詳細はこちら。制作支援のため国内外8か国でクラウドファンディングを実施しています。

イベント概要
日時: 2025年7月1日(火)19:00~20:30
会場: オンライン(Zoom・Youtube)
<ゲスト>
李若綺(リー・ローチー)さん(台湾)
弘道老人福利基金会 執行長
啓蒙活動から長期介護まで幅広い視点で高齢者福祉に取り組み、誰もが地域で安心して老いる社会を目指す。社会の高齢者に対する偏見を活動を通じて変え、多くの民間・公的機関の委員を務めながら、高齢者に優しい社会の実現を政策面からも推進。2023年「台湾第16回MVPマネージャー100人」に選出され、600人のチームを率いて地域ニーズに応じたサービスを展開し、基金会のビジョンである「すべての高齢者が自立・尊厳・安心・充実した老後を享受できる社会の実現」に向かって邁進しています。
吉国泰代さん(シンガポール)
医師、公認心理師
2008年にシンガポールへ転居し、日系クリニックで総合診療を担当しています。シンガポール在住中に日本の母が認知症を発症し、現在は要介護5で、姉が介護をしています。介護ができない自分に何かできないだろうかと考え、家族の介護の準備や自分の老後を考えることに役立てばと、2018年に認知症キャラバンメイト・サポーター研修を、2025年8月にはアジア在住者向けに「認知症世界の歩き方」研修会を企画・実施しました。
<ホスト>
森(issue+design)
アーカイブ
イベントの様子はYouTubeにてアーカイブ公開中です。
(https://www.youtube.com/live/9mBakO003uE)
当日の様子
<ゲストトーク>
シンガポール・吉国 泰代さん
はじめに、吉国さんより医師・公認心理師の立場から、シンガポールの認知症予防と支援の先進的な取り組みを紹介いただきました。
人口の4割を外国人が占める多民族・多言語国家であるシンガポールでは、2030年までに国民の4人に1人が65歳以上になると予想され、高齢化が急速に進んでいます。そのため、国を挙げて「Age Well SG」という包括的な高齢者支援プログラムが推進されているとのことでした。
認知症予防については、教育水準や生活習慣、運動、社会参加が大きく影響することが研究で明らかになっており、そのような科学的根拠に基づき、高齢者の認知症を予防して生活の質を上げるための「認知症予防プログラムIMPRESS-MIND2S」を政府が今年の夏はじめたところだと言います。これはフィンランドで行われた調査で、食事・運動・高血圧などの管理によって認知症が減ったという報告を参考にしているそうです。
他にも健康診断の結果管理や歩数計測、食事記録を行い、運動・健康増進にポイント報酬が付く仕組みも整備されています。さらに、認知症の家族支援者、介護してる人たちと、認知症当事者自身のサポートを行う支援アプリ「CARA」は、徘徊や行方不明時にすぐポスターを作成して捜索に動き出せるような仕組みも構築されているとのことです。
「多文化・多言語環境の中でも先進的な制度が整い、テクノロジーの力を最大限活用するシンガポールの取り組みは、他国の参考になるはず」と話し、データに基づく予防や支援体制の重要性をお話いただきました。

台湾・李 若綺(リー・ローチー)さん
台湾最大級の高齢者福祉NPO「弘道老人福利基金会」の李さんからは、超高齢社会に直面する台湾の現状と挑戦についてお話しいただきました。
弘道は30年にわたり、全国で多様な高齢者支援を展開。スローガンに「全ての高齢者が自主性を持ち、安心して生き生きとした生活を過ごせる社会」を掲げ、安心だけでなく「生きがい」を大切にし、誰もが尊厳を持って暮らせることを目指していると語りました。
台湾も、この7年間で「高齢社会」から「超高齢社会」に入りました。 実際に政府も非常に危機感を持っていると言います。認知症への関心が高まり、全国的にデイケアセンターなどの拠点が急増する一方、「これからは数だけでなく、サービスの質が問われる」と強調しました。
「注文をまちがえるレストラン」の開催や、高齢者体験プログラムを提供する、台湾で最も専門的な高齢社会教育機関と言える「老教室」など、様々な取り組みを展開しています。
「支援の現場だけでなく、社会全体が高齢者や認知症の人に優しい環境をつくることが必要」とし、映像や体験を通じた共感づくりが大きな力を持っていますと述べられ、これからも台湾の文化に根ざした啓発や支援を広げていきたいと話されました。

クロストーク
後半のクロストークでは、シンガポールと台湾それぞれの認知症支援の現状をふまえ、日本との共通点や課題について意見が交わされました。

クロストークの冒頭では、「認知症世界の歩き方」について、それぞれの立場からの感想を伺いました。 吉国さんは「認知症は誰もがなる可能性があり、どう生きるかを考えるきっかけが必要。診断や支援が整う日本の先進性は他国の参考になる。当事者の視点から『なぜ』を知ることが早期発見や共感に繋がる」と話しました。シンガポールでは健康支援のアプリなどテクノロジー活用が進む一方、こうした視点の啓発は少なく「日本から発信を続けてほしい」と述べました。
李さんは「他にも多くの書籍やAI体験を見てきたが、この本は『なぜそうなるのか』という問いが多く、行動の背景を考える視点が新鮮だった」と評価。「人を中心にしたケアを考える上で深い理解を促す本」と語りました。
その後の議論では、外国人労働者によるケアが進むシンガポールや台湾でも、当事者の視点を共有する意義が大きいという意見で一致。李さんは「台湾では数を増やす支援が進んだが、これからは質を問われる段階に入る。映像や体験で共感を育むことが必要」と述べました。
最後に、吉国さんは「日本が率先してこの取り組みを広げてほしい」と話し、李さんも「良い映画は悲しみではなく希望を残すもの。多くの人に届いてほしい」と締めくくりました。
クラウドファンディング開催中!
日本を皮切りに、世界8カ国(フランス、台湾、中国、韓国、イギリス、アメリカ、カナダ、シンガポール)でクラウドファンディングを展開中!
国内からは、以下の2つのサイトからご支援いただけます。
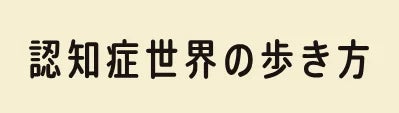
映画『認知症世界の歩き方』特設ウェブサイト
詳細・ご支援はこちら
主催者情報・問い合わせ先
issue+design(特定非営利活動法人イシュープラスデザイン)
issue+designは、「社会の課題に、市民の創造力を。」を合言葉に、まちづくり、防災、医療、福祉、教育など、さまざまな社会課題に対して、デザインの力で解決に挑む団体です。市民一人ひとりの創造力を引き出し、社会をよりよくする仕組みを共につくることを目指しています。
特定非営利活動法人イシュープラスデザイン事務局(担当:宮崎)
HP:https://issueplusdesign.jp/
Mail:info@issueplusdesign.jp
すべての画像
- 種類
- イベント
- ビジネスカテゴリ
- 福祉・介護・リハビリ
- ダウンロード

