子どもの栄養に関するユニセフ報告書 5~19歳の10 人に 1 人が「肥満」 利益優先の食環境、超加工食品が影響 【プレスリリース】
日本の子ども・若者の肥満率は横ばい

【2025年9月10日 ニューヨーク発】
ユニセフ(国連児童基金)は、本日発表した子どもの栄養に関する最新報告書で、栄養不良の形態として今年、肥満が低体重を上回ったことを明らかにしました。学齢期の子ども・若者の10人に1人、およそ1億8,800万人が肥満状態にあり、命を脅かす病気のリスクにさらされていると警鐘を鳴らしています。
* * *
190 以上の国々のデータに基づいた報告書「子どもの栄養報告書2025 ~利益優先の食環境が子どもたちに与える悪影響(原題:Feeding Profit: How Food Environments are Failing Children - Child Nutrition Report 2025)」によると、2000年以降、5歳から19歳までの低体重の割合が約13%から9.2%に低下した一方で、肥満の割合は3%から9.4%に増加しています。肥満率は、サハラ以南のアフリカと南アジアを除く世界のすべての地域で、低体重率を上回っています。
調査結果によると、世界で最も肥満率が高いのは太平洋島しょ国のいくつかの国で、ニウエでは5歳から19歳までの38%、クック諸島では37%、ナウルでは33%に達しています。これらすべての数値は2000年以降に倍増しており、伝統的な食生活から、安価で高カロリーな輸入食品中心の食生活への変化が主な要因となっています。
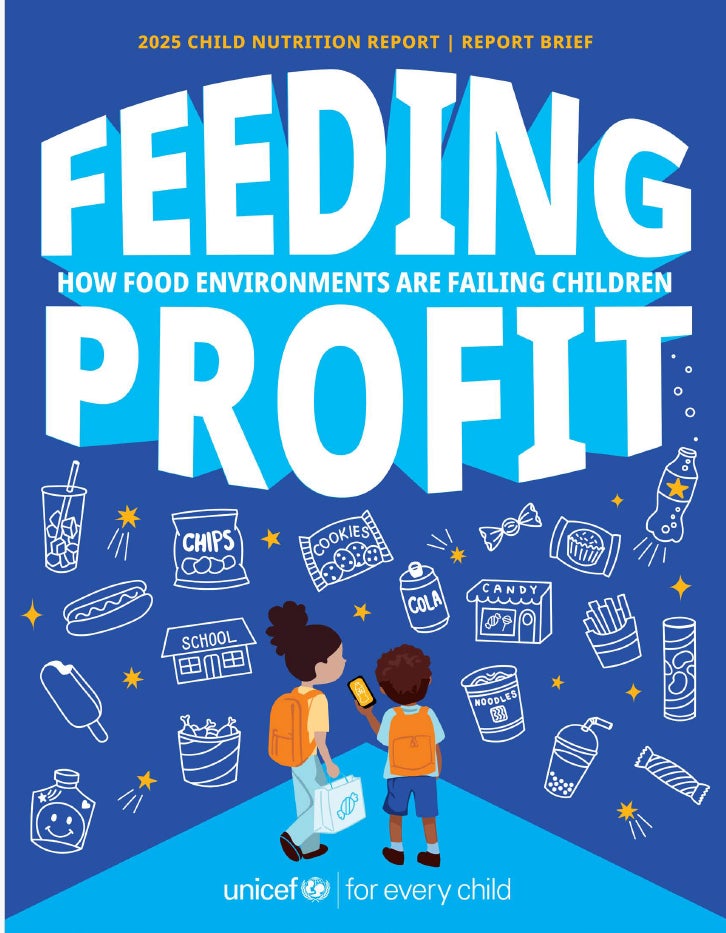
一方、多くの高所得国の肥満率は依然として高い水準にあります。例えば、チリでは5歳から19歳までの27%、アメリカ合衆国では21%、アラブ首長国連邦では21%が肥満状態にあります。
ユニセフ事務局長のキャサリン・ラッセルは次のように述べています。「栄養不良は、もはや低体重の子どもたちだけの問題ではありません。肥満は、子どもの健康と発達に影響を与える、ますます深刻な問題となっています。子どもの成長、認知発達およびメンタルヘルスにとって栄養が極めて重要な時期にもかかわらず、超加工食品が、果物や野菜、そしてタンパク質が豊富な食品に、急速に取って代わっているのです」

多くの低・中所得国で、5歳未満の子どもの消耗症や発育阻害(スタンティング)といった栄養不良が、依然として深刻な問題となっている一方で、学齢期の子どもや10代の若者たちの間では、過体重や肥満の割合が上昇しています。最新のデータによると、世界では5歳から19歳の子ども・若者の5人に1人、およそ3億9,100万人が過体重で、その多くは肥満と分類されています。
子どもが年齢、性別、身長に対して健康的とされる体重を大きく上回っている場合、過体重とみなされます。肥満はその中でも深刻な状態であり、インスリン抵抗性や高血圧のリスクを高めるほか、将来的に2 型糖尿病、心血管疾患、特定のがんなど命に関わる疾病を引き起こす可能性があります。

報告書は、砂糖や精製されたでんぷん、塩分、不健康な脂肪、添加物を多く含む超加工食品やファストフードが、不健康な食環境を通じて子どもたちの食生活を形成しており、それは子ども自身の選択によるものではないと警鐘を鳴らしています。これらの商品は、食品・飲料業界がデジタルマーケティングを通じて若年層に強力に働きかけているもので、店舗や学校で主流となっています。
例えば、ユニセフが開発したデジタルプラットフォーム「U-Report(ユー・レポート)」を通じて昨年、170 以上の国の 13~24 歳の若者 6万4,000 人を対象に行った世界規模の世論調査で、回答者の75% が、過去1週間に砂糖入り飲料やスナック菓子、ファストフードの広告を目にし、60% がその広告を見たことで、それらの食品を食べたくなったと答えました。紛争の影響を受けている国においてさえ、若者の68%が、同様の広告を見かけたと回答しました。
子どもの過体重や肥満を予防する取り組みが行われなければ、各国は長期的に深刻な健康面・経済面の影響を受ける可能性があり、例えばペルーでは、肥満に関連した健康問題による損失が2,100億米ドルを超えるとされています。肥満と過体重の世界全体の経済的損失は、2035年までに年間4兆米ドルを超えると予測されています。

報告書は、各国政府が講じた前向きな取り組みに焦点を当てています。例えば、10代の子ども・若者の肥満の割合が高く、砂糖入り飲料や超加工食品が子どもの1日の摂取カロリーの40%を占めるメキシコでは、政府が最近、公立学校における超加工食品および塩分、糖分、脂肪分の多い食品の販売と配布を禁止し、3,400万人以上の子どもの食環境の改善に良い影響をもたらしています。
食環境を変革し、子どもが栄養価の高い食事を確実に摂取できるように、ユニセフは政府、市民社会、パートナーに対し、以下の対応を緊急に求めています。
-
食品表示、食品の販促規制、食品への課税や補助金を含む、子どもの食環境を改善するための包括的かつ義務的な政策を実施する。
-
家族やコミュニティが、より健康的な食環境を求める力を持てるよう、社会的・行動的変容を促す取り組みを実施する。
-
学校における超加工食品やジャンクフードの提供・販売を禁止し、食品の販促活動や企業協賛も禁止する。
-
超加工食品業界が公共政策の策定に影響を及ぼすことがないよう、十分な保護措置を講じる。
-
脆弱な家庭における所得の貧困に対応し、栄養価の高い食事を経済的に入手しやすくするよう、社会的保護プログラムを強化する。
ラッセル事務局長は次のように述べています。「多くの国で、発育阻害(スタンティング)と肥満が併存するという栄養不良の二重負荷が見られます。この問題には、的を絞った介入が必要です。子どもの健やかな成長と発達のために、栄養価が高く手頃な価格の食品があらゆる子どもに提供できるようでなければなりません。親や養育者が、子どもに栄養価が高く健康的な食事を与えられるよう支援する政策が、緊急に求められています」
* * *
■ 日本のデータについて
日本の5~19歳の子どもの肥満の割合は、ほぼ横ばいで推移しており、2000年も2022年も同じく4%で、過体重の割合は、2000年の15%から2022年には16%へと上昇しました。一方、低体重の子どもの割合も2000年と2022年の両方で2%となっています。
* * *
■ 注記:
・「子どもの栄養報告書2025」の全文は、以下のURLからご覧いただけます。
https://www.unicef.org/reports/feeding-profit
・「子どもの栄養報告書2025」は、190を超える国々のデータに基づいており、世帯調査、モデル推計、将来予測および世論調査などを含んでいます。
・2000年から2024年までの5歳未満の子どもの過体重、発育阻害(スタンティング)、消耗症に関するデータは、ユニセフ、世界保健機関(WHO)、世界銀行による「子どもの栄養不良の共同推計」に基づいています。
・5歳から19歳の子ども・若者に関する過体重、肥満、低体重のデータは、人口ベースの調査、行政データ、または代表サンプルの身長と体重を測定した調査研究を用いて、モデル化されています。国別データは2000年から2022年までのものが利用可能であり、非感染性疾患危険因子共同研究グループ(NCD-RisC)によって統括・調整されています。
・5歳から19歳の子ども・若者における、肥満の割合が低体重を上回る状況を確認するため、ユニセフは2010年から2022年までの推移データに基づき、2022年以降の予測を行いました。
・過体重、肥満、低体重(痩せ)は、ボディマス指数(BMI)に基づいて分類されます。WHO の基準によると、5歳から19歳の子ども・若者について、以下のように定義されています。
過体重:BMI が中央値から 1 標準偏差を超えて上回っている状態
肥満:BMI が中央値から 2 標準偏差を超えて上回っている状態
低体重または痩せ:BMI が中央値から 2 標準偏差より下回る状態
・子どもの栄養不良には3つの側面があります。それは、低栄養(発育阻害と消耗症)、過体重・肥満、そして「隠れ飢餓」とも呼ばれる微量栄養素の欠乏です。
・超加工食品とは、精製された原材料と添加物を主成分とし、未加工または自然に近い形の食品をほとんどあるいは全く含まない、工業的に製造された食品および飲料を指します。超加工食品は、添加糖、精製されたでんぷん、塩、不健康な脂肪が高い割合で含まれていることが多く、利便性や嗜好性を高めるように商品開発されており、販促活動や商品パッケージ、ブランドイメージを通じて消費者に訴求するよう工夫されています。
* * *
■ ユニセフについて
ユニセフ(UNICEF:国際連合児童基金)は、すべての子どもの権利と健やかな成長を促進するために活動する国連機関です。現在約190の国と地域※で、多くのパートナーと協力し、その理念をさまざまな形で具体的な行動に移しています。特に、最も困難な立場にある子どもたちへの支援に重点を置きながら、世界中のあらゆる場所で、すべての子どもたちのために活動しています。ユニセフの活動資金は、すべて個人や企業・団体からの募金や各国政府からの任意拠出金で支えられています。(https://www.unicef.org )
※ユニセフ国内委員会(ユニセフ協会)が活動する32の国と地域を含みます
■ 日本ユニセフ協会について
公益財団法人 日本ユニセフ協会は、32の先進国・地域にあるユニセフ国内委員会の一つで、日本国内において民間で唯一ユニセフを代表する組織として、ユニセフ活動の広報、募金活動、アドボカシーを担っています。(https://www.unicef.or.jp )
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像