千葉大学環境ISO学生委員会と工学・情報学系講義棟の取り組み事例が「サステイナブルキャンパス賞2025」でダブル受賞
国立大学法人千葉大学は11月8日に開催されたサステイナブルキャンパス推進協議会(CAS-Net JAPAN)2025年次大会において、「第11回サステイナブルキャンパス賞」の学生活動部門の大賞と、建築・設備部門の奨励賞を受賞しました。
サステイナブルキャンパス賞について
一般社団法人サステイナブルキャンパス推進協議会が運営し、サステイナブルキャンパス構築に係る取り組み事例を表彰する制度で、持続可能な環境配慮型社会の構築に貢献することを目的に、2015年度より毎年実施されています。
詳細 http://casnet-japan.org/free/award
【表彰部門】
第1部門:キャンパスのサステイナビリティに配慮した建築・設備部門
第2部門:キャンパスのサステイナビリティに配慮した大学運営・地域連携部門
第3部門:キャンパスのサステイナビリティに配慮した学生活動部門
第4部門:キャンパスのサステイナビリティに配慮した民間事業者部門
受賞概要について
学生活動部門「サステイナブルキャンパス賞」(大賞)

受賞者:千葉大学環境ISO学生委員会
受賞事例:「楽しむだけで終わらないワークショップ ~学童クラブに対する新たな取り組み~」
審査講評:小学校での子どもたちへの環境教育は多くの大学で行っているものの、地域とのつながりが深い学童クラブでの環境教育は、大変貴重な事例となる。プログラムは、SDGsを題材とした海洋ゴミやフードロスを題材とする紙芝居講義、古着バッグやペットボトル工作などの体験型ワークと構成されており、子どもたちが楽しみながらリユースや資源循環の重要性を体験できる内容となっている。2024年度は14校約500名、2025年度は15校約310名が参加し、子どもの学びを通じて家庭や地域に広がっている。企画した学生たちのコミュニケーション力や教育力の向上にもつながり、持続可能な社会づくりに貢献できるWin -Winの好循環を示していて、サステイナブルキャンパス賞に相応しい取り組みである。
千葉大学環境ISO学生委員会は2015年度、2017年度、2021年度、2023年度に続き、5度目の受賞となりました。
建築・設備部門「奨励賞」

受賞者:国立大学法人 千葉大学/株式会社 佐藤総合計画/丘の上事務所株式会社/株式会社dpランドスケープ/株式会社テクノ工営
受賞事例:「千葉大学 工学・情報学系講義棟」
審査講評:1960年代に整備された並行配置の校舎群の間に、新講義棟を挿入して老朽化した校舎を再編する計画である。大学の講義室、ギャラリー、ホール、ラウンジ、通路を立体的・有機的につなぎ、各スペースや部屋・空間の連携を図って建物の魅力を創出している。環境配慮としては、建物屋根に降った雨水の流出経路をデザインするとともに、その雨どいを日射遮蔽ならびに外観デザインに活かしている点が評価できる。建物環境性能としてはZEB Readyを達成しており、国立大学系の施設ながら、完成度の高い建物として仕上げられている。
受賞事例:楽しむだけで終わらないワークショップ ~学童クラブに対する新たな取り組み~
■活動の経緯
千葉大学環境ISO学生委員会は、学生主体で環境活動を実践し、省エネや緑化、環境教育など多岐にわたる取り組みを行っている。本企画では、子どもたちが小さい頃から環境問題に親しみ、「身近な行動でも環境に貢献できる」ことを実感できる場を提供するため、学童クラブでワークショップを実施した。はじめは小学校の授業での実施を検討していたが、教育委員会の助言を受け、地域とのつながりが深い学童クラブでの展開に切り替えた。
■活動の内容
プログラムは、SDGsを題材にした紙芝居講義と古着バッグやペットボトル工作などの体験型ワークの二部構成。紙芝居では海洋ごみやフードロスを題材に、子どもたちが物語を通して環境問題を自分の生活に結びつけて考えるきっかけを作る。工作では、古着バッグやペットボトルキャップのマグネット、ペットボトルランタンなどを制作し、楽しみながらリユースや資源循環の重要性を体験する。
■活動の成果と今後
2024年度は14校・約500名、2025年度は15校・約310名が参加。子どもたちからは「楽しかった」「またやりたい」との声が多く寄せられ、保護者からも「家に帰って学んだことを楽しそうに話していた」との反応があり、学びが家庭や地域に広がっていることが明らかになった。学生にとっても、企画立案や運営、地域連携を経験することで社会人基礎力や教育力を養う貴重な機会となった。今後は、紙芝居や工作の内容をさらに改善し、学びの効果を一層高めるとともに、学童での活動を基盤とした新たな教育プログラムの開発を目指し、子どもたちと学生が共に成長できる活動として、持続可能な社会づくりに貢献する。

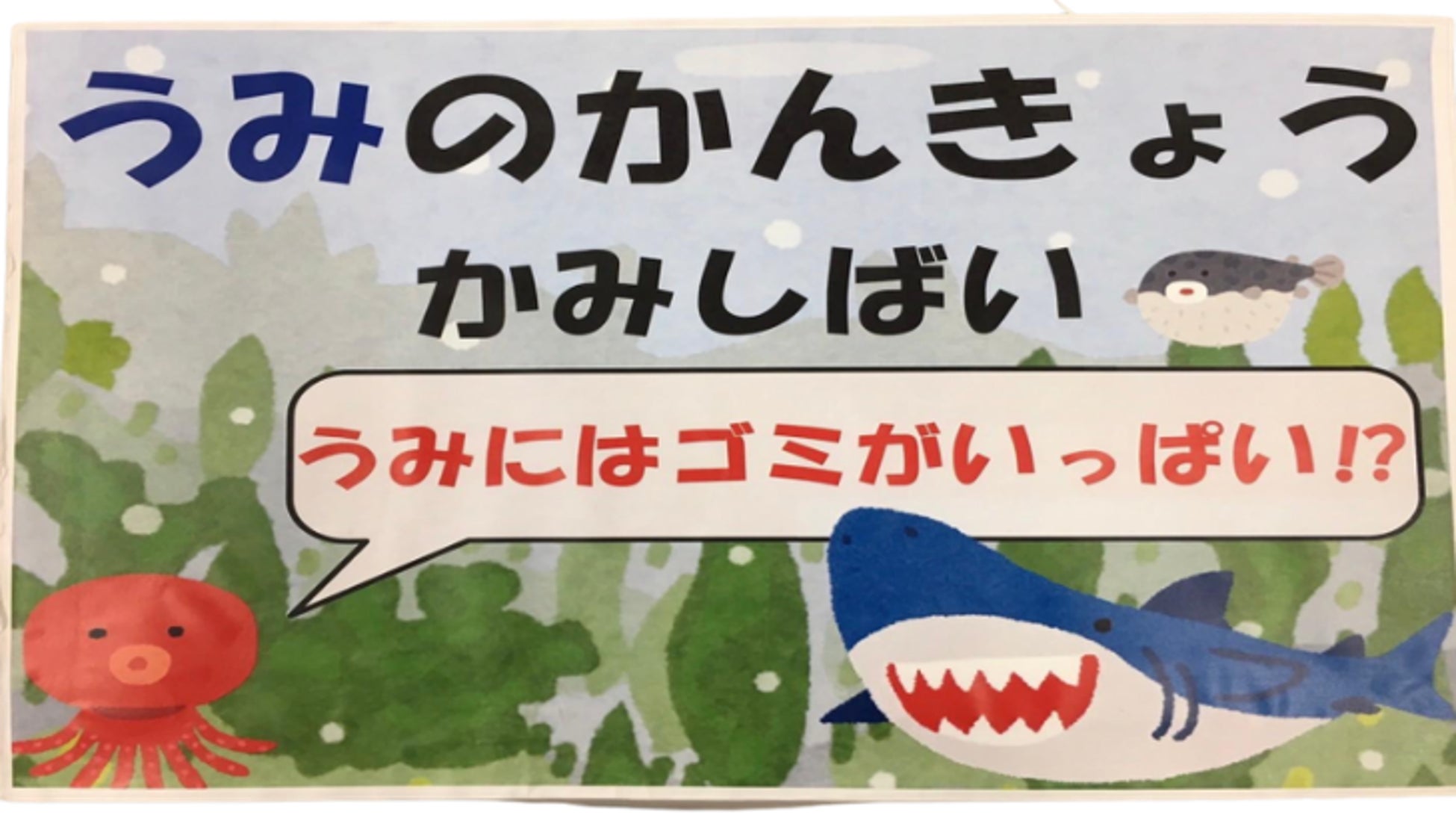

受賞事例:千葉大学 工学・情報学系講義棟
コンセプト:キャンパスコモンの連鎖による居場所と環境の形成
背景1:工学系エリア再開発とイノベーション・コモンズ(共創拠点)
1960年代に整備された平行配置の校舎群の再開発の第一弾として、既存の建物間に新講義棟を挿入し、老朽化した校舎の再編計画の端緒となる。西千葉キャンパスは「持続可能な社会と環境を科学するキャンパス」としてマスタープランに位置付けられ、また、文部科学省の掲げる「イノベーション・コモンズ」として多様な活動の拠点となることを目指した。
背景2:学科統合・ポストコロナにおけるキャンパスコモンの形成
工学部の10学科が統合されて総合工学科の元にフレキシブルなコース制となり、共通授業等における大空間が必要となった。また、情報データサイエンス学部も新たに設置された。コロナ期以降に、オンラインと対面の併用に伴う、授業間の学生の居場所や多様な学習形態が顕著となった。これらを受け止めるキャンパスコモンの形成を目指した。
■キャンパス動線を引込み、活動を表出させる:屋外空間を含む立体接続
既存校舎群の南面平行配置と渡り廊下による立体動線のモダニズムの構成を継承しつつ、既存棟から10mずつ離隔して挿入した。このエリアの唯一の新築校舎として、学生の多様な居場所を創出するとともに、環境的にも将来的なグリーンインフラに寄与する「キャンパスコモン」を形成する。各階の共用部(コモンズ)となるピロティやテラスを「厚みのある外皮」として、屋外階段と連動するように配置。弥生通り側に半外部空間の学びの場を表出させ、キャンパス空間が建築へシームレスに浸透し、居場所と動線、内外の活動が重なる「学びのアッセンブリー」を形成する。
■居場所にもなるフレキシブルな学びの場:壁柱と大梁による無柱空間
多様な講義形態に対応できるように、講義室は無柱のフレキシブルな空間とした。既存校舎と階高(3.6m)を合わせて接続を考慮し、PCaPC梁一体床板の架構により小断面でありながら16mの大スパンを実現する。水平力を耐力壁に負担させ、500角のコンパクトなRC柱とし、全体の躯体量を最小限にしている。イノベーションシアターは、人のふるまいや、スケールに寄り添うように段床空間とし、可変型の机によってモードを切り替え、日常の居場所や自習、ポスターセッション等の多様な利用も可能としている。
■ZEB Ready相当の省エネと居場所の形成:雨樋ルーバーとグリーンインフラ
西側の弥生通りへの活動の表出(開放)と、西日の日射の遮蔽(閉鎖)を両立させた。低層部は、学生の動きと呼応するように半外部空間を配し、上層部は既製雨樋を日射遮蔽ルーバーとして活用した(雨樋ルーバー)。奥行2mの庇を設け、居場所を創出しながら西日を97%遮蔽し、ZEB Ready相当の省エネ性能を有している。屋上に降った雨が西側の雨樋ルーバーと南面の屋外階段に流れ、雨道と居場所・動線が連動するファサードを形成。動線や居場所と雨や光、風の流れを統合したグリーンインフラ・アーキテクチャーを目指し、活動・環境の循環が連鎖する計画とした。


本事例は、2025年度グッドデザイン賞(公益財団法人日本デザイン振興会)も受賞しています。
詳細 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001052.000015177.html
表彰式の様子
表彰式は2025年11月8日(土)に北海道大学札幌キャンパスで開催された、「サステイナブルキャンパス推進協議会2025年次大会」(主催:一般社団法人サステイナブルキャンパス推進協議会)において行われました。表彰式の後に、受賞事例の紹介プレゼンが行われ、環境ISO学生委員会の発表が、特別賞を受賞しました。



年次大会の詳細 http://casnet-japan.org/info/6513189
表彰式の詳細 http://casnet-japan.org/info/6513210
本件に関するお問い合わせ
千葉大学企画部渉外企画課広報室
043-290-2018
koho-press@chiba-u.jp
すべての画像
