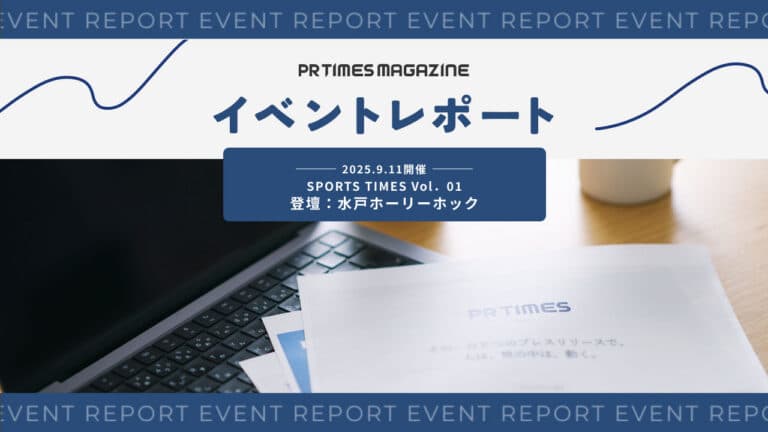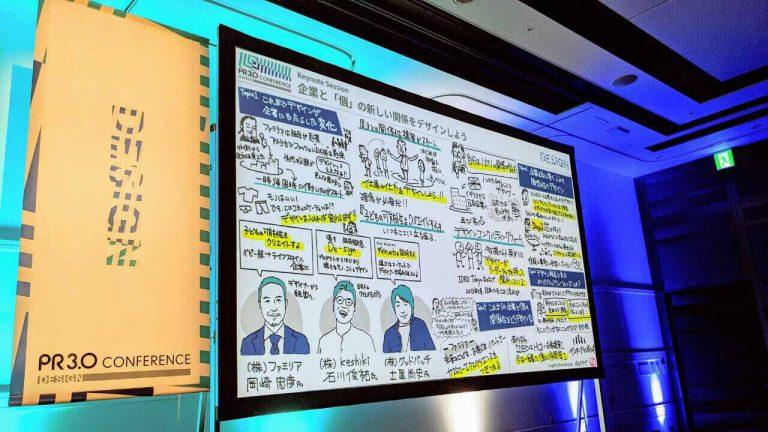プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を運営する株式会社PR TIMESは、2025年9月11日に「ファンとメディアを動かし、ブランドを築くJリーグクラブに学ぶ広報PR術」をテーマにスポーツチーム・団体向けセミナーを開催。
本レポートは、第一部「スポーツチームのブランド価値を高めるには?地域・メディアと共に価値を育む広報PR|水戸ホーリーホック」に続き、第二部のレポートをお届けします。J1リーグで国内最多20冠を誇り、スタジアムに平均2万人超を動員する「鹿島アントラーズ」が取り組む認知拡大・ファンベース拡大と売上目標100億円に向けた挑戦をご紹介。同セミナー第二部に登壇した株式会社鹿島アントラーズFCの松本隆吾さんのお話をもとにまとめています。

株式会社鹿島アントラーズFC マーケティングディビジョン コンシューマーグループ PRチームリーダー
大学卒業後、地方紙の茨城新聞社へ勤務し、2009-2010年に鹿島アントラーズ担当記者としてJリーグ3連覇などを取材。2014年の新聞社退職後は筑波大、在サウジアラビア日本国大使館勤務を経て、2017年2月に鹿島アントラーズへ入社した。アントラーズでは一貫として広報に携わり、広報PR戦略の策定、試合帯同などのチーム広報業務を担当。広報の責任者として、メディアとのリレーション構築や取材対応などクラブおよびチームに関する広報業務全般を行っている。
分業と専門性を強みとした広報PR体制
──松本さま、よろしくお願いいたします。鹿島アントラーズの広報PR体制について教えていただけますか。
鹿島アントラーズの広報PRは、「マーケティングディビジョン」に所属する「コミュニケーショングループ」の9名が担っています。その中でさらに「PR」と「コンテンツ」に携わるチームに分かれていて、PRには私を含めて3名、コンテンツは5名、統率するマネージャーが1名という体制です。
私は入社当初から現場の広報PRを主に担当していて、試合帯同や選手への取材調整、メディアとのリレーション構築、プレスリリースやニュースレターの企画・発信などを担っています。
──広報PRの中でも担当者を明確に分け、専門性を高めていらっしゃるんですね。
人数が多いほど専門性が高くなり、より有効な施策を打てるようになると思うんです。Jリーグのクラブの中には、リソース不足に悩んでいるところも多いのですが、その点、うちはデジタル周りのコンテンツに専念できるチームがいるのは強みかもしれません。私自身の目線でアドバイスや調整をすることはありますが、基本的にはそれぞれに「オーナー」がいて、自分の領域を責任もって担っているのが大きなポイントだと思います。
──多くのメンバーがいる中で、情報発信の軸となっているものは何ですか。
コミュニケーショングループとして掲げている目標としては、4つ。
- クラブブランド価値の向上
- ファンベースの拡充
- 観戦体験向上への貢献
- 収益貢献力の向上
この中でも特にPRチームは「クラブブランド価値の向上」にいかに貢献できるのか具体的なアクションへ落とし込んで、日々の活動を積み上げることを軸にしています。
選手とクラブの価値向上を後押しする施策と発信
──鹿島アントラーズさんは、数多くのプレスリリースを配信されていますが、どのような点にメリットがあるとお考えでしょうか。
関係の薄いメディアともタッチポイントをつくれることが、最大のメリットだと思っています。数多く、またさまざまな情報を配信することで、興味を持ってもらえる情報を試すことができるのもポイントです。クラブとしての取り組みや、選手が関わるイベント、プロデュースしたグッズなどの情報が特に引きがあると感じています。どこが情報取得のきっかけになるかわからないからこそ、「選手」というクラブ最大の資産に関わる情報はできるだけ幅広く発信していきたいですね。
またPR TIMESでのプレスリリース配信は拡散性が高いので、ビジュアルも非常に重視していて、選手のイベントやコラボ企画では、画像を見ただけで内容が伝わる構成を意識しています。
──SNSで拡散される際、やはり画像は大切ですよね。松本さんが携わられてきた中で反響の大きかった企画、想像以上の効果があった取り組みなど、印象的だったものをご紹介いただけますか。
2023年からホームゲーム開催日に毎年行っているイベント「男祭り」は大きな反響がありましたね。サポーターのみなさんに「この選手はこういうイメージ」と自然に伝わるようにするには、やはり試合に絡めることがもっとも有効と考え、「選手のブランディング」と「選手の価値向上」を意識しながら、企画しました。
選手のキャラクターとうまくマッチすればサポーターにも受け入れていただけますし、関連する施策も打ち出しやすくなります。毎年コラボ企画を考えるのは決して簡単な作業ではありませんが、おかげさまで認知も着実に広がっています。
プレスリリースではキャラクター(選手)の見せ方にこだわりました。男祭りの中心メンバーの植田直通選手は、日本代表や海外でのプレー経験もあり日本のサッカーファンには知られていますが、パーソナリティも含めてもっと知ってもらいたいと思い、選手の趣味とマッチした企画で注目が集まるように工夫。今は選手個人のSNSでの発信も当たり前になっているので、うまく協働しながらキャラクターに自然とフォーカスできる形を意識しています。
また、2024年は「男祭り」とは対照的に、女性ファンを対象にした試合日のPR施策を行いました。男祭りとは別の選手を起用して女性誌とコラボレーションし、グッズ展開にもつながる施策を仕掛けています。このように、選手一人ひとりの自然なパーソナリティを施策に結びつけることは、企画を考えるうえでも常に意識している点です。

参考:特別企画「720たぎる!男祭り」と『範馬刃牙』のスペシャルタッグが実現!
──「選手のブランディング」という点で、選手ごとの施策をそれぞれ年間計画などで定めているのでしょうか。
年間で計画を立てることまではしていません。やはりシーズンの終盤にかけては、選手が試合に集中できる環境も整える必要があります。また時期に関係なく、試合の2~3日前ぐらいからは、基本的に取材もセーブしていくという決まりを設けて調整していますね。
チャレンジングな施策はできるだけ上期に集中するように心がけ、クラブハウスの外に選手を連れ出す必要がある企画は、試合の間隔が空いた時の週頭に入れるなど、チーム側との連携は常に大切にしています。
また、今後の活躍が期待される選手については「注目の選手」として取り上げてもらえるような施策も検討していくことが必要だと思っています。「どういった文脈でアプローチを行い、その結果どれだけ実現したか」を考え、優先順位をつけながら広報PR活動に取り組むことが大切です。
──今年6月は、新愛称『メルカリスタジアム』の決定について発表していましたが、こうしたスポンサーやパートナーが関連する情報発信ではどのようなことを意識されていますか。
ネーミングライツ取得の件は、クラブ側の担当者がプロジェクト全体をハンドリングしつつPRに関する部分は私たち広報セクションが担当し、親会社のメルカリとも連携して進めました。「どこまでの情報を、どのように出すか」というプレスリリースの内容まで含めて、綿密に調整を重ねましたね。
スポンサーやパートナーに関連する発信は、プレスリリース発表の時点で情報量を最大化することもあれば、記者会見のタイミングに合わせて最大化することもあります。今回は後者を選び、記者会見でのインパクトを重視。単なる発表には終わらせないよう、会見以外の個別対応も事前に仕込むなど、深みのある報道につながるように工夫できたと思います。
参考:株式会社メルカリによるカシマサッカースタジアムのネーミングライツ取得のお知らせ
番記者会から放送枠まで「積み重ね」で育むメディアリレーションズ
──地元メディアとのコミュニケーションについても伺いたいのですが、どのようなことを大切にされていますか。
クラブによっては、一般紙の記者がほかのクラブと掛け持ちで試合日だけ取材に来るケースも多く、練習や日常の取材を通じて関係を築くことが難しい状況も珍しくありません。しかし、私たちの場合はありがたいことに、地元の新聞社やスポーツ紙が専任の担当者をつけてくださっていて、中には都内から車で1時間以上かけてクラブハウスに足を運んでくださる方もいらっしゃるんです。そうした方々にどのようなインセンティブを提供できるのかを常に考えていますね。
また、スタジアムと隣接した施設で夏に開催するビアガーデンに担当記者の方々を招き、「番記者会」を年1回開催するなど、クラブへの愛着を深めていただけるよう、こうした交流の機会を定期的につくるようにしています。
──2025シーズンからは「オンライン取材」を廃止したそうですが、どのような意図があってのことなのでしょうか。
都内からいらっしゃる記者も多く、取材機会を増やすためにオンライン取材を中心にしてきましたが、鬼木達さんが監督に就任したことを機に廃止しました。鬼木さん自身、メディアとの関係づくりが非常にうまい方で、直接の取材を重ねることによって記者の方が顔を覚え、深みのある記事につながると思ったためです。私自身も記者の経験があるので、直接取材のメリットはよく理解しています。結果的に露出は大きく減っておらず、この判断は成功だったと思いますね。
──オンライン取材の廃止は別かもしれませんが、ほかの取り組みをお伺いするに取材のハードルを下げているように感じます。
そうですね。そこはかなり意識している部分です。まずはクラブの顔が見える人間が「書いてもらいたい」と思ってアプローチすることが大切だと思っていて、たとえ記事にならなくても、「何かあればこの人に聞こう」と思っていただける関係をつくることが重要だと思います。
クラブハウス内の選手用カフェをリノベーションした際に、選手が普段食べている食事を一般の方にも体験していただけるイベントを実施したことがありました。「うちのクラブは栄養にこだわっている」というストーリーを整理して、直接コンタクトを取ったことで、日本経済新聞や茨城新聞、NHK水戸放送局など複数のメディアに取り上げていただいています。また、選手が普段食べている食事は担当記者の方に提供する機会を作り、体験記事として書いていただきました。
メディアは自らさまざまな情報を集めていますが、こちらから「こういうストーリーで記事になりますか」と提案することで、「ではこういう取材はできますか」と話が進みやすくなる。そのままにしておけば流れてしまうような題材でも扱ってもらえるようになるのだと実感しましたね。
──ほかにもメディアアプローチが成功した事例があればお聞きしたいです。
観戦体験を増やすため、2024年シーズンからホームタウンや茨城県内だけでなく「全国の小学生以下」をホームゲームに無料招待する施策を開始しました。この施策をどう取り扱ってもらうかを2023年の秋ごろからチーム内で検討し、目標を「キー局での企画放送につなげる」と設定。提案書をメディアにとってちょうどいいタイミングで題材を提供できたことで日本テレビの『News zero』とテレビ朝日の『報道ステーション』で放送されました。
実は当時、安全面などの理由からスタンド内にカメラを入れることはJリーグとして原則認められていなかったのですが、Jリーグ側と交渉し、「Jリーグの魅力をどう外に発信するか」を理解してもらえたことで、無事子どもたちの姿を撮影することができたんです。チームとしてもJリーグとしても影響力のある取り組みになったと感じています。
【質疑応答】参加者からの質問に長谷川さんと松本さんが回答
ここからは、当日セミナー会場で寄せられた参加者からの質問の一部を抜粋し、おふたりの回答と合わせてご紹介します。
──過去の協業でクラブの活動や広報PRにプラスにはたらいた事例をお伺いしたいです。
長谷川さん(以下、敬称略)/水戸ホーリーホック:「Vポイント」を運営しているCCCMKホールディングス株式会社さんとのマーケティング連携は、広報活動においても大きなプラスになりました。
ホーリーホックのスタジアムに来てくださった方々が普段どんな生活をしているのかを、Vポイントの活用履歴などと掛け合わせて分析し、そのデータをもとに「スタジアムでどんなブースを展開すべきか」を一緒に検討。今年2期目に入ってデータも蓄積されてきたので、具体的なアプローチを始めています。
松本さん(以下、敬称略)/鹿島アントラーズ:パートナー企業がクラブと接点を持つことで、ホームタウンやフレンドリータウンの地域と新しい取り組みができるのはとても良い循環だと思います。私たちの場合、食品会社の昭和産業さんがパートナーとなり、選手を教材にした食育授業を教育委員会を通じて提供してきました。
クラブをハブとして地域と企業をつなぎ、新しい価値を生み出す。プロスポーツクラブらしい事例だと思います。
──Jリーグクラブにおける広報PRは、「集客・認知拡大・ファンとの関係構築」のうちどれが最終ゴールなのでしょうか。
松本/鹿島アントラーズ:私たちが重きをおいているのは「認知拡大」です。クラブの最終的なゴールが集客であることは間違いありませんが、チケット担当などと比べると、広報PRが担う度合いは異なります。
もちろん、メディアに取り上げてもらうことで集客に繋がるのが理想的ですが、広報の最終目標を「集客」としてしまうと難しさがあるのも事実です。まずは認知度を高め、その先にどんな行動変容や数字としてのエビデンスがついてくるのかを考えるという順番で取り組んでいます。
長谷川/水戸ホーリーホック:全体としての最終ゴールは「集客」と「収益」とした上で、各部門がどう貢献するかを分担しており、広報はそのための「認知拡大」や「ファンとの関係構築」を担うレイヤーだと考えています。施策を行ったときに、どんな行動変容が起きるのか。例えば、私たちのチームは駅ビルにバナーを出す際、どれくらいの人が通って何人が見るのか、それがどうつながるのかを意識して設計しています。どれをゴールとするかはクラブとしての設定による部分が大きいのではないでしょうか。
──ゴールを集客とした場合、どのような広報PRが望ましいですか。
松本/鹿島アントラーズ:例えば、壁面広告にQRコードを仕込んで、その場から申し込みにつなげるような仕組みをつくれば、実際の数字を測定することも可能です。すべての施策がそうできるわけではありませんが、理想は「認知してもらい、来場のきっかけまで持っていく」こととし、手段はいろいろとあると思います。それがチーム主体であれ、選手に関するものであれ、クラブや選手を知って好きになってもらうことで、観戦への興味を高められるコンテンツを届けることが、広報PRの役割ではないでしょうか。
長谷川/水戸ホーリーホック:私たちの場合は「どんな人に来てもらいたいか」というペルソナを事前に設定しているんです。例えば、ファミリー層をターゲットにする場合、ある人物像をつくり、その人が普段どのような生活をしているのかを想定する。その上で、その生活スタイルに適したプロモーションを当てていくことを意識しています。
──最終的なゴールや目的のお話で、集客か認知拡大という2つが挙げられましたが、ほかにもあればお聞きしたいです。
松本/鹿島アントラーズ:まったく別の軸というわけではないのですが、毎試合観戦に来る人、年間数試合の人、一度は来たけれど離れてしまった人、まったく知らない人といった層をピラミッドのように想定し、それぞれにどうアプローチしていくかを常に考えています。バランスよく取り組むには時間やリソースも必要なので、期間を区切って「この時期は観戦未経験の人を呼び込む施策を打つ」とか、「すでに好きな人にもっと深く好きになってもらってピラミッドの階層を上げる」といった施策を展開していくこともポイントにしています。
今年取り組んでいることのひとつに、アントラーズをよく見る人だけでなく、いわゆるライト層に向け、アントラーズのストーリーを短時間で理解できる『よくわかるシリーズ』の配信というものがあります。注目選手や見てほしいプレー、試合を紹介し、アントラーズに興味を持つきっかけにもなるよう意識してコンテンツをつくりました。
長谷川/水戸ホーリーホック:認知度といっても「選手を知ってほしい層」と「選手は知らなくてもいいけれどスタジアムを楽しんでほしい層」とではアプローチが違いますね。ホームゲームにはグルメやイベントもあり、公園感覚でふらっと来ても楽しめる。その点を知ってもらうのも大事な認知のひとつです。
今年特に力を入れたのがファミリー層なのですが、地域の大型商業施設のフードコートでサッカー色を出さないイベントを行ったり、マスコットキャラクターだけを使った配布物を児童支援施設に置いたりしました。集客や認知拡大も、対象を細分化すればもっと広がりが生まれるのではないかと思っています。
まとめ:地域とメディアとともに磨くブランド価値
今回のセミナーでは、Jリーグクラブにおける広報PR活動の工夫や地域との関係づくり、メディアに向けたアプローチのコツなど、スポーツチーム・団体の広報PR活動に役立つ知見が共有されました。特に、参加者からの質問では、チームが行ってきた具体的な施策が多数紹介され、次シーズン以降の企画づくりのヒントになったのではないでしょうか。
長谷川さんと松本さんのお話から見えてきたのは、「地域」と「メディア」というふたつの存在を軸にした情報発信のあり方です。スポーツチームに限らず、どんな組織にとっても「誰に」「どのように情報を届けるのか」を意識した広報PRは欠かせません。
メディアとの関係を一方的にとらえるのではなく、相互にとって意味のある情報を生み出し、地域や社会の「知りたい」に応えていく。その積み重ねこそが、クラブのブランドを支える力になるのだと感じさせられる内容でした。これから広報PR活動に取り組むスポーツチーム・団体の広報PR担当の皆さまにとって参考になれば幸いです。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする