企業や組織が持続的に活動していくためには、「何のために存在するのか」「どこを目指すのか」「どのような価値観を大切にするのか」といった軸を明確にすることが欠かせません。こうした考え方を言語化したものが、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)です。MVVは、単なる理念の掲示ではなく、社内外の共通認識をつくり、意思決定や行動の指針となる重要な基盤でもあります。
近年は、急速な社会変化や価値観の多様化により、企業が自社の存在意義や役割を見つめ直す機会が増えています。その中で、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を再定義し、明確に打ち出すことの重要性が高まっています。
本記事では、MVVとは何かをはじめ、MVVの策定方法や運用計画について、広報活動に生かすための具体的なポイントを例示しながらお伝えします。
MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは?それぞれの意味と違いをわかりやすく解説
MVVとは、「Mission(ミッション)」、「Vision(ビジョン)」、「Value(バリュー)」の頭文字をとった言葉で、企業や組織が活動するうえでの基本的な考え方や判断軸を示す概念です。
ミッションは企業が果たすべき使命や存在意義を、ビジョンはその先に目指す将来像を、バリューは日々の行動や意思決定において大切にする価値観を示します。これらを整理し、言語化することで、社内外に共通の認識を持たせ、ブレのない意思決定や行動につなげることが可能になります。
ここからは、ミッション・ビジョン・バリューそれぞれの意味や役割、策定される目的の違いについて、順に解説していきます。
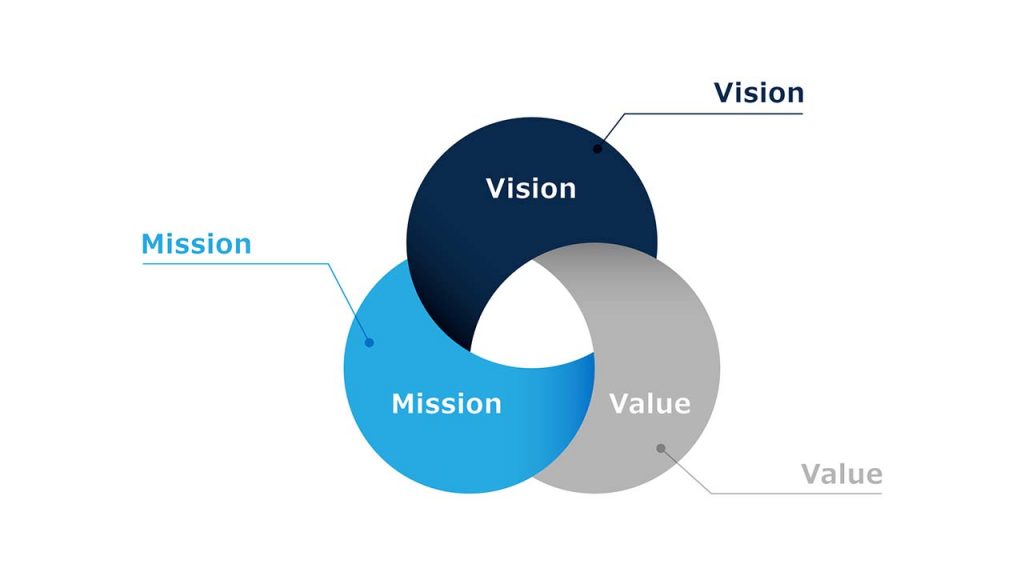
M(ミッション):企業が社会に対して「なすべきこと」
ミッション(Mission)とは、企業・組織が果たすべき使命や存在意義を表す言葉です。なぜこの企業・組織が存在するのか、社会にどのような価値を体現するのかなど、企業・組織が目指す社会について明文化します。
V(ビジョン):企業・組織が目指す「あるべき姿」
ビジョン(Vision)とは、企業・組織の理想像、中長期的な目標を表す言葉です。ミッションを実現するために、企業・組織はどのような状況になるべきか、どのような志であるべきかを明文化します。
V(バリュー):企業・組織の構成員が具体的に「やるべきこと」
バリュー(Value)とは、ミッションやビジョンを達成するための具体的な行動指針、行動基準を表す言葉です。企業・組織の構成員の行動や判断の基準となる価値観を明文化します。
MVVと企業理念や経営理念、行動指針、パーパスとの違い
企業理念や経営理念、行動指針といった言葉は、企業が大切にする価値観や行動基準を示す点でMVVとよく似た役割を持っています。実際、企業ごとに使い方が異なるため、明確な統一基準はありません。一般的には、ミッションが「企業理念」、ビジョンが「経営理念」、バリューが「行動指針」に対応するケースが多く、ステートメントやフィロソフィー、クレドなどを独自に用いる企業も見られます。
これらの言葉は形式よりも、一貫したメッセージとして社内外に共有できているかどうかが重要です。企業が置かれたフェーズや価値観に合わせて、何をどのような枠組みで表現するかを整理することが欠かせません。
近年注目される「パーパス」も、MVVと混同されやすい概念です。パーパスは「企業がなぜ存在するのか」を示す最上位の考え方で、事業の社会的意義を起点に据えます。一方、MVVはそのパーパスを実現するための使命(ミッション)、未来像(ビジョン)、行動基準(バリュー)を体系化したものです。言い換えれば、パーパスが企業の根幹を示し、MVVはその根幹を具体的な言葉として展開したものになります。
策定の順番については、原則としてパーパス → MVVの流れが適しています。存在意義が定まることで、どのような使命を果たし、どのような未来を目指すかが自然に言語化できるためです。ただし、成長フェーズにある企業やスタートアップでは、まず行動基準や組織文化を整えるために先にMVVを作り、事業が拡大した段階でパーパスを再定義するケースもあります。
大切なのは、パーパスとMVVが矛盾なくつながっていることです。これらの概念が連動して初めて、企業の理念体系が社員の行動や外部発信にまで影響し、意思決定の基盤として機能していきます。
MVVはなぜ必要?策定する重要性
MVVの意味を理解しても、「MVVはなぜ必要なのか?」「策定する価値が本当にあるのか」と疑問を抱く人は少なくありません。しかし、MVVを明確にすることは、企業経営の基盤を整えるうえで大きな役割を果たします。
まず、MVVは企業の存在意義や価値観を言語化し、経営陣から現場のメンバーまで共通認識を持つための軸となります。判断のブレを防ぎ、事業計画や目標設定を行う際の一貫性を保つ効果があります。また、組織として大切にしたい考え方が明確になることで、従業員のエンゲージメントも高まり、企業文化が育ちやすくなります。
さらに、MVVは社外への発信にも強い影響力を持ちます。投資家・求職者・顧客といった幅広いステークホルダーに対し、「この企業は何を目指し、どんな価値観で事業を進めているのか」を明確に示すためのメッセージとなるからです。採用広報やIRの場面でも、MVVが整理されている企業ほど、伝えたい企業像を正確に届けやすくなります。
インナーコミュニケーションだけでなく、社外との接点においても企業の信頼を高める存在がMVVです。自社のありたい姿や判断基準を統一し、社内外に向けて一貫したメッセージを発信するためにも、MVVの策定は欠かせません。
MVVを策定するタイミング
MVVは、企業・組織の基礎となる言葉なので、本来は起業時・創業時に策定することがもっともふさわしいタイミングといえます。
しかし、起業時に策定したMVVに固執する必要はなく、社会の変化や経営方針に合わせて変更することも必要です。例えば、社長の代替わり、M&A後、周年記念時、上場など、組織の体制や経営方針が大きく変わるタイミングには、新たな指針となるMVVを再定義することで、組織の意思統一を図る好機となります。MVVの見直しは単なる文言の修正ではなく、企業の価値観と方向性を再構築する重要な経営判断といえるでしょう。
MVVの作り方3ステップと活用できるフレームワーク
MVVは「マクロからミクロへ」という一貫した構造で策定します。ミッションが示す大きな社会的役割を起点に、ビジョンで未来像を描き、バリューで日常の行動基準へ落とし込んでいく流れです。この階段構造が明確になるほど、組織全体が迷わず意思決定できるようになります。
一般的には ミッション → ビジョン → バリュー の順で策定しますが、フレームワークを活用すると議論が整理され、抜け漏れのないMVVを形づくれます。
STEP1.代表や経営陣が事業内容を整理する
最初のステップでは、代表や経営幹部、役員層など、経営に関わるメンバーが中身となり、企業が果たすべき役割や価値創造の原点を掘り下げます。MVVは企業・組織の根幹となるため、事業理解の深いメンバーが議論をリードすることが欠かせません。
具体的に下記の方法で創業の想いや事業の主目的を抽出します。
- 代表・経営陣などキーパーソンからのヒアリング
- 創業ストーリーや、経営判断の共通点を探るセッション
- 過去の施策・意思決定を時系列で振り返るワーク
このとき、以下のようなフレームワークが活用できます。
- ゴールデンサークル(Why / How / What)
Why=ミッション、How=バリュー、What=事業内容に対応し、MVVの土台として非常に親和性が高い考え方です。 - 5F(ファイブフォース)
業界構造を明確にすることで、自社が担うべき「存在意義(ミッション)」が浮かび上がります。
STEP2.ステークホルダーの分析を行う
続いて、企業を取り巻く環境を客観的に整理します。自社視点だけでMVVをつくると独りよがりになりやすいため、環境分析のフレームワークを使いながら、外部の期待や市場構造を把握することが重要です。
活用できる代表的なフレームワークは以下です。
- 3C分析(Customer / Competitor / Company)
顧客ニーズ、競合のMVV、自社の特徴を整理し、差別化されるミッション・ビジョンの方向性をつかむ。 - SWOT分析
内部の強み・弱みと、外部の機会・脅威をまとめることで、組織がどの方向を目指すべきかのヒントが得られます。 - PEST分析(政治・経済・社会・技術)
社会変化やテクノロジー進展を踏まえ、未来を見据えたビジョンの検討がしやすくなります。
特にリサーチしておきたい項目は以下です。
- 顧客が企業に求めている価値・期待
- 競合のMVVやブランド戦略
- 自社の強み・弱み、価値提供の特徴
- 業界構造や社会変化(PEST)の影響
これらを整理することで、社会と組織の接点を踏まえた「ぶれないMVV」が見えてきます。
STEP3.社員ワークショップを行う
最後のステップでは、現場の社員を巻き込みながらMVV案を磨き上げます。トップダウンだけでつくられたMVVは浸透しづらいため、社員の声を取り入れるプロセスが欠かせません。
ワークショップでは次のようなテーマを話し合います。
- 日々の業務で「価値を生み出せた瞬間」
- 会社らしい判断だったと感じたエピソード
- 逆にブレが生じた場面や、迷いが発生した出来事
- 会社の未来をどう描きたいか
こうした現場視点が加わることで、バリューの表現が具体的になり、社員一人ひとりが「自分も運用に参加できる」と感じやすくなります。
最終的に経営陣と現場の両方の視点を統合することで、日常の判断にも使える実践的なMVVに仕上がります。
MVVを策定する際の5つのポイント
MVVは策定しただけで完了するものではありません。それを日々の業務や意思決定に活かし、企業文化の中に根付かせることが重要です。社内外への浸透を図るには、策定段階から以下のポイントを意識しましょう。
ポイント1.MVVのつながりを意識する
「MVVの作り方」でも述べたように、MVVは単独で存在するものではなく、一貫したストーリーで結ばれている必要があります。ミッションが示す社会的役割を達成するために、どんな未来を目指すのか(ビジョン)、そのためにどんな価値観を持ち行動すべきか(バリュー)を明確にし、論理的かつ感情的にも納得できる構成にすることで、社員一人ひとりの行動に落とし込みやすくなります。
ポイント2.頭に残る情報量にする
MVVは、誰もが理解し、記憶できるものであるべきです。特にミッションやビジョンは、日常的に語られたり、共有されたりする場面が多くあるため、複雑な構造や長文では浸透しづらくなります。
実際に多くの成功事例では、ミッションを一文で表現し、ビジョンも簡潔なフレーズにまとめる工夫がされています。社員がいつでも想起できるよう、言葉のリズムや表現のインパクトにも配慮することが求められます。ぱっと見て内容が理解でき、頭に入れておける情報量を意識してください。
ポイント3.共感できる言葉にする
MVVに用いる言葉は、経営層や一部の社員だけが理解できるような専門用語や横文字ではなく、全社員が共感し、自分ごととして受け止められる表現にすることが重要です。特にバリューについては、具体的な行動指針として使われるため、「何をすればよいか」がイメージできる表現が求められます。
また、企業外に向けてもMVVは発信されるため、ステークホルダーにとっても分かりやすく、信頼や共感を得やすい言葉選びが必要です。
耳慣れない横文字の言葉や人によって解釈が分かれる言葉、難解な言葉の使用は避けましょう。
ポイント4.時代や社会性を踏まえる
企業視点で伝えたい内容だけでなく、時代性・社会性にあった言葉選びや表現を意識しましょう。特に現在はネットやSNSの発達で、企業情報を目にする接点が多いので、企業のメッセージがリスクになる可能性もあります。
たとえばSDGsやDE&I(多様性・公平性・包括性)、サステナビリティといったキーワードが重視される今、これらに無関心な表現や、一部の価値観に偏ったメッセージは批判の対象になる可能性もあります。MVVに社会性を盛り込むことで、社会的信頼の獲得や、社外ステークホルダーとの接点強化にもつながります。
ポイント5.策定プロセス自体を価値あるものにする
MVVの策定は、トップダウンで作って終わりではなく、社員を巻き込みながら共創していくプロセス自体が組織にとって大きな意味を持ちます。たとえばワークショップを通じて社員が自らの考えを言語化し、組織の方向性を再認識する機会にもなります。
このプロセスを通じて得た納得感や当事者意識は、その後のMVV浸透・実践の原動力になります。策定の過程もまた「MVVを体現する場」であるという視点を持つことが重要です。
MVVを浸透させる5つの方法
MVVは策定して終わりではなく、日々の業務やコミュニケーションに根づかせることで初めて意味を持ちます。どれほど優れたMVVでも、社内外のステークホルダーに共有されず、活用されなければ形骸化してしまいます。浸透を図るには、社内コミュニケーション戦略と広報施策を連動させ、継続的な接点と体験を設計することが重要です。
以下に、MVVを浸透させるための具体的な5つの方法を紹介します。

1.社内でお披露目する
周知にもっとも効果的なタイミングは策定の直後です。社内報に留まらず、朝礼や全社会、決算報告会など社員が集まるタイミングで、策定担当者や代表の口から直接MVVの内容や策定への想いを語り、お披露目する機会を設けましょう。
特に策定に関わったメンバーの登壇や、策定プロセスのビジュアル化(スライド・動画など)も加えることで、「自分たちで作った価値観」であるという共感を醸成しやすくなります。この初期の共感形成が、その後の社内浸透に大きく影響します。
2.Webサイトや社内報に掲載する
社内外に向けた継続的な発信も重要です。Webサイトの「会社概要」ページやIR資料、採用ページにMVVを明記することで、投資家や求職者に対して企業の価値観を明示できます。また、社内報やオウンドメディアでは、MVVに関連した特集を組む、MVVにまつわる社員のエピソードを紹介するなど、具体的なストーリーとして展開することが効果的です。
対外的にはプレスリリースを発行することで、MVVが企業の経営基盤であることを示すこともできます。
3.人事評価に組み込む
MVVは「日常の行動に反映されるかどうか」が最大のカギです。そこで、人事制度や評価項目にMVVに沿った行動基準を組み込むことで、社員一人ひとりがMVVを意識せざるを得ない仕組みを作ることができます。
MVVを体現した社員を評価・表彰するポジティブな仕組みを取り入れれば、社員が目標設定する際にMVVを意識するだけでなく、面談や表彰式を通して評価された社員本人を起点としてほかの社員に伝播し、MVVが現場レベルでも意味を持つ指針となり、組織全体のカルチャーとして定着していくでしょう。
4.そのほかツールに組み込む
MVVを「目に見える形」で繰り返し接触させることも効果的です。名刺や社員証、クレドカード、デスクトップの壁紙、社内掲示物など、社員の日常に自然と触れるツールにMVVを記載すれば、無意識のうちに価値観が刷り込まれていきます。
また、新入社員研修や全社イベントのコンテンツに取り入れることも、全社員への意識づけに繋がります。五感で体験する「MVVとの接点」を意識的に増やすことが、浸透施策の鍵です。
5.MVVを体現するリーダーの育成
MVVを社内に浸透させるうえで、組織の要となるのが「リーダー層」の存在です。管理職やチームリーダーが日々の意思決定や部下へのフィードバックにおいてMVVを言語化し、体現する姿勢を見せることで、メンバーは自然とそれに倣い、価値観が組織に根づいていきます。そ
のためには、MVVの背景や意味を理解し、自身の業務と結びつけて語れるリーダーを育成する必要があります。リーダー向けのMVV研修やワークショップ、1on1の対話支援などを通じて、行動に落とし込める支援体制を整えることが重要です。単なるトップダウンの伝達ではなく、現場を支えるミドル層からの発信によって、MVVの浸透力は格段に高まります。
MVVを浸透させるための5つのポイント
次に、MVVの浸透方法を実践していく際に、具体的に押さえたい5つのポイントを解説します。

ポイント1.継続的な発信
MVVの意義や方向性は一度伝えたからといってすぐに根づくものではありません。むしろ、時間の経過とともに風化してしまうリスクもあります。そのため、社内報や全社会議、チャットツールなどを通じて定期的にMVVを取り上げるなど、継続的な発信の仕組みを作ることが必要です。
MVVは短期的な目標ではなく、企業文化や戦略の根幹を担う中長期の軸です。年間計画や四半期ごとのテーマに組み込むなど、継続的な取り組みとして計画的に設計することが求められます。
ポイント2.経営者、代表からの発信
MVVの浸透には、トップマネジメントによる一貫したメッセージの発信が欠かせません。経営陣がMVVに基づいた言動を日々の判断や対話に織り込み、「自ら体現する」姿勢を見せることで、組織全体の納得感と共感が生まれます。
特に社内向けのキックオフミーティングや定例会などでは、経営者自らがMVVの背景や言葉の意味、これに込めた思いを経営幹部の言葉で噛み砕いて、熱量を持って発信することで、より強く社員への浸透を図ることが期待できます。
ポイント3.会社ごとに紐付ける・組み込む
MVVの発信は、単発で行うのではなく、企業活動のあらゆる文脈に紐付けていくことが効果的です。たとえば、新卒・中途社員の入社時研修、期初の方針説明、表彰制度、評価面談、あるいは新サービスのローンチやM&A時など、節目のあらゆる場面でMVVを参照し、関連づけることで、社員は自然とその意義を実感するようになります。MVVが企業のあらゆる行動判断の基準となるよう、繰り返し結び付けて語ることが重要です。
ポイント4.周知だけでなく、「理解」の機会をつくる
MVVの言葉を知っているだけでは、真の浸透とは言えません。社員一人ひとりが自分ごととしてMVVを理解し、業務に落とし込めるようにするには、「対話」を通じた理解の機会が必要です。
具体的には、部門別のワークショップや少人数制の対話会などを設け、MVVの内容と自部門・自身の業務をどう結び付けられるかを深掘りします。こうしたプロセスを通じて、単なる標語ではない「行動指針」としてのMVVが根づいていきます。
ポイント5.ストーリーやエピソードで語る
MVVを社員に浸透させるには、抽象的な言葉だけでなく、実際のエピソードを通じて語ることも効果的です。たとえば、「この施策はミッションの○○を体現した取り組みです」といった具体的な文脈で共有することで、MVVの意味を感覚的に理解しやすくなります。
また、社内で表彰された事例や成功体験などをMVVに絡めて紹介すれば、言葉の価値が実感を伴って記憶に残ります。MVVが実際に「機能している」事例を積極的に語り、社内の共通言語として育てていきましょう。
MVV運用でよくある課題と失敗パターン
MVVは「つくった瞬間」がゴールではなく、そこからどう運用するかで価値が決まります。実務の現場では日々の行動や評価に結び付かず、「社長のスローガン」で終わってしまうケースも少なくありません。
ここまでポイントをお伝えしてきましたが、次は、MVV運用でありがちな具体的なつまずきと、その背景にある原因を整理します。あわせて、明日から何を見直せばよいかという観点も押さえ、失敗パターンを再発させないヒントをまとめていきましょう。
言葉が抽象的で、現場の行動に落ちない
MVVが「世界を良くする」「人を幸せにする」といった抽象的な表現だけに留まると、現場のメンバーは具体的に何をすればよいのか判断しづらくなります。その結果、日々の業務では従来どおりの優先順位で動き、MVVは壁に貼られたポスターの一文として扱われてしまうでしょう。
まずはバリューに「具体的な行動例」や「やってよいこと・やめること」をひも付け、職種や階層ごとに解像度を上げることが欠かせません。評価面談や1on1の場で「この行動はどのバリューとつながるか」を対話し続けることで、少しずつ日常の意思決定に落ちていきます。
策定しても日常の会話や評価に出てこない
せっかくMVVを策定しても、会議やチャット、評価シートのどこにもその言葉が登場しなければ、社員にとっては「年に一度だけ見かける標語」です。会議で新しい施策を決める際に「この案はミッションとの整合性があるか」と問い直したり、表彰理由のコメント欄に「ビジョンの○○を体現した事例」と記載したりするだけでも、接触回数は大きく変わります。
人事評価の項目にもMVVを直接組み込むと、上司と部下の対話の中で自然とキーワードが使われるようになり、日常会話のレベルで「当たり前の言葉」として根付きやすくなるでしょう。
経営陣と現場でMVVの解釈がずれている
経営陣が描いているミッションのイメージと、現場メンバーが理解している内容にギャップがあると、同じ言葉を使っていても実態はバラバラに進んでしまいます。特に、横文字や抽象的なキーワードが多いMVVほど解釈の幅が広がりやすく、部署ごとに意味が変わってしまう恐れがあります。
このギャップを埋めるには、トップからの一方向の説明だけでなく、「あなたの部署ではこのビジョンをどう解釈するか」をテーマにした対話型ワークショップが有効です。事例やストーリーを用いながら、経営陣が考える背景を丁寧に共有し、現場からも疑問点や違和感を率直に上げてもらうことで、少しずつ共通の理解に寄せていくことができるでしょう。
見直しのタイミングがなく、実態とずれたまま放置される
事業の方向性や組織構造が大きく変化しているにもかかわらず、創業当時のMVVをそのまま掲げ続けている企業も少なくありません。現場からすると「今のビジネスや顧客を見ていない言葉」に見えてしまい、かえって白々しい印象を与えてしまうこともあります。
こうした形骸化を防ぐには、周年や中期経営計画のローンチ、上場・M&Aなどの節目ごとに「MVVが今の実態と合っているか」を定期的に点検する仕組みを設けることが重要です。完全な作り直しではなくても、表現のアップデートやバリューの追加・統合といった微調整を行うことで、現場にとって「今も有効な北極星」として機能し続ける状態を維持できます。
MVVの事例
実際に、企業はどのようなMVVを策定しているのでしょうか。MVVの事例を広告会社、事業会社、スタートアップ、官公庁の順でご紹介します。
事例1.博報堂
電通と並んで日本を代表する広告代理店。「未来を発明する会社へ。」というミッションの実現を目指して、発想の原点として「生活者発想」、ビジネスの原点として「パートナー主義」という言葉を置いています。特に「生活者発想」は、オウンドメディアやレポート、セミナー、著書の名称など多方面で活用されています。
※本記事では、博報堂で用いられるビジョンをミッション、フィロソフィーをビジョンとしてそれぞれ言い表しています。
Mission(ミッション):
・未来を発明する会社へ。Inventing the future with sei-katsu-sha
Vision(ビジョン):
・生活者発想
・パートナー主義
Value(バリュー):
・Ask 第一生活者として問いを立てる
・Draw まだ見ぬ生活場面を描き出す
・Build 次の時代状況を出現させる
事例2.ファーストリテイリング
日本を代表するアパレルブランド「ユニクロ」を展開する、世界トップクラスの大企業。アパレルブランドとして世界をリードする想いが込められています。
※本記事では、ファーストリテイリングで用いられるステートメントをミッション、ミッションをビジョンとしてそれぞれ言い表しています。
Mission(ミッション):
・服を変え、常識を変え、世界を変えていく
Vision(ビジョン):
・本当に良い服、今までにない新しい価値を持つ服を創造し、世界中のあらゆる人々に、良い服を着る喜び、幸せ、満足を提供します
・ 独自の企業活動を通じて人々の暮らしの充実に貢献し、社会との調和ある発展を目指します
Value(バリュー):
・お客様の立場に立脚
・革新と挑戦
・個の尊重、会社と個人の成長
・正しさへのこだわり
事例3.グッドパッチ
2021年に創業10周年を迎えたグッドパッチ は、UI/UXデザインを得意とする会社です。2020年にデザイン会社として初めて東証マザーズへの上場を果たしています。
ミッションをWeb検索時の企業名と併記したり、ホームページのファーストビューに表示したり、浸透のための工夫が見られます。
Mission(ミッション):
・デザインの力を証明する
Vision(ビジョン):
・ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる
Value(バリュー):
・Inspire with why
・Go beyond
・Play as a team
・Craft details, create delight
・Good design equals good business
事例4.デジタル庁
2021年に設置されたことが記憶に新しいデジタル庁。日本でもっとも新しい行政機関で、日本のIT化・DX化推進を目的に設置されました。
国の行政機関として、リーダーシップを感じさせる力強さと、国民に広く遍く目的や存在価値を伝えるためのわかりやすさが表現されたMVVです。
Mission(ミッション):
・誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を
Vision(ビジョン):
・Government as a Service
・Government as a Startup
Value(バリュー):
・この国に暮らす一人ひとりのために
・常に目的を問い
・あらゆる立場を超えて
・成果への挑戦を続けます
企業のアイデンティティをつくるMVVは、社内外のコミュニケーションの根幹
MVVの必要性から具体的な策定と運用方法までご紹介しました。MVVは部署や役職を問わず、全社員が関わります。さらにインナーコミュニケーションはもちろん、企業が生き残るためのマーケットへの影響や採用広報、IRにもつながることから、MVVは社内外のコミュニケーションにおいてもっとも重要です。そのため、企業そのものの価値を体現するアイデンティティともいえる言葉です。
時代の変化が著しい現在、MVVを見直し、策定し直す必要があるかもしれません。MVVについて理解を深め、自社のMVVについて、改めて考えてみてはいかがでしょうか。
<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>
MVVに関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事
- あわせて読みたい記事事業の成長スピードに負けない活動が役割。MVVCを大切にした広報PR|株式会社マネーフォワード

- 次に読みたい記事採用ブランディングとは?目的・手法・成功のポイントなど基礎知識を徹底解説

- まだ読んでいない方は、こちらから企業理念とは?経営理念との違いや構成要素、浸透させる7つのポイントを解説

- このシリーズの記事一覧へ

