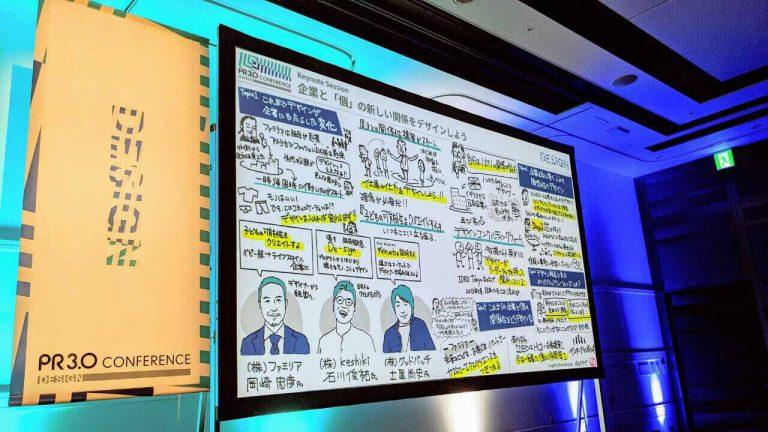広報PR担当者にとって、商品やサービスの魅力を発信することは大切な役割のひとつ。しかし、いざその魅力を言葉にしようとすると、ありきたりな表現になってしまったり、うまく伝えられなかったりともどかしい思いをした方は多いのではないでしょうか。
PR TIMESは、2025年2月18日に学びとつながりの広報・PR担当者向けコミュニティイベント「PR TIMESカレッジVol.9」を開催。第二部では、文芸評論家の三宅香帆さんが登壇し、「魅力を言語化する技術」をテーマにお話いただきました。
言語化する際に意識していることやそのプロセスなど、具体的なメソッドがつまった講演の様子をレポートします。

文芸評論家
文芸評論家。京都市立芸術大学非常勤講師。1994年高知県生まれ。京都大学人間・環境学研究科博士前期課程修了。天狼院書店京都支店長、リクルート社を経て独立。小説や古典文学やエンタメなど幅広い分野で、批評や解説を手がける。著書『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』等多数。
魅力を言語化するときに意識すべき2つのこと
広報PRの重要な役割のひとつ、「伝える」こと。自社の商品やサービス、取り組みなどを言葉にして、わかりやすく、かつ価値ある情報として届けるにはどうしたらよいのでしょうか。
自分の中の言語化と他者への言語化を分ける
自社の商品やサービスを伝えるとき、使ったことがある人に対してと、そうでない人に対してでは伝え方を変えているかと思います。同じように、魅力を言語化する際にも「自分の中での言語化」と「他者への言語化」を明確に区別することが大切だと三宅さんは言います。
- 自分の中での言語化:自分の考えや気持ちを整理すること
- 他者への言語化:相手にわかりやすく伝えること
しかし、単に「他者への言語化」を意識すればよいかというとそうではなく、「他者に対する言語化」をする前に、「自分は何を考えているのか」を整理しておくことが必要だそうです。三宅さんは、日頃から日記やメモに自分の思考を記すことが習慣。広報PRの方はまず「このサービスについて自分はどのように感じているのか」を紐解く作業をしておくと、魅力を言語化するポイントになるでしょう。
抽象的なクリシェを使わずに言語化する
魅力を言語化する際に「クリシェ(決まり文句)を避ける」というのも、三宅さんが意識していることのひとつです。
例えば、「〇万部突破」「毎日食べたくなる」「死ぬまでに行きたい」などの言葉は、一見すると「PRっぽい言葉」ですが、本当に言語化すべき「魅力」や「伝えたいこと」に辿り着かずに終わってしまうことがあります。
業界によってもクリシェは異なりますが、自社にとってのクリシェが何かを具体的に考えたうえで、その言葉を使わずに言語化することを意識してみましょう。また、自分が普段よく使いがちな言葉のクセを見つけ、それ以外の言葉でどのように伝えるのかを考えることもおすすめです。
三宅さんが実践する言語化のプロセス
ここからは、魅力を言語化する際のプロセスを詳しく見ていきましょう。
大切なのは「語彙力」よりも「細分化力」
まず、よかった点を「できるだけ具体的に例を挙げて書き出す」ということ。例えば、好きなアイドルの魅力を高尚な言葉で語るよりも、「この歌のこの微笑みが良かった」と細かく語られたほうが相手には伝わるでしょうし、「この定食はおいしい」と全体の感想を伝えるよりも、「白米はいまいちだけれど、肉じゃがは美味しい」と、それぞれの感想を伝えたほうが信頼度は増すでしょう。
語彙力の高さや難しい言葉を使いこなすのではなく、曖昧さを避けてより具体的に伝えられるかという「細分化力」がポイントだと三宅さんは言います。
具体的に挙げた魅力の中から一番を見つける
具体的に「よかった点」を書き出したら、その中から「一番よかった点」を選びます。実際に三宅さんも書評を書く際には、「その本の中の一番好きな場面」や「一番好きな登場人物の一番良かった部分」を取り上げることが多いそうです。
世の中に無数のコンテンツがあふれ、視聴者や読者の目が肥えている現代において、「おもしろそう」「良さそう」「好きになれそう」と思ってもらうためには、伝える側が一番ぐっときた部分を表現することが効果的なのではないでしょうか。
伝わる着眼点かを他者の反応で確認・熟成
自分が一番良かったと思っていても、その視点が的外れだった場合には正しく魅力を伝えることはできません。そのため、自身が挙げた「一番良かった点」が伝わる着眼点かを他者の反応で確認することが大切です。
三宅さんいわく、この「他者の反応」を確認するのに役立つのがSNS。切り口は合っているのか、推す点は本当にここで正しいかなど、伝わる着眼点かどうかを他者の反応を見ながら探るそうです。
「自分の中でどれだけ練られたのか」「どれだけ熟成させたものを差し出すのか」。言語化を熟成することも欠かせないポイントになります。

広報PR担当者からの質問に三宅香帆氏が回答
ここからは、広報PR担当者から三宅さんへ寄せられた質問への回答をご紹介します。当日は時間の関係で回答いただけなかった質問に対し、追加でお答えいただきました。
──「ChatGPT」などの生成AIは、今や広報PR活動においても有用なツールとなっていますが、その活用についてどのようにお考えでしょうか。
生成AIに任せるところは任せて、熱量を込めなくてはいけないところは自分で、というメリハリが大切だと思います。今後は、情報を伝えるだけでいい部分などは生成AIを活用し、魅力が本当に伝わってほしいところなどは人が担当するというふうになっていくのではないでしょうか。
とはいえ、生成AIの作成した文章には文体のクセがあるのも事実です。また、具体例の中でどこを選ぶのかなどは生成AIがまだうまくはない部分なので、切り口や具体例のどこに着眼点を持つのかという問いの立て方が大切になってくると思います。
──書評を頼まれた本に魅力を感じなかった場合、どうしていますか。
私は基本的に自分が心からおすすめしたいと思ったり、好きだと思ったりするもの以外はおすすめしないようにしていますが、広報PR活動の場合には「自分が熱を注ぎきれないのはなぜか」「どこに引っかかるのか」を具体的に挙げてみることが大切だと思います。
ここでもポイントとなるのは「具体的に」ということです。魅力を全体からとらえるのではなく、「興味は持てないかもしれないけれど、この部分はおもしろいかも」「この部分は世間のためになるかも」というように、具体的なポイントを見つけていくということをしています。
──BtoBの広報は魅力を伝えることが難しいと感じています。実体験に紐づかない、なおかつユーザー目線にもならないとき、どのように言語化をすればよいのでしょうか。
BtoBの広報の場合、「超抽象化」か「超具体化」のどちらかの方法で言語化するのがよいと思います。例えば「印刷」というサービスの場合、それが世間にとってどのような意味があるのかをとらえるのはなかなか大変です。しかし、視点を変えて「人々の文字を支える仕事」「メディアの土台をつくる仕事」といった形で抽象化することで、その価値や意義がより明確になるのではないでしょうか。
また、逆に超具体化して「もし紙がない世界だったらどうなるか」といったシナリオを想像することで、サービスの必要性を浮き彫りにすることも可能です。このように超抽象化と超具体化のどちらかを意識することで、BtoBであっても魅力を言語化しやすくなると思います。
──本を出版する際、あえて造語や自社オリジナルの言葉を使ったタイトルにして売るべきか、共感性を重視して「自分の抱えている課題を解決してくれそうな本」だと思ってもらえるようなタイトルにするべきか悩んでいます。
造語というのは「流行語大賞を狙う」「世間にこの言葉を本気で流行させたい」というぐらいの意気込みがあれば使ってもよいと思っています。しかし、そうではなくて自社や作者の意思や世界観を伝えるための造語の場合は、帯やサブタイトルに入れたほうがよいかもしれませんね。SNSでシェアされることを考えたとき、タイトルで共感して帯で詳しい内容を見て「おもしろそう」と感じる人が多いので、タイトルは共感性を高くして、サブタイトルや帯文で独自性を出すほうが、「読みたい」と思ってもらえるのではないでしょうか。
──広報PR活動を複数名で取り組む際、打ち出し方や訴求ポイントを決めていくときのコツや、社内で説明をする際に意識しているポイントなどあれば教えていただけますでしょうか。
複数名で取り組む場合には、「誰にこれを届けるのか」の合意を取ることがとても大切だと思います。例えば、タイトルやキャッチコピーなどを決める際にも、複数名だとどうしてもセンスだけで決めてしまいがちです。「誰に届けるのか」をきちんと定めていないとぼやけた印象になってしまうので、「疲れて帰ってきた人が見たときにぐっとくる言葉」というように、こういう人がこういうシチュエーションで見たときに、こういうふうに感じるタイトルという部分からそろえていくのがよいと思います。
──【追加質問】クリシェを使っていることにすら気がつかない感覚があります。クリシェだと自分で気づくための良い方法はありますか。
自分の書いた文章や資料をまとめて読み返すといいかもしれません。以前書いたものを、時間が経って再読すると、自分の手癖に気づきます。
──【追加質問】最後まで読んでもらえるプレスリリースを目指しています。読み手が離脱しないような文章にするにはどのような点を意識したらよいですか。
最初の書き出しに重要な情報を出すことです。もちろんプレスリリースの作法もあるので難しいかもしれませんが、SNSだと重要でない情報を投稿の冒頭に出している例がとても多いと感じます。重要なことは早めに伝えると、逆にその後も興味を持って読んでもらえると思います。
──【追加質問】潜在的に本を必要としているユーザーを考える際、魅力を伝える際、ターゲット層として年齢や性別、職業などをイメージしているのでしょうか。また、ターゲット層を検討するときのポイントはありますか。
ぼんやりと考えます。「こういう人が手に取りたくなる本になるといいな」と。ポイントはできるだけ伝えたい人の心情や論理に寄り添うことです。
──【追加質問】社員インタビューや取材を受ける方へのサポートをする機会が多いのですが、インタビュイーが言語化しやすいような質問、言語化できないときのサポートとしてどのような点を意識したらよいですか。
インタビューする側が自分の話をしすぎないことは大切だと思います。あなたの話を私は聞きたいんです、という姿勢に心理的安全性を持つ人は多いです。
──【追加質問】広報PR活動の中でもすべてを明らかにできないケースがあります。作品の内容(ネタバレ)を控えつつ、具体的に表現するポイントがあれば教えてください。
どこからどこまではネタバレしていいのか、のラインをはっきりさせることだと思います。そのラインが曖昧だと何も書けないと感じます。
──【追加質問】『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』このタイトルはどのようにして誕生したのか伺いたいです。
対談記事で「働いてると本読めないですよね」としゃべったのですが、その発言について言及しつつ記事をシェアしている方が何人かいらっしゃって、ここには何かあるのかなと思ってタイトルにしました。
──【追加質問】広報PR担当者に「一番おすすめ」の本を教えてください。
『「好き」を言語化する技術』を読んでもらえたら嬉しいです!

まとめ:魅力の言語化に必要なのは、よく練られ、熟成させた言葉たち
単に言葉を並べるのではなく、本当に伝えるべき価値を明確にして相手に届く形にする。魅力を言語化するプロセスがよくわかるお話でした。
三宅さんが大切にしている言語化の際のポイントは以下の通りです。
- 自分の中での言語化と他者への言語化を区別する
- 日記やメモを活用し、自分の考えを整理しておく
- 抽象的な「クリシェ(決まり文句)」を使わない
- 魅力を具体的に書き出し、その中から一番を見つける
- SNSなどを活用して他社からのフィードバックを得る、反映する
自社の商品やサービスの魅力を伝える際に、ぜひ参考にしてみてください。
【カレッジVol.9に関する記事】
【PR TIMESカレッジVol.9ダイジェスト】
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする