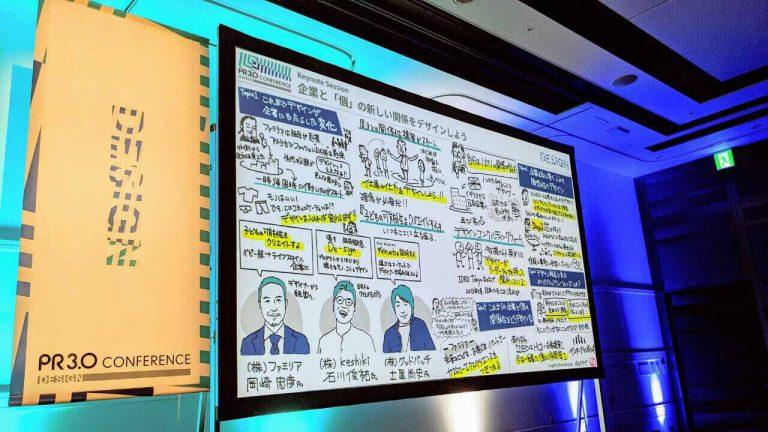スタートアップの企業数が年々増えている中で、自社の挑戦を社会にいかに伝えるか──。事業拡大や採用、資金調達において非常に重要なテーマです。しかし、何から始めればよいかわからずに悩む経営者も多いのではないでしょうか。
こうした悩みに応えるべく、プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を運営する株式会社PR TIMESは、2025年6月11日に「スタートアップ経営における広報戦略セミナー」を開催しました。
本セミナーでは、株式会社THE BRIDGE代表取締役の平野武士さんと、株式会社天地人で広報を担当する砂流恵介さんをお招きし、スタートアップの現場で直面するPRのリアルや、実践的な工夫、成果につなげるための考え方について語っていただきました。
本記事では、当日の内容をもとに、スタートアップ企業のPRに携わる方が「明日からできること」につながるヒントをお届けします。
伝わらないことを認識して、創業者が自ら伝える|THE BRIDGE・平野武士
PR成功の行動指針は「説明コストを下げる」
ご存知のとおり、PRはパブリックリレーションズの略ですが、抽象的で定義が曖昧です。一方で、PRを「プレスリリースを書くこと」と定義してしまうと、それだけで満足してしまいます。会社のためにPRをしっかりと機能させるためには、「PR=特定の何か」と定めることなく、抽象化した行動指針を作り、言語化することが大切。その行動指針としておすすめなのが「説明コストを下げること」です。
たとえば、メディアが今話題の「万博」「Nintendo Switch2」などと比較して、スタートアップ企業の事業内容を他者に伝えることはとても難しい。スタートアップ企業でPRを担当する場合、まず「説明コスト」が高いことを自覚する必要があります。
PRをわかりやすくするマジックワード・語り・ファンコミュニティ
では、説明コストを下げるために大切なことは何か。
ポイントは3つあり、1つ目は「事業を一言で説明できる『マジックワード』を開発すること」です。たとえば、楽天ラクマやメルカリなどのサービスを紹介するために「フリマアプリ」というマジックワードが作られ、広く知られたことで、事業の説明が一言で済むようになるのです。
2つ目は「創業者のナラティブ」です。創業者のストーリーを交えた話は思わず耳を傾けてしまいます。ただし、うんざりさせない程度の自分語りができることが大切です。
3つ目は「自社サービスを好きだと言ってくれる『ファンコミュニティ』を作ること」です。投資家、サービス利用者、協業企業など、いろいろな方と積極的にコミュニケーションを図るためのコミュニティを作る。このファンコミュニティが、サービスの認知度や事業拡大の原動力となり、スムーズに上場に至ったケースを見たことがあります。
社員に任せず、創業者がPRの前線へ
先ほどの「語り」に通じることですが、注目されるスタートアップの共通点のひとつは、創業者の巧みな話術です。事業に関する説明コストを認識したうえで、創業者のバックグラウンドを含めたストーリーが語られると、魅力的に映ります。その際、共感が得られない過剰な自分語りは避けましょう。社会との接点を持ち、トレンドをきちんと押さえた話にすることが求められます。ただし、世の中のトレンドを意識しすぎて、発言にブレが生じないよう、常に芯となるメッセージを意識したほうがよいですね。
また、社員が「自分が何をしているか」「事業内容がなにか」をしっかりと語れるためにも、創業者自身が説明コストを下げる努力をする必要があります。創業者の顔が見えないものは生活者から選ばれにくいものです。ぜひ創業者自ら、関係者とコミュニケーションを取ってほしいですね。
資金調達のために必要なコミュニケーション
資金調達に必要なのは、投資家に合わせた成長ストーリーを語ることです。創業初期に支援する方たちの思い入れが強いほど、事業の成功率が高まる傾向があります。PRといえば、ついメディアリレーションズを重視してしまいがちですが、それよりも今目の前にいる投資家や生活者との1対1のコミュニケーションのほうが大切です。中期経営計画などを徹底的に調べ、相手がどのような情報を欲しているか理解したうえでストーリーを作り、密にコミュニケーションを取りましょう。
前提として、リアルタイムな活動内容がきちんとわかるよう、定期的にプレスリリースを配信するなどの当たり前のことは欠かさないほうがいいですね。

経営に寄り添い、採用と発信をつなぐ|天地人・砂流恵介
経営層とのコミュニケーションで採用・PRに寄与
まず、スタートアップ企業のPRは、採用と切っても切れない関係です。当社では、採用候補者が求人情報を調べたときにより興味を持っていただけるよう、読んでほしい記事や見てほしいコンテンツに誘導できる導線を整えています。
また、スタートアップ企業が置かれる立場や社内の状況は目まぐるしく変化し、考え方が日々更新されていくことを実感している方も多いのではないでしょうか。僕は、少なくとも週に1度、必ず経営層との1on1ミーティングを実施し、密なコミュニケーションを図るようにしています。これにより、サービスや経営の状況、方向性を確認し、採用などに関わる会社紹介の資料がPRの方向性と合っているかを確認しています。
差別化のためには他社情報を読み込む
PRは「プレスリリースを書くことだけではない」と言っても、やはりプレスリリースは大切です。シード期やシリーズA期のスタートアップがプレスリリースの配信頻度を検討する際には、「同業他社がどれくらい出しているか」を確認し、その量を下回らないように意識することも大切です。他社がプレスリリースをほとんど配信していない、もしくは配信しているものの内容がわかりづらい場合、わかりやすい内容を頻度高く配信することで差別化できます。
プレスリリースでは、何から伝えるべきか情報に優先順位をつけ、「世の中にどう役立つのか」が伝わるよう、情報を届けたい人の気持ちになりながら言葉を整理し、効果的な表現を模索していく。そうすることで、より良いプレスリリースが作成できると思います。
PRを成功させるための社内広報
PRの価値や取り組む意義を社内に理解してもらうため、社内広報は欠かせません。効果的な方法のひとつが、オウンドメディアのインタビュー記事です。インタビューを受けることになった人は過去の記事に目を通し、参考にしますよね。部署を跨いでインタビューを回していくだけで自ずと社内理解が進み、読んだ人同士の共感が広がり、一体感が生まれやすくなると思います。
「隣の部署は何をしているかわからない」といった状況を防ぐためにも、事業部間の相互理解は欠かせません。また、就職・転職を考えている方にとっても、インタビュー記事は有益な情報源となるため、蓄積していくことは重要です。
業務効率UPは生成AIで実現
当社では、プレスリリース作成に生成AIを利用し始めました。出力したものをそのまま使えることはなく手直しは必要ですが、圧倒的に時間短縮になり、ある程度のクオリティのものが誰でも作れます。初稿は30分程度で作成できるため、忙しくても着手できますし、下書きを作っておくことで、「プレスリリースを配信し損ねた」ということも防げるでしょう。
ちなみに、PR部として生成AIを導入するか悩んでいた時期がありました。しかし、「早く導入しないと世の中から取り残されるぞ」という危機感を覚えて導入。事業を進めるうえでのスピード感にも大きく影響しますので、まだ使っていないという方がいれば、早めに使い始めることをおすすめします。

まとめ:スタートアップPRはできることからひとつずつ取り組もう
自社の魅力やビジョンをどう社会に届けていくのか。平野さん、砂流さんが実際に取り組まれてきたことや、お二人のお話の中にあった、PRで意識すべきポイントは、スタートアップ企業でPRに取り組む方にとって大きなヒントになったのではないでしょうか。
今回のお話を通じて意識していただきたい点は、以下の5点です。
- 説明コストの高さを自覚して、説明コストを下げる努力をする
- 創業者自身がPRに携わり、関係者と積極的にコミュニケーションを図る
- 社内にPRの価値や必要性を理解してもらう
- 社外への情報発信は定期的に行い、競合他社を上回る質と量を意識
- 生成AIを用いて業務のスピードUPを進める
自社の状況を振り返り、スタートアップならではの課題を認識したうえで、できることから取り入れてみてください。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする