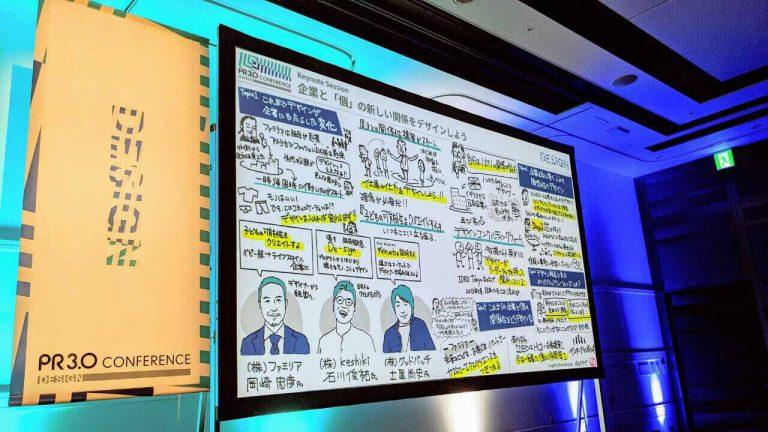世界中で取り組みが進むSDGs。2030年という具体的な期限が設けられ、企業、個人、すべての人が取り組んでいかなければならない問題です。ユーグレナ広報宣伝部長の北見さんはSDGsの注目すべきポイントとして、「やりがい」が掲げられている点を挙げました。「人が幸せになりながら地球も幸せにならなければならない」そんな中で、ユーグレナが企業として持続可能な社会をどのように実現しようとしているか、北見さんの分科会の様子をレポートします。
株式会社ユーグレナの最新のプレスリリースはこちら:株式会社ユーグレナのプレスリリース
待ったなしの持続可能な社会の実現を達成する
2030年までに達成しなければならない目標。すべての人が幸せに生きる社会を実現し、環境問題をはじめとするさまざまな社会課題を解決するという前提に、ユーグレナは自分たちはどのように取り組むべきか考え、そこで生み出された言葉が「Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)」だったといいます。
サステナビリティを実現する「イノベーション」と「社会実装」
SDGsに挙げられる指標の中でも、最初に語られるひとつが環境問題ではないでしょうか。ユーグレナは、我慢することや、消費を少し減らすなど生活水準を落とすようなことではなく、自分たちが担うべきこととして、常にサステナビリティを念頭においた「イノベーション」と「社会実装」にたどり着いたそうです。どんなに優れた技術やサービスで「イノベーション」が起こせても、それが社会に受け入れられ「社会実装」されないと意味がない、と北見さんは話します。
完璧でなくても社会に問い続ける
完璧でなくても未来を良くする可能性があるならば、新しい研究や開発、サービスなどを積極的に社会に出して問うていくと決めたユーグレナ。その想いをこめて、創業15周年の年にユーグレナ・フィロソフィーとして「Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)」を掲げています。
持続可能な社会を実現のための事業推進
持続可能な社会を実現するには、ボランティアでは務まらず、資金力を持ち事業として大きく展開していくことが近道です。「イノベーションを起こしていくことで社会課題を縮小する」この考えをベースにすべての事業に臨んでいるといいます。フィロソフィーとして全社に浸透し事業と一体であるからこそ、ユーグレナは常にぶれない事業展開を実現しているのでしょう。

バイオ燃料を社会実装する広報
2018年、ユーグレナはカーボンニュートラルを実現するバイオ燃料の製造実証プラントを完成させ、2020年4月から供給を開始しています。事業としてはBtoBであるバイオ燃料の広報においても、ユーグレナならではの発信方法がありました。
バイオ燃料の安全さとSDGs貢献の体験
同社は微細藻類ユーグレナの大量培養に成功した後、藻類を原料とするバイオ燃料の研究開発生成に着目します。バイオ燃料は、使用時に発生するCO2を原料の生育段階で光合成し吸収するため、循環をつくり出すことができる、いわゆるカーボンニュートラルと呼ばれる考え方を実現する燃料。2018年に国内に構えた工場で製造を開始し、2020年4月にはバスや船・車両を運用している運輸会社などBtoB向けに供給を開始するというスピードでした。
一方で、将来を見据えたとき、バイオ燃料の良さを広く一般に知らしめる必要性を感じたといいます。そこで、「サステナブル」と「オイル」から「サステオ」というブランドネームを設定。ロゴデザインや自動車車体へのラッピングや、さらに、ガソリンスタンドでの販売イベントなどを行い、一般消費者にバイオ燃料の安全性や、SDGsに貢献し地球環境を改善する体験を促す、「徹底」した広報PR活動をしました。
別会場でも話題に上がっている「徹底」というキーワード。一見、直接関係しない、影響しないことに対しても目的に対する実現方法を見極め、徹底して実行するという点はどの分科会においても共通する点でしょう。
パートナーシップでサステナビリティ実現を加速
バイオ燃料で飛び立った飛行機の映像を、これまでに目にした方も多いのではないでしょうか。実はこの飛行機は、燃料のすべてがバイオ燃料ではなく、化石燃料にバイオ燃料を混合しています。フライトの発着地である羽田と鹿児島で行った記者会見では「一部しか供給できていないじゃないか」という、メディアの指摘があったそうです。
しかし、「この一歩が大切だった」と北見さんは話します。
何もないところからイノベーションを生み出し、「ここまではできる」ことを証明できれば、「ここ」から先に進むためのパートナーシップを提案でき、パートナーシップを組めば、自社だけで取り組むよりも供給量や認知度が上がり、結果的に市場の拡大につながる。そんな確証があった、と。
「これがうける」という外のニーズを拾うだけではなく、「未来のためにこうしなくてはいけない」という信念も持って広報活動をしているといいます。この広報スタイルに悲観的なメディアの方もいると思いますが、そこは広報として真摯に対応していくことで理解してもらい、社会をはじめ、地球を救う事業に注力する会社の体制づくりを広報の立場で支えたい、と北見さんは締めくくりました。

質疑応答|株式会社ユーグレナ 北見裕介氏
分科会のはじめに、「質疑応答でたくさん話しましょう」とあった通り、会場から多くの質問がでました。寄せられた質問の数は全分科会の中で最多。それでもまだ聞き足りない、という声も挙がったほどです。
バイオ燃料という分野はなかなか広報しづらいと思うのですが、見せ方など工夫されているところはありますか?
広報PR活動をするときは「このコンテンツをどう見せたら響くか」を考えるのですが、最終的に「情報が響いてほしい層」をターゲットにしています。例えば、バイオ燃料というものをどう見せたら消費者は面白いと思うのか、ということです。メディアに取り上げてもらうことを優先して、「メディアに響く企画」では考えません。ご紹介したガソリンスタンドのイベントはそれです。「ガソリンスタンドでやったら面白いのでは?」が先にありました。「消費者が面白いと思うかも」を考えて企画したら、結果的にメディアも面白いと思ってくれたのではということです。
消費者が望むことをキャッチアップしてコンテンツに反映するということですね。ニーズの調査はどのようにされていますか?
今のユーグレナのステークホルダーも意識しています。例えばユーグレナ商品を定期購入してくださっている方とか、株を長期保有してくださっている方とか、我々を応援してくれている人たちが求めていることが一番わかりやすいニーズだと思っています。その方々たちと同じニーズを持っているけれど、「ユーグレナをまだ知らないからつながっていないんだ」と仮定して発信方法を決めたりもします。ニーズの調査についてですが、実は会社の仲間の肌感覚も大切だと思っています。担当事業外だったりすると知識があまりなかったりするんですね。その素の状態から出てくる疑問とか「こういうことは出来るんですか?」みたいな意見を取り入れて企画していくこともあります。
100%じゃない状態でも外に投げかけるということを決めるときや、ストーリーの着地点を浸透させる社内コミュニケーションについて伺いたいです。
社外に出していく大前提として「安心安全」は絶対だと思っているので、そこは理論上確実であることを確認したうえで共有します。バイオ燃料を供給するときも真っ先に確認しました。バイオ燃料の例でいえば、2020年4月に路線バスでの供給が決まったときに「普通に生活空間を走るバスに使われているという状況は、社会実装の第一歩なんじゃないか」と考えて発信を提案したんです。
当時はコロナ禍の混乱の中なので当然社内からも、「10年かけてやってきたのに記者会見できないなら出すべきじゃない」「新型コロナウイルスで話題が最大化しないのでは」などの反対意見が出ました。そのときは、「ニュースが今コロナ禍一色だからこそ、別のニュースが面白いんです」「大丈夫です、社会に良いニュースだと感じてもらえるようにアプローチするので出させてください」と説得したんです。人を集めることが難しい中、個別に記者会見をセットするなど最大限のできることをしました。しかし、社内では私がこういう判断をすることをみんなわかっているところもあります。それはやはり日ごろのコミュニケーションの積み重ねかなと思います。

分科会まとめ|株式会社ユーグレナ 北見裕介氏
事業として完成していないものでも積極的に発信していく北見さんの広報スタイルは、広報の立場からするとなかなかチャレンジしづらいことかもしれません。
しかし、限りある時間の中でサステナビリティの実現を市場形成から担っていくことを全社員がミッションとして捉え、同じゴールを共有しているからこそ可能なスタイルだといえます。
あらためて、社内における理念の浸透の大切さを認識させられたセッションだったのではないでしょうか。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする