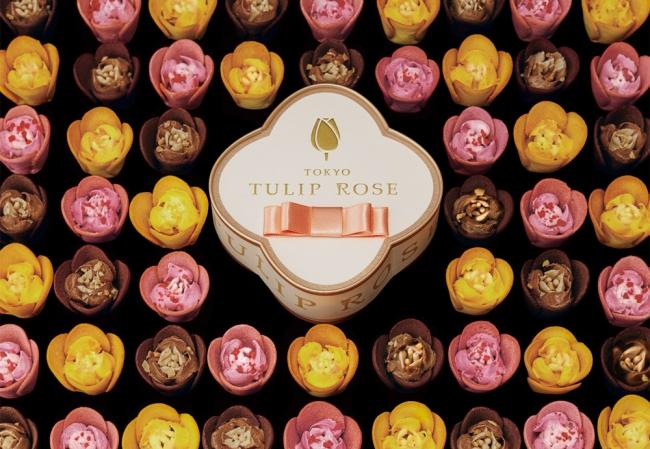本稿は、石川貴也氏による寄稿です。
会社を経営していくうえで重要な役割を持つ広報PR活動。しかし、地場に根付き古くからの取り引き先がある、BtoBメーカーとして現在の取り引き先で十分、などの理由で必要性をあまり感じられていない方もいるのではないでしょうか。
本記事では、明治から続く愛知県の製缶メーカー側島製罐株式会社の代表取締役であり、自ら執筆したプレスリリースで「プレスリリースアワード 2022」インフルエンス賞を受賞した、石川貴也氏に執筆していただいています。
多様化するPRとプレスリリース
「プレスリリースは発信してみたいけどうちなんか大したネタがないし……」
「配信プラットフォームで発信したけどメディアから反応がない……」
中小企業でのプレスリリースに関する悩みは多数寄せられます。以前はプレスリリースを配信するのは大企業を中心とした一部の企業に限られていましたが、最近ではプレスリリースに注力する企業が増え、SNSなどの発信の手段にも多様化しており、記者側もさまざまな角度で情報を収集するようになりました。そのような環境下において、プレスリリースを作成する際、テンプレートを使うことで、初めての人でも基本に沿った伝わりやすい内容にできる一方で、差別化しづらい、どうしても埋もれてしまうという課題もあり、中小企業のプレスリリースの悩みは尽きないものだと推測されます。
しかし、中小企業には中小企業にしかできないプレスリリースの打ち出し方があります。日頃当たり前にやっているようなことが、実は世の中の人たちにとってはユニークに感じるものだったりします。今回は、経営者が自らプレスリリースを書くことの意義とそのポイントについて解説していきます。
そもそも中小企業がプレスリリースを出す意義とは
これまで積極的に広報PRの活動を行ってこなかった中小企業にとって「プレスリリース」というものは非常にハードルが高く感じるものです。特に中小企業のBtoBの製造業などにとっては、大企業のように多くの一般消費者に向けた製品を取り扱っているわけでもないことから、ますます広報PRの意義は感じ辛い状況にあります。どれだけ広報PR活動に注力したところで自社製品の売り上げに直結したり、短期的な収益に貢献したりするわけでもないとなれば、限られた社内のリソースを広報PR活動に割く判断をするのも難しく感じ、なかなか広報PR活動に踏み切れない企業も多い印象です。
しかし、プレスリリースとは新商品を紹介するためだけのものではなく、あらゆる企業活動を公に発信するためのものです。普段テレビや新聞などのマスメディアを見ていると華々しい大企業の発表ばかりに目が行きがちですが、よく観察してみると地方の中小企業で話題になっている会社も多数あります。その中身は新商品に限らず、長年働いている職人さんの話だったり、不良品の処分の話だったり、その中小企業ならではのユニークなストーリーであることが多いです。
自社製品以外のことでメディアに露出しても売り上げに直結するわけではありませんが、企業活動がメディアを通じて公になることは社会的な信頼性の獲得という大きな効果を秘めており、そこに中小企業の広報PRの意義があります。
経営者ならではの視点、想いこそが強みに
中小企業の独自性は“What・How”ではなく“Why”にある
まず、プレスリリースを書く際のポイントとして新規性、地域性、社会性などさまざまな要素がありますが、中小企業のプレスリリースで特に大切なのは「独自性」だと考えています。とはいえ、「あなたの会社の独自性を生かしてプレスリリースを書いてみましょう」と言われてもなかなか思いつかないことも多いのではないかと思います。
例えば、大企業のように福利厚生で社内ビュッフェを作ったとか、社内の公用語を英語にしたとか、そういった最先端の独自性事例と比べるとどうしても自分たちの取り組みが見劣りするように感じてしまい、せっかくのユニークな企業活動も独自性という認識に至らないままになっているケースが多い印象です。
しかし、ここに大きな誤解があります。確かに「何をしたか」という点も大切なのですが、それよりメディアや世の中の方々が知りたがっているのは「なぜそうしたのか」という背景にあります。例えば「新たに福利厚生の制度を導入した」という趣旨のプレスリリースを作成する際に、ただ「福利厚生の制度を導入」したという内容だけでは、その独自性は伝えられません。そうではなく、例えば「採用の難しい人口の少ない地方で」「離職の多さが課題で」「子育て世代の負担が大きかったことが原因で」「子どもの急な病気などに対応できるように」など、福利厚生の制度を導入するに至るまでには色んな事情やプロセスがあったはずです。
「なぜそうしたのか」という理由を深く掘り下げることはその企業独自のストーリーを生み出すことでもあり、それこそがその企業にしかない個別具体的な独自性としての輪郭を帯びていきます。自分たちがどんな想いでやったのか、なぜそうしたのか、社内や地域に意義があるのか、そうした情報を丁寧に切り出して文章にまとめていけば、自然に独自性の高いプレスリリースは生まれるはずです。
等身大のプレスリリースが共感を呼ぶ
また、このようなストーリーを書く際に大事なポイントは「良いことも悪いこともオープンにする」ということだと考えています。プレスリリースは社会に向けて全方位的に発信するものなので、「ダメな会社だと思われたくない」「自分たちの会社のことを良く見せたい」という気持ちが湧いてきて、ネガティブな要素をできるだけ省いたプレスリリースを発信する企業も散見されます。
しかし、悪い部分をあえて書かずに良い部分だけを見せるような少し背伸びをしたプレスリリースは、中小企業ならではのストーリーを薄めてしまい、情報としての深みが失われてしまいます。世の中のどんな会社も、何もかも順風満帆でうまくいっていることはまずありません。
どの会社もさまざまな悩みを抱えながら日々を過ごしているものです。世の中の人はそんな悩みを解決しようと奮闘している人たちの姿に希望を見いだしますし、メディアの方々はそんな企業を取材したいと思うのではないでしょうか。そういう意味では、たとえ完璧にできていないことだとしても、挑戦して変えようとするそのプロセスにこそ価値があるものであり、できるだけ包み隠さず等身大の姿を発信することは、中小企業のプレスリリースについては特に肝要だと思われます。
経営者の生の言葉は大きな武器
さらに、中小企業のプレスリリースの独自性を強くするもうひとつの方法として「経営者が自らプレスリリースを書く」というものがあります。私自身も自分が経営する会社ではプレスリリース作成の役割を担っていますが、特にストーリー色の強いプレスリリースにおいては経営者が思いの丈を直接記すことはとても有効だと感じています。
プレスリリースは社会に向けて発信するその特性上、決裁や合議などを経て作成されることが多いです。もちろん、そのようなプロセスは質を担保するうえで大切なことではありますが、複数人の意見を集約するその過程でどうしても独自性が弱くなってしまう傾向にあります。しかし、プレスリリースというものに正解はありません。もちろん最低限の形式というものはありますが、プレスリリースの目的は決して形式や表現を標準化して小綺麗にまとめるものではありません。多少不完全で荒い内容であったとしても、発信する人の想いが色濃く表れていたり、読んだ人が身近に感じるような迫力や手触り感があったり、「この情報をもっとほかの人に伝えたい」とメディアの方々に感じてもらえるようなことのほうが大切です。
経営者の生の言葉で書かれたプレスリリースは、受け手のメディアの方にとって取材のイメージがしやすいという点も大きなポイントです。メディアの方は取材先を選定する際に、どんな記事が書けるのか先行してイメージし、書きたい記事と取材先でのインタビューの内容に齟齬や相違がないように検証を重ねたうえで取材先を決めています。経営者自らが発信しているプレスリリースは、誰にインタビューしてどんな言葉がもらえるのかが明確な取材先であるというメッセージでもあり、メディアの方が記事を書きやすいという意味でも有効です。濾過されていない生々しい言葉での情報発信は、経営者だからこそできるプレスリリースの表現であり、中小企業の広報PRにおける大きな武器のひとつだと言えるのではないでしょうか。
プレスリリースの情報の裏付けは日常的なSNSでの発信で
しかし、いくらユニークなプレスリリースを書いてメディアの方に興味を持っていただけたとしても、取材に至るまでにはもう少しハードルがあります。特に初めて取材する先については、メディアの方はプレスリリースの内容の信憑性や取材先としての企業の妥当性について入念に検証されることがほとんどです。その際に信用の足しになるのが、SNSやオウンドメディアでの企業の日常的な発信だと考えます。
プレスリリースはすべての情報を盛り込むことはできませんが、どんな思いで事業をやっているのか、どんな活動をしているのかというのは、日常的な広報PRとして発信することが可能です。プレスリリースの内容と日常的な発信の整合性が取れていることが前提にはなりますが、そのような発信は取材するに値する企業なのかという判断のポジティブな要素になるほか、メディアの方が記事の構想を練る際の材料にもなります。
広報PRの大きな起点はプレスリリースであることは間違いありませんが、常日頃から地道な発信をすることも、成果をあげるうえで大切な要素のひとつです。そして、経営者が日常的に発信することで、企業としての独自性をさらに強めていくことができるのではないでしょうか。
まとめ:プレスリリースの恥はかき捨て
今回は中小企業ならではのユニークなプレスリリースの書き方について解説しました。多忙を極める経営者にとって自ら挑戦して書いてみるというハードルは非常に高いと思います。しかし、周りを見渡してみると、そこまで経営者が広報PRにコミットしている企業はほとんどありません。
経営者が直接想いを発信すること自体にも価値があり、埋もれない大きな理由にもなります。経営者という肩書はいったん横において、広報初心者としてまずは一度発信してみてはいかがでしょうか。不格好で粗かったとしても、頑張って挑戦する姿は誰かの心を必ず打つはずです。
本記事が、プレスリリースに迷う経営者の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする