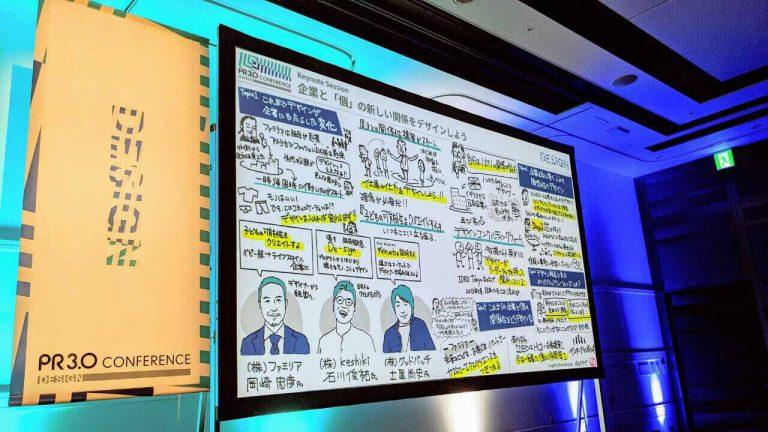広報PR活動における情報発信手段のひとつであるSNS。「ファンづくり」を目的にSNSアカウントを作成したものの、本格的な運用やプレスリリース配信との連携に課題を感じているという広報PR担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。
プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を運営する株式会社PR TIMESでは、2024年4月26日にユーザー会を開催。昨年からX(旧 Twitter)の本格運用を開始した株式会社セブン銀行ブランドコミュニケーション部の能勢恵美さんと村上陽祐さんにご登壇いただきました。本格的にXを運用開始した背景、プレスリリースとの連携や使い分けなど、広報PR思考のファンづくりについて話を伺いました。

株式会社セブン銀行 ブランドコミュニケーション部 部長
ダウ・ジョーンズ社にてウォール・ストリート・ジャーナル日本版の立ち上げに参画したのち、ブルームバーグ日本支社でマーケティングマネージャーとして、外資系企業の日本でのコミュニケーション戦略に携わる。その後、MS&ADインシュアランスグループホールディングス入社。2022年2月よりセブン銀行に入社し、2024年4月からブランドコミュニケーション部 部長となりブランド戦略も統括。

株式会社セブン銀行 ブランドコミュニケーション部 グループ長
広告代理店やEC運営会社を経て2014年セブン&アイグループの株式会社セブンネットショッピングへ入社。ECサイトのデジタルマーケティングを担当。2023年3月、セブン銀行に入社し、企業広告やデジタルコミュニケーションを担当。2024年4月からブランドコミュニケーション部 ブランディングG グループ長となりブランド戦略を推進。
本当の意味でのファンづくりに向けた公式SNS運用
──セブン銀行では、昨年からX(旧 Twitter)の公式運用をスタートされたそうですが、その背景を教えていただけますでしょうか。
村上さん(以下、敬称略):はい。Xの公式アカウントそのものは2020年からありましたが、毎日同じようなサービス紹介の投稿をしている状態でした。セブン銀行は支店を持たない金融機関ということもあり、お客さまの声を直接聞く機会がほとんどありません。だからこそ、SNSからATMを利用するお客さまの声を拾い上げて、サービスに反映するという流れをつくることが大切だと思い、本格的に運用することにしたんです。
2023年2月にSNS運用業務が旧コーポレートコミュニケーション室へ移行されたこともきっかけのひとつで、運用の課題や改善点を洗い出し、「運用ルールとガイドラインの作成」「チャンネルとコンテンツの整理」「KPIの設定・検証体制」という情報発信体制の基本を構築。お客さまの声を拾う活動に加え、よりプロアクティブに伝えたい情報を発信し、双方向のコミュニケーションによってファンづくりに取り組んでいます。
能勢さん(以下、敬称略):また、これまで経営企画部の中にあったコーポレートコミュニケーション室が「ブランドコミュニケーション部」に格上げされたのですが、これは、今後セブン銀行グループとして企業価値の向上やブランド力の強化を目指すうえで、独立した部署で取り組むほうがよいという考えからでした。

──現在のSNSの運用体制についても教えていただけますでしょうか。
村上:ブランドコミュニケーション部の下に、「オペレーション統括部(ATMコールセンター)」と「バンキング統括部(コンタクトセンター)」が配置され、連携を取って運用しています。
オペレーション統括部は、「ATMの使い方がわからない」「ATMが使いにくい」など、メンション付きでXに投稿された声に対するインバウンド対応と、「負の投稿」に対するアウトバウンド対応が主な業務です。一方、バンキング統括部の業務は、主にセブン銀行の口座やカードローンなどに関する問い合わせに対してのインバウンド対応になります。
──ファンづくりの実現に向けて難しかったことなどはありますか。
村上:当初はお客さまからのリアクションがほとんどなく、投稿内容などの見直しを検討する必要があると思いました。セブン銀行は新商品やキャンペーンをなかなか展開しにくいアカウントのため、Xの中にいるお客さまやフォロワーとのコミュニケーションを取るのが難しいと感じています。投稿する企画を考える際にも、われわれのような金融機関にとってどのようなコミュニケーションの取り方が最適なのかを見極めるのに苦労しました。
──そうした課題をどのようにして解決していったのでしょうか。
村上:運用方針を見直し、まずはこれまで1日3本投稿していたものを1日1本に削減しました。何が一番お客さまに伝わるのかをしっかり見極めた上でコンテンツを検討していくべきだと思ったからです。
コンテンツについても、これまでは「キャッシュレス決済の現金チャージができますよ」「セブン銀行口座は7時~19時までATM利用手数料無料!」というように、ひたすらサービスを訴求する投稿をしてきたものを、お客さまとの対話が生まれる内容も増やしていきました。
また、インプレッションやエンゲージメント率を軸にして、投稿内容が良かったのかどうかを検証・改善していくことも、新たに始めたことのひとつです。

認知向上とファンづくりに向けて行ったこと
Xの公式運用をスタートし、ファンづくりに取り組むセブン銀行。ここでは、同社のSNSの戦略立案をサポートする株式会社NAVICUSの中村さんも交えて、お話いただいた公式SNS活用のポイントをまとめています。
アンケートやクイズなど親近感の醸成を意識
──Xで投稿する内容はどのように決めているのでしょうか。
中村さん(以下、敬称略):セブン銀行さんは、国内に約27,000台のATMを設置し、年間約10億件のお取り引きを生み出していて、今ではみなさんにとってのライフラインとも言えるATMサービスを提供しているのですが、「こういうサービスを展開しています」という投稿だけでは、そのときにサービスのことを気にしている方にしか反応していただけません。
そうではなく、クイズ形式の投稿でXユーザーが気になるポイントをつくり出したり、気軽に意見を反映できるアンケート形式の投稿をしたりと、投稿を見たユーザーに参加していただくことで、双方向のコミュニケーションの場となるコンテンツづくりを意識しました。また、動画で見せるほうがより伝わりやすい内容は動画コンテンツで投稿しています。
──実際クイズやアンケートなどの反応はありますか。
村上:ありますね。アンケートはワンクリックで回答できる手軽さも、反応の良さにつながっていると思います。回答部分には、われわれが訴求したい内容を入れるよう意識しているので、回答した人だけでなく結果を見たほかのXユーザーにも「セブン銀行はこんなことができるのか」という気づきになってもらえたら嬉しいですね。
生活者が共感できるコンテンツとターゲット選定
──「#〇〇の日」に絡めた投稿やオリジナル企画など、ユニークな投稿が多く見受けられますが、これにはどのような意図があるのでしょうか。
中村:セブン銀行の公式Xアカウントをご存知ない方や、まだライトファンにもなっていない方が、「#〇〇の日」に便乗して投稿をキャッチしてくれることもあると思い、投稿しています。例えば、3月12日の「駄菓子の日」には懐かしい駄菓子にちなんで「千本引きチャレンジ」という投稿をしたり、3月7日の「魚の日」には魚へんの漢字クイズを投稿したりしています。
サービスに関することだけではなく、生活者が共感できるストーリーに乗せたコンテンツの発信を通して、「セブン銀行はこういうコミュニケーションを取ってくれるんだ」と親近感を持っていただきたいと思っています。
また、キャンペーンを実施する際には、セブン銀行に関心のあるユーザーにしっかりフォロワーになっていただくため、ターゲット選定も意識しているポイントのひとつです。その結果、キャンペーンを入り口としてフォロワーになってくださった方が、キャンペーン終了後もフォローを外すケースが少なくなりました。クイズなどのコミュニケーション投稿を通して毎日の楽しみをつくっていくことを意識したことで、フォロワーの保持率が高まったと思います。

プレスリリース・SNSの連携と使い分け
積極的、かつスピード感あるプレスリリース配信を推進
── セブン銀行では、プレスリリース配信の体制も社内で少し変化があったそうですね。
能勢:以前はプレスリリースの配信については比較的受け身の印象でした。外に出すべきネタがたくさんあるのに、とても消極的な姿勢だったと思います。それではメディアへの露出は広がらないですし、セブン銀行をしっかり認知してもらうためにも、積極的にプレスリリースを配信していきましょう、というメッセージをチームのメンバーをはじめ、社内の関係部署にお伝えしました。
先ほどXでは投稿数を減らして質を高めるという話が出ましたが、プレスリリースに関しては配信数が多いほど、メディアとの接点が見つかるので、量も出しながら質も高めたメッセージを発信していくことが大切だと思っています。
また、以前はプレスリリースを配信する場合には、1週間前には申請しなくてはいけない部署もありましたが、そこもスピード感を持って配信ができるように社内の仕組みを変えました。
──これまでの仕組みを変えるにあたって、どのように社内の理解を得たのでしょうか。
能勢:広報PRを担当している方の中には、組織の中でどのようにして情報のハブになれるのか、どうすれば情報が上がってくるのかという課題を持っている方も多いと思いますが、私自身は、こちらからプロアクティブに動くことによって、社内のステークホルダーのマインドを変えることを重点的に取り組んできました。
例えば、どの部署でどのような取り組みをしていて、どれをプレスリリースにしたいのか、各部長宛にメールを一斉配信するということを年に何度かしています。そこで上がってきたものに関しては、こちらから情報を取りに行きますし、そのプロジェクトが無くなったりローンチが遅れたりした場合でも、必ずその部署に確認をします。
メディアをはじめ、社外の人は社内のことは知りません。取り組みの大小に限らずそれが会社の目指す方向性に合っているのであれば、どんどん積極的に情報発信するという形で、社内の人を巻き込んでいくのがよいと思います。
プレスリリースはメディアへ、SNSは生活者へ
──プレスリリースとSNS、どのように使い分けをされているのでしょうか。また、どのように連携しているのでしょうか。
能勢:使い分けでいうと、プレスリリースの対象は基本的にはメディアです。そのメディアにきちんと伝えたい内容を理解していただけるように、フォーマットの基本形に沿って情報をまとめています。
ポイントはファクトベースで書くということ。「なぜ取り組むのか」「それを通じてセブン銀行が何を実現したいのか」という部分にフォーカスしてプレスリリースを作成しています。
村上:Xの投稿は生活者のみなさまを意識した内容になっていて、行動変容を起こさせることを目的にしています。「#〇〇の日」など、セブン銀行とは直接的には関係のないユニークな投稿をする一方で、きちんと訴求していきたい情報もあるため、昨年からはプレスリリースの情報をSNSでも投稿するようになりました。
ただ、プレスリリースのSNS投稿は、見せ方も含めて検討の予知があると感じています。
──プレスリリースとSNSが連携した事例で、反響の大きかったものなどはありますか。
能勢:セブン銀行のATMを通じて対象団体に募金をした方に、環境貢献活動をコンセプトにしたNFT(非代替性トークン)のデジタル作品をノベルティとして配布する「セブン銀行ATMでNFT募金キャンペーン」は、反響の大きかった事例のひとつです。
NFTという新しいテクノロジーを使っていることに加え、それが社会貢献活動にもつながるというスキームで、多くの新しさが詰まったキャンペーンだということを、プレスリリースできっちり説明しました。
「どうしてこの取り組みをすることになったのか」「NFTのこの絵は何を意味しているのか」という部分にフォーカスしたプレスリリースになっています。
──プレスリリースが背景やストーリーにフォーカスしているのに対し、SNSの投稿はそれをどのようにして生活者のアクションにつなげるのかに主眼を置いているそうですね。
村上:そうですね。プレスリリースがメディアに対して、環境配慮など「社会性」の部分をファクトベースで出していくのに対し、Xの投稿では生活者の方に行動変容を起こさせることを目的にした投稿を意識しました。
セブン銀行ATMでNFT募金キャンペーン

参考:環境貢献活動をコンセプトにしたデジタルアートがもらえる『セブン銀行ATMでNFT 募金キャンペーン』を実施!
参加者からの質問|SNS上の「負の声」を商品開発に活かす
──以前、Xを運用していたときに、カスタマーサポートから「あまり負の声を拾われると困る」という反応が出たことがありました。セブン銀行さんでは、SNSの声をコンタクトセンターの方とも共有されてサービスに活かしているということでしたが、社内から同様の反応はありませんでしたか。
村上:当社の場合は、コンタクトセンターのメンバーがそういうコメントを探しています。セブン銀行をメンションしていなかったとしても、「セブン」「ATM」というキーワードで検索をして、「使いにくい」という声を見つけると、その投稿に対してコメントを残していくということをしています。もともとその点を目的としていたので、積極的に声を拾いに行っていますね。
能勢:「負の声」をどのように商品開発に結び付けていこうかという意識で、声を拾いにいくという感じですね。
電話やWebでの問い合わせをするまででもないけれど、私たちに対して何かしらの不満を持っているサイレンスカスタマーの声は、SNSが一番見つけやすいと思うんです。その声を拾っていくことによって、私たちが掲げている【お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。】というパーパスの実現につながっていくと思うので、特に力を入れて取り組んでいます。

まとめ:双方向のコミュニケーションでファンづくりを実現
SNSを活用して生活者とのコミュニケーションを創出し、プレスリリースとの連携でより深い情報も広く届けているセブン銀行。
同社が取り組む広報PR思考のファンづくりのポイントは以下の通りです。
- SNS、Xの本数をあえて減らしてコンテンツを重視する運用方針に転換
- セブン銀行自体に親しみをもってもらえるアカウントに
- 誰に何を届けたいか、どんな行動変容が起きてほしいかをイメージした発信を徹底
- プレスリリースとSNSが相互に連携を図ることでリーチを最大化
- SNS上の負の声も商品開発に活かすために積極的に拾う
これらのポイントは金融業界だけでなく実店舗を持たない企業や、生活者の声を拾いにくい業種にとっても、参考になる内容だったのではないでしょうか。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする