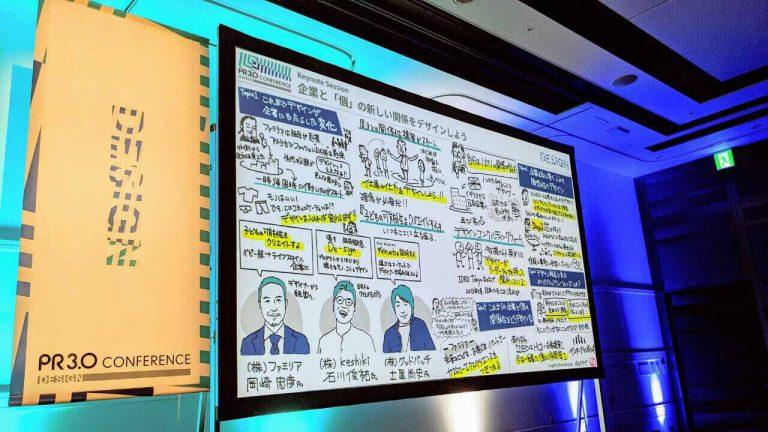プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を運営する株式会社PR TIMESは、サービスの利用の有無にかかわらず、広報PRについて学びたい方を対象としたセミナーを定期的に開催しています。2025年7月10日には神戸新聞社とANCHOR KOBE(神戸・三宮のビジネス交流拠点アンカー神戸)の後援で、「神戸発の企業が全国展開するための広報戦略 ~中小企業広報と新聞記者の視点から学ぶ~」をテーマにセミナーを実施しました。
第一部では、創業30周年を迎えるアパレルブランドを展開する株式会社クロシェから村岡乃里江さんがご登壇し、広報戦略や情報発信の工夫を紹介。第二部では神戸新聞社の谷口夏乃さんが、記者・メディアの視点から「取材したい企業」のポイントを解説しました。本レポートでは、当日のお話をもとにまとめています。
※所属や役職はすべて登壇当時のものです。

株式会社クロシェ マーケティンググループ リーダー/マーケティング・広報・人事
大学卒業後、広告代理店で新聞・雑誌の媒体を担当。その後、2つの出版社で雑誌広告の営業に従事。出産を経て、2010年に神戸のアパレル企業クロシェのプレスルーム立ち上げに伴い入社。EC運営、広報、人事、マーケティング等を歴任。2021年に配信したパンプスのプレスリリースで「プレスリリースアワード2021特別賞」を受賞。

神戸新聞社 編集局経済部
1998年千葉県市川市生まれ。2021年神戸新聞社入社。報道部で半年間の警察署担当を経て、同年10月に丹波総局へ赴任。地域のイベントから行政ニュースまで幅広く取材に従事。24年3月から現職。学生時代からファッションに強い関心を持ち、アパレル業界を中心に担当するほか兵庫県内の地場産業や中小企業関連の話題もカバーする。
メディアに届くナラティブな発信|クロシェ
神戸市に本社を構える株式会社クロシェは「ここち良さを、あたらしい視点から」を企業理念に、レディースアパレルを中心とした5つのブランドを展開。主力ブランド「farfalle(ファルファーレ)」のプレスリリースは、「プレスリリースアワード2021 特別賞」を受賞しました。
ECやポップアップ、常設展など複数のチャネルを活用し、新規事業にも挑戦する同社の広報PR活動について村岡さんにお話いただきました。
事業発展につながる出会いを商品ではなく企業軸から
──まず、クロシェさんが広報PR活動に積極的になったきっかけを教えていただけますか。
2020年ごろ、ホームページや取引先を通じて少しずつ取材依頼が入るようになり、取材を対応する人が必要になったのがきっかけでした。当時、EC運営やSEO対策に協力いただいていた方から勧められて、「PR TIMES」でのプレスリリース配信を始めたのが最初の一歩でしたね。
──未経験から広報PR、大切にしてきたことを教えてください。
広報設置の目的は「事業の発展につながる出会いや関係をつくる」ことでした。IRやブランド広報、商品広報、採用広報、社内広報などさまざまな形がありますが、クロシェでは「企業広報」としての活動を重視。ブランドや商品を取り上げてもらうというよりは、まず企業そのものに注目していただくことを目指しました。
社長の経済団体や各種交流会での活動がメディアに取り上げられ、そこから商品紹介や売り上げにつながっていく。そうした流れを広報PRの役割として大切にしてきましたね。
──きっと手探りの日々だったと思います。振り返ってみて、いかがですか。
そうですね。広報PRはまったくの未経験で、「広報PRって何をすればいいの?」という状態からのスタートでした。ただ、広報PR活動をやるかやらないかでいえば、間違いなくやったほうがいいと自信を持って言えますし、「経営の一環」として広報PRを置くことは、とても意味があると思います。
スタッフ総出が続いたテレビの反響
──クロシェさんはさまざまなテレビで取り上げられていますが、放送後の反響はいかがですか。
もっとも大きな反響があったのは、『ガイアの夜明け』です。ECサイトのサーバーが一時的に落ちてしまうほどのアクセスがあり、売り上げも驚くほど跳ね上がりました。放送後しばらくはスタッフ総出で出荷作業に追われていましたから、相当なインパクトだったと思います。
必ずしも反響があるとは限りませんが、常に準備を整えておくことが必要ですね。年に2回ほどそうした大きな反響を生み出せるよう、自身の小さな目標として掲げています。
──そのためには、定期的に多くの方の目に触れるような日々の情報発信が必要ですね。情報発信をする際の工夫を教えていただけますか。
「どういう角度から発信すれば響くのか」を常に工夫してきました。
ただ「新商品が出ました」と発信するのではなく、ブランド担当者の思いをヒアリングして、伝える。どういう気持ちで企画したのか、どんなお客さまを想定しているのか、ブランドのタグラインやコンセプトとどのようにつながっているのかを整理して反映させています。
また、「お客さまを中心にした開発」や「お客さまの声から生まれた商品」であることが伝わるよう、お客さまの困りごとやリクエストに応えた背景をしっかり言葉にするよう心がけています。
──プレスリリースやSNS、複数の手段を使っている中で、情報によって使い分けていたり、発信する内容を変えていたりしますよね。
そうですね。ブランド側が発信するInstagramなどのSNSでは、夢のある世界観を大切にしているため、あまり裏側の部分は見せたくないというのが本音です。一方、プレスリリースでは、SNSには載せない制作過程での苦労などの裏側を丁寧に拾い上げて伝えるようにしています。
プレスリリースは「誰が」「どんなシーンで読むか」によって受け取られ方が変わります。すべての人が最後まで読んでくれるとは限らず、1本だけ目にする方もいれば、継続的に読んでくれる方もいます。そのため、プレスリリースは1本ごとに「一話完結」でありながらも、クロシェがどのような企業なのかが伝わるような「ナラティブ(ストーリー)」を意識し、ヒストリーやブランドの世界観など企業の姿が浮かび上がることを目指しているんです。
──昨年5月に配信された、バレエシューズブランド「farfalle」のプレスリリースも、まさに担当者の思いが伝わる構成で印象的でした。
「クラシカルシリーズ」の中敷きは、体温で柔らかくとろけて形状記憶する素材「ヒューモフィット」が使われているのが特徴です。そのパンプスが『ガイアの夜明け』で紹介されて以降、「中敷きだけを販売してほしい」という声が多数寄せられていました。
通常は1足1万円前後で販売しているパンプスの中敷きだけを2,000円ほどで販売することで、パンプスそのものの売上に影響が出るのではないかという葛藤もあったんです。そのような感情もまた興味深いと感じ、「お客さまの声を商品化にどう生かすのか」という視点から作成しました。
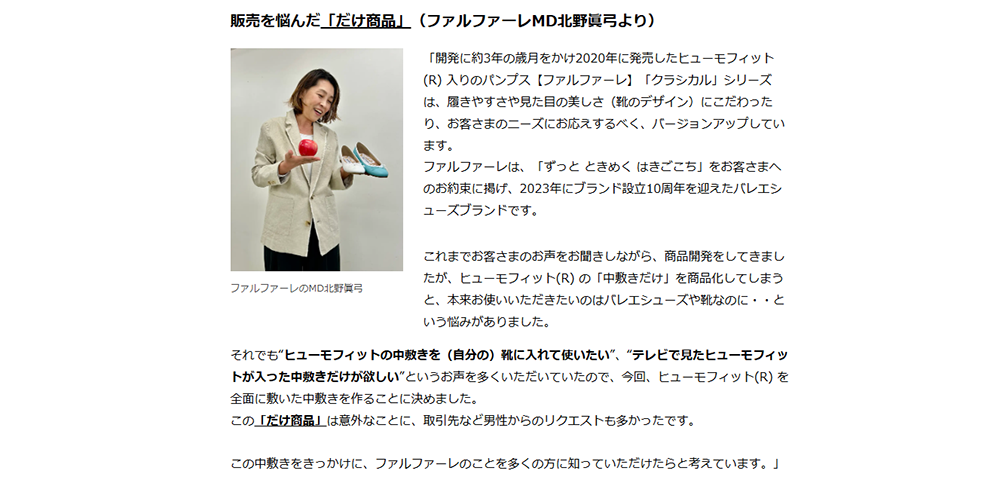
参考:足型を記憶する「ヒューモフィット入り靴の中敷き」だけ販売【farfalle/ファルファーレ】
メディアと「コツコツ」「個別」のコミュニケーション
──広報PRを進めるうえで、普段から社内での情報共有やコミュニケーションは欠かせないと思いますが、対外的なアプローチとしてはどのようにされていますか。
社外の方とのコミュニケーションは、とにかく「コツコツ」と「個別」にアプローチすることが基本です。例えば、スタイリストさんやライターさんなどはInstagramでフォローするところからがスタートで、普段から「いいね」やコメントをすることで交流を重ねていますね。DMで展示会のご案内をすることも。こうした草の根的な一見地味なアプローチも、とても効果的なんです。
また雑誌や新聞などのメディア関係者の方にアプローチする際には、敬意が伝わるよう、必ずそのメディアをしっかり読み込み、特集の特徴や担当者を理解したうえで連絡しています。
時には、あえて一部の方にだけ先に情報を共有する「リーク的な」工夫も取り入れることもありますね。
──メディア関係者限定配信の機能も積極的に活用されていますよね。
はい。プレスリリースはお客さまを含め、良くも悪くも情報が広く伝わります。メディア限定のプレスリリースは、本音を込めたメッセージを書ける場として、個人的な思いも交え、あえてストレートな表現を使っているんです。
ストーリー性のある読み物がアクションを起こす|神戸新聞社
第二部では、神戸新聞社 編集局経済部でファッションを担当する谷口夏乃さんが登壇。経営者の歩みを紹介する同紙の人気企画『マイストーリー』では、株式会社クロシェホールディングスの沼部美由紀社長の取材も行っています。取材に至った経緯や、取材時に大切にしていることなど、記者・メディア視点でのお話を伺いました。
取材準備はホームページで情報収集
──神戸新聞の経営者インタビュー企画『マイストーリー』で、今年の5月から6月にかけて連載されていた沼部社長の記事を拝見しました。とても読み応えのある記事でしたが、取材をすることになった経緯を教えていただけますでしょうか。
ファッション担当になったときに、まずは広報PRを担当する方にご挨拶に伺おうと思いました。せっかくなら取材の機会にできればと思い、当時発売された「farfalle」の中敷きについて、開発の経緯やストーリーをお聞きしたのが始まりです。
取材準備の際、ホームページにある『クロシェものがたり』というコンテンツが強く印象に残りました。創業からの苦労や成長の瞬間など、30年の歩みがエピソードごとにまとめられていて、経営者として活躍する現在の沼部社長の姿しか知らなかった私にとって、とても心惹かれる内容だったのです。
ちょうど『マイストーリー』の担当が自分に回ってきたこともあり、節目やストーリーが豊富な沼部社長に取材をしたいと思ったんです。そのことを村岡さんに伝えたところ、企画が一気に具体化していきました。
──取材準備の際に目にした情報から始まったのですね。
はい。取材の際には、その企業が展開している事業やこれまでの歴史など、オープンになっている情報は必ず確認するようにしています。
「失敗を経験し、そこから成功に至った」というストーリーは、どの企業にとっても学びになるものです。単なる成功事例より失敗を経た成功のほうが説得力があり、共感しやすい。そのような情報が公開されていると目に留まりますね。
──今回の『マイストーリー』は5回連載でしたが、連載の構成はどのように考えているのでしょうか。
『マイストーリー』の構成は、学生時代や会社の現状からスタートし、現在に至るまでを時系列で追うことが多いです。連載なので1話ごとの切れ目や次回へのつながりに気をつけて、枝葉のエピソードを差し込むことを意識しています。
沼部社長の場合、創業当初から掲げてこられた「女性の経済的自立」というテーマは、ぜひ組み込みたい部分だったのですが、クロシェの歴史そのものとは少し異なるテーマのため、どこに入れるか悩みました。『マイストーリー』は通常4話構成ですが、この話を削ってしまうのは惜しいと考え、編集デスクに相談して特別に5話構成にしたんです。そして創業時からの目標が、新しいビジネスを通して30年越しに達成できる見込みということもあり、時系列にも合わせ、はじめに30年の歩みを振り返り、「女性の経済的自立」の話を最後5話に入れました。
背景・ストーリーを深掘りした刺さる長尺記事
──谷口さんが記事を執筆する際、特に意識していることや工夫されている点はありますか。
Web版「神戸新聞NEXT」では字数制限がなくなったことで、紙面では書ききれなかった部分まで丁寧に伝えられるようになりました。
しかし、新聞やテレビ、ラジオも含め各社がWeb発信するようになったことで、世の中には無数のニュースがあふれています。ストレートニュースは企業のプレスリリースとほぼ同じ内容になりがちで、差別化しにくいという課題も出てきました。
そのような中で私たちが重視しているのは、「ニュースに付加価値をどう与えるか」です。背景やストーリーを丁寧に掘り下げた「長尺の読みもの記事」はアクセス数が伸びやすく、読者の共感を得られると拡散され、より広く読まれる傾向があります。関連する記事への誘導にもつながるため、神戸新聞としても近年一層力を入れ、メディアとしての価値を高められるようにしているんです。また、読者の次の行動を促すということも個人的に意識しています。
思わず反応する企業発信の6つのポイント
──普段情報収集される中で「この企業気になる!」となるのは、どのようなポイントですか。
やはり取り上げやすいのは、新商品や新サービスといった「新規性」です。クロシェを最初に取材したきっかけも新商品の発売でしたが、メディアと企業がつながる入り口として、「新しさ」は大きな要素だと思います。とはいえ、新商品の情報だけでは記事にする必然性が弱いので、その背景や開発過程にある苦労や工夫などの「定性的なストーリー」も大切です。例えば先ほどの中敷きのプレスリリースには、開発担当の方の葛藤や思いが赤裸々に書かれていて、とても興味を惹かれます。そこからさらに取材を進めるポイントになるのが、「社会性」や「地域性」。地元との関わりがある企業は自然と関心を持ちやすいですね。
そして、説得力を高めるうえで欠かせないのが「定量的なデータ」です。売り上げの伸びや効果など、数値として示せるものがあれば記事に厚みが出ますし、読者の納得感も高まります。
これらとは少し異なりますが、「周年」は記事に取り上げる理由としてとてもわかりやすく、関心を持ちやすい題材のひとつだと思います。周年のタイミングでプレスリリースを出す企業も多いと思いますが、自然と目に留まりますし、私自身は年初に「今年何周年を迎える企業があるか」を確認するぐらい意識しています。
──ありがとうございます。最後に、谷口さんがいま注目しているテーマなどあれば教えてください。
今、経済部の中で『働き方の今』という企画が進行中で、企業がどのように人材を確保して定着させようとしているのかを取材しているところです。
特にコロナ禍以降、その動きが活発になっているのを感じていて、女性活躍推進法が成立されて今年で10年という節目でもあるので、この10年で企業がどのように進んできたのか、そして今後どのように進んでいこうとしているのかを丁寧に取材していきたいと思っています。
【質疑応答】参加者からの質問に、村岡さん・谷口さんが解答
ここからは、参加者のみなさんから寄せられた村岡さんと谷口さんへの質問の一部を抜粋し、おふたりの回答と合わせてご紹介します。
──クロシェさんではKPIは設定されていますか。具体的な目標設定や指標のようなものがあればお聞きしたいです。
村岡さん(以下、敬称略):KPIとして数値をきっちり設定しているわけではありませんが、リリース後1週間のページビューや転載状況、PR TIMESの管理画面で見られる「PCとスマホの閲覧比率」などいくつかの指標は追っています。当社の場合、PCが約9割を占めるので、スマホ比率が高ければ「一般の方にも届いたのだな」とウォッチしています。また、1本のプレスリリースからどれくらい取材が生まれたかも指標のひとつです。
一方で、「PV数をどこまで伸ばすか」というKPIを前面に置くと、広報PR活動が窮屈になりそうなので、そうした目標はあえて置いていません。事業はチーム戦なので、広報が投げたボールをECやSNSが受けて広がっていく流れが理想だと考えているので、「広報だけのKPI」というよりも、正しく発信できたか、メディアにきちんと届いたかといった部分を大事にしています。
──『マイストーリー』に取り上げられる企業には選定の基準のようなものがありますか。それともデスクに一任されているのでしょうか。
谷口さん(以下、敬称略):もちろんデスクの判断も大きいのですが、それよりも「記事を4話分成立させられるだけの情報があるか」という点が重要です。4話すべてが読み応えのある記事として成立するだけのエピソードが必要になります。
掲載時期が考慮されることも少なくありません。1月は阪神・淡路大震災に関する記事が多くなるため被災企業への取材が増えますし、オリンピックの年には、元オリンピック選手が社長を務める日本酒メーカーを取り上げたケースもありました。こうした情報は、日頃の広報PR担当の方との「実はうちの社長はこんな背景がある」というような会話からヒントを得ることも多いんです。
──新聞記者の方は、情報を探す際にSNSをチェックすることも多いのでしょうか。
谷口:私はSNSから情報を探すことはそこまで多くありません。まずはやはりネットで検索を始め、ホームページなどでも十分な情報が得られなかった場合にSNSへ飛ぶことはあります。情報をさらに集めるための第二手段のような形で使うことが多いです。
理由としては、やはり情報量が多すぎるということが大きいですね。情報の信頼性という部分でも、ホームページのほうが安心だと考えています。
──1日にどのくらいのプレスリリースをチェックされていますか。
谷口:経済記者クラブから届くものが多いときで10件ほど、それに加えて「PR TIMES」をチェックしたり、検索をかけたりすることもあります。足すと、1日30件くらいかなという感覚です。
経済部ではまずデスクがリリースを確認し、担当記者に振り分ける仕組みになっていて、自身に届いたものは必ず目を通しています。一方、PR TIMESでチェックするプレスリリースは、アパレルやファッションなど自分の担当分野に関わるものが中心です。地域の新聞という立場上、兵庫県に関わるものは優先的に確認しますが、ほか地域の企業からの情報などは、取材につなげにくいので流し読みしてしまうこともあります。そういう意味でも、件名などに地名がわかりやすく入っているプレスリリースは目に留まりやすいです。また、私個人宛に直接ご連絡いただいたものについては必ず確認しています。
──最後に、村岡さんに質問です。広報PRを担当するにあたって、新たに勉強されたことはありましたか。
村岡:広報PRを担当するようになってからは、新しく学ぶことばかりだったと思います。前任者がいなかったので、まずは「何から始めればよいのか」ということから情報収集したほどです。「PR TIMES MAGAZINE」を読み込んだり勉強会に参加したりしながら、基礎を身につけていきました。
また、イベントに参加した際には名刺交換をしながら、ほかの方がどんな勉強をされているのかを知るように心がけています。Xで広報PRについて発信している方をフォローして、その方の行動や発信内容から学ぶことも多いですね。広告会社や出版社でのこれまでの経験も役に立っていますが、やはり日々のインプットを意識して積み重ねてきたのが大きいと思います。

まとめ:ストーリー性を重視した発信で自社の魅力を全国へ
今回のセミナーでは、企業とメディアの双方の視点から、ストーリー性を重視した情報発信のポイントなど、実践的な知見が共有されました。そこから見えてきた、地方の企業が全国展開するうえで参考にしたいポイントは以下の5つです。
- 商品だけでなく企業理念や経営者の思いを発信する
- 商品開発の背景や担当者の思いなどナラティブな発信を意識する
- EC・店舗・SNS・メディア露出などを組み合わせて相乗効果を出す
- メディアとの関係づくりは、相手を理解し、使いやすい情報を提供して信頼を築く
- 新規性・社会性・地域性・ストーリー・数値・周年、メディアが注目しやすい要素を盛り込む
今回のセミナーの内容を参考に、今後の広報PR体制の強化や情報発信に役立ててみてください。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする