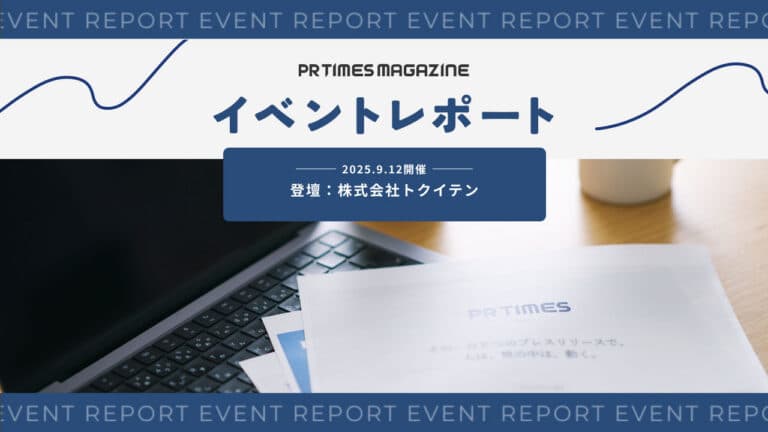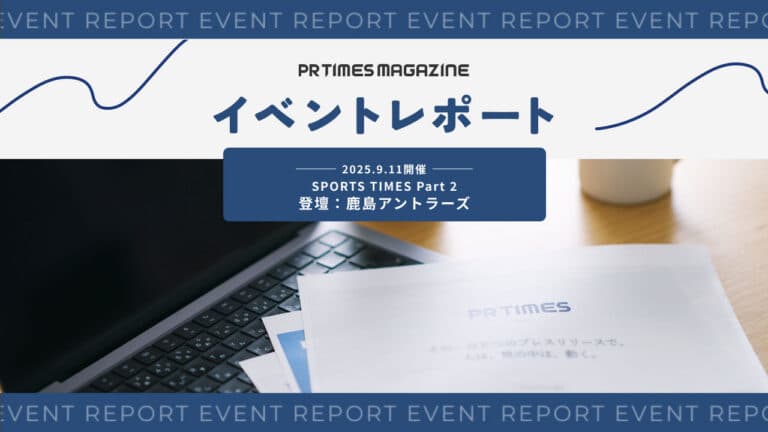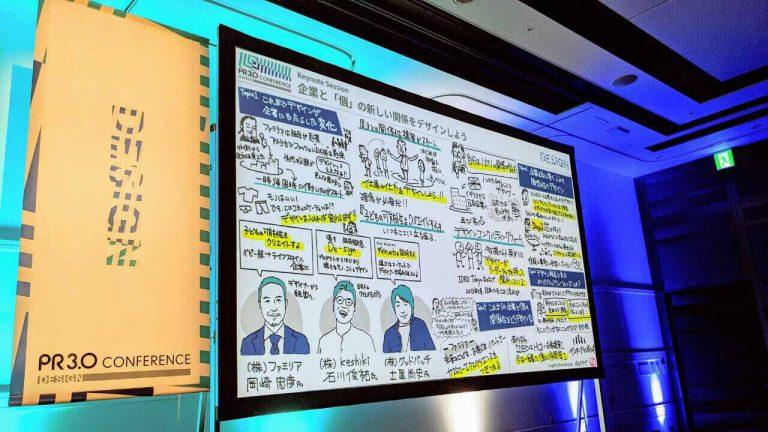試合の勝敗がニュースのメイントピックになりがちなスポーツの現場。しかしその背景には、選手たちの日々の努力やチームの想い、地域やファンとのつながりなど、勝敗を超えたドラマや魅力が数多く存在しています。
そうした背景を広く届けるために、プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を運営する株式会社PR TIMESは、2018年よりスポーツチーム・団体による情報発信を支援する「SPORTS TIMES」プロジェクトをスタート。スポーツチームや団体が自ら発信することで、スポーツ人気の高まりによる経済効果を生み、応援の楽しみを通じて地域と人を元気にすることを目指すプロジェクトです。
PR TIMESは、2025年9月11日には「ファンとメディアを動かし、ブランドを築くJリーグクラブに学ぶ広報PR術」をテーマにスポーツチーム・団体向けセミナーを開催。第一部には、J2リーグ「水戸ホーリーホック」の運営会社である株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック広報部ディレクターの長谷川拓也さんが登壇しました。本レポートは、今季は31節終了時点で首位を堅守し、チーム一丸となってJ1昇格を目指す同チームの広報PR活動について、当日の講演内容をもとにまとめています。
「想いを描き、価値を届ける」情報発信軸
──まず、水戸ホーリーホックの広報PRの体制について教えてください。
ホーリーホックの広報は、昨年までは事業部の一部門として位置づけられていましたが、今年から「広報部」として独立した体制になり、現在は3名で運営しています。具体的な業務分担としては、私が部全体の統括と事業サイドのコーポレート広報を、もう一人がチームや選手に関わる活動を支えるチーム広報、そしてもう一人がデザインなどのクリエイティブ制作を担当、というように分かれています。
一方、SNSでの情報発信やプレスリリース発信・更新などは広報PRの基本業務にあたるため、誰でも対応できるように日ごろから業務や情報をシェアし、属人化しないようにすることを強く意識しているのも特徴です。
──どなたでも対応できるよう、属人化させない体制づくりは大切ですよね。一方で、担当ごとに業務が分かれるなかで注意すべき点もあるかと思います。広報PRとしてのメッセージがぶれないようにするために取り組んでいることはありますか。
日々立ち返る軸として、今季は「想いを描き、価値を届ける」というひとつのコンセプトを定め、以下を広報部内の共通認識として理解しています。
- 想い:情報が感情に届くことを大切にする姿勢(想像力)
- 価値:情報が持つ価値を正しく理解し、最大化する工夫(価値最大化)
- 届ける:情報の正確性・丁寧さ・タイミングを担保する責任(正確性)
毎週の定例ミーティングで、コンセプトから外れていないかを確認したり、それぞれが担当している案件の進捗状況や懸念点などを共有したりしています。社内のコミュニケーションツールも活用しながら、自身の領域に関わらず、何らかの違和感があればその都度指摘をすることを、広報部内で意識していることです。
──日ごろからの共有や、お互いに意見を言い合える環境が大切ですね。話は変わりますが、長谷川さんの中で印象に残っている施策を教えてください。
水戸駅の駅ビル「水戸エクセル」に掲出した巨大な壁面バナーは印象に残っている取り組みのひとつです。「想像力×価値最大化」という視点で実施した施策で、「誰に」「何を届けるのか」に特にこだわっています。
クリエイティブ担当者がいくつかの方向性でデザインを提案してくれた中から部内で話し合いました。駅との親和性を意識して駅ホームの案内板をモチーフにし、「行き先:J1」と掲げることで、「水戸ホーリーホックは今調子がいいチームなんだ」と自然に感じていただけるような仕掛けをしています。ファンやサポーターに喜んでもらうことはもちろんですが、まだ水戸ホーリーホックを深く知らない地域の方々の目に留まるものにしたいと考えたものです。
おかげさまでSNSでも好評でしたし、駅ビル側にも大変喜んでいただきました。屋外広告や交通広告の業界誌にも取り上げられ、狙っていた以上の効果を実感できた企画だったと思います。

移籍先のファン・サポーターも視野に、選手自らの言葉で届ける
──スポーツチームの情報発信には選手人事に関するものも多いと思いますが、広報PR視点で意識されていることはありますか。
プレスリリースなどで情報を発信する際には、移籍先のファン・サポーターも移籍する選手も「水戸ホーリーホックでよかった」と思っていただけることを意識しています。移籍はステップアップであるものの、チームを裏切るような後ろめたさみたいなところが多少あると思います。ただ、選手自身の言葉で移籍への決意を発信することで「そうではない」ということを伝えたいと思っています。
一人ひとりの選手が強い意志を持ってこのクラブに来たこと、キャリアを歩む中で「移籍」という大きな決断をしたことを、情報発信を通じて水戸ホーリーホックのサポーターはもちろん、移籍先のサポーターにも感じていただきたいですね。両クラブのサポーターにとって「良い選手である」ことを認識していただくことが、選手にとってもクラブにとっても価値向上につながるのではないでしょうか。
──スポンサーやパートナー企業との取り組みに関する発信を拝見していても、ファンやサポーターに向けたメッセージ性が強く印象的です。
パートナー企業関連の情報発信で意識しているのは、コメントの見せ方です。契約締結に関するリリースには、「〇〇株式会社 代表取締役社長 〇〇からファン・サポーターのみなさまへ」といった小見出しを付け、メッセージを記載しています。
最近では「J1昇格に向けてがんばりましょう!!!!」と、熱量のあるコメントをいただくことも多いのですがファン・サポーターの気持ちが上がるだけでなく、パートナー企業に対しても好印象を持っていただけて、その企業のサービスを利用するきっかけになることもあります。双方にとってメリットがあるので、このような発信の仕方は大切にしていきたいですね。
──ファン・サポーターに向けてと同様に、全国への認知拡大も重要かと思いますが、そのあたりはどのように考えていますか。
地元メディアさんとのコミュニケーションは比較的円滑にさせていただいていますし、Jリーグはスポーツ関連のメディアに向けた情報発信の仕組みが整っているので、スポーツ関連の情報はきちんとメディアに届くようになっているんです。
一方で、スポーツ以外へのアプローチは難易度が高いと感じています。そもそも接点がないことも多いので、そこはプレスリリース配信を通じて、「地域のスポーツチーム×〇〇〇」という文脈でスポーツ以外の軸を大切にしながら、より広い流入を期待しています。
──スポーツ以外の軸でのアプローチは各チーム難しいと伺いますね。これまでで成功した事例、反響があった事例などはありますか。
ひとつは、全国知的障がい者サッカー選手権「太平電業カップ」を開催したときのプレスリリースです。サッカーに関わる大会ではありますが、どちらかというとインクルーシブの文脈が強く、福祉関連の領域へどうアプローチしていくかが課題でした。プレスリリースだけがきっかけだったのかを判断することは難しいですが、複数のメディアからの取材があり、実際に記事にもなったので、それは成果として捉えています。
参考:全国知的障がい者サッカー選手権「太平電業カップ」を開催!
また、ソーラーシェアリング事業ではプレスリリースの配信に合わせて、「PR TIMES STORY」も活用しました。今までホーリーホックが取り組んできた農業とは何なのかというところと、次にどんなステップを目指しているのかを、プレスリリースよりも「読みもの」として読みやすい短編小説のようになることを意識しながら書いたんです。公開して数日後には問い合わせもあったので、取り組んでよかったなと思う事例のひとつですね。
参考:水戸ホーリーホック、「GXプロジェクト」ソーラーシェアリング事業を開始
参考:『再エネと農業』―地域に根ざすサッカークラブ、水戸ホーリーホックのグリーントランスフォーメーションへの挑戦

地域密着型!相思相愛の関係を構築
──ここからは、水戸ホーリーホックが積極的に取り組んでいる「ホームタウンPR大使」の活動について、詳しく教えてください。
簡単に言うと、ホームタウンに指定している15市町村それぞれに担当の選手をつけ、広報PR合戦のような形で活動をしています。ファン・サポーターは「推しの選手」を通じて地域との関係を深めることができ、地域は街を盛り上げることができるという活動です。
一方、選手側も在籍期間中の生活を公私ともにより豊かにすることができ、結果的に「相思相愛型」の活動が生まれると考えているんです。水戸市のPR大使になった選手が、「休日に水戸市のカフェに行ってみようかな」と考えてお気に入りの店を探し、実際に訪れた様子をSNSに投稿する。それを見たファン・サポーターは「水戸にこんなカフェがあるんだ」と知り、地域に足を運ぶきっかけになる。また、クラブとして「選手がどこそこに行きました」と発信をサポートすることで、ファン・サポーターに喜んでもらえる。さらに、ホームタウンを回遊してもらうことにもつながり、多方面にメリットが生まれる、というわけです。
ホームタウンPR大使の活動では、自治体の広報PR活動にも選手を積極的に活用していただいています。市報や行政のPR動画など行政のプロモーションに貢献することで、クラブと自治体の双方にとって良い循環が生まれているのを実感しています。このWin-Winの関係づくりや、地域の文脈でネタを生み出し発信していく点が評価され、2024年にはJリーグの「シャレン!AWARDS」でメディア賞をいただくことができました。
──自治体と一緒に活動することで、地域全体での応援に一層つながりますね。ホームタウンPR大使の選手を活用したケースで、反響の大きかった取り組みは何かありますか。
常陸太田市のYouTube企画「現役Jリーガーをバンジーからぶっ飛ばしてみた」は、大きな反響があった取り組みのひとつではないでしょうか。
常陸太田市は、日本で2番目に高いバンジージャンプができる橋「竜神大吊橋」を観光名所として押し出しており、当時常陸太田市のホームタウンPR大使を務めていた安藤瑞季選手に依頼があったんです。
実際にバンジージャンプをした様子が、市観光PR動画として公開。安藤選手はバンジーを飛んだ次の試合でハットトリックを決めるという偉業を成し遂げ、ファン・サポーターの間では「縁起のよい橋」として注目されているんです。チームにとっても良い広報PR活動になったと思います。
──聖地巡礼のスポットにもなりそうですね。ほかにも、地域と連携した農業や再生可能エネルギーに関する活動もされているかと思いますが、どのようにして始まったのでしょうか。
ホーリーホックは「地域の課題はクラブの課題」という認識を持っていて、地域のさまざまな課題をクラブが先導して取り組むことで、その課題を広く認識してもらうことを大切にしています。そのなかで、2021年9月から始めたのが「GRASS ROOTS FARM」という農業事業でした。
茨城県は農業大国である一方で、高齢化によって耕作放棄地が年々増加しているという課題に対し、チームとして何か啓発的な取り組みができないかと考え、農事業への参入を決意。農業が事業として成り立つ姿を示すことで、農業に興味を持つ人や新たに参入する人が増えればいいなと考えたんです。
2025年6月からはさらにステップアップし、太陽光発電を運営しながらその下で農業を行う「ソーラーシェアリング事業」も始めました。事業として大きな効果があっただけでなく、従来のスポーツクラブ運営だけでは得られなかった農業関連メディアとのつながりも生まれましたね。今後は、畑で収穫した野菜をホームゲームで販売したり、活動にストーリー性を持たせることによって、さらにメディアや地域との接点を広げていきたいと考えています。
──地域課題との関わりとして、今年5月からは新たに空き家についての取り組みもスタートされたそうですね。
そうなんです。これも地域課題から新たなサービスにつながった取り組みのひとつです。茨城県には約19万6200戸(2023年時点データ)もの空き家が存在していて、その数は年々増加しているといわれています。この問題に対し「自分たちに何ができるのか」と考えた際に、クラブが一時的な窓口となって空き家に関する相談を受け付ける「ホーリーホックの“空き家”相談窓口」をスタートしたんです。
プレスリリース配信後には実際にいくつかの相談が寄せられ、内容に応じて専門企業や行政につなぐなど、最適な解決方法を一緒に模索しています。その後、2025年8月には茨城県と「空き家に関する連携協定」を締結することができました。クラブと行政が協力し、この地域課題に本格的に取り組んでいくストーリーを描けたことは、大きな成果だと言えると思います。
「露出しにくい環境」でもいかにメディアとつながるか
──最後に、メディアリレーションズに関して伺います。地域に密着した活動を大切にされる中で、メディアとの関係構築において大切にされていることはありますか。
茨城県は日本で唯一、県域の民放テレビ局が存在しない県なんです。そのため県内で流れる番組は東京キー局のものが中心で、地域情報に特化した番組がとても少なく、地域の情報がユーザーに届きにくい状況で、水戸ホーリーホックとしても露出が限られてしまいます。
だからこそ、スポーツ担当のメディアだけでなく、地域メディア全般とのコミュニケーションを丁寧に築いていくことを大切にしています。シーズンの始めと終わりといった節目に必ず定期的なあいさつ回りを行い、私自身だけでなくクラブ代表も同行してごあいさつさせていただく。また、担当してくださっている記者のほかの記事にも目を通し、「地域のスポーツチーム×〇〇〇」といった切り口で、担当者にとっても価値のある情報を一緒に作り出すことを意識しています。スポーツ以外の分野を取材されている記者と取り組むことが多いため、その方が普段どんな記事を書いているのかを知ることが必要です。
プレスリリースに関しても「出す前の段階」でのコミュニケーションを重視し、「現在こういう案件が進んでいて、リリースを予定しているが、どんな形なら取り上げやすいか」といった相談を率直にすることもありますね。取材につなげられるようにという思いはもちろん、プレスリリースの質がブラッシュアップされることにもつながっています。
──とても積極的にメディアに働きかけていらっしゃるんですね。貴重なお話の数々、ありがとうございました。
まとめ:地域もメディアもWin-Winを目指す
「Win-Winになることは惜しまずに行うのがチームのスタンス」と語る長谷川さん。地域への貢献を起点に「本気で応援したい」チームになるための活動やリソースが限られる地域メディアとの関係づくりが印象的でした。Jリーグクラブにおける広報PR活動としてはもちろん、スポーツ・団体全体へのヒントになったのではないでしょうか。
続いて、第二部の登壇者・株式会社鹿島アントラーズFCの松本隆吾さんのレポートです。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする