本記事は、公益財団法人筑波メディカルセンターで広報を担う、遠藤友宏氏に監修いただきました。
自院の利用者を増やしたり、地域住民に強みを伝えたりといった施策を通して認知拡大を図る「病院ブランディング。自院ならではの魅力を多くの人に知ってもらうために必要な取り組みですが、具体的な目的や施策がわからないという方もいるのではないでしょうか。
病院ブランディングの効果を発揮させるためには、ブランディング設計や組織づくりも重要です。本記事ではブランディングにおける基本的なフローと実際の成功事例をご紹介します。効果を高める広報PR施策の具体例も解説していますので、自院の魅力・強みを発信したい方はぜひ参考にしてください。
病院ブランディングとは?目的と必要性を解説
病院ブランディングは、自院のよさや強みを広く知ってもらい来院につなげるために必要な施策です。「ブランディング」と聞くと企業経営のイメージを抱くかもしれませんが、医療機関においてもその需要性が高まっています。まずは病院ブランディングの概要を押さえておきましょう。ここでは、具体的な目的と必要性を解説します。
病院ブランディングの目的と病院経営に必要な理由
情報化社会である近年は、いわば「調べれば行きたい診療科や近くの病院が見つかる」という状態。生活者の選択肢が広がり、SNSなどによる拡散力が劇的に高まった時代でもあります。自院の良さをはじめ、いかに生活者にとって身近な存在であるかを積極的に伝えることで、認知拡大・利用促進効果が期待できるでしょう。
さらに、医師や看護師をはじめとするスタッフを対象とした「インナーブランディング」も重要。人手不足が深刻化する中で、自院で働く意義を知ってもらうことは人材確保につながる可能性があるためです。院内外のあらゆるステークホルダーに自院を発信し、関係性を深めるためには、ブランディングが必要であるともいえるでしょう。
病院ブランディングがもたらす効果
病院ブランディングを実施することにより、以下のような効果が期待できます。
- 地域住民に来院のきっかけを与える
- 既存の通院患者の安心感・信頼感を高める
- 地域や自治体との関係性を強化する
- 理念や方針の共有によるインナーブランディング効果
- SNSや雑誌などメディアへの露出
- 自院を認知拡大する広報PR効果の強化
ブランディングというと、一般的には患者を中心とする生活者が対象と考えがちですが、実際には優秀な看護師を採用するきっかけになったり、離職率を低下させたりといった人材面での好影響が見込めます。また、メディアに露出する機会を増やすことができれば、地域を限定せず幅広いエリアに自院を発信できるでしょう。
病院ブランディングの基本要素と設計の流れ
一般的なブランディングは、利益確保を主な目的としていますが、非営利組織である医療機関は「来院してもらうこと」が重要な目標となります。この目標を達成するためには、理念やビジョンを明文化し、ステークホルダーとの関係構築を図るブランディング設計を検討することが大切です。基本要素と設計の流れを4つのステップに分けて解説します。

STEP1.理念・ビジョンの明文化・ブランドコンセプトの策定
まずは自院の理念や強み、ビジョンを整理し、具体的なブランドコンセプトを策定しましょう。地域性や診療科目といった要素はもちろん、「何に力を入れているか」や「どんな診療・治療に強いと感じているか」を明らかにすることが大切です。
理念とビジョンが明確になると、対外的に発信すべき内容もおのずと見えてきます。強みの核となる部分を固めたうえで、それを中心にブランドコンセプトを構築していくとよいでしょう。
STEP2.主要なステークホルダーとの関係構築を図るブランド設計
コンセプトを策定したあとは、ステークホルダーとの関係構築を図るブランドを設計していきます。重要なのは、主要となる層を把握しておくこと。自院ならではの地域特性や、来院の多い年齢層を軸にペルソナを設定し、その人たちに伝わるブランディングを検討することが肝要です。
例えば、ファミリー層の利用が多い病院であれば、小さな子どもが親しみやすい雰囲気づくりを徹底したり、親子で受診しやすい時間帯に配慮したりといった環境整備につなげることができます。子ども、学生、シニアなど、主要な年齢層に応じた伝え方を再考するきっかけにもなるでしょう。
STEP3.ビジュアルアイデンティティの設計
ビジュアルアイデンティティは、病院ブランディングにおいて重要な施策のひとつです。外観の要となる看板をはじめ、病院のロゴや建物の色彩、内観、配布物などあらゆる「見た目」と自院のアイデンティティを統一させましょう。
特に病院は、患者にとって「痛い」「怖い」といったマイナスイメージが強くなりやすいため、少しでもポジティブな印象を与えるデザイン性が重要。色彩の統一感はもちろん、特定の診療・治療に特化した病院であれば、「骨粗しょう症外来」「頭痛外来」のように対象者にリーチできるわかりやすい表現に変えてみてもよいでしょう。
STEP4.スタッフ全員でブランドを体現する組織づくり
病院ブランディングを展開する際には、院長や医師だけでなく院内スタッフ全体の組織づくりに取り組まなければなりません。スタッフの考え方や業務に差・誤解が生まれないよう、院内研修や行動指針といった施策も含めて全体共有しましょう。
単に共有・統一するだけでなく、スタッフ一人ひとりが自分に関わることとして意識できるかどうかも重要なポイントです。当事者意識を高めることで、病院の理念や思想を自分ごととして語れるようになります。病院の規模が大きくなるほど共有・統一も困難になりますが、中長期的な施策を前提に展開することが大切です。
STEP5.対外的な広報PR活動と効果検証でアップデートしていく
病院ブランディングの効果を高めるためには、病院自体の取り組みや魅力を対外的に発信する活動が必要です。病院ブランディングの一環として広報PR業務に力を入れ、プレスリリースをはじめとするツールやサービスを通じて、積極的に発信していきましょう。
広報PRを続けるうえで、効果検証も重要な作業となります。反響を確認し、継続すべき点と改善すべき点を洗い出すことでブランディングを強化できるためです。
病院ブランディングを支える具体的な広報PR施策
現在、病院ブランディングを検討している方の中には、実際にどのように発信すべきかわからず、悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。自院ホームページの活用はもちろんのこと、広報誌を配布したりイベントを企画したりするなど、さまざまな広報PR施策が提案できます。5つの項目に分けて詳しく解説しますので参考にしてみてください。
ホームページ・SNSでの発信
自院での取り組みを院外へ発信するには、公式情報として公開しやすいホームページやSNSが有用です。コラムやブログでイベントレポートを書いたり、「病院からのお知らせ」のような表題で記事を公開したりするとよいでしょう。
手軽かつ定期的に発信しやすいのは、XやInstagramをはじめとするSNSです。写真・動画も簡単に掲載できるため、イベントの準備から開催後までの様子を段階的に発信することで、スピーディかつタイムリーにコンテンツを公開できます。使用ツールをひとつに限定せず、掲載内容やボリュームに応じて有効活用することが重要です。
病院広報誌・ニュースレターの刊行
病院広報誌やニュースレターは、物理的な広報PRとして実践したい施策です。院内外での出来事やイベント情報などを掲載した広報誌を配置することにより、患者や地域住民、医療関係者など自院に関わる層へアプローチできます。
ホームページやSNSに比べると作業工程も多くなりますが、インターネットを利用しない層に情報を届けるためには特に必要な施策といえるでしょう。なお、以下の記事では、病院ブランディングに有用な広報誌について、メリットや具体的な作り方を紹介しています。こちらもぜひご覧になってください。
地域との接点をつくるイベント・セミナーの開催
現在通院中の患者や、過去に来院経験がある人以外の層へ認知を広めるために、イベント・セミナーの開催も検討してみましょう。特に地域密着型のイベントは、病院を知らない人との接点を作る広報PR施策として有用です。
イベントをきっかけに健診・検査を促したり、「〇〇な症状があったら受診してみよう」と候補に入れてもらえたりといった結果が期待できます。地域とのつながりを発信する際にも役立つため、積極的に取り入れたい広報PR施策の一環といえるでしょう。
プレスリリース・メディアリレーションズ
プレスリリースをはじめとするメディアリレーションズは、テレビ・新聞・雑誌といったメディア関係者にアプローチするために有用です。地域住民へ直接届けるのではなく、メディアを介して生活者が自院の情報を目にする間接的な施策ともいえます。
ホームページやイベントは生活者が能動的に触れる機会であるのに対し、メディアは受動的な要素が強く、来院を考えていない層にも情報を届けられる点がメリット。院長のプロフィールや医師・看護師の実績など詳しい情報があれば、自院ならではの実績・強みを伝える機会にもなります。
患者が親しみやすい院内設計を検討する
「自院らしさ」を強化するためには、患者のペルソナを想定した院内設計が重要です。患者が来院しやすく、通院が苦にならないような親近感を持たせることを重視し、自院のブランドコンセプトに合った設計を考えましょう。子どもの患者が多い病院を例にあげると、以下のような病院設計を提案できます。
- 外観・内観に親しみやすいキャラクターデザインを採用する
- 子どもが理解できる診察・検査方法を説明できるイラストを作る
- 待ち時間が苦にならないキッズスペースを充実させる
病院ブランディングの成功事例5選
全国各地の病院でブランディングを展開しており、実際に成功したといえる事例も多く見られます。今回は、プレスリリース配信で情報を発信した病院の中から、特に魅力的なブランディングを手掛けた事例を5つピックアップ。地域密着型やシニアを対象とした施策など、病院ブランディングの詳細と特徴をご紹介します。
事例1.病院を主体とした取り組みで地域密着型ブランディング
社会医療法人・清風會は「住み慣れたまち。ここで、一緒に、自分らしく。」を理念に掲げ、さまざまなブランディングを展開しています。プレスリリースで紹介しているのは、「きっかけドロップス」と名付けた地域を中心とした取り組みです。
医療とは直接的な関連のない取り組みですが、近年深刻化している問題に着目し、オリジナルプロダクトとして実施。病院を主体とした実践的な活動を知ってもらう機会として講座も開催しています。
参考:「あめ食べる?」から始まる“やさしい見守り”社会医療法人清風會が考案「きっかけドロップス」で地域に心の支えを育む
事例2.医療系の進路相談が可能な学生向けイベントを開催
高知県高知市を中心に展開する社会医療法人近森会(近森会グループ)のプレスリリースです。医療に興味を持ってもらうことを目的に、学生を対象とした医療職進路相談イベントを開催。2025年に初めて開催したイベントでは、医師・看護師はもちろん臨床工学技士・ソーシャルワーカー・介護福祉士・事務など多様な職種に対応する相談ブースを設けました。
若者に興味を持ってもらうイベント企画は、生活者へのイメージアップだけでなく人材確保のメリットにもつながるでしょう。若者を応援するプロジェクトでもあるため、地域住民や患者の安心感・信頼感を高めるきっかけにもなります。
参考:【近森病院】高校生向けの医療職進路相談イベントを初開催します!
事例3.快適性と安心性を両立したシニア向けの賃貸住宅
公益財団法人・星総合病院は、医療体制を整えたシニア向け賃貸住宅の提供をスタート。一般的な賃貸住宅や介護施設とは異なり、看護師・保健師の常駐、救急コールボタン設置など「快適性を重視したうえでの安心感」を強みとしています。
食事・運動・体験など多様な過ごし方に対応することで、地域での暮らしやすさを体現した事例といえるでしょう。シニア層はもちろん、利用者家族の印象も左右する病院ブランディングの一例です。
参考:シニア向け賃貸住宅 入居者募集ーおおまちてらすレジデンスー
事例4.身体的・精神的負担を減らす歯科治療機器を導入
愛知県名古屋市で地域医療に貢献する「丘の上歯科醫院」は、新しい機器の導入をプレスリリースで発表しました。口内炎や虫歯、歯周病など幅広い症状に対応できる最新の歯科用レーザーです。
歯を削る独特な音と痛みが苦手な人に向けて、身体的・精神的負担を軽減できるとしているのが特徴。歯医者に抱かれがちなマイナスイメージを払拭することはもちろん、治療の早さや安全性の高さも強みとしています。患者にとって魅力的な機器導入のプレスリリースは、来院のきっかけを促す一助となるでしょう。
参考:歯を削る”キーン”という音や痛みが苦手な方へ。名古屋市緑区の丘の上歯科醫院、患者様の負担を大幅に軽減する「Er:YAGレーザー」を導入。
事例5.オンラインクリニックがSNSキャンペーンを展開
オンラインクリニックを展開する東京TMクリニックは、株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレットと連携して新しいプログラムをスタートしました。重炭酸入浴剤を使用し「おうち温泉湯治 快眠プログラム」と題したセルフケア習慣を提案。
地域に根差さないオンラインクリニック独特の病院ブランディングですが、チャレンジキャンペーンを展開することで認知を広め、プログラムはもちろん自院を知る機会へとつなげています。不眠症を抱える人など、対象者を限定した施策で関心・利用を促した事例ともいえるでしょう。
参考:不眠症・睡眠障害を抱える方へ ー 医療機関が推進する入浴革命!純正・無添加の「重炭酸入浴剤ホットタブ」で睡眠改善へ6月13日よりチャレンジキャンペーン開始
病院ブランディングを成功させる5つのポイント
病院ブランディングを成功に導くためには、「利用者がどのような体験をするか」を重視することが大切です。院外の生活者だけでなく、医師や院内スタッフの士気を高めて提供サービスを統一・向上させるのも重要なブランディング要素のひとつ。病院ブランディングを成功させる5つのポイントを解説します。

ポイント1.患者や地域住民の体験にフォーカスする
病院の利用者層は地域住民がメインとなりますが、「利用したいかどうか」を左右するのは個人の体験談です。「〇〇病院がよいと聞いた」という評判は来院の大きな理由になり得るため、患者や地域住民の体験にフォーカスしたブランディングを展開していきましょう。
したがって、認知拡大を重視しすぎて「知ってもらえればよい」と考えるのは病院ブランディングにおいて適切といえません。期待値だけが高まり実体験が伴わない可能性があるためです。診察内容など自院で提供しているサービスと魅力・強みをもとに、通院というかたちで長期的に体験してもらう流れを想定しておきましょう。
ポイント2.病院以外に発信できる施策を活用する
病院のよさを多くの人に知ってもらうためには、院内にこだわらず、さまざまな場所で発信する取り組みが重要です。印刷物を用いた病院広報誌やSNS、プレスリリースなど多様な手段があるため、「誰に届けたいか」を明らかにしたうえで適切なツールを決めましょう。
- 個人事業主など健康診断の義務がない人:SNSで重要性を発信
- 60代以上の地域住民:病院や関連施設で広報誌を配布
- 来院経験のあるファミリー層:ホームページでイベント情報を公開
- メディア関係者:プレスリリースで取り組みを紹介
ポイント3.院内スタッフの働く意欲や熱意を維持する
人材確保や離職率低下といった効果を発揮させるためには、院内スタッフに「ここで働くことによるベネフィットが大きい」と感じてもらう必要があります。スタッフのモチベーションアップそのものだけでなく、「院内の雰囲気がよい」「医師・看護師に相談しやすい」といった患者の評判にも影響する重要なポイントです。
特に医療関係の仕事において、やりがいや動機は「ここで働きたい」という想いを左右する要素といえるでしょう。自院で働く意義を感じてもらうためには、充実した研修制度の導入や、コミュニケーション機会の強化といった施策が大切です。
ポイント4.他院の魅力的な要素を積極的に取り入れる
病院ブランディングを成功させるためには、他院が実践している施策を取り入れてみるのも一案です。すでに成功している活動はもちろん、自院と関連性の深い施策や、病院として魅力に感じた要素を積極的に取り入れてみるとよいでしょう。
施策そのものを真似するのではなく、あくまでも自院らしさを重視して展開していくことが重要。地域での自院の役割や地域性を再認識したうえで、自院が伝えたいことを全面的に盛り込んでいくイメージです。多種多様な病院ブランディングを参考にすることで、よりオリジナリティの高い施策を構築できるでしょう。
ポイント5.分析と改善を長期的に繰り返す
病院ブランディングは短期間で終わるものではなく、中長期的に継続して効果へとつなげていくものです。自院のブランディングとして好ましくない施策があった場合には、改善して新たな施策を検討しなければなりません。
継続的な病院ブランディングで効果を発揮するためにも、分析と改善を繰り返し行いましょう。例えば、満足度アンケートを用いることでブランディング前後の評価やイメージを把握できます。インナーブランディングにおいては、院内スタッフを対象に匿名意見箱を設けたりフィードバックの機会を設けたりするとよいでしょう。
病院ブランディングに効果的なプレスリリースの掲載内容
病院ブランディングと連携しやすい広報PR施策のひとつが、プレスリリース配信です。メディア関係者を中心に幅広い層が目を通すため、自院での診療内容や新設備などあらゆる情報を発信できます。ただし「情報が多ければよい」というものでもありません。4つの連携方法をもとに掲載内容をご紹介しますので、プレスリリース制作の参考にしてみてください。
新しい医療サービスの提案や最新機器の導入を発表
新しい医療サービス・設備を導入した場合は、プレスリリースで積極的に紹介しましょう。専門的な要素を含むものでも、以下の例のように患者にとってメリットの大きい内容であれば「ここに行ってみたい」という関心の向上に役立ちます。
- 従来より痛みの少ない最新医療機器を導入
- 地域に少ない診療科を新しく設置
- 〇〇の診断・治療が可能な専門外来を新設
プレスリリースに掲載する際は、医療広告ガイドラインに則ったうえでどういったサービス・機器なのか、なぜ導入するのか、どんな結果を見込めるのかといった情報を詳しく伝えることが大切です。
論文や医療サービスの受賞歴をレポート
自院の関係者が発表した論文や、医療サービスの受賞歴もプレスリリースに掲載できる魅力的なトピックです。例えば院長の個人的な実績であっても「この病院の院長が受賞した」と認識してもらうことで信頼感・安心感を向上させられるでしょう。
論文や受賞歴といった情報は生活者が自ら調べるケースが少ないため、プレスリリース配信により受動的なアプローチが期待できます。専門的な論文は情報の簡略化が難しいかもしれませんが、メディアを通してわかりやすく伝えられれば専門外来・専門機器・研究などの取り組みを知ってもらうきっかけになるでしょう。
広報誌の特集内容をメディア関係者向けに再構成
広報誌で自院の情報を発信した際は、再構成してからプレスリリースで発信するのも一案です。プレスリリースでは、ひとつの記事あたりひとつのテーマに絞ることが重要。広報誌の内容そのままでは「何を伝えたいか」がわかりづらくなってしまうため、メディア関係者が興味を持つトピックに絞って制作していきましょう。
プレスリリースを制作する際に意識したいのは、あくまでもメディア関係者を主な対象とする点。病院ブランディングはおもに地域住民をイメージしますが、プレスリリースはメディア関係者を通じて生活者に読んでもらうことが目的となるためです。
周年イベントや地域のセミナーなどユニークな取り組みを紹介
自院ならではの取り組みをプレスリリースで発信する場合は、記念行事やイベント・セミナーのように独自性の高いものを取り上げるとよいでしょう。自院の設立〇周年をきっかけにしたイベント企画は、歴史と実績を認知してもらうという意味でも有用な情報源となります。
また「七夕」「ひなまつり」などにちなんだイベントの様子を写真で紹介するのもおすすめです。イベント企画だけでなく、院内スタッフ向けに実施している行事をSNSなどでタイムリーに発信し、医師・看護師らが楽しむ様子を伝えられれば親しみやすさを感じてもらえるのではないでしょうか。
病院ブランディングと広報PRで自院の魅力を発信しよう
病院ブランディングは、病院経営において非常に重要な施策です。自院の存在を知ってもらうことはもちろん、自院ならではの強み・魅力を伝える施策として積極的に取り入れていきましょう。
病院の内外を問わず幅広い層に情報を届けるためには、病院ブランディングと広報PR活動の連携も重要です。内観をはじめとする院内設計を見直したり、SNSやプレスリリース配信を活用したり、あらゆるツールを用いることで改善すべき点も見えやすくなります。今回ご紹介したポイントや具体例を参考に、自院の特色を伝えるブランディングを構築してください。
【監修者のご紹介】
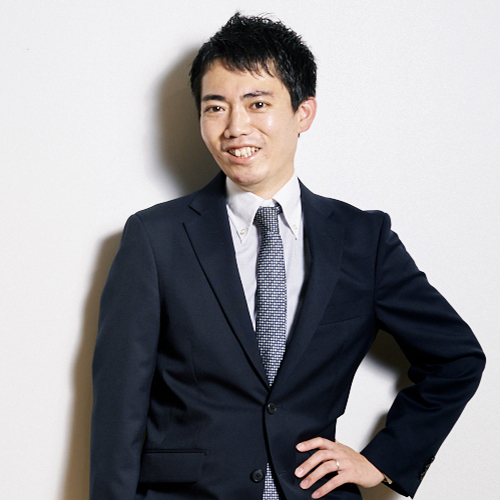
公益財団法人筑波メディカルセンター 総務部 経営企画課 広報係
2009年、近畿日本ツーリスト株式会社に入社。教育旅行分野の添乗・営業を経て、2012年、公益財団法人筑波メディカルセンターへ入職。2015年6月より法人広報部門にて、広報誌の企画編集、動画制作、公式SNSの運営、プレスリリース配信などを担当。2021年に実施したクラウドファンディングでは広報・PR実務を担い、プロダクト完成後に配信したプレスリリースが、株式会社PR TIMES主催のプレスリリースアワード2022「ヒューマン賞」を受賞。2023年10月よりPR TIMES公認プレスリリースエバンジェリストとして活動。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする


