多くの企業が取り入れている「オープンイノベーション」ですが、具体的にどういった活動なのか、自社と親和性があるのかわからないという方もいるのではないでしょうか。企業としての理解が深まれば、今後取り組むべき施策も見えてきます。
本記事では、オープンイノベーションの基本的な概要から、推進することによるメリットなどをご紹介。成功させるためのポイントや実際の企業事例もピックアップしていますので、社内の取り組みを理解し、広報PR活動に役立てるヒントにしてください。
オープンイノベーションとは
オープンイノベーションは、自社が保有する技術やノウハウを社外へ展開するだけでなく、外部の知見やアイデアを取り入れて新たな価値創出を目指す手法です。近年は特に注目が高まっているため、「イノベーション」「クローズドイノベーション」などについても知識を深めておきましょう。まずはイノベーションの概要について解説します。

イノベーションとは
「イノベーション(Innovation)」とは、日本語に直訳すると革新・刷新・新機軸といった意味。技術革新によって社会に変化をもたらす取り組み全般を指します。
技術的な研究・開発のみならず、商品・サービスやビジネスモデルなど幅広い領域の革新を目指すのがイノベーションです。特に技術革新を目的とする取り組みを「プロダクトイノベーション」、新しい仕組みを作ることを「プロセスイノベーション」と呼びます。
クローズドイノベーションとの違い
オープンイノベーションとクローズドイノベーションの大きな違いは、「リソースを社内に限定するかどうか」という点です。社内外と連携するオープンイノベーションに対し、クローズドイノベーションは社内のみの人材や知的財産を活用します。
リソースは社内に限られるものの、流出リスクを低減しながら利益率向上を目指せるのがメリット。一方で、効率やスピードを重視する場面では、外部との連携を取り入れるオープンイノベーションの方が有効な場合もあります。
こうしたイノベーションの考え方を理解しておくことで、自社の新しい取り組みを社内外に伝える際にどのような文脈で語るとよいか、など広報PR活動でも活かされるはずです。
オープンイノベーションが注目されている背景
オープンイノベーションが注目されている背景には、デジタル技術の進展やコスト増大といったさまざまな理由があります。多くの企業が推進している理由がわかれば、自社で採用する意義やメリットも見いだせるでしょう。オープンイノベーションが注目されている背景・理由を4つの視点から解説します。
技術革新の加速と製品ライフサイクルの短縮化
技術革新のスピードは近年特に加速しており、あらゆる業界で進展している現状が見受けられます。スマートフォンをはじめとするガジェットやソフトウェアなど、技術力・流行ともに目まぐるしく変化している時代です。
社外の知的財産や優秀な人材と連携することで、このような激しい変化をタイムリーに把握できるようになります。製品ライフサイクルが短縮している時流に応じた有効な取り組みのひとつがオープンイノベーションであるといえるでしょう。
研究開発コストの増大
技術が高度かつ複雑になると、研究・開発に必要な投資も増加します。最先端の研究設備を導入したり、専門的な人材を長期間確保したりといった施策が必要な場合は、特に莫大なコストを想定しなければなりません。
オープンイノベーションでは社外のパートナーとコストを分担できるため、コストを抑えながら研究・開発に取り組みやすくなります。コスト削減を重視する企業にとっても、ベネフィットの大きい取り組みです。
グローバル競争の激化
さまざまな市場がグローバル化し、競争が激化しているのもオープンイノベーションが注目される理由のひとつ。日本国外で競争力を維持したり、これから強化したりするためには、自社だけでなく世界中の情報を活かしていくことが不可欠。同時に、企業同士の協働も一層重要となるため、外部の知見や技術を取り入れるオープンイノベーションが注目されています。
デジタル技術の進展による外部連携の容易化
クラウドサービスやコミュニケーションツールの発達により、場所を問わず情報を共有したりプロジェクトを管理したりできるようになりました。オフラインにこだわらず連携を強化できるため、オープンイノベーションも展開しやすくなったといえるでしょう。
また、自治体によってマッチング事業が推進されたり、産学共創活動も活発になり、オープンイノベーションを目的としたマッチングプラットフォームを提供する企業も登場したり、同じ目標を持つ企業・団体が相互につながりやすくなったのも理由として挙げられます。
オープンイノベーションを推進させる4つのメリット
オープンイノベーションの推進により、コスト削減・リソース確保・市場参入といったメリットが期待できます。リソースを効率化しつつコストを抑えられるという点は、特にオープンイノベーションならではの利点といえるでしょう。4つのメリットについて詳しく解説します。
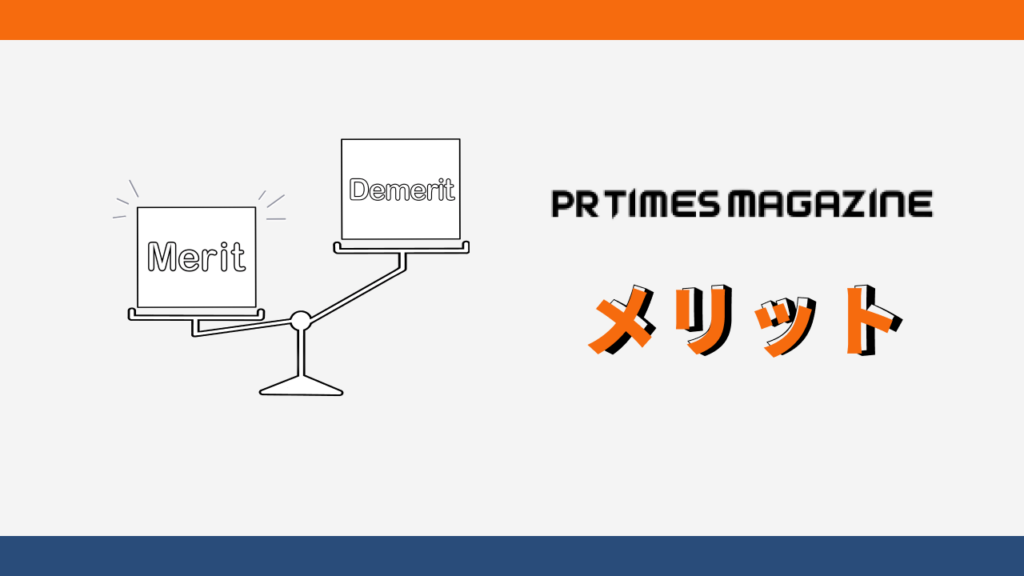
メリット1.コスト削減とリソースの効率化
まず、オープンイノベーションにおける大きなメリットは、コスト削減とリソースの効率化です。外部の知的財産を活用することで、ゼロからすべてをスタートする必要がなくなり、研究・開発において時間的にも金銭的にもコストを抑えられます。
研究設備はもちろん、専門的な人材を採用したり、時間をかけて育成したりといったコストの削減も期待できるでしょう。大企業に比べてリソースが不足しがちな中小企業でも、十分なイノベーションを目指せる点は特に魅力的です。
メリット2.研究開発期間の短縮
次に、研究・開発にかかる時間短縮がオープンイノベーションのメリットです。通常であれば基礎研究から取り組むような開発プロジェクトも、既存の外部技術を取り入れることで大幅な時間短縮を期待できます。
ゼロの状態から実用化までは数十年をかけることも珍しくないため、早期の市場投入を目指すためにも魅力的なメリットといえるでしょう。
メリット3.新たな市場・技術領域への参入機会獲得
さらに、新たな市場・技術領域への参入を見込めるのもオープンイノベーションのメリットです。自社にない知的財産を持つパートナーと協働することで、自社が開拓していない領域に参入する機会を獲得できるかもしれません。
事業ポートフォリオが多様化するため、経営リスクを分散させるメリットも。また、外部パートナーのネットワークを活用することで、新たな市場での認知拡大やブランディングにもつながる可能性があります。
メリット4.イノベーション文化の醸成
技術的なメリットだけでなく、自社組織全体のイノベーション意識を高められることも重要な効果です。社内のみでは確保しづらい専門人材と交流したり、異なる企業文化に触れたりすることで視野が広がるためです。
社内組織が活性化すれば、自発的なイノベーション活動も生まれやすくなります。特定のプロジェクトに対する技術力アップはもちろん、企業そのものの持続的な成長を支える変革の一助となるでしょう。
オープンイノベーションの種類
オープンイノベーションは大きく、取り入れる「インバウンド型」、提供する「アウトバウンド型」共に創る「カップリング型(連携型)」の3つに分類されます。多くの企業が採用しているインバウンド型をはじめ、各手法によって特徴やメリットを見ていきましょう。
インバウンド型:知識や技術を外部から取り入れる
まずもっとも一般的とされるオープンイノベーションは、社外のアイデア・技術・知識を自社に取り入れる「インバウンド型」です。大学の研究室と協働でプロジェクトを進めたり、他社の技術ライセンスを購入したりといった例が挙げられます。
自社にない技術を迅速に獲得することで、研究・開発の時間を短縮して効率化するのが主な目的。オープンイノベーションの中でも一般的な手法であり、日本国内でも多くの企業がインバウンド型を採用しています。
アウトバウンド型:自社の知的財産を社外に提供する
次に挙げられるのが、自社が保有する技術を社外に提供する「アウトバウンド型」です。自社が保有する技術や特許をライセンス供与したり、共同事業として展開したりすることで、収益化や新しい領域への展開を目指します。
自社で活用しきれない知的財産を有効活用してもらうことで、収益源を開拓できるのがメリット。自社が強みとする技術を普及させることになるため、技術の社会実装を加速させたり、競争優位を確立したりといった効果も期待できます。
カップリング型(連携型):技術や知識を相互共有する
そして近年注目されているのが、インバウンド型とアウトバウンド型の要素を掛け合わせた手法「カップリング型(連携型)」です。コンソーシアムやジョイントベンチャーの設立のほか、ハッカソンや共創イベント、事業提携もカップリング型に含まれます。
特徴的なのは、一方に依存せず、各パートナーの強みを組み合わせて研究・開発を進め、リターンはもちろんリスクも共有する点。そのため、大規模なプロジェクト、長期的なプロジェクトにも取り組みやすい形態といえます。
いずれの場合も、広報PR担当者の方にとって、ストーリーを描く際に欠かせない視点です。
オープンイノベーションの対象となるリソース
オープンイノベーションで活用されたり、共有されたりするリソースは、人材、アイデア、技術、知的財産などが挙げられます。そのほか、研究・開発に必要な設備やインフラ、顧客ネットワークへのアクセスといったリソースも対象です。それぞれオープンイノベーションを推進するうえでどのように関わってくるのか理解しておきましょう。
人材・専門知識:外部の専門家との協働
オープンイノベーションにおいて必要不可欠ともいえるのが、人材や専門知識といった人的リソースです。特定分野の専門家・技術者・研究者など、高度なスキルを持つ人材は技術革新に欠かせません。
社外の専門性を補完することにより、研究・開発のスピードを高めることができます。視野が広がるため、これまでに想定していなかったアイデアを生んだり、交流を通じて組織を活性化させたりといった効果も期待できるでしょう。
さらに、外部人材との協働は社外への発信機会にもつながります。どんな人と共に取り組んでいるかを伝えることは、企業の信頼や共感を高める重要な要素です。
アイデア・技術:新たな発想や最新技術獲得
新製品をリリースするためのコンセプトや改善提案など、イノベーションの源泉となるアイデア・技術も重要なリソースです。オープンイノベーションに特化したプラットフォームでアイデアを募集したり、ベンチャー企業の技術を取り入れたりといった方法が検討できます。
新たな技術として導入するだけでなく、技術的な課題解決を目的に提案を受けることもあるでしょう。社外から新鮮な発想を積極的に取り入れることで、クローズドでは実現できなかった製品の研究・開発を進めるきっかけとなります。
社外発のアイデアや技術を取り入れる姿勢を示すことで、開かれた企業文化として受け入れられるのではないでしょうか。
知的財産・ノウハウ:特許や商標の戦略的活用
ノウハウや商標といった無形資産(知的財産)は、オープンイノベーションを成功させるうえで重要なリソースのひとつです。社内外の知的財産を有効活用することで、研究・開発の自由度が高まります。
自社の特許や商標がライセンスアウトできれば、相互供与やライセンス契約による収益の効率化も見込めるでしょう。自社技術を新たな市場で活用したり発展させたりすることで、知財ポートフォリオの最適化も可能です。
研究開発設備・インフラ:高度な設備へのアクセス
アイデアや知識などの無形資産以外に発生するのが、研究・開発に必要な設備や施設といった物理的リソースです。オープンイノベーションにおいては、大学や研究機関の高度な実験装置を用いたり、共同ラボを設置したりといった取り組みも多く見られます。
クローズドでは莫大なコストがかかる初期投資も、オープンイノベーションであれば高額・高度な環境にも素早くアクセスできるのが魅力。
人・技術・知的財産・設備など、共有できるリソースは多岐にわたるため、資源を柔軟に組み合わせることが、オープンイノベーションの可能性を広げるカギになるでしょう。
市場:販路・顧客基盤の相互活用
オープンイノベーションでは、研究・開発を進めることはもちろん、市場に展開していかなければなりません。研究・開発の成果を社会に届けるためには、認知・販売チャネルの拡大、顧客基盤の拡充が必要です。そのため、統一されたブランディング構築、販売チャネルや顧客ネットワークの活用など連携が重要です。
既存顧客との関係性が密であれば、新規顧客開拓にかかるコストを抑えながら市場浸透のスピードを上げられるでしょう。国内に限定した技術革新はもちろん、グローバル展開を目指すオープンイノベーションでも重要なリソースとなります。
オープンイノベーションを成功させる5つのポイント
オープンイノベーションを成功させるためには、明確な目標設定と社内組織での理解促進が必要です。トラブルを避けるため、法的な知識をもとにルールを共有することも不可欠といえます。長期的な取り組みを前提に、広報PR活動も積極的に取り入れましょう。オープンイノベーションの成功に向けた5つのポイントをご紹介します。

ポイント1.目的設定を明確にする
オープンイノベーションを本格展開する前に、企業として何を目指しているのか明確にしなければなりません。「新しい市場へ参入したい」「新プロジェクトの開発コストを抑えたい」など、具体的な目的・目標を考えてみましょう。
目指す場所が明らかになれば、パートナーとして適切な企業・団体を選定しやすくなります。最終的な成果指標(KGI)を立て、これを達成するための中間指標(KPI)を組み立てることで、より段階的なプロセスをイメージできるでしょう。
ポイント2.社内全体で理解を促進する
オープンイノベーションは、企業や団体など組織単位でつながりを持つ取り組みです。特定の人物や部門に限定せず、組織全体で理解を深め、協働する意識を高めなければなりません。
イノベーションに対する意欲を促すためにも、合同セミナーを開催したり、社内報で成功事例を共有したりといった施策を取り入れましょう。オープンイノベーションに直接的な関わりがない人でも、理解促進により抵抗感を取り除き、統一感のある企業文化を醸成できます。
ポイント3.知的財産権の取り扱いルールを共有
自社のアイデアや技術を守るためには、知的財産権をはじめとするルールの強化が重要です。特に、共同研究を行う場合など、知的財産の扱いが複雑になります。秘密保持契約(NDA)の締結、共同開発契約、ライセンス契約などの条件、取り決めを徹底しましょう。
知的財産に関する専門家や弁護士の協力をあおぐことも有効です。自社の財産を守るだけでなく、パートナー企業とのトラブルを防ぐためにも大切な環境整備を進めましょう。
ポイント4.PDCAを回して長期的に取り組む
研究・開発期間の短縮やコスト削減がメリットにあがるオープンイノベーションですが、取り組み自体は長期を前提に進めます。プロジェクトの規模が大きいほど長期戦になりやすく、想定どおりに進まないケースも多くなります。目標に向けてPDCAを回しながら評価・改善を繰り返し、試行・学習を繰り返しましょう。
オープンイノベーションにおいては、特許出願数や新製品の売上高といった指標のほか、組織文化の変化のように数値化しづらい指標も重要となります。短期間での結果に一喜一憂することなく、あくまでも長期戦を前提に継続的な改善を重ねることが大切です。
ポイント5.プレスリリース配信で社内外に発信する
オープンイノベーションや関連の取り組みを広く知ってもらうためには、プレスリリースでの発表、広報PR活動が欠かせません。新技術や製品の発表だけでなく、「なぜこの共創を行うのか」「どんな価値を社会にもたらすのか」という背景まで発信することで、活動の理解と共感を広げられます。
革新的な企業イメージを持ってもらうだけでなく、新たなパートナー候補を見つけたり、自社従業員の意識を高めたりといった効果にもつながるでしょう。社内外を問わず情報共有し、イノベーションを透明化できるため積極的に取り入れたい施策です。
オープンイノベーションの事例5選
オープンイノベーションに取り組む企業・団体は多数見られますが、具体的にイメージできていないという方もいるのではないでしょうか。ここからは、実際にオープンイノベーションを推進している企業の事例を5つご紹介します。特徴的な取り組みや成果を参考にしてみてください。
事例1.社内の複数のオープンイノベーションを統合
情報通信事業を手掛ける日本電気株式会社(NEC)は、複数のプロジェクトでオープンイノベーションを展開しています。2025年10月には、点在していたオープンイノベーションの取り組みを「NEC Open Innovation」として束ねました。
国内外のパートナー企業やスタートアップとの共創を進めており、プレスリリース配信による情報発信も積極的に実施しています。「NEC Open Innovation」の発足はブランディングの観点でも評価され、2025年グッドデザイン賞を受賞しました。
参考:NECのオープンイノベーションの取り組み「NEC Open Innovation」が2025年グッドデザイン賞を受賞
事例2.助成金検索サービスを活用したオープンイノベーションを始動
キャリアイベントや転職支援サービスなどを運営する、株式会社LabBaseのオープンイノベーション事例です。助成金検索サービスをアップデートし、第1弾パートナーとしてクラシエ株式会社との共同プロジェクトをスタートすることを発表しました。
研究資金不足や助成金の複雑な申請業務といった課題解決に向けた取り組みで、「新たな事業の芽を育てていく」ことを目的のひとつとしています。今後は社会実装の機会拡大も予定しており、オープンイノベーションに取り組む積極的な姿勢が見て取れる事例です。
参考:研究者の新たな資金獲得体験を提供する「LabBase Grant」を開始 第1弾クラシエとの共同プロジェクトからスタート
事例3.営業課題の解決を目指し、戦略的パートナーシップを締結
PRM「PartnerProp」を提供する株式会社パートナープロップは、スタートアップ企業の株式会社ナレッジワークと戦略的パートナーシップを締結しました。パートナーセールスの重要性が高まっていることをうけ、「パートナーイネーブルメント」カテゴリーを新たに創造。
今回の連携により、営業現場のコンテンツやノウハウなどを双方向に共有し合い、顧客企業が抱える課題を包括的・戦略的に解決することが可能になりました。2社のノウハウや技術力を活かしたオープンイノベーションにより、相乗効果を高めた事例です。
参考:パートナープロップ、ナレッジワーク社との戦略的パートナーシップを発表。「パートナーイネーブルメント(販売代理店向けの営業支援)」領域を強化
事例4.投資ノウハウとテクノロジーのオープンイノベーション
グローバル・ブレイン株式会社は、ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社と、共同出資による合弁会社の設立を発表しました。スタートアップの支援を目的に、長期的な成長機会を創出するプラットフォームとしての役割を提言しています。
こちらはグローバル・ブレインの投資ノウハウと、ソニーグループのテクノロジーを活用したカップリング型(連携型)の事例です。設立日にはプレスリリースを配信し、メディア関係者を中心に認知を拡大しました。
参考:グローバル・ブレインとソニーフィナンシャルベンチャーズがAIネイティブな次世代CVCを運営する新会社を設立
また、イノベーションの取り組みが重視されつつある昨今、オープンイノベーション促進に向けてプラットフォームを運営する企業・団体も見られます。
参考:JR西日本グループの技術と社会が繋がる「イノベーションプラットフォーム」がリニューアルオープン
参考:グローバルスタートアップ連携プラットフォームを展開するThird Ecosystem、オープンイノベーションプラットフォームTMIPにゴールドパートナーとして参画
参考:日本最大級OIプラットフォーム「AUBA(アウバ)」、全面リニューアル | 株式会社eiiconのプレスリリース
事例5.プリンターのメーカーと印刷サービスをオープンイノベーション
アフリカ農村のデジタルプラットフォームを運営する株式会社Dots forは、プリンターやミシンなどの製造・販売を手掛けるブラザー工業株式会社とオープンイノベーションの取り組みをスタート。「村の印刷サービス」と題し、アフリカの地方農村部における印刷・コピー事業を展開しました。
プリンターの製造を得意とする企業の製品技術を取り入れたオープンイノベーションで、アフリカ農村に特化したエリア性も特徴的なプロジェクトといえます。実際に複合機を設置した様子などをプレスリリースで紹介し、業種を問わず認知拡大した広報PR活動も魅力的な事例です。
参考:ブラザー工業と進めるアフリカ農村での印刷・コピー事業「村の印刷サービス」を本格始動します
オープンイノベーションを理解し、企業の成長に貢献しよう
社外の技術や知識を活用し、自社の技術変革を加速させる「オープンイノベーション」。技術やノウハウを獲得できるだけでなく、研究・開発コストの削減や、人的リソースの確保にもつながる重要な手法です。
オープンイノベーションを成功させるためには、目標設定や社内理解の促進など、組織全体で取り組むことが必要です。広報PRとしては、オープンイノベーションに取り組む意義を社内外へ伝え、積極的かつ長期的に共創を推進することで、企業の成長を後押ししましょう。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする



