プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を運営する株式会社PR TIMESは、2025年8月29日に「伝わるプレスリリース 情報の原石を見つける、届ける。」をテーマに、自治体向けの広報PRセミナーを開催。PRDESIGN JAPAN株式会社 代表の佐久間 智之さんと、京都府福知山市 広報担当の宇都宮 萌さんをお招きしました。
第一部では、「伝わるプレスリリースの作り方と届け方」をテーマに、佐久間さんが自治体プレスリリースの基礎について講演。第二部では、福知山市で広報PRを担う宇都宮さんが「福知山市はなぜ『職員』に注目するのか? 担当者×広報で作るプレスリリースの工夫」をテーマにセミナーを行いました。
本レポートでは、第二部のセミナーをピックアップ。福知山市が「職員」を主語にした広報PR活動に取り組む理由や、実際に成果を生み出した具体的な事例、さらに広報担当者が職員と伴走するうえで意識すべきポイントなど、役立つ実践的なヒントをお届けします。
京都府福知山市:最新のプレスリリースはこちら

京都府福知山市役所 広報広聴係
民間企業と公益財団法人での制作職・広報職を経て、2018年に社会人採用で福知山市役所に就職。新設された「シティプロモーション係」に配属され、1ヵ月目に「明智光秀が主人公の大河ドラマ」の製作が発表となる。地元ゆかりの武将・明智光秀からの「謀反のお知らせ」、市民共創型企画「福知山の変」など、市のPR企画を多数手掛け、2025年より現職。全国広報コンクール特選、シティプロモーションアワード金賞、CAMPFIREアワード特別賞、PRアワードブロンズなどを受賞。
なぜ福知山市が「職員」に注目するのか
京都府北部・中丹地方にある人口約7万3千人の福知山市。同市で広報PRを担うのは、民間企業での舞台制作や広報職の経験を持つ宇都宮さん。第二部の冒頭では、宇都宮さんが入庁後に感じた福知山市の広報課題と、解決のための取り組みについてお話しいただきました。
成果はあるのに、育ちにくい「PRマインド」
現在、福知山市は廃校利活用の成功事例を数多く生み出したり、電子図書館の利用率で3年連続全国1位を達成したりと、さまざまな成果を上げています。こうした取り組みを発信するため、記者発表の場も積極的に設けています。
宇都宮さんは入庁当時の7年前、価値や成果を発信する広報意識が弱いのではと感じたと言います。背景にあるのは、地域に密着し強い到達力を持つ夕刊紙「両丹日日新聞」の存在。発行部数は市内世帯の4割以上に達し、同紙に掲載されれば市民に確実に情報が届くという心強いメディア環境です。しかし、その安心感があるがゆえに、「業務を社会的な価値や共感へと翻訳し、社会へ届ける」というPRマインドが育ちにくくなっていると感じたのだそうです。
職員自身をまちの大切な資源として表舞台へ
そうした状況を打破し、福知山市の魅力を広く伝えるにはどうすればよいのか──。宇都宮さんが前職で舞台作品の広報PRを担っていた際、舞台の価値を世の中に届けていたのは、俳優や演出家といった「表に立つ存在(タレント)」でした。福知山市でも同じように「タレント」が必要だと感じ、注目したのが福知山城を築城した明智光秀でした。市役所内外の協力を得て「光秀がしゃべる自動販売機」を福知山城に設置したところ大きな話題に。フジテレビの『めざましテレビ』でも紹介され、宇都宮さん自身にも担当職員としてコメント取材が入ったそうです。
タレントではないごく普通の市役所職員でもコメントを求められることに驚き、この経験から自治体の職員そのものが、まちにとっての大切な資源であるという気づきにつながったと話します。
主語を「職員」にすることで生まれる「共感」
市役所の職員を「黒子」から「表舞台」に。宇都宮さんがその手応えを実感したのが、2020年から2021年に放送された大河ドラマ『麒麟がくる』でした。福知山市では、主人公・明智光秀ゆかりの地としてぜひ福知山市を取り上げてほしいと、「麒麟よ来い」を合言葉に広報PR活動を展開。
当時のシティプロモーション担当課長はお祭り男的なキャラクターを活かし、自ら「歩く広告塔」となりました。特に福知山城周辺で始めた毎朝の清掃活動は、市民の注目を集め、地元紙の両丹日日新聞にも大きく取り上げられたそうです。さらに、最終回直後に実施したYouTubeライブは1万回視聴を記録し、課長が涙を流すとコメント欄には「おめでとう!」「福知山に行くね!」と温かい声が殺到。翌日には市民からサインを求められるほどの盛り上がりとなりました。「市役所」を主語にすると行動に制約が多い一方で、担当者個人を主語にすると自由度が増し、受け手からの共感も格段に高まるということを実感したそうです。

福知山市によるフォロワーシップを軸とした広報PR事例
その後、「もっと自然に職員を表舞台に立つタレントとして活かす方法はないか」と模索した結果たどり着いたのが、リーダーや挑戦する人に寄り添う「フォロワーシップ」の視点です。
職員の挑戦に光を当てる「でしゃばり小僧」
宇都宮さんは無理に起点を演出するのではなく、すでに信念を持って動いている職員に共感し、フォロワーとして伴走することで、自然で持続可能なアプローチにつなげる。それを「でしゃばり小僧」と表現し、熱量のある挑戦を見つけると現れて、主役ではないけれど主役と同じ熱さでそばに立つ存在として広報担当者は活動する。自分自身が「でしゃばり小僧」になることによって、表に立つ人の挑戦や物語を見つけ、光を当てるために、部署の垣根を超えてサポートに徹することをめざしました。
全国初の獣害対策専門職員によるコラム
農業振興課で全国の市町村初の有害鳥獣対策専門職員を務める望月優さんも、「でしゃばり小僧」として光を当てた職員のひとりです。平時の啓発から現場対応、さらにはプライベートで猟師としても活動する獣害のプロです。
その存在に気づいたのは、日々チェックしていた「広報カード」(事業担当者が書く、福知山市版簡易プレスリリース)。読み手を惹きつける書き方に、「この人の話をもっと多くの人に届けたい」と感じ、コンタクトを取ってコラム執筆を依頼したところ、快く引き受けてくれたそうです。
1ヵ月後に届いた原稿は4,000字。移住から専門職員になるまでの経緯が小気味よい文章でまとめられ、写真もふんだんに盛り込まれるなど完成度の高い仕上がりでした。
【広報としてサポートした6つのポイント】
- 見出し・リードの再設計:検索性や社会性を意識しタイトルを再設計
- 記事構成の工夫:長文の分割やタイムラインの整理、小見出しの追加
- 面白さの補強:望月さんの話から面白いと思える部分を見つけて補強
- リスクチェック:誤解や批判につながるリスクがある内容は、望月さんの意図を確認し補足説明を追加
- プレスリリース支援:社会的に意義のある取り組みとして発信
- 反響の共有:SNSでの広がり具合や、記者からの反応などをフィードバック
参考:「実録・クマ立てこもり事件」現場に向かった獣害対策公務員によるレポートとクマ被害対策記事を京都府福知山市公式noteにて公開
子ども政策室 若手職員3人による自作紙芝居のプロモーション
事業担当者自身の立場では、「この取り組みをニュースにするのはちょっと気が引ける」「でしゃばっていると思われたらどうしよう」という心理が働くことも。「でしゃばり小僧」が「この取り組みには伝える価値があります」「ぜひ担当者のみなさんに出てほしいです」と声をかけ、担当者が一歩を踏み出しやすくなる環境をつくることに意味があると宇都宮さんは話します。
親子で防災を考えるきっかけづくりとして取り組まれた「コドモト防災プロジェクト」は、若手職員3人が自分たちでストーリーを考え、絵を描き、完全オリジナルの防災紙芝居『きみならどうする?』を制作したもの。プレスリリースでは「若手職員3人がつくった完全オリジナル」というユニークさを前面に押し出すことで注目度を高めました。「テレビにも取材してほしい」という3人の思いから、テレビ局へアプローチする挑戦をサポートし、2局から取り上げられました。職員の挑戦や思いがより多くの人に届き、共感を広げる可能性が格段に高まることを実感したそうです。
参考:大雨シーズン、親子の防災意識向上へ! 若手職員作、子ども向け防災紙芝居『きみならどうする?』発表! 部署横断「福知山市コドモト防災プロジェクト」

職員と共創し、まちの魅力が伝わる5つのポイント
宇都宮さんのお話から、職員と広報が共創していくために意識したい5つのポイントは以下の通りです。
- ポイント1.情報の流れを止めない:情報は自分で抱えこまずに循環させることが大切です。同じ課の人はもちろん、上司や別の課の人にも自治体で使えるチャットツールなどを活用して情報を共有することで、大きな可能性を生むこともあります。
- ポイント2.情報の橋渡しをする:「この情報は、あの人に役立つかも」と感じた時には、積極的に情報を橋渡ししましょう。ふとした橋渡しがセレンディピティ(予期せぬ発見)を呼び込み、新しい価値を生み出すことにつながる可能性もあります。
- ポイント3.周囲に相談する:完成した情報だけを出すのではなく、企画の途中でも「こんな情報ない?」と周囲に聞くようにしましょう。小さな相談が次のヒントにつながります。
- ポイント4.「すごい」を言葉にして伝える:誰かの取り組みや成果を見て「すごい」と感じた時には、必ず本人に伝えることも大切なポイントです。さらに周囲にも伝えることで、その人の取り組みが評価されて広がっていきます。
- ポイント5.タイミングが合わなければ無理しない:広報と担当者のタイミングが合えば共創は加速しますが、合わないときも当然あります。大切なのは「関係」という資本を持ち続けること。無理をせず、また次の機会を待ちましょう。
【一問一答】自治体担当者からの質問に宇都宮さんが回答
セミナーでは、広報PR活動やシティプロモーションを担う自治体職員の方から、さまざまな質問が寄せられました。ここでは、その一部を抜粋し、宇都宮さんの回答と合わせてご紹介します。
──庁内の情報に対してアンテナを張っているものの、事業課から必要な情報が上がってこないことがあります。情報を提供してもらうために意識していることはありますか。
事業課から必要な情報が上がってこない理由のひとつに、広報課に相談するのを遠慮していることがあるかもしれません。例えば、一度相談に来てみたものの、広報課の人がとても忙しそうに見えたために気が引けて、それ以降は声をかけづらくなるというケースです。だからこそ、まずは相談を受けた際に「全力でウェルカム感」を出すことを心がけ、その一度の接点をきっかけに、「こんな情報がありましたよ」とこちらから連絡をしたり、日頃から接点をつくっておくことが大切だと思っています。
また、「面倒だから」「記事にしてもらう必要はない」と判断して情報が上がってこないこともあります。その場合は「こういう機会をつくってみませんか」とこちらから逆提案して情報を引き出すというのも方法のひとつです。ただし、担当課が「余裕がないのでやりたくない」というスタンスである場合は無理に進めず、諦めることも必要。結局のところ、情報発信は案件の重要性もさることながら、人の熱量が大事だからです。
──組織として、業務が属人的にならないようにするにはどうしたらいいでしょうか。広報担当や、他所管のスター職員が異動しても持続可能な広報とはどのようなものだと考えますか。
ひとつの成功事例が生まれたら、それをできるだけ仕組みに落とし込んで日々のルーティーンに取り入れることが大切だと思います。例えば、広報資料のフォーマットを統一することや、プロセスをきちんと言語化してルールとして残す。そうすることで、担当者が変わっても同じ質で情報発信を続けられるようになります。属人的なスキルや経験だけに頼るのではなく、形にして残すことで持続可能な広報体制が整っていくのではないでしょうか。
──スター職員を探したことがなく、現場から上がってきた情報をプレスリリースで届けるだけでした。地域内にスターがいないかも…と思うこともあります。彼らを探す第一歩として、何から始めますか。
現場から上がってきた情報の届け方に「PRマインド」を感じたら、そういう方とは共創しやすいので、まず注目してみてはどうでしょうか。私は日々の広報カードからそうした兆しを読み取る程度しかできていませんが、本来であれば市役所内を実際に回って探すのも効果的だと思います。
また、自分の知っている情報や見えている範囲は限られているという自覚も必要です。私は最近、広報誌の特集などにアイデア出しの段階から関わるようになりましたが、担当者を集めてのブレインストーミングやアイデア出し会議を意識的に行っています。分野の異なる人が集まると、自分では出会えなかった情報が一気に広がり、さらに「いいね」と皆が感じればその場でコンセンサスも取れる。自分だけで頑張るには限界があるので、人に聞きながら関わってもらうことが第一歩になると考えています。
──「事後リリース」は記事にしにくいためメディアの目に留まりにくいと聞きました。しかし、役所としてはさまざまな兼ね合いで事後リリースを発信しなければならない場合もあります。事後リリースを効果的に発信する方法はありますか。
先ほどお話しした、望月さんの「クマ立てこもり」の記事や若手職員3人の紙芝居もそうですが、事後リリースはどうしてもニュースバリューが低く、新規性や今後の取材機会を提供という点では限界があります。しかし、事後リリースは「言語化」や「ノウハウの蓄積」という意味でも十分意味のあるものではないでしょうか。
まとめ:職員を起点に広がる共感とまちの可能性
今回のセミナーでは、職員を主語にした広報PRの意義や、伴走者として職員をサポートする際の心得など、日々の実践に落とし込めるポイントが数多く含まれていました。
福知山市の広報PR事例から見えてくるのは、「市役所」という組織の枠を超えて、職員一人ひとりの挑戦や思いをまちの大切な資源として発信することの力強さ。宇都宮さんが示した「でしゃばり小僧」という姿勢は、職員の挑戦に寄り添い、光を当てることで物語を広げていく新しい広報のあり方といえるでしょう。
大切なのは、個々の職員の挑戦や思いを一過性の成果に終わらせず、仕組みや関係性として積み重ねることで持続可能な広報PR文化へと育てていくこと。情報の循環や橋渡し、小さな相談や「すごい」を言葉にする日常的な実践が、やがて大きなムーブメントへとつながっていきます。
社会が求めているのは制度や数値の報告だけではなく、その裏にある人の顔やストーリー。福知山市の取り組みは、職員一人ひとりを大切な資源としてとらえ、共感を起点にまちの価値が伝わる広報PR活動の新たな可能性を示しています。広報PR活動に取り組む自治体の皆さまにとってヒントとなれば幸いです。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事
- あわせて読みたい記事思いや背景を共感に。ストーリーで魅せる広報PR戦略|クロシェ×神戸新聞社

- 次に読みたい記事使い方次第で力強い伴走者に。生成AIを活用したプレスリリース作成のコツ|株式会社トクイテン
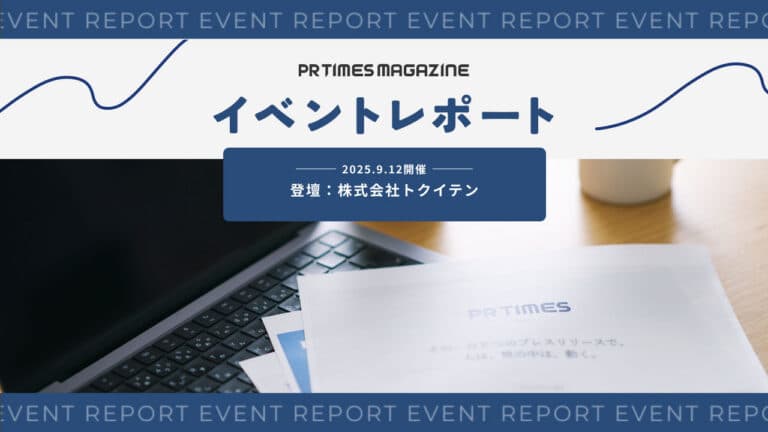
- まだ読んでいない方は、こちらからデザインの力で企業と「個」の関係を刷新する #PR3.0 Conference
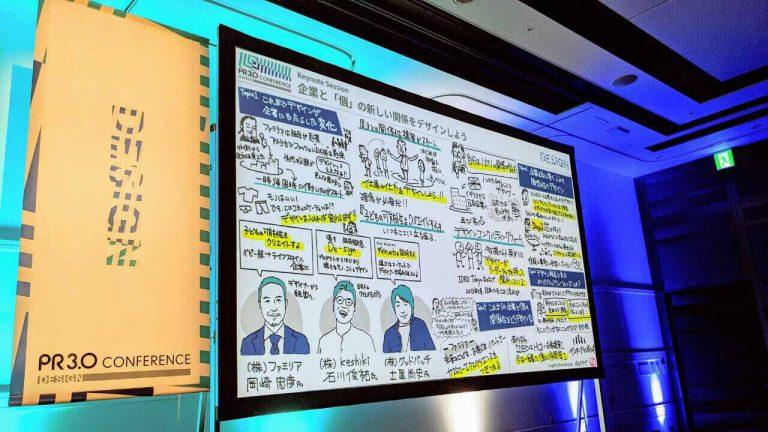
- このシリーズの記事一覧へ

